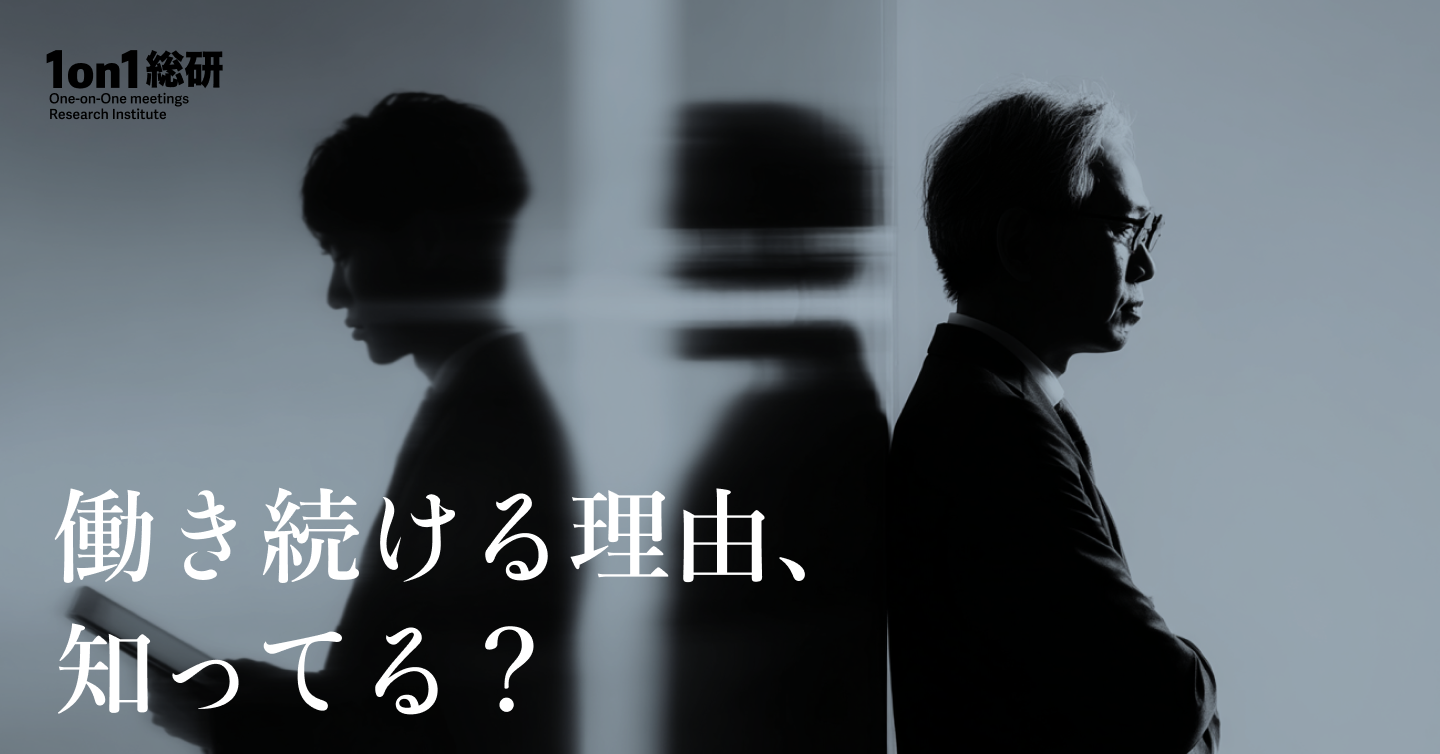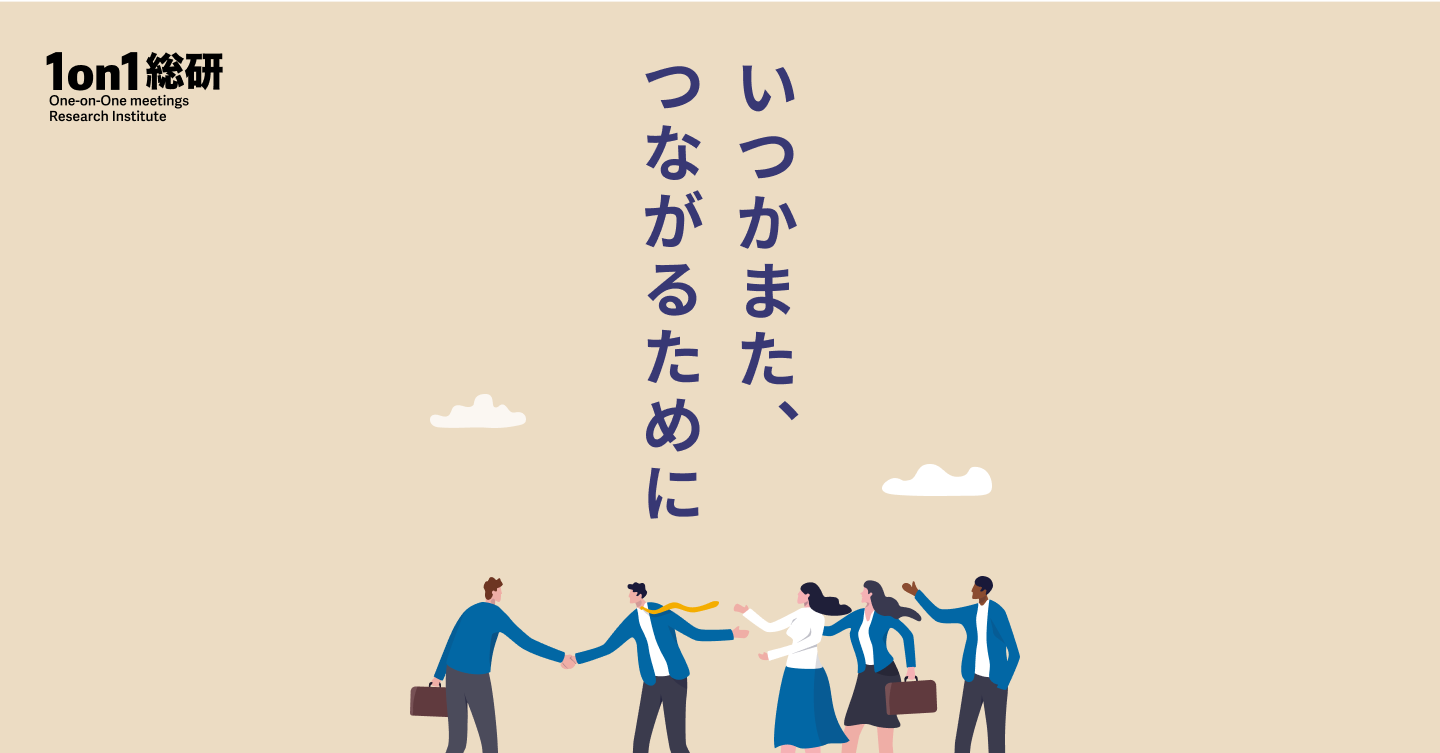人材マネジメント
その発言、地雷です。1on1を台無しにする発言と、良い対話のつくり方
「今日はどんな話ができるだろう」と意気込んだ1on1の場で、上司の発言にがっかりしたことはないでしょうか。
本記事では、部下から寄せられた“実際にあったがっかり発言”をもとに、どんな言葉が1on1を壊し、なぜすれ違いが生まれるのかを丁寧に紐解きます。そして、上司・部下の双方がすぐに実践できる「1on1を良い時間に変えるコツ」を紹介します。
1on1は、上司が評価する場でも、部下が愚痴を言う場でもありません。互いの意図を理解し合い、一緒に作り上げる“上司と部下の共同作業”です。がっかり発言の裏側には、実は改善のヒントが隠れています。明日の1on1を、今日より少しよくするための材料として、ぜひ参考にしてみてください。
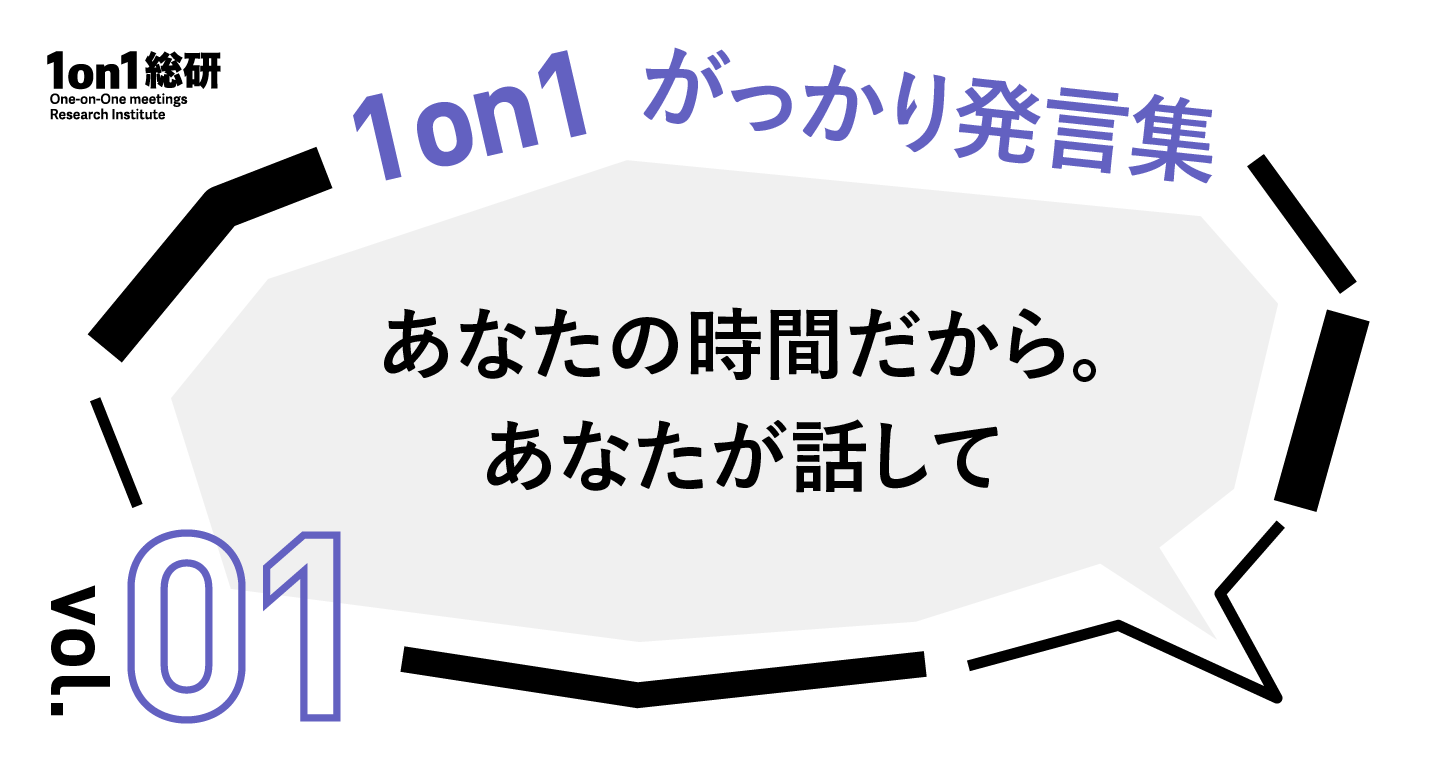
業務委託人材が真価を発揮する1on1実践法
マーケティングの高度化、複雑なプロダクト開発、AIを使った新規企画など、いまや社内人材だけではプロジェクトが回りづらい状況が広がっている。
こうした背景から、外部のプロ人材がプロジェクトに参画する機会は増えている。しかし、業務委託という雇用関係でも主従関係でもないからこそ、従来のマネジメントは通用しにくい。そのなかでエンゲージメントを高め、モチベーションを維持することは、チームの成果を大きく左右する。
この記事では、外部人材と信頼を築きながら成果を上げるためにマネジャーが取るべきアプローチを整理し、1on1の実践ヒントやチェックリストを紹介する。
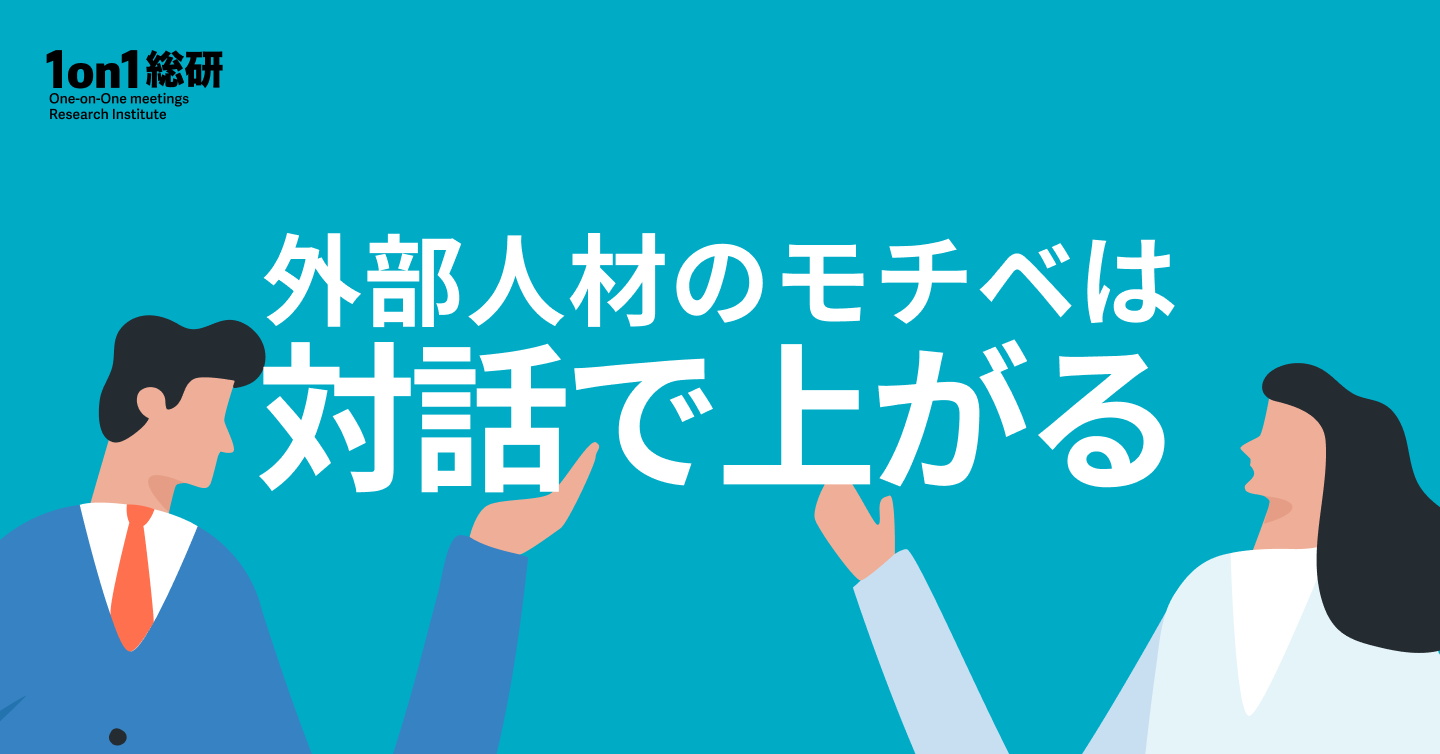
事業責任者が見落としがちな「対話」という経営課題──なぜ今すぐ着手すべきなのか
「方針は明確に伝えた」「目標は共有済みだ」「みんな理解しているはずだ」──多くの事業責任者がそう信じている一方で、現場では全く異なる現実が展開されています。
ある企業で実際に起きた事例があります。経営陣は幹部に対して事業方針を丁寧に説明したつもりでした。
しかし、試しに「理解した内容を紙に書いてもらう」という簡単なテストを実施したところ、15人の幹部のうち、社長がOKサインを出せる回答はわずか3人だけでした。
この事実は、多くの事業責任者が直面している深刻な問題を浮き彫りにします。
情報は伝達されているが、真の理解と腹落ちは起きていない。結果として、組織は同じ方向を向いているようで、実際にはバラバラの方向に進んでいるのです。
.webp)
【5分解説】ドラッカーのマネジメントとは? 原則・理論・名言まで完全理解
「現代マネジメントの父」と称され、体系的に提示したピーター・F・ドラッカー。彼の思想は、今なお世界中の経営者やビジネスパーソンに大きな影響を与え続けています。
しかし、「ドラッカーのマネジメントは難しそう……」「理論が古くて現代では通用しないのでは?」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、マネジメントの初心者や、ドラッカーの思想に初めて触れる方に向けて、「ドラッカーのマネジメント」をわかりやすく解説します。彼が定義したマネジメントの意味から、五つの基本、心に響く名言、そして現代のビジネスシーンで実践するためのステップまで、網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、ドラッカーのマネジメントがなぜ「思考の原点」として今こそ学ぶべきなのかが、きっとご理解いただけるはずです。
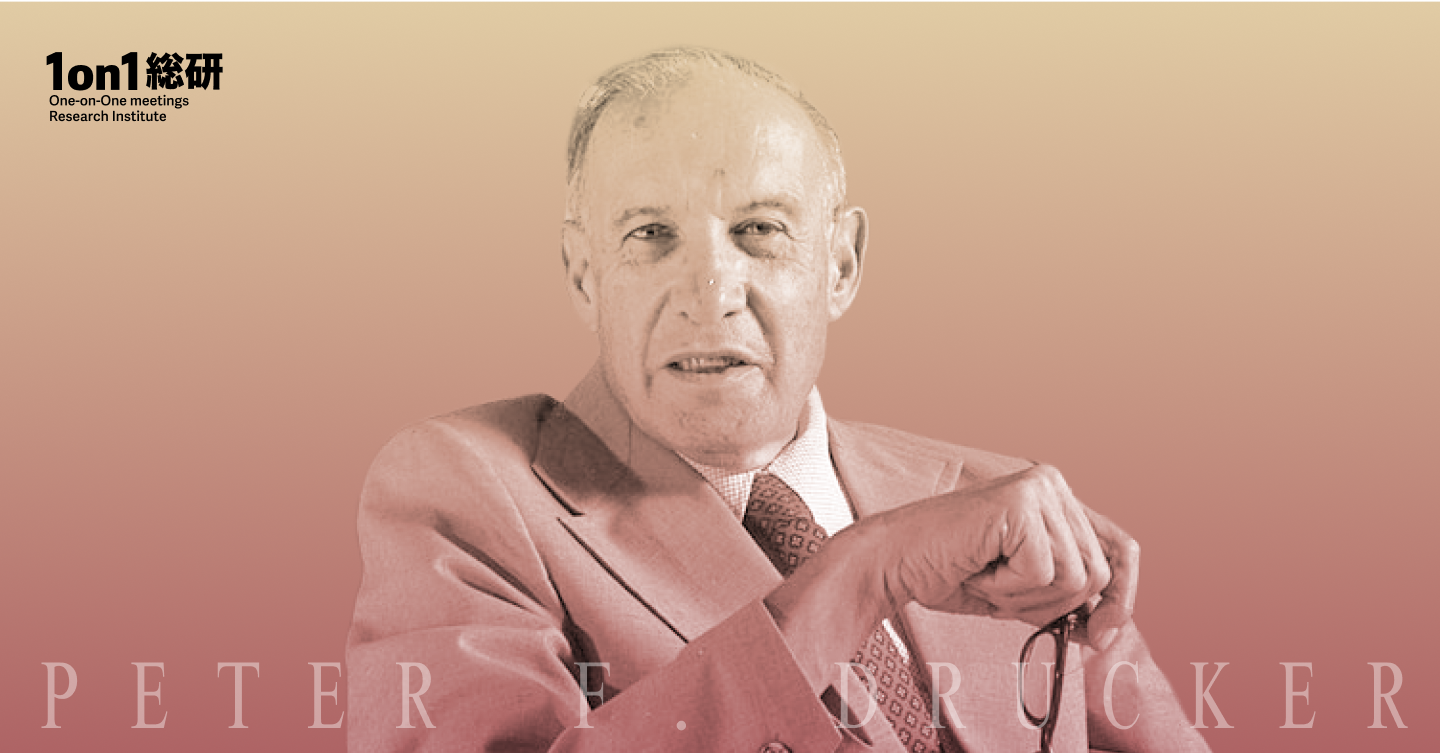
マネジャーの仕事は変えられる──マネジメントを「機能」から再設計する六つのステップ~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(後編)
現場のマネジャーが疲弊している背景には、単なる業務量の増加やスキル不足ではなく、構造的な機能不全がある──。
前編では、この問題の本質を掘り下げ、改善には「役割」の再配分ではなく「機能」からマネジメントを捉え直すことが不可欠であることを明らかにした。しかし、組織に必要な「機能」をどう見極め、どのように再設計すればよいのか。
本記事では、リクルートワークス研究所が提示する六つの実践ステップを軸に、同所主任研究員・辰巳哲子氏の知見を交えながら、構造的な変革を実現する具体的方法論を紹介する。
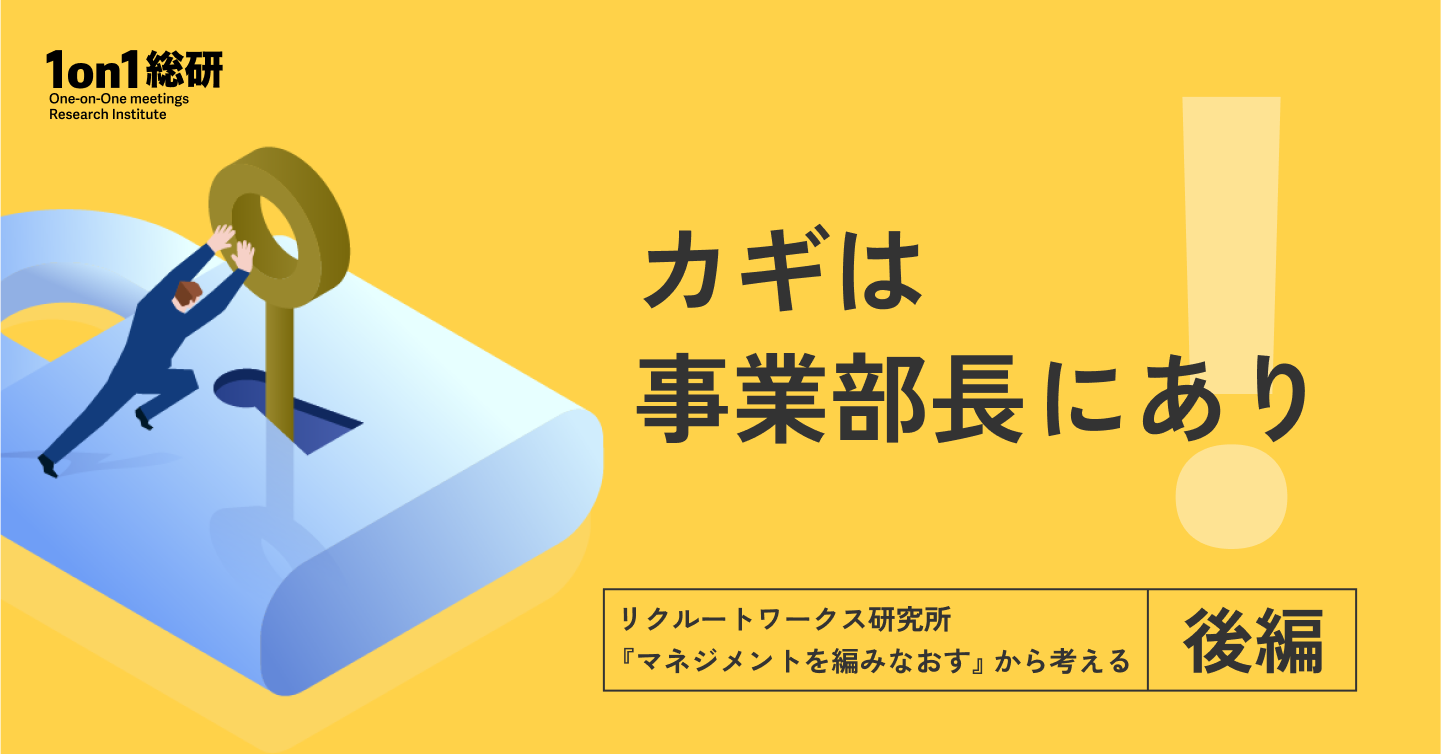

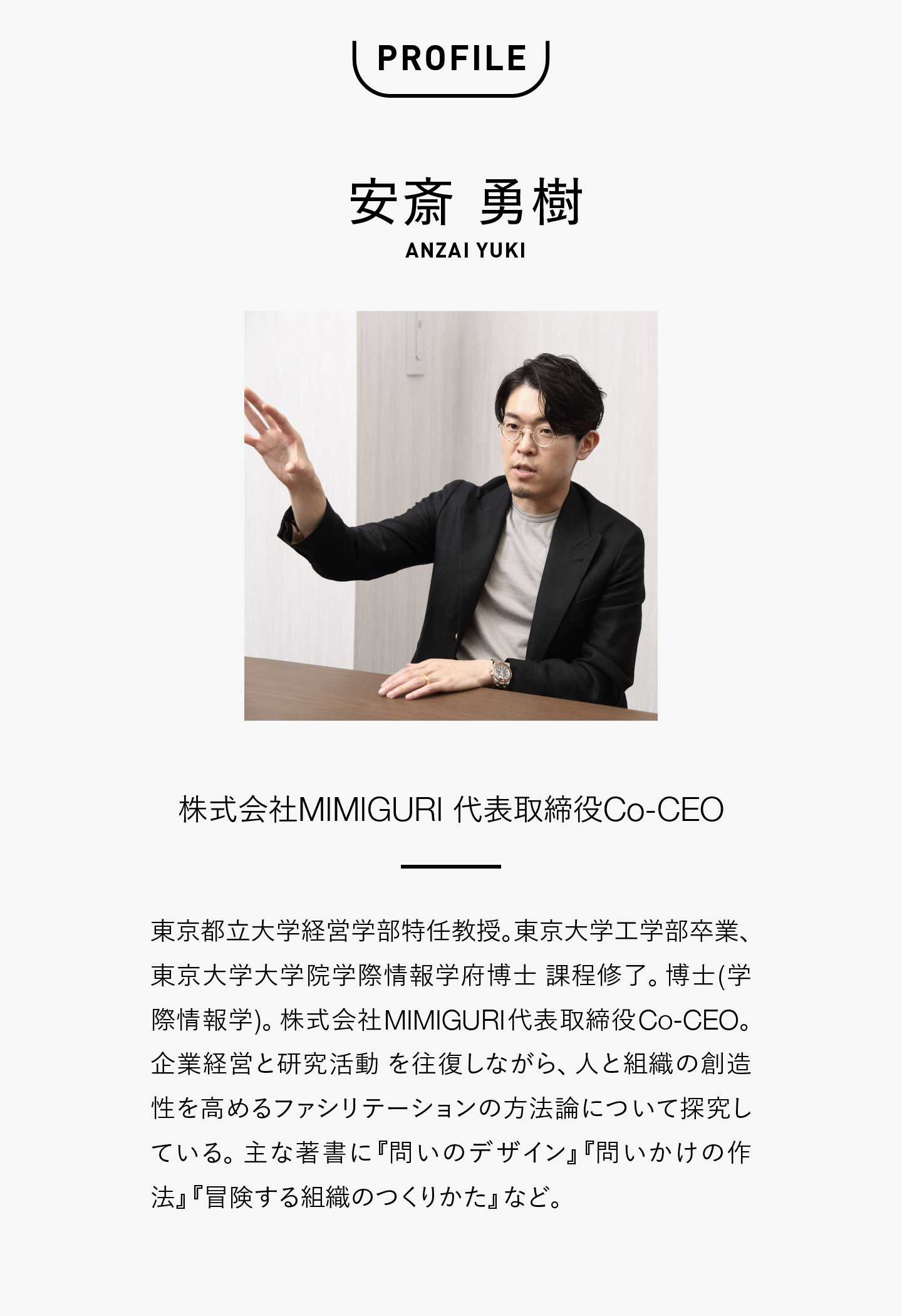
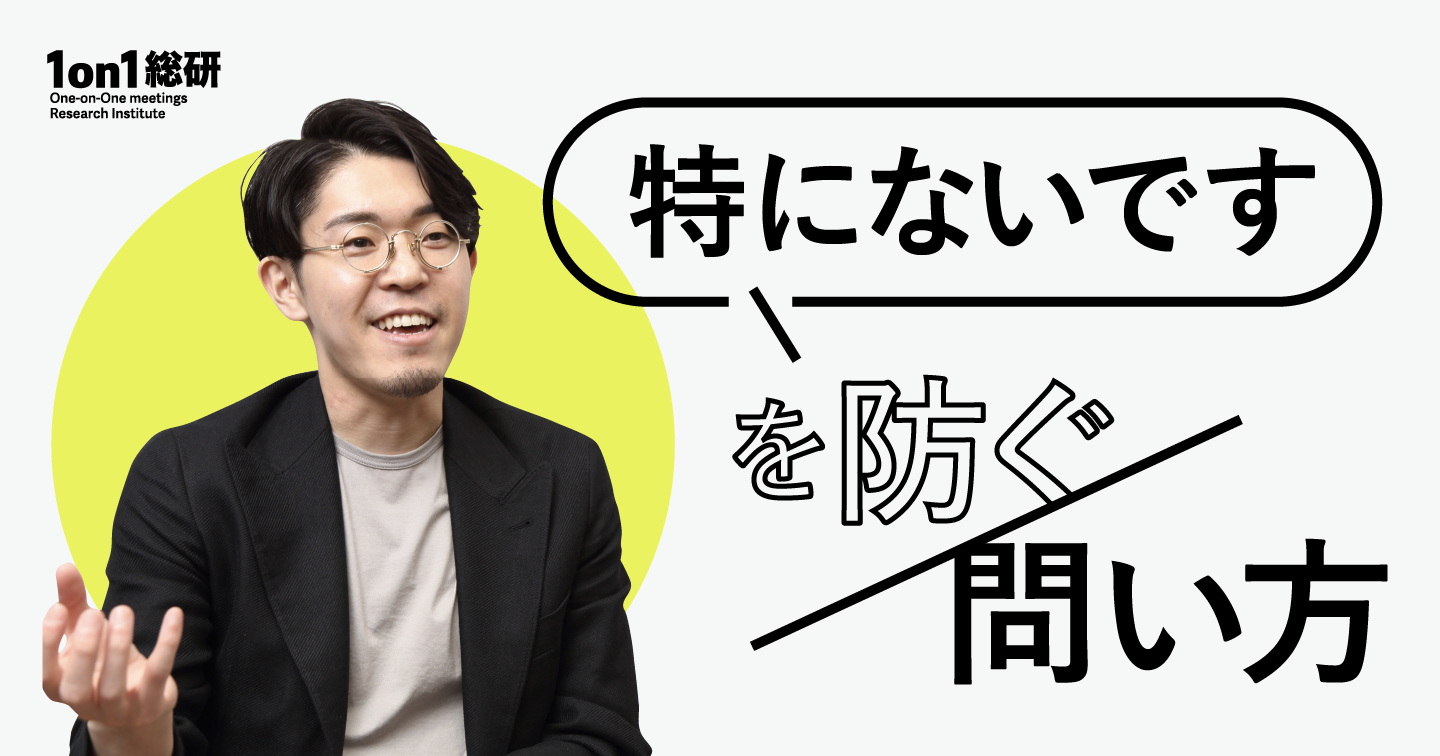
.webp)
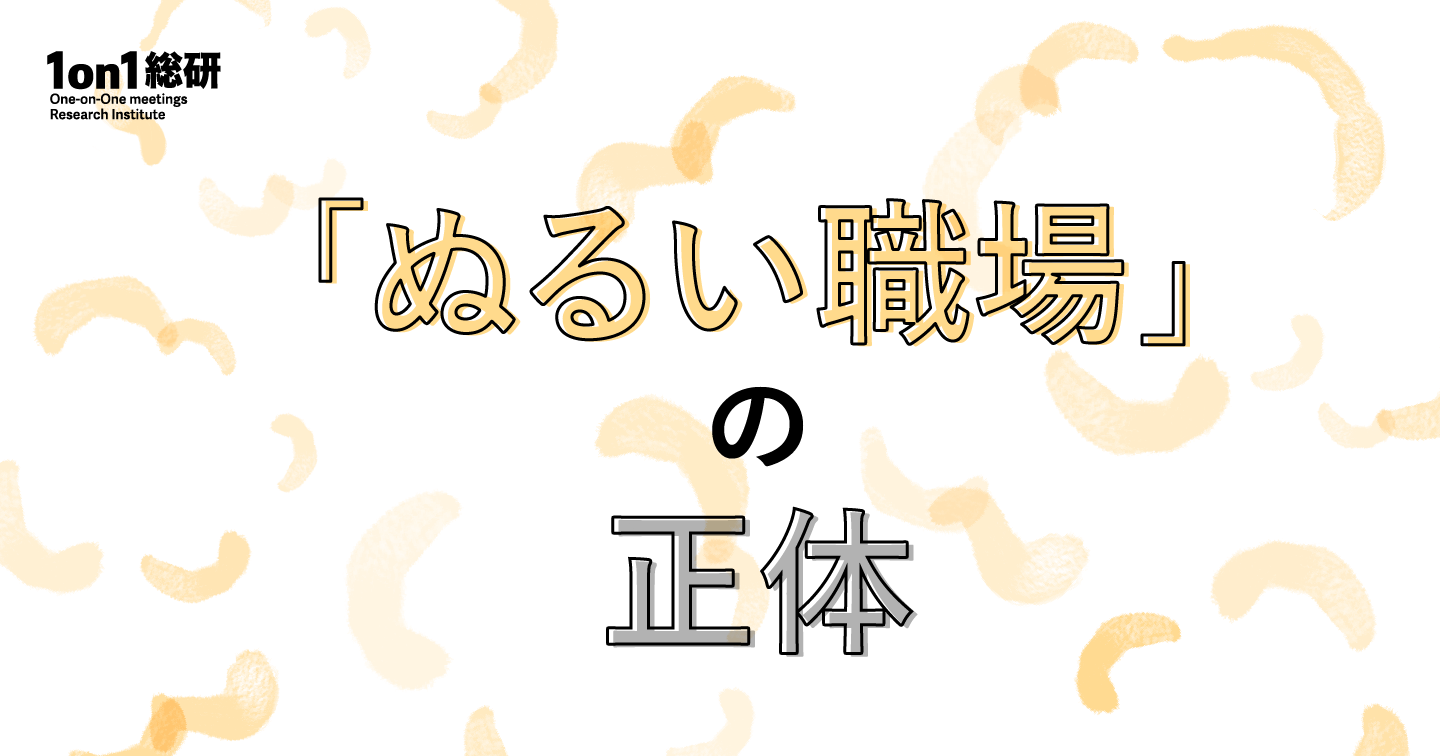
.webp)