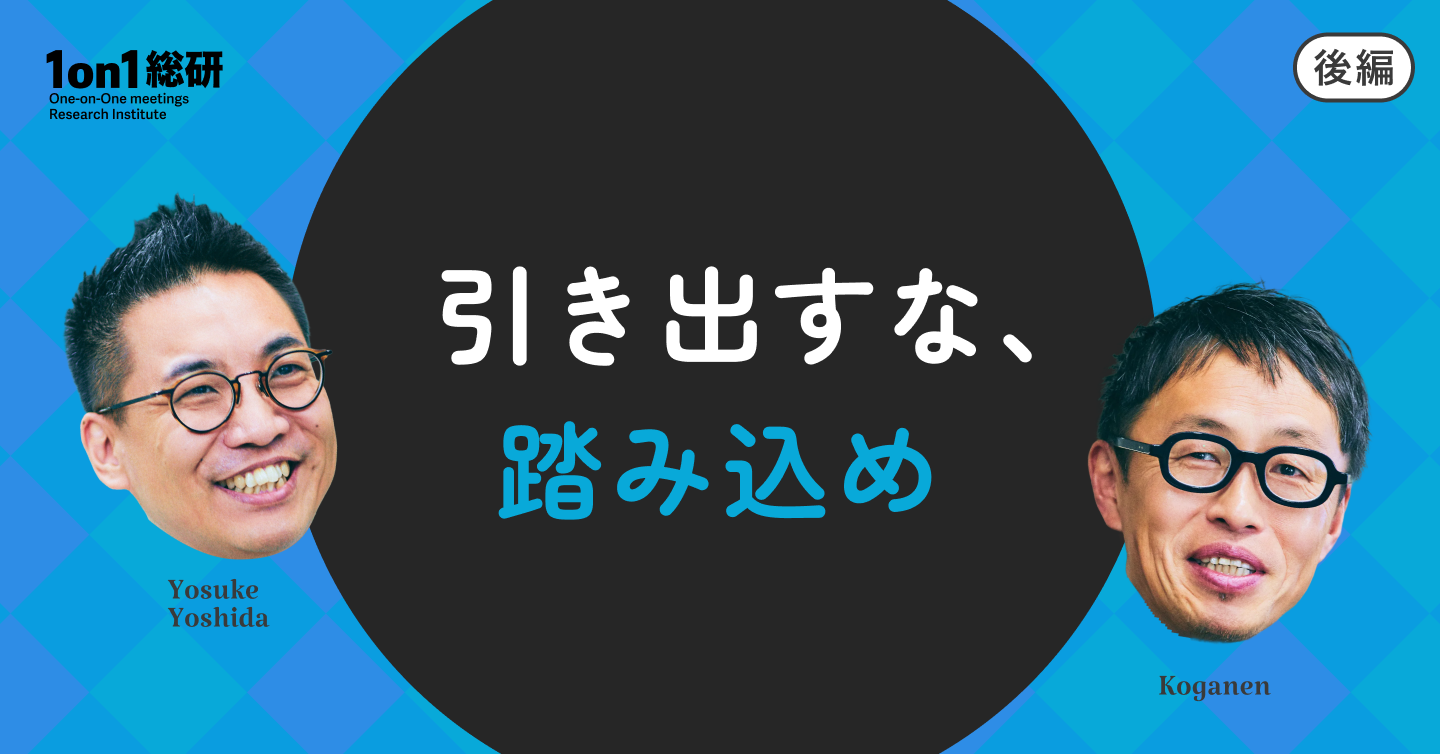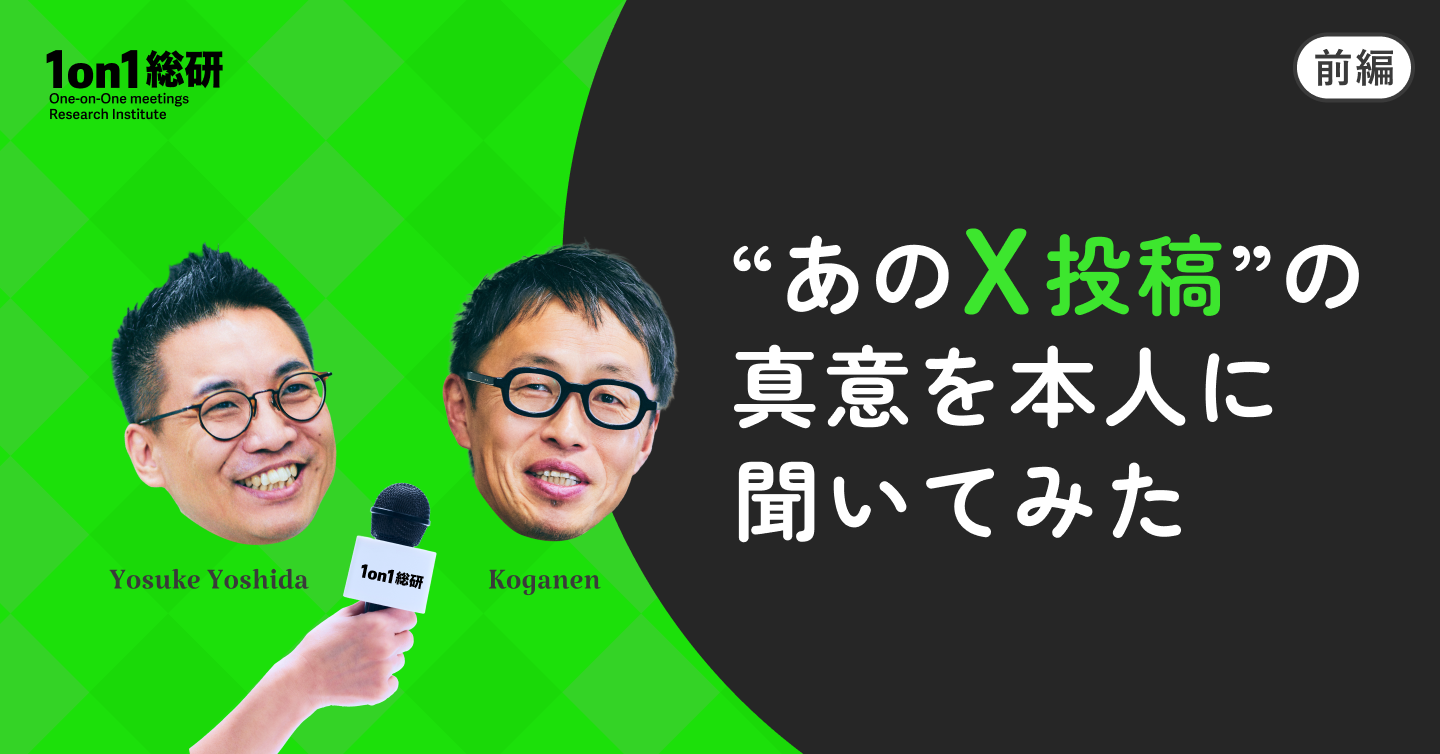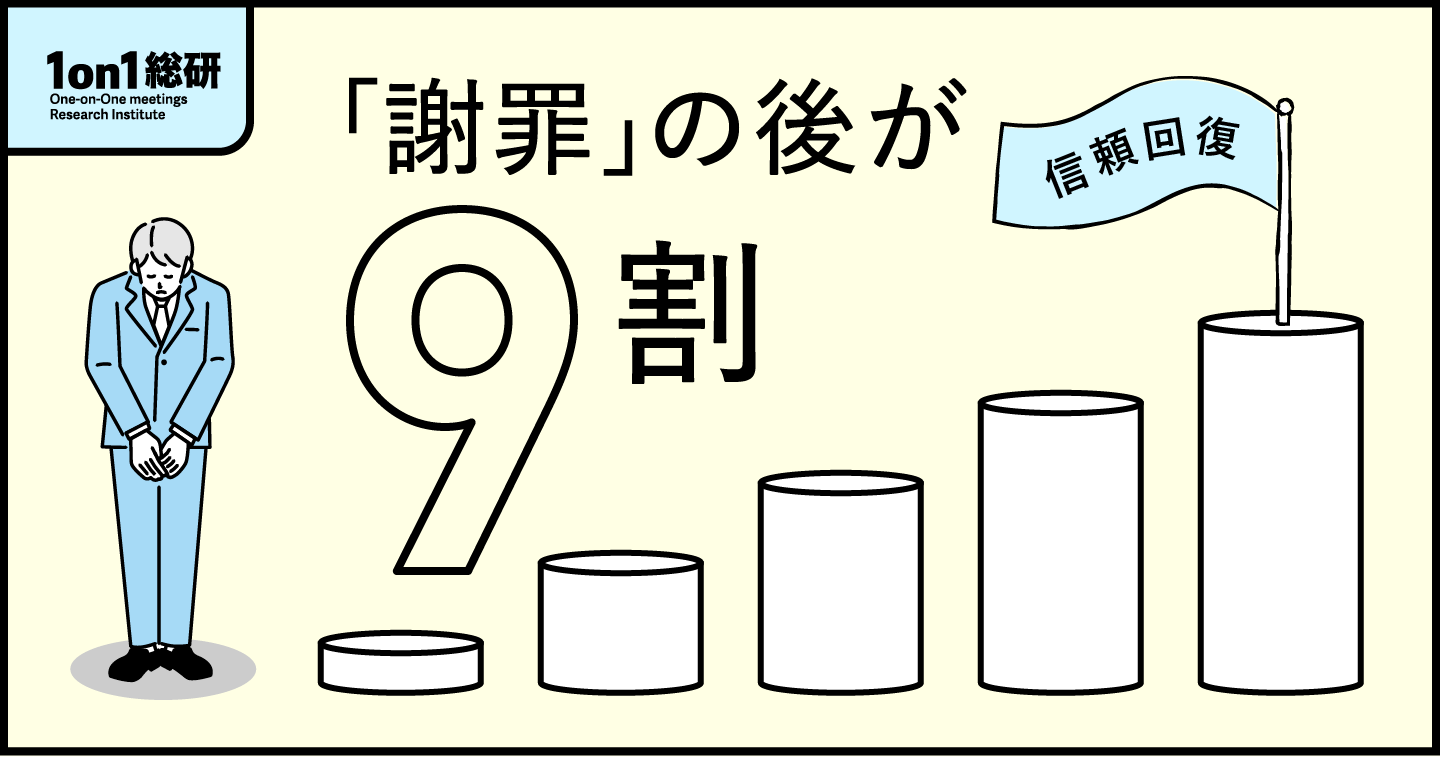基礎研究になぜ対話が欠かせないのか。キユーピーが「相互理解」を追求する真意
マヨネーズの老舗メーカーの研究所が、なぜ組織運営で脚光を浴びているのか。
キユーピーの基礎研究部門「未来創造研究所」は、徹底した対話重視の組織づくりでリンクアンドモチベーション主催の「Motivation Team Award 2025」優秀賞を受賞した。技術者集団を束ねる糀本明浩所長が語る、基礎研究に「相互理解」が不可欠な理由とは——。

コロナ禍で進めた大胆な「改組」
未来創造研究所はキユーピーグループの基礎研究組織です。10年、20年先の社会課題解決や価値創造につながる研究に従事しています。
5年前、私たちに大きな転機が訪れました。コロナ・パンデミックに加え、大規模な鳥インフルエンザが発生し、経営に大打撃を与えたのです。
想定外の出来事が続くVUCA時代。未来の社会課題により深く向き合う必要性を感じ、経営層と対話を重ねました。そして組織名を「技術ソリューション研究所」から「未来創造研究所」へ変更し、短期視点の研究組織から未来志向の組織へと転換を図りました。
しかし、メンバーには動揺が走りました。「仕事の在り方も変わってしまうのか」「私たちの立場はどうなるのか」。そんな声が聞かれるようになったのです。
組織を変革しながら、メンバーの不安をどう解消していくか。この問いがエンゲージメント向上への取り組みの出発点となりました。

エンゲージメント向上は「相互理解」から
エンゲージメント向上を進める上で、私が最も大切にしているのは「相互理解」です。
ある企業にご協力いただき所長と部長が価値観を理解し合うプログラムを実施した際のことです。何十年も同じ会社にいて、しょっちゅう飲みに行っている間柄にもかかわらず、お互いに「こんな価値観だったの?」「週末はそんなことを?」という発見ばかりでした。
知っているつもりで、実は知らなかった――。この光景を見て、組織全体はもちろんのこと、一つひとつのチーム単位でもメンバーを理解できていない可能性があると直感し、対話の仕組みづくりが急務だと感じました。
技術系組織では、この相互理解がより重要になると考えます。一つの技術領域に複数の専門分野が存在し、リーダーといえども全てに精通しているわけではないからです。
「発酵」を例に取ってみましょう。この領域だけでも専門性の幅は極めて広く、リーダーがある分野に詳しくても、別の分野ではメンバーの方が圧倒的な知識を持っているケースは珍しくありません。

こうした構造の中で、リーダーシップに悩むマネジャーは少なくありません。一方、メンバーの側も「なぜリーダーは自分の技術を理解してくれないのか」と感じているかもしれません。だからこそ、双方が密な対話を通じて互いを深く理解する場が不可欠だと考えました。
1on1で「対話密度」を高める
相互理解を深めるため、私が重視しているのは「対話密度」という概念です。頻度だけでなく、価値観や考えを共有し合える深いコミュニケーションこそが組織の力を高めるのではないかと思います。
4年前から始めた1on1は、この実践の場です。業務の話に加え、普段なかなか話せない内容も含めて対話できる貴重な時間。定期的に1対1で向き合うからこそ、相互理解が格段に深まります。
技術系組織では、1on1はメンバーのための時間であると同時に、リーダーの成長機会でもあるように感じます。対話を通じてリーダー自身が役割を見つめ直し、成長していくのです。
今年からは1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入しました。施策の効果を定量的に把握したかったからです。既存のエンゲージメント測定システムと連携し、エンゲージメントスコアと1on1スコアの相関分析を進めています。
Kakeaiによって対話の記録が効率化されましたが、個々の対話内容は私に報告しないルールにしています。所長が詳細を把握すると、メンバーが忖度してしまう恐れがあるからです。心理的安全性を何より重視したいと考えています。
プロセスを丁寧に進めることの価値
1on1以外にも対話を深める機会を設けています。その際に重視しているのは、プロセスの工夫です。
例えば、研究開発本部主催でメンバーが経営層にプレゼンする機会があります。こうした対話の場を有意義にするには入念な事前準備が欠かせません。そこでリーダーが「橋渡し役」を担います。

具体的には、リーダーがメンバーと事前対話を重ね、経営層の考えをメンバーにわかりやすく伝える一方で、メンバーの意見を丁寧にヒアリングし、その主張が経営層に届きやすい形に資料を練り上げていきます。
このプロセスには相当な時間をかけていますが、丁寧に進めることでメンバーと経営層の真の相互理解が生まれ、経営層からの共感や応援を得られるのではないかと思います。同時に、この事前準備自体がメンバーとリーダーの深い対話の場にもなっていると考えます。
評価プロセスにも「対話」を重視
人事考課でも同様の考え方を貫くよう心がけています。
基礎研究は成果が出るまでに10年かかることもあり、適切な評価は困難です。評価への不満はメンバーのモチベーション低下や離職につながりかねません。
そこで考課プロセスを非常に丁寧に行い、相互理解を深めることに重点を置くようにしています。
具体的には二段階で進めます。
第一段階では各部のチームリーダー全員が集まり、自分のチームメンバーはもちろん、他チームのメンバーについても一人ひとりのコンピテンシーを評価し、議論を重ねながら部内でのフラットな考課を決定します。
第二段階では三つの部の部長と私が参加し、改めて横並びで評価を行います。最も重要な考課後のフィードバックも、部長とチームリーダーの双方から実施しています。
こうした対話を重ねるプロセスを大切にしているからこそ、最終的な考課への満足度は全員満点ではありませんが、納得感は得られているのではないかと考えています。
「対話密度」こそ未来創造の鍵
私が対話を通じて目指していきたいのは、メンバー一人ひとりが「自分ブランド」を高められる組織です。技術系であれば「専門性×人としての魅力」。高い専門性を持ちながら、周りが一緒に研究したくなる人材の集合体でありたいと考えています。

価値観も専門性も多様な人たちが「未来に向かって新たな価値を生み出していこう」と本気になったとき、計り知れない力が生まれるのではないでしょうか。
食を取り巻く社会課題の解決には産学官との協働が不可欠であり、ここでも対話が重要な役割を果たすと思います。対話こそが社会課題解決につながる力を秘めている——私はそのように考えています。
コロナ禍で進めた大胆な「改組」
未来創造研究所はキユーピーグループの基礎研究組織です。10年、20年先の社会課題解決や価値創造につながる研究に従事しています。
5年前、私たちに大きな転機が訪れました。コロナ・パンデミックに加え、大規模な鳥インフルエンザが発生し、経営に大打撃を与えたのです。
想定外の出来事が続くVUCA時代。未来の社会課題により深く向き合う必要性を感じ、経営層と対話を重ねました。そして組織名を「技術ソリューション研究所」から「未来創造研究所」へ変更し、短期視点の研究組織から未来志向の組織へと転換を図りました。
しかし、メンバーには動揺が走りました。「仕事の在り方も変わってしまうのか」「私たちの立場はどうなるのか」。そんな声が聞かれるようになったのです。
組織を変革しながら、メンバーの不安をどう解消していくか。この問いがエンゲージメント向上への取り組みの出発点となりました。

エンゲージメント向上は「相互理解」から
エンゲージメント向上を進める上で、私が最も大切にしているのは「相互理解」です。
ある企業にご協力いただき所長と部長が価値観を理解し合うプログラムを実施した際のことです。何十年も同じ会社にいて、しょっちゅう飲みに行っている間柄にもかかわらず、お互いに「こんな価値観だったの?」「週末はそんなことを?」という発見ばかりでした。
知っているつもりで、実は知らなかった――。この光景を見て、組織全体はもちろんのこと、一つひとつのチーム単位でもメンバーを理解できていない可能性があると直感し、対話の仕組みづくりが急務だと感じました。
技術系組織では、この相互理解がより重要になると考えます。一つの技術領域に複数の専門分野が存在し、リーダーといえども全てに精通しているわけではないからです。
「発酵」を例に取ってみましょう。この領域だけでも専門性の幅は極めて広く、リーダーがある分野に詳しくても、別の分野ではメンバーの方が圧倒的な知識を持っているケースは珍しくありません。

こうした構造の中で、リーダーシップに悩むマネジャーは少なくありません。一方、メンバーの側も「なぜリーダーは自分の技術を理解してくれないのか」と感じているかもしれません。だからこそ、双方が密な対話を通じて互いを深く理解する場が不可欠だと考えました。
1on1で「対話密度」を高める
相互理解を深めるため、私が重視しているのは「対話密度」という概念です。頻度だけでなく、価値観や考えを共有し合える深いコミュニケーションこそが組織の力を高めるのではないかと思います。
4年前から始めた1on1は、この実践の場です。業務の話に加え、普段なかなか話せない内容も含めて対話できる貴重な時間。定期的に1対1で向き合うからこそ、相互理解が格段に深まります。
技術系組織では、1on1はメンバーのための時間であると同時に、リーダーの成長機会でもあるように感じます。対話を通じてリーダー自身が役割を見つめ直し、成長していくのです。
今年からは1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入しました。施策の効果を定量的に把握したかったからです。既存のエンゲージメント測定システムと連携し、エンゲージメントスコアと1on1スコアの相関分析を進めています。
Kakeaiによって対話の記録が効率化されましたが、個々の対話内容は私に報告しないルールにしています。所長が詳細を把握すると、メンバーが忖度してしまう恐れがあるからです。心理的安全性を何より重視したいと考えています。
プロセスを丁寧に進めることの価値
1on1以外にも対話を深める機会を設けています。その際に重視しているのは、プロセスの工夫です。
例えば、研究開発本部主催でメンバーが経営層にプレゼンする機会があります。こうした対話の場を有意義にするには入念な事前準備が欠かせません。そこでリーダーが「橋渡し役」を担います。

具体的には、リーダーがメンバーと事前対話を重ね、経営層の考えをメンバーにわかりやすく伝える一方で、メンバーの意見を丁寧にヒアリングし、その主張が経営層に届きやすい形に資料を練り上げていきます。
このプロセスには相当な時間をかけていますが、丁寧に進めることでメンバーと経営層の真の相互理解が生まれ、経営層からの共感や応援を得られるのではないかと思います。同時に、この事前準備自体がメンバーとリーダーの深い対話の場にもなっていると考えます。
評価プロセスにも「対話」を重視
人事考課でも同様の考え方を貫くよう心がけています。
基礎研究は成果が出るまでに10年かかることもあり、適切な評価は困難です。評価への不満はメンバーのモチベーション低下や離職につながりかねません。
そこで考課プロセスを非常に丁寧に行い、相互理解を深めることに重点を置くようにしています。
具体的には二段階で進めます。
第一段階では各部のチームリーダー全員が集まり、自分のチームメンバーはもちろん、他チームのメンバーについても一人ひとりのコンピテンシーを評価し、議論を重ねながら部内でのフラットな考課を決定します。
第二段階では三つの部の部長と私が参加し、改めて横並びで評価を行います。最も重要な考課後のフィードバックも、部長とチームリーダーの双方から実施しています。
こうした対話を重ねるプロセスを大切にしているからこそ、最終的な考課への満足度は全員満点ではありませんが、納得感は得られているのではないかと考えています。
「対話密度」こそ未来創造の鍵
私が対話を通じて目指していきたいのは、メンバー一人ひとりが「自分ブランド」を高められる組織です。技術系であれば「専門性×人としての魅力」。高い専門性を持ちながら、周りが一緒に研究したくなる人材の集合体でありたいと考えています。

価値観も専門性も多様な人たちが「未来に向かって新たな価値を生み出していこう」と本気になったとき、計り知れない力が生まれるのではないでしょうか。
食を取り巻く社会課題の解決には産学官との協働が不可欠であり、ここでも対話が重要な役割を果たすと思います。対話こそが社会課題解決につながる力を秘めている——私はそのように考えています。