
上司より詳しい部下をどう率いるか。対話が解決する「基礎研究組織の難題」
2023年、キユーピーが「アレルギー低減卵」の研究成果を発表すると、研究所には感謝の手紙や応援の声が寄せられるなど異例の反響となった。すぐには事業化が困難な基礎研究でも、社会課題への取り組みが人々の共感を呼び、企業価値を高める可能性があることを示した出来事である。
この研究成果を生み出したキユーピーの「未来創造研究所」では、対話を軸にした組織づくりで高い従業員エンゲージメントを実現している。研究者たちの創造性を引き出す取り組みの実態に迫った。(※肩書きは2025年6月時点)
基礎研究組織が抱える独特な課題

キユーピーの未来創造研究所は、10年、20年先を見据えた基礎研究を担う組織だ。三つの部の下に九つの専門チームが配置され、各チームには4、5名の研究者が所属している。扱う研究テーマは一般生活者に身近なものから、月面生活を見据えた研究開発まで多岐にわたる。
各メンバーは常に新しい研究テーマを探している。アイデアの豊富さが生命線だ。機能素材研究部のチームリーダー児玉大介氏は、「コグニティブダイバーシティ(認知の多様性)が競争力の源泉」と語る。
だが、多様性を育むのは簡単ではない。その土壌づくりも含め、児玉氏は4年前に組織的な1on1を開始した。
「『何を言っても受け止めてもらえる』という感覚を、私は"意見効力感"と呼んでいます。全てのメンバーがその感覚を持つことが多様性の出発点だと考えています。ただ、意見効力感は心理的安全性がなければ芽生えません。そこで1on1という『何を話してもいい場』を設け、心理的安全性を育もうと考えました」(児玉氏)
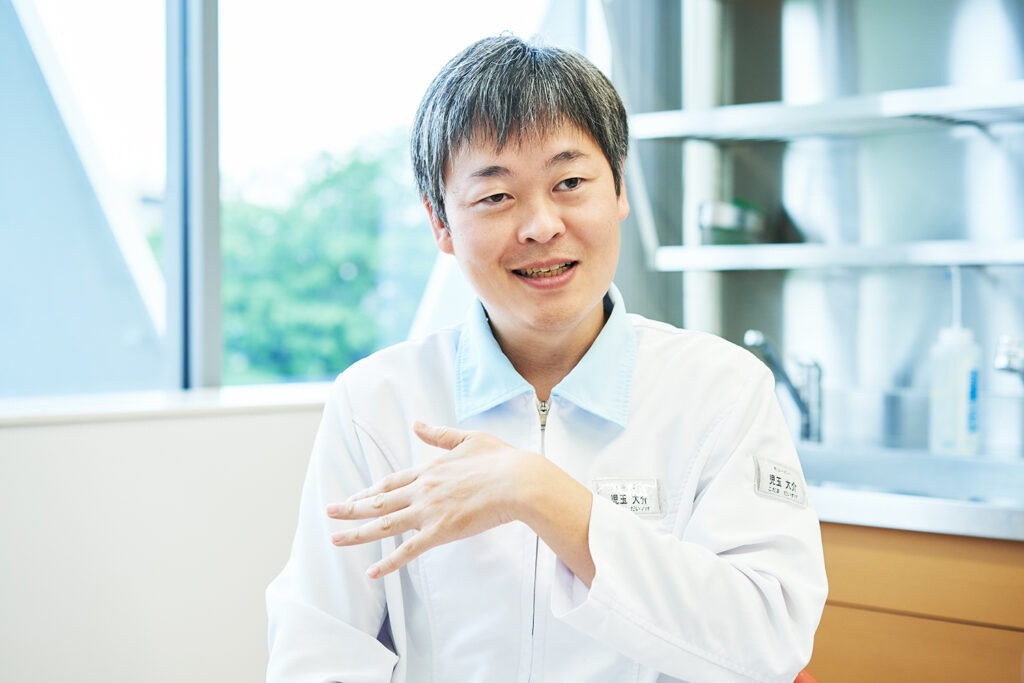
児玉氏は現在、週1回30分、チームメンバーと1on1を実施している。高頻度の背景には「量」へのこだわりがある。
「日常的な対話の積み重ねの中で生まれる価値を大切にしています」(児玉氏)
専門性の壁を越える工夫
未来創造研究所は従業員エンゲージメントが高い組織だ。リンクアンドモチベーション主催の「Motivation Team Award 2025」では優秀賞を受賞。所長の糀本明浩氏は「対話」を軸にした相互理解を長らく推進している。
その背景にあるのは、基礎研究組織特有の課題だ。
技術系組織では、管理職に昇進すると自分の専門外の分野を含むチームの管理を任されることが珍しくない。その結果、メンバーの方が専門知識で上回る状態が生じ、双方のコミュニケーションを難しくさせている。
2年半前に本研究所に異動してきたヒューマンヘルス研究部のチームリーダー竹田優美氏も同様の立場にあった。
かつてはメンバーの実務を助けるプレイングマネジャーだったが、ここでは通用しない。専門が大きく異なるからだ。
「着任当時は自分にしかできない役割を常に問い続けていました」。そう語る竹田氏が最初に取り組んだのは、チーム全体でのワークショップだった。チームのミッション・ビジョン・バリューを皆で考え、相互理解を深めるワークショップを企画した。
「専門性が高く、同僚がどういうプロセスでどのようなテーマに取り組んでいるのかがわかりにくい——それが当時のチーム状況です。そこで、私も含め、メンバー全員が互いを知ることから始めました」(竹田氏)
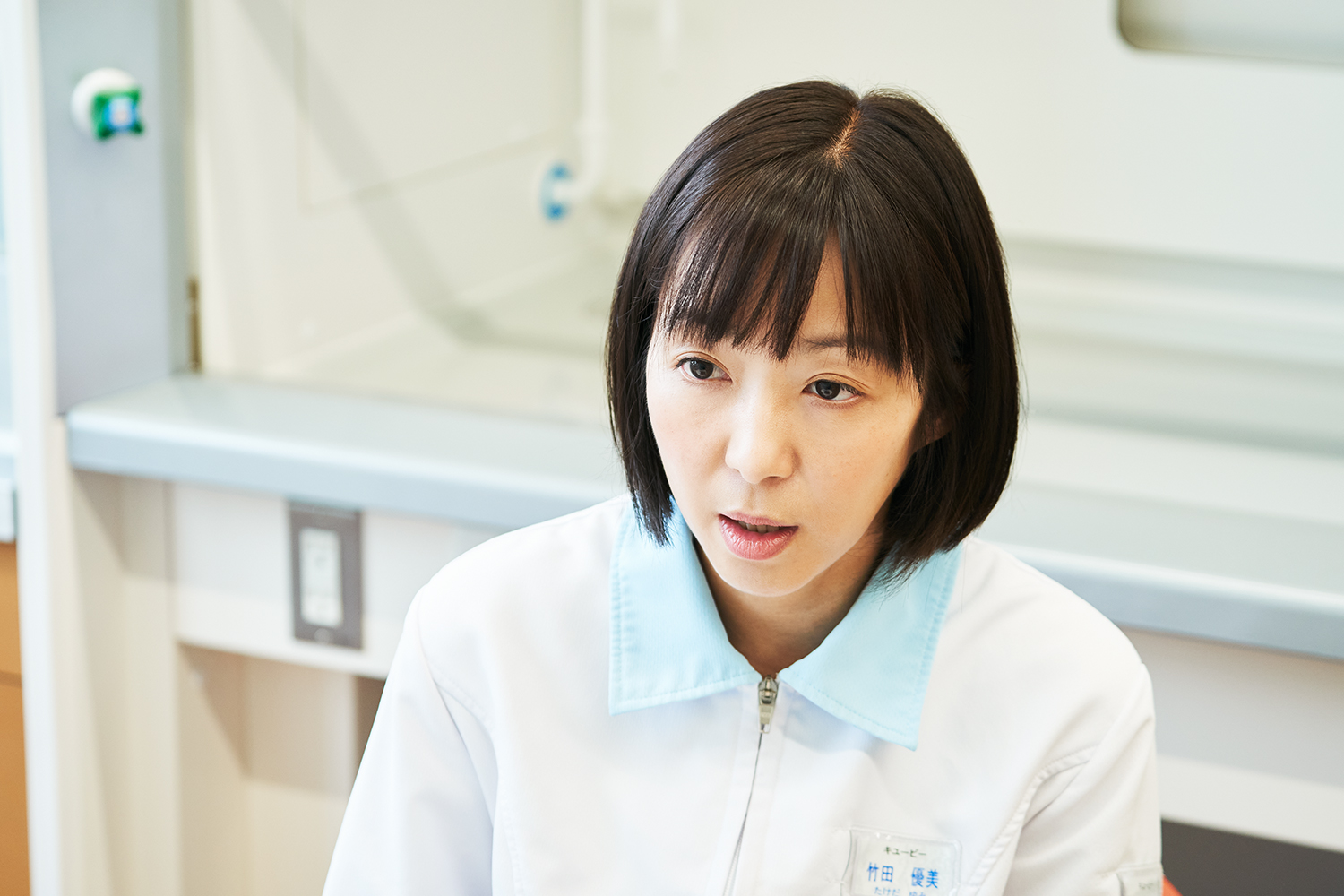
基礎研究の世界では、専門性の異なるメンバー同士が連携し、時には社外パートナーとも協働する。竹田氏のワークショップはその基盤づくりとも言える。
「ワークを通じて『この人はこの分野のエキスパート』『自分はこの領域で専門性を磨きたい』といった認識が共有され、専門性を尊重し合う文化とプロフェッショナル意識が自然と育まれていきました」(竹田氏)
理解を深めたのはメンバー同士だけではない。竹田氏にとっても「専門性の逆転現象」を乗り越える一歩となった。
ツールが変えた対話の質
未来創造研究所では相互理解を深める施策の一つとして1on1が浸透している。だが、児玉氏は4年間続けてきた1on1に課題を感じていた。
「対話の記録に手間がかかり、もっと効率化できないかと感じていました」(児玉氏)
そこで今年から1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入した。対話の内容や実施回数が自動で可視化され、記録の煩雑さから解放された。
竹田氏が最も実感している変化は、メンバーからのフィードバックが見える化されたことだ。
「自分の相談対応の得意・不得意が可視化され、改善点が明確になりました」(竹田氏)

ツールは対話の質も向上させた。メンバーがマネジャーに期待する対応を事前に選択する仕組みになったためだ。
「これまでの1on1では、メンバーが『ちょっと聞いてほしい』程度のつもりで話したことを、リーダーが大ごとに捉えてしまうことがありました」(竹田氏)
今は対話の目的や到達点について、お互いが共通認識を持って始められているという。
対話が深まり見えてきたもの
1on1の定着により、メンバーから深い相談が寄せられるようになった。竹田氏が1on1で多く聞くのは、メンバーの専門性への不安だ。
「私から見れば専門性の高いメンバーばかりですが、本人たちは『自分の専門性はまだ足りていない』と思っていることが多くあります」(竹田氏)
長年同じ環境で働いてきた研究者たちは、社内では"専門家"として一目置かれていても、外の世界で通用するかという不安を抱えている。
竹田氏はメンバーの自信向上を図るため、共同研究や技術相談で大学教授と面談する際、自分ではなくメンバーを前面に押し出すようにした。外部での経験を積ませることで、専門性への不安を解消する狙いだ。
児玉氏のチームでも、長期的なキャリア相談が行われている。メンバーから社会人ドクターとして博士号を取得したいという相談を受けた際、会社に所属しながら取得する道筋を1on1で継続的に話し合っている。
メンバーが実感する変化
昨年10月にグループ会社から異動し、児玉氏のチームに加入した漆畑亘氏は、1on1の効果を身をもって体験している。基礎研究の世界では、研究者が自主的にテーマを設定する姿勢が求められるが、アイデアの段階で相談できる場は意外に少ない。
「その点、1on1では具体化する前のアイデアでも気軽に相談できます。上司は否定せず『どうすれば実現できるか』を一緒に考えてくれますから」(漆畑氏)
児玉氏は「メンバーが1on1で語る『こんなことをやってみたい』という思いが新たな研究テーマに発展することもある」と説明する。
現在、機能素材研究部では40を超える研究テーマを15人で推進している。2040年の月面生活を想定した宇宙食開発のような壮大なテーマも、こうした対話から生まれたという。
漆畑氏にとって、1on1は研究を前進させる重要な場となっている。
「自分の中では答えが出なくて難しいと思っていたことも、アドバイスをもらって次に何をすべきかがクリアになり、進めやすくなりました」(漆畑氏)
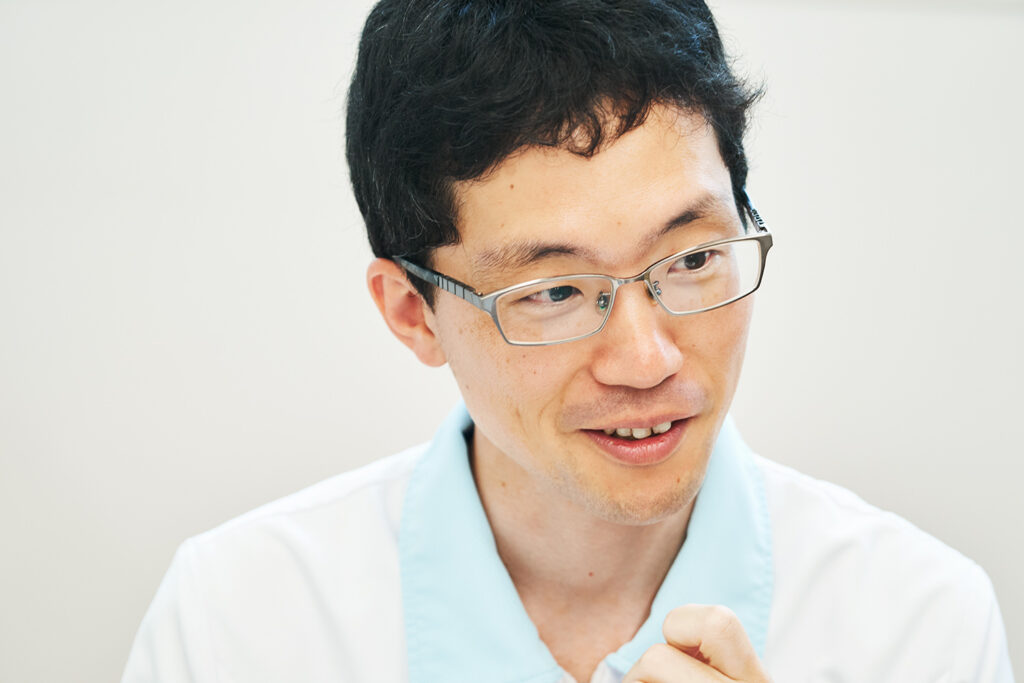
もっとも、漆畑氏は最初からこのような対話ができていたわけではない。
前職時代の1on1は「考課面談の延長のように感じていて、プライベートや価値観等も含めて本音の話しをする機会が少なかった」。
異動当初も「しばらく本音を話せていなかった」が、上司が親身に話を聞いてくれることが分かり、週1回という頻度も相まって徐々に信頼関係が築かれていったという。
企業価値向上への道筋と今後の展望
未来創造研究所では各チームが自主的なルールの下に1on1を運用している。その成果をどう測るのか。
竹田氏は「1on1に関する明確なKPIは設定していません」と話す。
児玉氏も同様の考えだ。「1on1そのものの成果を追うより、事業貢献など、より先の成果への貢献を意識すべきだと思います」(児玉氏)
児玉氏が重視するのは、研究成果が企業価値に与える影響だ。実際、2023年のアレルギー関連研究の発表後には、生活者からの反響が寄せられると同時に、自社の株価も上昇した。
「本研究の発表だけが株価上昇の要因ではなかったと思いますが、企業価値向上への貢献もあると考えられます」と児玉氏は振り返る。

だが、基礎研究者が経営インパクトを意識することは少ない。基礎研究は即座に商品やサービスに直結しないため、企業価値への貢献を実感しにくいからだ。この距離を縮める役割を1on1が担っている。
「1on1の場で“あなたの研究テーマはどう『愛は食卓にある。』につながっていますか? ”など、抽象的な質問をメンバーに問いかけることも心がけています。当社のコーポレートメッセージと自身の研究を結びつけて、企業価値向上への貢献を意識してもらうためです。メンバー自身が研究の価値を語れる、そんな組織でありたいと思っています」(児玉氏)
一つの問いかけがメンバーの意識を変え、新たな価値創造へとつながっていく。心理的安全性の構築から始まった1on1は、4年の実践を経て研究と経営をつなぐ架け橋に。組織の成長を支える確かな基盤が築かれた。
基礎研究組織が抱える独特な課題

キユーピーの未来創造研究所は、10年、20年先を見据えた基礎研究を担う組織だ。三つの部の下に九つの専門チームが配置され、各チームには4、5名の研究者が所属している。扱う研究テーマは一般生活者に身近なものから、月面生活を見据えた研究開発まで多岐にわたる。
各メンバーは常に新しい研究テーマを探している。アイデアの豊富さが生命線だ。機能素材研究部のチームリーダー児玉大介氏は、「コグニティブダイバーシティ(認知の多様性)が競争力の源泉」と語る。
だが、多様性を育むのは簡単ではない。その土壌づくりも含め、児玉氏は4年前に組織的な1on1を開始した。
「『何を言っても受け止めてもらえる』という感覚を、私は"意見効力感"と呼んでいます。全てのメンバーがその感覚を持つことが多様性の出発点だと考えています。ただ、意見効力感は心理的安全性がなければ芽生えません。そこで1on1という『何を話してもいい場』を設け、心理的安全性を育もうと考えました」(児玉氏)
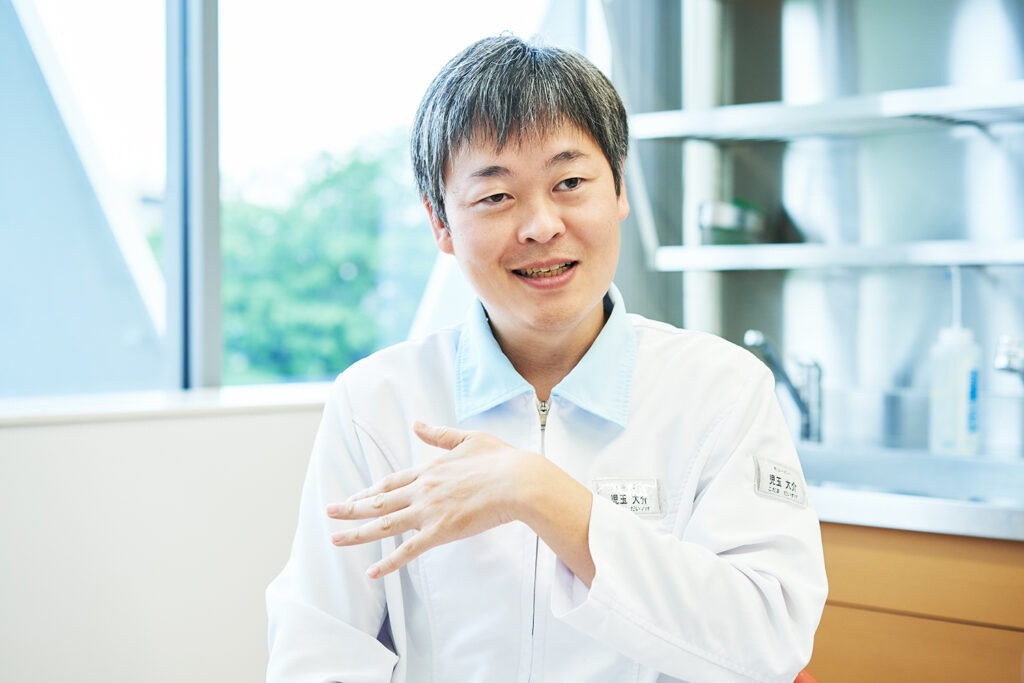
児玉氏は現在、週1回30分、チームメンバーと1on1を実施している。高頻度の背景には「量」へのこだわりがある。
「日常的な対話の積み重ねの中で生まれる価値を大切にしています」(児玉氏)
専門性の壁を越える工夫
未来創造研究所は従業員エンゲージメントが高い組織だ。リンクアンドモチベーション主催の「Motivation Team Award 2025」では優秀賞を受賞。所長の糀本明浩氏は「対話」を軸にした相互理解を長らく推進している。
その背景にあるのは、基礎研究組織特有の課題だ。
技術系組織では、管理職に昇進すると自分の専門外の分野を含むチームの管理を任されることが珍しくない。その結果、メンバーの方が専門知識で上回る状態が生じ、双方のコミュニケーションを難しくさせている。
2年半前に本研究所に異動してきたヒューマンヘルス研究部のチームリーダー竹田優美氏も同様の立場にあった。
かつてはメンバーの実務を助けるプレイングマネジャーだったが、ここでは通用しない。専門が大きく異なるからだ。
「着任当時は自分にしかできない役割を常に問い続けていました」。そう語る竹田氏が最初に取り組んだのは、チーム全体でのワークショップだった。チームのミッション・ビジョン・バリューを皆で考え、相互理解を深めるワークショップを企画した。
「専門性が高く、同僚がどういうプロセスでどのようなテーマに取り組んでいるのかがわかりにくい——それが当時のチーム状況です。そこで、私も含め、メンバー全員が互いを知ることから始めました」(竹田氏)
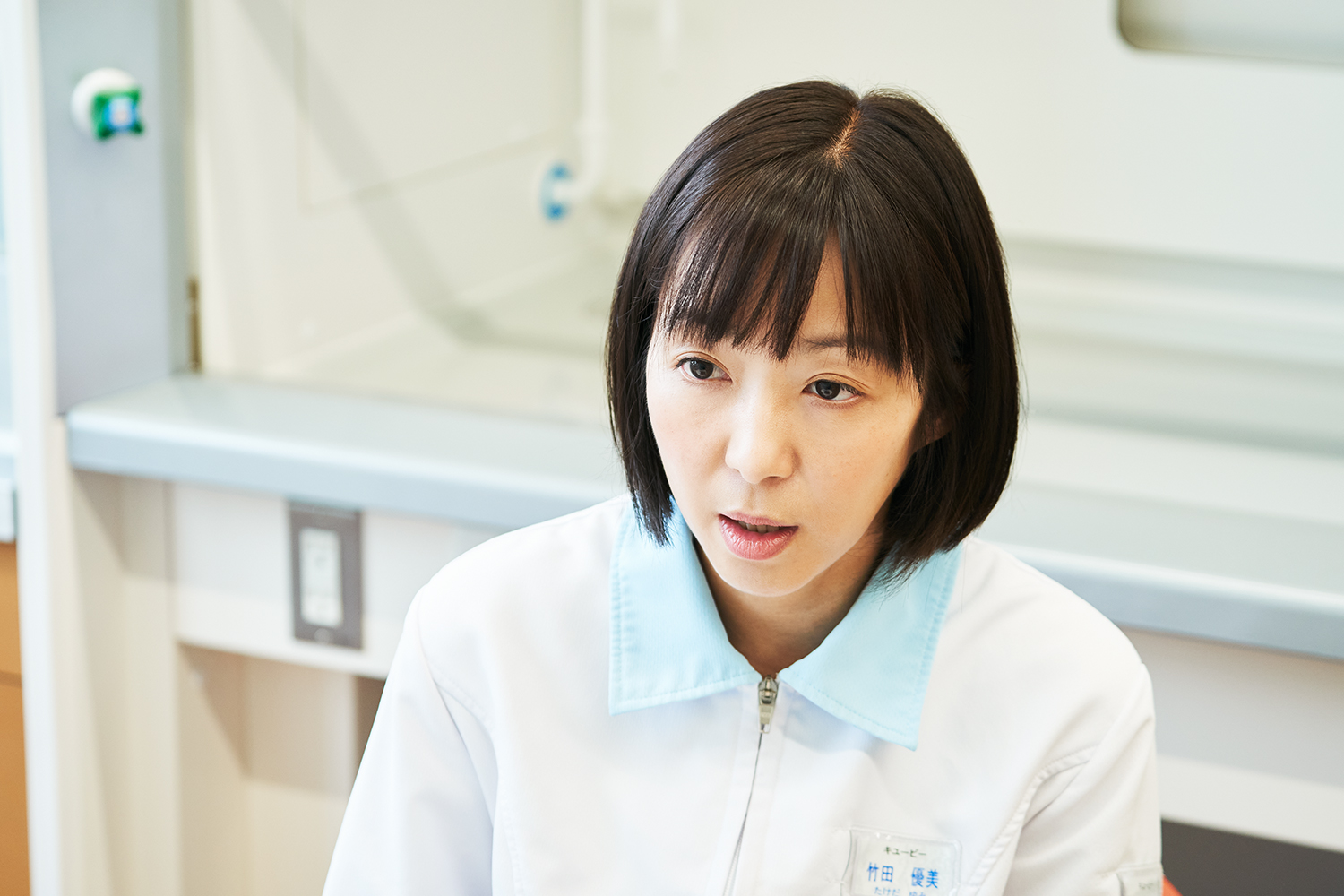
基礎研究の世界では、専門性の異なるメンバー同士が連携し、時には社外パートナーとも協働する。竹田氏のワークショップはその基盤づくりとも言える。
「ワークを通じて『この人はこの分野のエキスパート』『自分はこの領域で専門性を磨きたい』といった認識が共有され、専門性を尊重し合う文化とプロフェッショナル意識が自然と育まれていきました」(竹田氏)
理解を深めたのはメンバー同士だけではない。竹田氏にとっても「専門性の逆転現象」を乗り越える一歩となった。
ツールが変えた対話の質
未来創造研究所では相互理解を深める施策の一つとして1on1が浸透している。だが、児玉氏は4年間続けてきた1on1に課題を感じていた。
「対話の記録に手間がかかり、もっと効率化できないかと感じていました」(児玉氏)
そこで今年から1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入した。対話の内容や実施回数が自動で可視化され、記録の煩雑さから解放された。
竹田氏が最も実感している変化は、メンバーからのフィードバックが見える化されたことだ。
「自分の相談対応の得意・不得意が可視化され、改善点が明確になりました」(竹田氏)

ツールは対話の質も向上させた。メンバーがマネジャーに期待する対応を事前に選択する仕組みになったためだ。
「これまでの1on1では、メンバーが『ちょっと聞いてほしい』程度のつもりで話したことを、リーダーが大ごとに捉えてしまうことがありました」(竹田氏)
今は対話の目的や到達点について、お互いが共通認識を持って始められているという。
対話が深まり見えてきたもの
1on1の定着により、メンバーから深い相談が寄せられるようになった。竹田氏が1on1で多く聞くのは、メンバーの専門性への不安だ。
「私から見れば専門性の高いメンバーばかりですが、本人たちは『自分の専門性はまだ足りていない』と思っていることが多くあります」(竹田氏)
長年同じ環境で働いてきた研究者たちは、社内では"専門家"として一目置かれていても、外の世界で通用するかという不安を抱えている。
竹田氏はメンバーの自信向上を図るため、共同研究や技術相談で大学教授と面談する際、自分ではなくメンバーを前面に押し出すようにした。外部での経験を積ませることで、専門性への不安を解消する狙いだ。
児玉氏のチームでも、長期的なキャリア相談が行われている。メンバーから社会人ドクターとして博士号を取得したいという相談を受けた際、会社に所属しながら取得する道筋を1on1で継続的に話し合っている。
メンバーが実感する変化
昨年10月にグループ会社から異動し、児玉氏のチームに加入した漆畑亘氏は、1on1の効果を身をもって体験している。基礎研究の世界では、研究者が自主的にテーマを設定する姿勢が求められるが、アイデアの段階で相談できる場は意外に少ない。
「その点、1on1では具体化する前のアイデアでも気軽に相談できます。上司は否定せず『どうすれば実現できるか』を一緒に考えてくれますから」(漆畑氏)
児玉氏は「メンバーが1on1で語る『こんなことをやってみたい』という思いが新たな研究テーマに発展することもある」と説明する。
現在、機能素材研究部では40を超える研究テーマを15人で推進している。2040年の月面生活を想定した宇宙食開発のような壮大なテーマも、こうした対話から生まれたという。
漆畑氏にとって、1on1は研究を前進させる重要な場となっている。
「自分の中では答えが出なくて難しいと思っていたことも、アドバイスをもらって次に何をすべきかがクリアになり、進めやすくなりました」(漆畑氏)
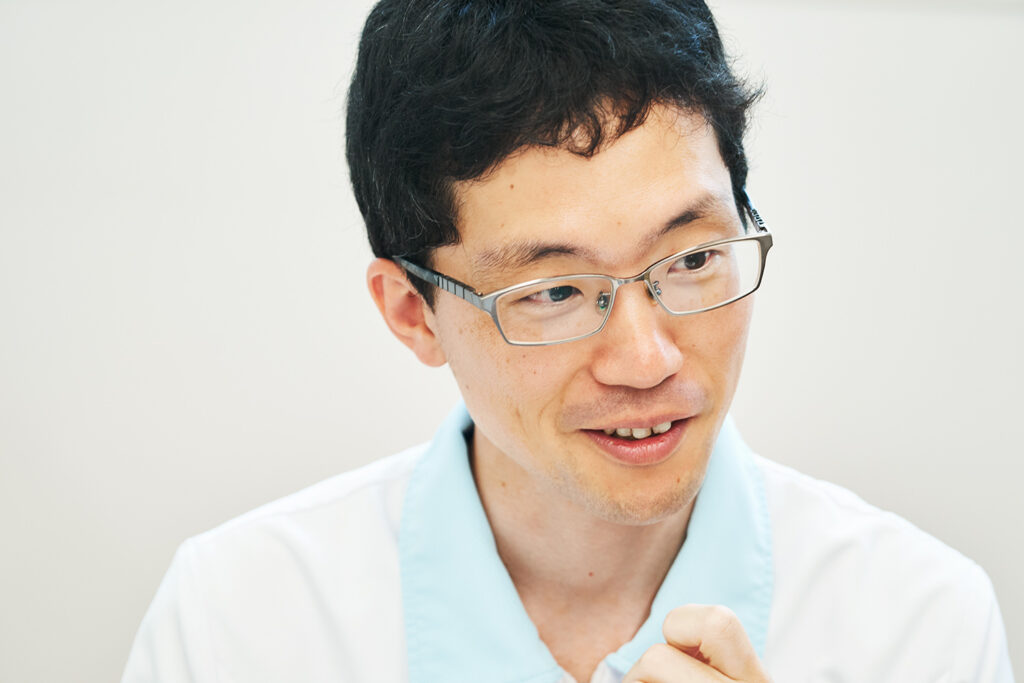
もっとも、漆畑氏は最初からこのような対話ができていたわけではない。
前職時代の1on1は「考課面談の延長のように感じていて、プライベートや価値観等も含めて本音の話しをする機会が少なかった」。
異動当初も「しばらく本音を話せていなかった」が、上司が親身に話を聞いてくれることが分かり、週1回という頻度も相まって徐々に信頼関係が築かれていったという。
企業価値向上への道筋と今後の展望
未来創造研究所では各チームが自主的なルールの下に1on1を運用している。その成果をどう測るのか。
竹田氏は「1on1に関する明確なKPIは設定していません」と話す。
児玉氏も同様の考えだ。「1on1そのものの成果を追うより、事業貢献など、より先の成果への貢献を意識すべきだと思います」(児玉氏)
児玉氏が重視するのは、研究成果が企業価値に与える影響だ。実際、2023年のアレルギー関連研究の発表後には、生活者からの反響が寄せられると同時に、自社の株価も上昇した。
「本研究の発表だけが株価上昇の要因ではなかったと思いますが、企業価値向上への貢献もあると考えられます」と児玉氏は振り返る。

だが、基礎研究者が経営インパクトを意識することは少ない。基礎研究は即座に商品やサービスに直結しないため、企業価値への貢献を実感しにくいからだ。この距離を縮める役割を1on1が担っている。
「1on1の場で“あなたの研究テーマはどう『愛は食卓にある。』につながっていますか? ”など、抽象的な質問をメンバーに問いかけることも心がけています。当社のコーポレートメッセージと自身の研究を結びつけて、企業価値向上への貢献を意識してもらうためです。メンバー自身が研究の価値を語れる、そんな組織でありたいと思っています」(児玉氏)
一つの問いかけがメンバーの意識を変え、新たな価値創造へとつながっていく。心理的安全性の構築から始まった1on1は、4年の実践を経て研究と経営をつなぐ架け橋に。組織の成長を支える確かな基盤が築かれた。






