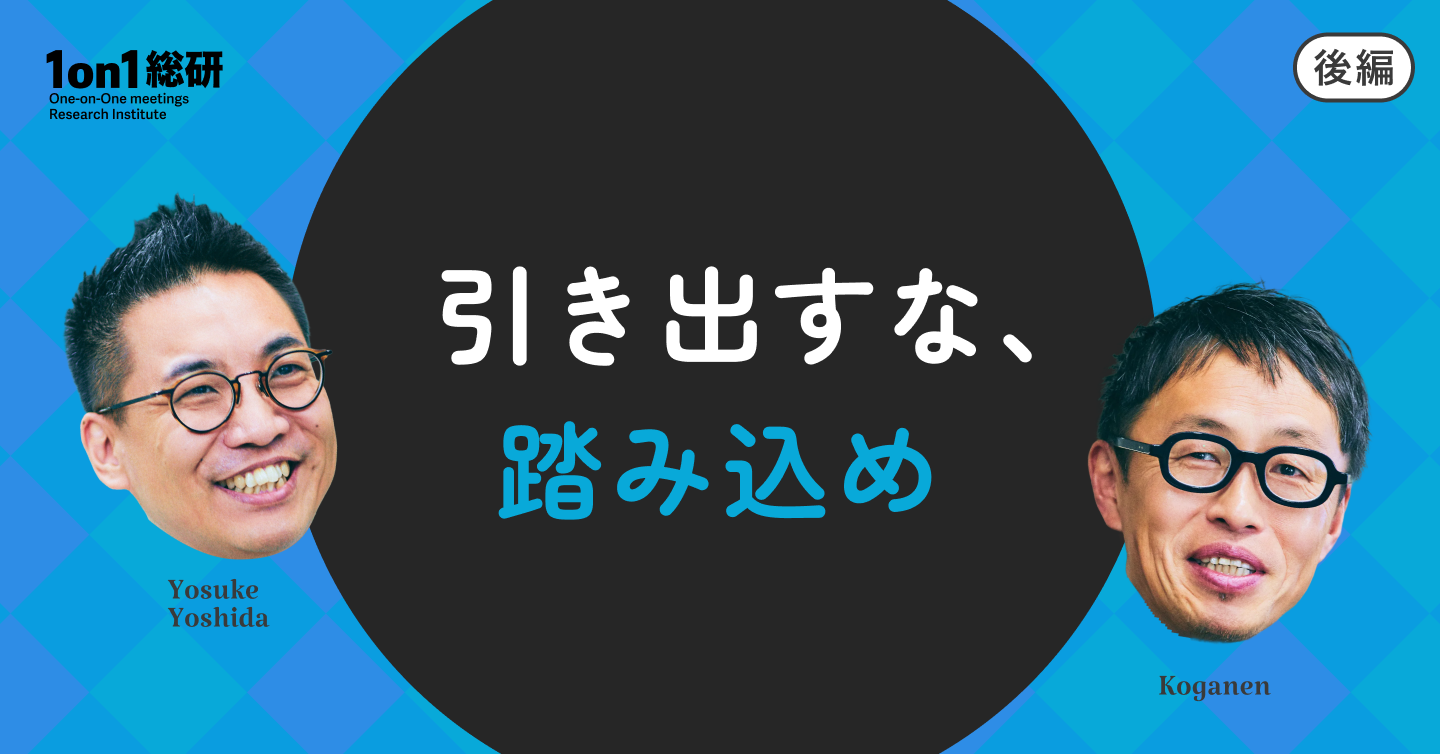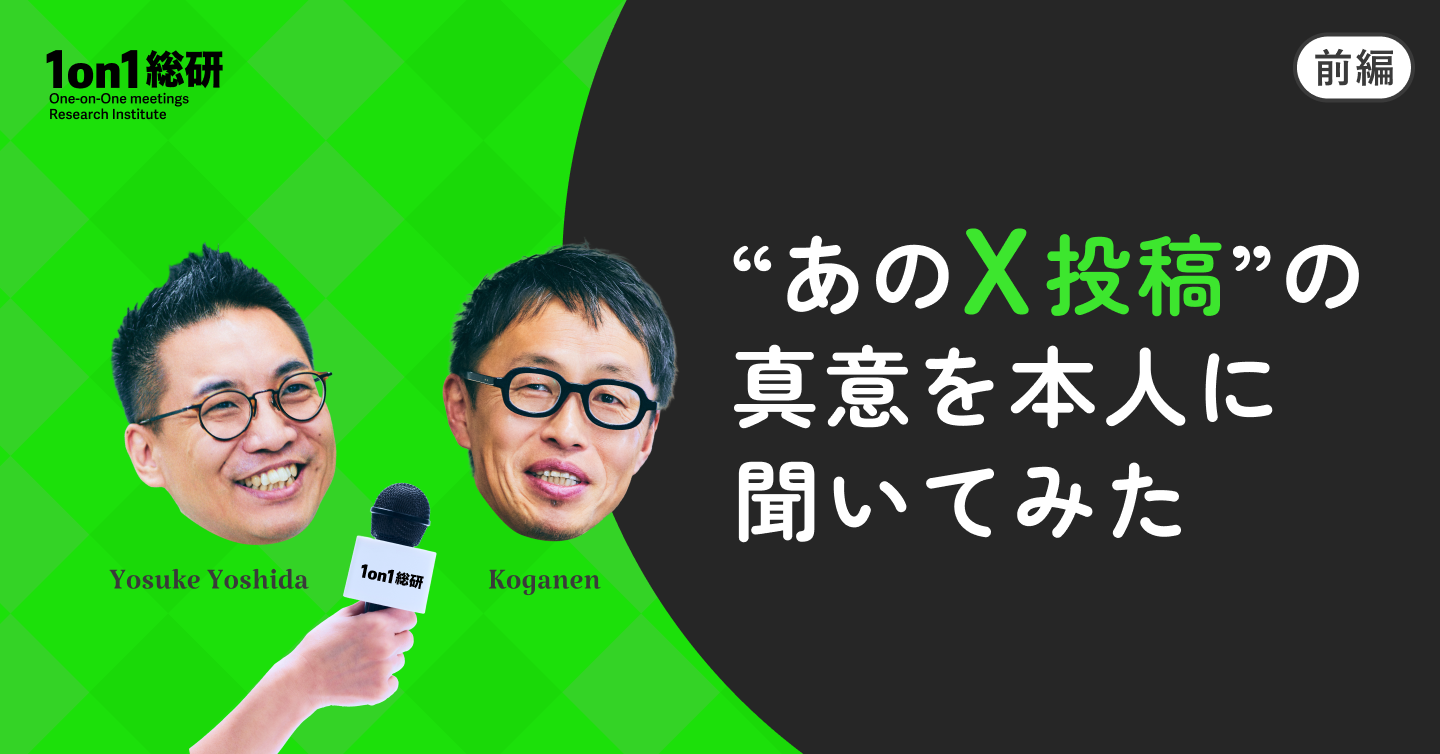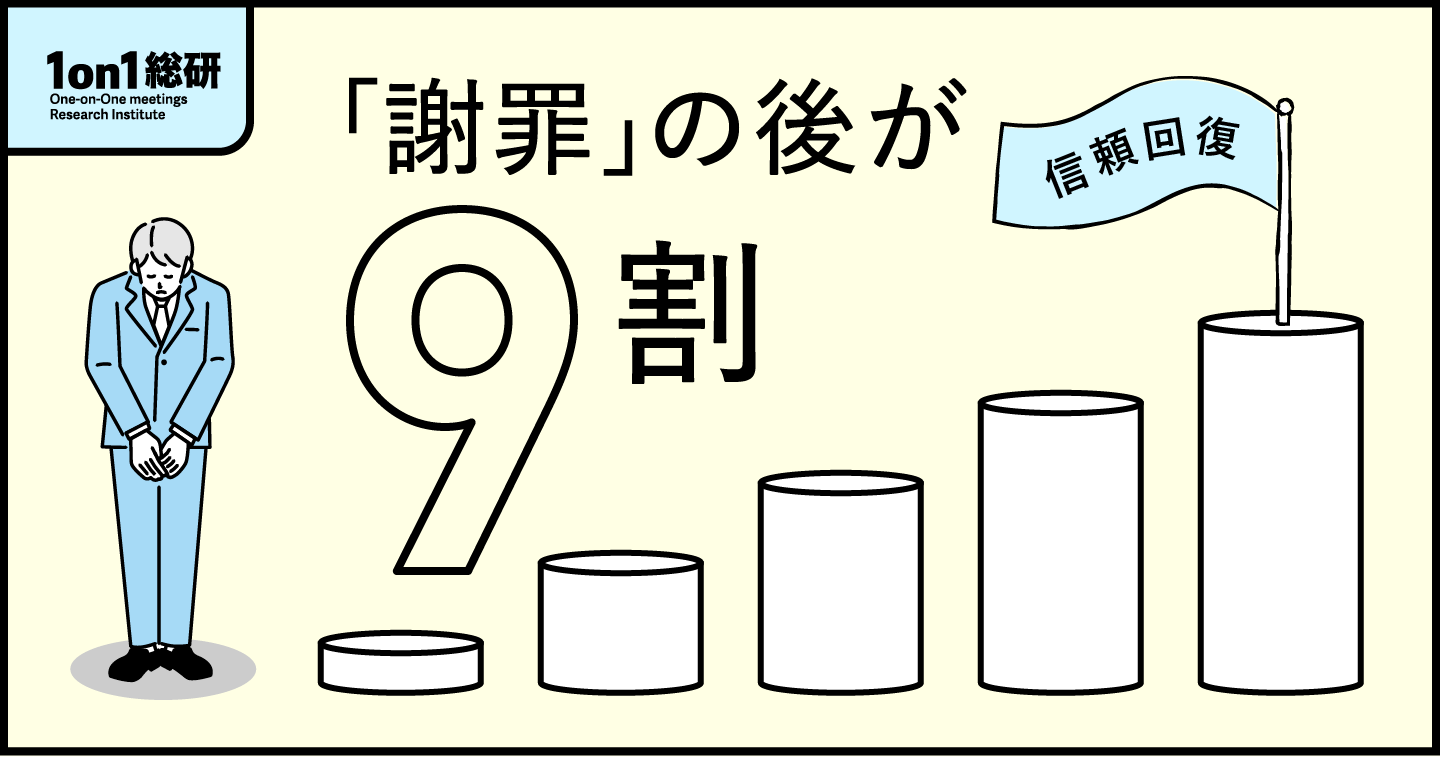デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術
「この人になら、メンバーやチームを任せられる」。そう思える“デキる上司”に共通する特徴とは何でしょうか。
部下の活躍や成長を、安心して任せられる上司。そんな存在に求められているのは、圧倒的な指導力や経験ではなく、日々の対話の中で発揮される、一見すると気づきづらい技術です。
今、1on1は多くの企業で制度化され、導入が進んでいます。背景にあるのは、従業員の自律や上司と部下の関係性の質が、組織の成果に直結する時代になったこと。変化が激しく、答えが一つではない時代においては、指示命令ではなく「問いかけ」「寄り添い」「支援する力」が求められているのです。
私たちKakeaiが150万回以上の1on1データを通じて見出したのは、そうした時代において信頼される上司が実践している、「感情の受け止め」「言語化の支援」「成果と成長の橋渡し」という三つの対話の技術です。
単に話すのではなく、“どう向き合い、どう聴き、どう残すか”。これらを意識した対話が、部下からの厚い信頼を生み、行動へと駆り立てる原動力となるのです。
① 感情の受け止め:信頼は“聴き方”で築かれる
Kakeaiの1on1データを分析すると、部下が「満足」と答えた1on1にはある共通点がありました。それは、1on1で話されるテーマに「感情」「価値観」「行動スタイル」といった、内面に関わる内容が含まれていることです。
とくに「感情」が含まれる対話は、含まれない対話に比べて部下の満足度が10ポイント以上高いという明確な差が出ています。
逆に、「業務の進行」「課題整理」など、タスク寄りの話題に偏った1on1では、満足度が下がる傾向があります。部下は、上司が何を言ったかよりも、「どう聴いてくれたか」を見ています。
ある若手社員はこう語っています。
「上司との1on1で『最近モヤモヤすることある?』と聞かれて、何も用意してなかったけど思わず『ちょっと今、役割の整理がついてなくて』って口にしてました。驚いたのは、上司がすぐに意見を言うんじゃなくて、『言葉にならなくても大丈夫。そこから話そう』と言ってくれたこと。その時間が、実はその週一番気持ちが軽くなった瞬間でした」
信頼される上司は、アドバイスを急がない。自分の視点をすぐに差し挟まず、相手が言葉を見つけるまでの“余白”を尊重します。うなずき、黙る時間も対話の一部と捉え、「いま、何が一番気になってる?」とそっと問いかける。
この丁寧な“感情の受け止め”が、「この人なら話せる」と思える安心を生み出しているのです。
② 言語化の支援:対話は「整理の場」である
次に見えてきたのは、上司と部下の“満足のズレ”です。
上司が「良い1on1だった」と感じたケースで頻出している1on1で話されるテーマは、「課題」「改善」「提案」など。つまり“対応”にまつわるものです。
しかし、部下が高評価をつけた1on1では、「考えを整理できた」「自分のことを理解してもらえた」といった、内省や共感に関する要素が目立ちます。
この「1on1の目的や場の位置付けの期待のすれ違い」は、Kakeaiのテーマ×対応データでも明確に表れています。
たとえば、上司が積極的に「提案」したとき、部下の満足度が伸びないケースも多く、逆に「話しているうちに自分で気づいた」と感じた部下ほど、満足度が高い傾向があります。
ある管理職の方が印象的なことを話してくれました。
「以前は“良い1on1”って、アドバイスできた時だと思ってたんです。でもある時、部下が『今日、自分の言葉で考えをまとめられてよかったです』って言ってくれて。その経験をきっかけに“問いを渡して、考えてもらう”ことの価値に気づきました。」
デキる上司は、答えではなく、問いを渡す人。
たとえばこうです。
👦「今の話、あなたの中で何が一番残ってる?」
🧒 「話していて、どこで“あ、これだ”と思えた?」
このような問いが、部下の思考を促し、言語化のきっかけを生み出します。1on1は、課題を解決する場ではなく、部下が自分で言葉を見つけていく場なのです。
③ 成果と成長をつなぐ:「問いを残す」終わり方
部下が「この1on1は良かった」と感じるもうひとつの条件に、終わり方があります。
Kakeaiのデータや定性的な声を分析すると、満足度の高い1on1に共通するのは、上司が以下のような行動をとっているときでした。
✅ 今日の話を簡単にまとめる
✅ 次回扱うテーマを仮決めする
✅ 話を聞いて感じたことを共有する
これにより、1on1は「対話で終わる」のではなく、「次回につながる約束」で締めくくられます。一方で、「また予定を入れておいてね」で終えるような1on1は、部下の満足度が明らかに低くなる傾向がありました。
デキる上司は、問いを残して終えます。
🧒「じゃあ、次回までに何か気づいたことがあれば、またそこから話してみよう」
👦「今回の話で考えたいこと、来週また聞かせてね」
ある20代の社員はこう言います。
「“また次回この続きを”って言われると、なんだか一人で抱え込まなくていい気がするんです。継続して見てもらっている実感が、自分の背中を押してくれます。」
まとめ:では、どうすればいいのか?
信頼される1on1は、特別なスキルではなく、日々の実践で磨かれていきます。まずは、以下のポイントから始めてみてください。
信頼される1on1にするための五つのアクション
① 感情に触れる問いから始める
テーマは業務だけでなく、「最近、気になっていること」「印象に残ったやりとり」など、感情の動きに注目を。
② 答えを急がず、問いを渡す
アドバイスよりも、「あなたならどう考える?」「他に選択肢はある?」という問いかけを。
③ 相手の言葉を繰り返し、整理を支援する
「つまり○○ってことかな?」と返すことで、部下が自分の考えを客観視できるように。
④ 次回につながる一言を添えて終える
「この続きはまた来週」など、継続性のある対話のリズムをつくる。
⑤ 記録を「信頼と対話の質」の土台にする
過去の会話を覚えておくことで信頼が増し、対話に連続性も生まれる。
感情を受け止め、思考を支え、対話の終わりに問いを残す。この三つの対話の技術が、部下の信頼と自走力を育てていきます。
1on1という場は、上司が部下を評価する時間でも、アドバイスを提供する時間でもありません。 関係を耕し、内省を促し、未来につなげる“関係性のマネジメント”の時間なのです。
私たちKakeaiが蓄積した150万回以上のデータは、そのことをはっきりと示しています。
「ただ話す」のではなく、「どう向き合うか」によって、1on1はまったく別のものになる。デキる上司とは、話し上手ではなく、信頼と成長を“待てる人”です。
📕あわせて読みたい
・ 挑戦しないメンバーに効く! マネジャーの1on1対応ガイド
・ 個人と組織の成長が加速。マネジャーのための「1on1完全ガイド」
・ なぜあなたのフィードバックは受け入れられないのか? 知っておきたい”部下の期待”
① 感情の受け止め:信頼は“聴き方”で築かれる
Kakeaiの1on1データを分析すると、部下が「満足」と答えた1on1にはある共通点がありました。それは、1on1で話されるテーマに「感情」「価値観」「行動スタイル」といった、内面に関わる内容が含まれていることです。
とくに「感情」が含まれる対話は、含まれない対話に比べて部下の満足度が10ポイント以上高いという明確な差が出ています。
逆に、「業務の進行」「課題整理」など、タスク寄りの話題に偏った1on1では、満足度が下がる傾向があります。部下は、上司が何を言ったかよりも、「どう聴いてくれたか」を見ています。
ある若手社員はこう語っています。
「上司との1on1で『最近モヤモヤすることある?』と聞かれて、何も用意してなかったけど思わず『ちょっと今、役割の整理がついてなくて』って口にしてました。驚いたのは、上司がすぐに意見を言うんじゃなくて、『言葉にならなくても大丈夫。そこから話そう』と言ってくれたこと。その時間が、実はその週一番気持ちが軽くなった瞬間でした」
信頼される上司は、アドバイスを急がない。自分の視点をすぐに差し挟まず、相手が言葉を見つけるまでの“余白”を尊重します。うなずき、黙る時間も対話の一部と捉え、「いま、何が一番気になってる?」とそっと問いかける。
この丁寧な“感情の受け止め”が、「この人なら話せる」と思える安心を生み出しているのです。
② 言語化の支援:対話は「整理の場」である
次に見えてきたのは、上司と部下の“満足のズレ”です。
上司が「良い1on1だった」と感じたケースで頻出している1on1で話されるテーマは、「課題」「改善」「提案」など。つまり“対応”にまつわるものです。
しかし、部下が高評価をつけた1on1では、「考えを整理できた」「自分のことを理解してもらえた」といった、内省や共感に関する要素が目立ちます。
この「1on1の目的や場の位置付けの期待のすれ違い」は、Kakeaiのテーマ×対応データでも明確に表れています。
たとえば、上司が積極的に「提案」したとき、部下の満足度が伸びないケースも多く、逆に「話しているうちに自分で気づいた」と感じた部下ほど、満足度が高い傾向があります。
ある管理職の方が印象的なことを話してくれました。
「以前は“良い1on1”って、アドバイスできた時だと思ってたんです。でもある時、部下が『今日、自分の言葉で考えをまとめられてよかったです』って言ってくれて。その経験をきっかけに“問いを渡して、考えてもらう”ことの価値に気づきました。」
デキる上司は、答えではなく、問いを渡す人。
たとえばこうです。
👦「今の話、あなたの中で何が一番残ってる?」
🧒 「話していて、どこで“あ、これだ”と思えた?」
このような問いが、部下の思考を促し、言語化のきっかけを生み出します。1on1は、課題を解決する場ではなく、部下が自分で言葉を見つけていく場なのです。
③ 成果と成長をつなぐ:「問いを残す」終わり方
部下が「この1on1は良かった」と感じるもうひとつの条件に、終わり方があります。
Kakeaiのデータや定性的な声を分析すると、満足度の高い1on1に共通するのは、上司が以下のような行動をとっているときでした。
✅ 今日の話を簡単にまとめる
✅ 次回扱うテーマを仮決めする
✅ 話を聞いて感じたことを共有する
これにより、1on1は「対話で終わる」のではなく、「次回につながる約束」で締めくくられます。一方で、「また予定を入れておいてね」で終えるような1on1は、部下の満足度が明らかに低くなる傾向がありました。
デキる上司は、問いを残して終えます。
🧒「じゃあ、次回までに何か気づいたことがあれば、またそこから話してみよう」
👦「今回の話で考えたいこと、来週また聞かせてね」
ある20代の社員はこう言います。
「“また次回この続きを”って言われると、なんだか一人で抱え込まなくていい気がするんです。継続して見てもらっている実感が、自分の背中を押してくれます。」
まとめ:では、どうすればいいのか?
信頼される1on1は、特別なスキルではなく、日々の実践で磨かれていきます。まずは、以下のポイントから始めてみてください。
信頼される1on1にするための五つのアクション
① 感情に触れる問いから始める
テーマは業務だけでなく、「最近、気になっていること」「印象に残ったやりとり」など、感情の動きに注目を。
② 答えを急がず、問いを渡す
アドバイスよりも、「あなたならどう考える?」「他に選択肢はある?」という問いかけを。
③ 相手の言葉を繰り返し、整理を支援する
「つまり○○ってことかな?」と返すことで、部下が自分の考えを客観視できるように。
④ 次回につながる一言を添えて終える
「この続きはまた来週」など、継続性のある対話のリズムをつくる。
⑤ 記録を「信頼と対話の質」の土台にする
過去の会話を覚えておくことで信頼が増し、対話に連続性も生まれる。
感情を受け止め、思考を支え、対話の終わりに問いを残す。この三つの対話の技術が、部下の信頼と自走力を育てていきます。
1on1という場は、上司が部下を評価する時間でも、アドバイスを提供する時間でもありません。 関係を耕し、内省を促し、未来につなげる“関係性のマネジメント”の時間なのです。
私たちKakeaiが蓄積した150万回以上のデータは、そのことをはっきりと示しています。
「ただ話す」のではなく、「どう向き合うか」によって、1on1はまったく別のものになる。デキる上司とは、話し上手ではなく、信頼と成長を“待てる人”です。
📕あわせて読みたい
・ 挑戦しないメンバーに効く! マネジャーの1on1対応ガイド
・ 個人と組織の成長が加速。マネジャーのための「1on1完全ガイド」
・ なぜあなたのフィードバックは受け入れられないのか? 知っておきたい”部下の期待”