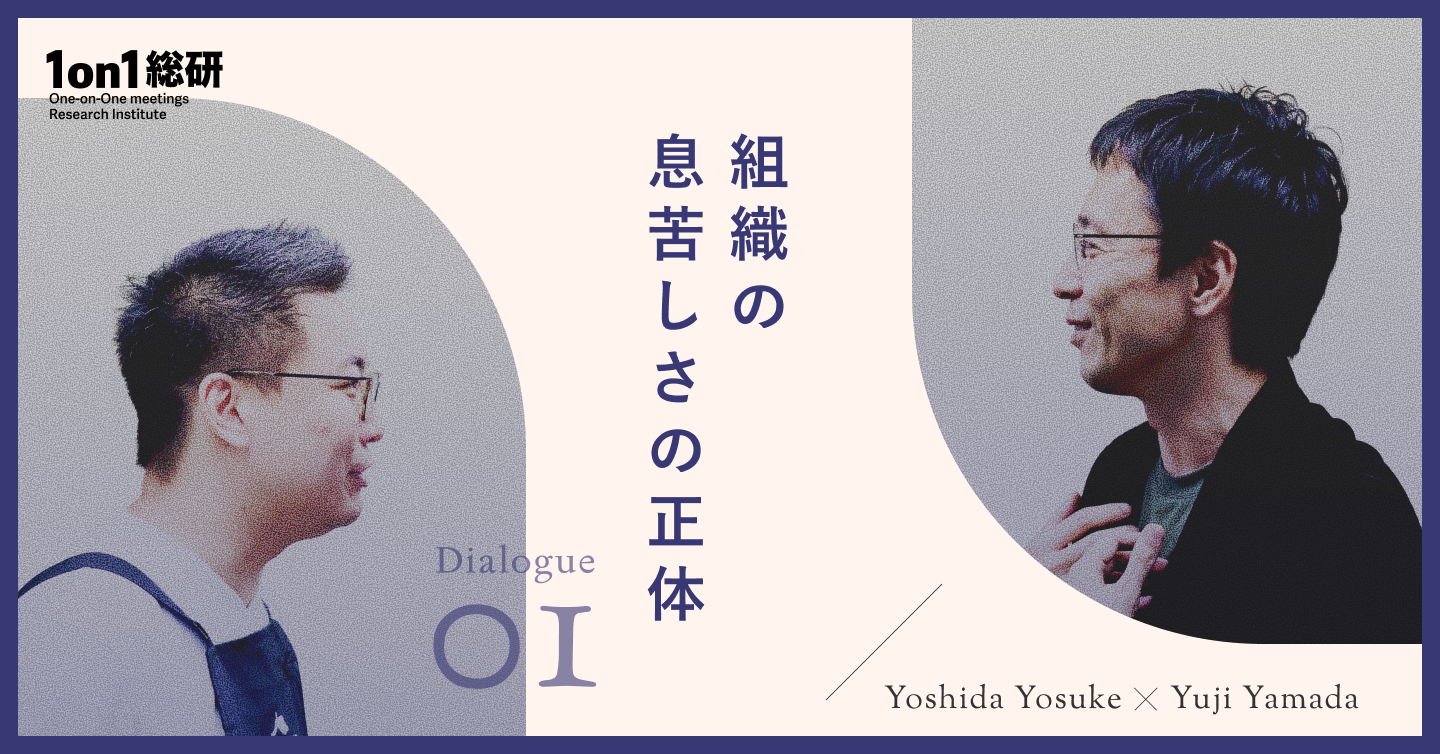心理的安全性を高める組織づくりと1on1の実践
「なぜ、部下が本音を言ってくれないのか」「雰囲気は悪くないのに、会議がかみ合わない」「頑張ってフィードバックしても、反応が薄い」ーー。
このような悩みを抱えるリーダーが増えています。職場における「心理的安全性」の重要性は広く認知されてきましたが、実際に高めようとすると、どこから手をつけるべきか分からず、漠然としたモヤモヤを抱えたまま日々のコミュニケーションが続いている組織も多いのではないでしょうか。
信頼や本音が育ちにくい背景には、職場に無意識のうちに積み重なる“静かな壁”が存在します。たとえば、報われなかった経験や、対話が設計されていない状態は、知らず知らずのうちに「声をあげない方が安全だ」という空気を生んでしまいます。
こうした課題に対して、いま注目されているのが、1on1ミーティングという「継続的な対話の仕組み」です。
上司と部下が定期的に向き合う1on1は、安心して話せる関係性を築く土台となり、心理的安全性を育て直すための有効なアプローチとして導入する企業が増えています。
本記事では、心理的安全性がなぜ損なわれるのかという根本要因から、1on1が信頼と対話をどう再構築するのかまでを、実際の事例も交えながら解説します。
心理的安全性とは?|定義と注目される理由
心理的安全性とは、「このチームでは、失敗や疑問を口にしたり、意見を述べても非難されたり恥をかくことはない」とメンバーが感じられる状態を指します。
これは単に「仲が良い」ということではなく、立場に関係なく発言ができ、異なる意見を尊重し合える、健全なチームの状態を意味します。
なぜ心理的安全性が重要なのか?
組織が成長し、変化に柔軟に対応するためには、心理的安全性が不可欠です。具体的には、以下のような効果が期待されます。
📌 学習と成長の促進
→ 失敗を恐れずに新たなことへ挑戦できる環境が、イノベーションを生み出します。
📌 問題解決力の向上
→ 意見を自由に出し合えることで、多様な視点から課題の本質にアプローチできます。
📌 エンゲージメントの向上
→ 自分の意見が受け入れられる経験が、組織への信頼と貢献意欲につながります。
📌 離職率の低下
→ 安心して働ける職場は、メンバーの定着率を高め、優秀な人材の流出を防ぎます。
📌 生産性の向上
→ 円滑なコミュニケーションが無駄を減らし、業務効率を高めます。
このように、心理的安全性は、組織の土台として機能します。しかし、実際の現場では「大事なのは分かっているけれど、どうすればいいか分からない」という声が多く聞かれます。次項では、心理的安全性を妨げている“静かな壁”の正体について掘り下げていきます。
心理的安全性を妨げる“静かな壁”とは?
💬 「心理的安全性の重要性は理解している。でも、なぜか声が出てこない」
実際、多くの職場ではこうした“言いにくさ”が日常に潜んでいます。一見、表面的にはコミュニケーションが成立しているようでも、会議のあとに「言いたいことを言えなかった」と感じるメンバーは少なくありません。
こうした「心理的安全性の低下」は、以下のような無意識の要因から生まれます。
心理的安全性を損なう主な原因
原因内容結果としての行動学習された慎重さ過去に発言を否定されたり、スルーされた経験がある発言を控え、自分を守るようになる構造的な抑制評価制度や意思決定の“暗黙のルール”が発言を妨げている無難な意見しか出ず、沈黙が増える認知バイアス「自分が話す立場じゃない」と思い込んでしまう弱い立場の人ほど発言しづらくなる
これらが日々の中で積み重なると、職場には「何も言わない方が安全」という空気が広がります。これは心理学でいう学習性無力感に近く、「どうせ何も変わらない」と感じることで、声をあげる意欲そのものが失われていきます。
日常に潜む“無意識のつまずき”が対話を壊す
心理的安全性の低下は、突然起きるわけではありません。多くの場合、小さなつまずきの積み重ねによって静かに進行します。
安全性低下の要因起きていること結果としての影響表面的な会話業務連絡や進捗確認だけで終わり、本音や雑談が出にくい対話が深まらず、信頼関係が築かれない上下関係の力学上司が話すと場が静まり、意見が出なくなる議論が単調になり、創造性が失われる失敗の記憶過去の否定体験により再び挑戦することを避けるようになる沈黙や守りの姿勢が強まる新しい提案への抵抗前例主義や「無理そう」という反応が繰り返される提案が出にくくなり、改善が形骸化する
心理的安全性のある組織とない組織の違い
“静かな壁”があるかどうかで、職場の雰囲気やメンバーの行動は大きく異なります。以下に心理的安全性の有無による違いを整理しました。
観点心理的安全性が高い組織心理的安全性が低い組織対話の質自由に意見交換ができ、未完成な考えも共有される本音が出づらく、報告や確認で終わる挑戦と失敗失敗も学びと捉えて挑戦を後押しするミスが恐れられ、守りに入りやすい関係性困ったときに「助けて」が言える信頼関係がある遠慮が強く、問題を抱え込むフィードバック建設的で率直なやりとりができる否定・回避・沈黙に偏りがち雰囲気前向きで柔らかく、自発的な行動が生まれやすい緊張感や閉塞感が漂い、指示待ちの空気になる
心理的安全性を育て直すために必要なのは「継続的な対話」
心理的安全性は、一朝一夕で築けるものではありません。信頼関係とは、日々の接し方・環境・対話の積み重ねによって育まれるものです。
そのためには、以下の二つの視点からのアプローチが欠かせません。
① リーダーのふるまいを変える
📌 「ありがとう」「その視点、面白いね」と肯定的なリアクション
📌 ミスを責めず、「次にどうするか」を一緒に考える
📌 「違う」ではなく「もっと良くするには?」と建設的な対話
📌 「なんでも聞いて」「聞いてくれてうれしい」など、相談歓迎の姿勢
② 組織としての“対話を育てる土壌”をつくる
📌 会議に自由発言の時間を設ける(例:3分トーク、雑談タイム)
📌 傾聴・質問・フィードバックなどの対話スキルを共有・学習
📌 匿名アンケートや声を拾う仕組みの整備
📌 対話や関わりそのものを成果と同様に評価する文化づくり
なぜ1on1が、心理的安全性を育てるのか?
対話を促進する工夫を組み込んでも、信頼は一度きりの言葉や対応では育ちません。だからこそ、1on1という「継続的な対話の場」を定期的に設けることが、心理的安全性を高める上で極めて効果的です。
1on1によって得られる心理的安全性の効果
📌 信頼関係の構築
→ 継続的に話すことで、相互理解が深まる
📌 率直な意見が言える場
→ 周囲を気にせず、不安や迷いを表現できる
📌 一人ひとりに向き合う対応が可能
→ 状況に応じたフィードバックや承認がしやすくなる
📌 課題の早期発見と解決
→ トラブルが深刻化する前に対処できる
📌 挑戦や成長を後押しする
→ キャリアの話題を扱うことで、意欲を引き出す
このように、1on1は単なる制度ではなく、「信頼と対話を育て続ける仕組み」です。次項では、1on1によって実際に心理的安全性が高まったチームの事例を紹介しながら、どのような変化が起きるのかを具体的に見ていきます。
実例で見る:1on1が心理的安全性を高めたチームの変化
ある企業のチームでは、1on1を導入して継続的に運用することで、心理的安全性の状態が「低→中→高」へと段階的に変化していきました。
そのプロセスを通じて、メンバーが1on1に求めるものや、感じる価値も大きく変化していったのです。
▷ 初期段階:心理的安全性が低い状態
導入直後は「話を聞いてもらえるだけでもありがたい」と感じる段階。メンバーは不安を抱えやすく、人間関係の安心感を得ることが目的となりがちでした。1on1の内容は雑談が中心で、「とりあえず話す場」というレベルにとどまっていました。
▷ 中期段階:心理的安全性が中程度に向上
1on1が一定のリズムで定着すると、メンバーの信頼感も育ちはじめ、業務に関する相談や進捗の確認といった“具体的な対話”が増加。「この時間で仕事が前に進む」と実感する声も多く聞かれるようになりました。
▷ 現在:心理的安全性が高まった状態
継続的な1on1を通じて、チーム内の信頼関係が深まり、会話のテーマもキャリアや成長、未来の挑戦といった中長期的な視点へと進化。メンバー自身が「自分を理解してくれる時間」として1on1を捉えるようになりました。
心理的安全性の“段階”によって、1on1の焦点は変わる
心理的安全性のレベルによって、メンバーが1on1に求めることや、効果的な対話の焦点は大きく異なります。チームの状態を見極めながら、1on1のあり方を調整することが重要です。
心理的安全性が低いチーム
目的:人間関係の安心感づくり
特徴:緊張感が強く、フィードバックへの恐れがある
対応:雑談や日常会話からスタートし、「話しても大丈夫」と感じられる空気をつくる
心理的安全性が中程度のチーム
目的:業務の進め方や成果の明確化
特徴:タスクの優先順位や進捗相談のニーズが高い
対応:アドバイスや承認を明確に伝え、「見ているよ」と声をかけることで信頼を醸成
心理的安全性が高いチーム
目的:成長やキャリアの対話、組織づくりへの参画
特徴:未来志向の会話が自然に出てくる
対応:中長期的な目標、挑戦意欲、チーム全体のビジョンなどをテーマに深く語り合う
心理的安全性を高める1on1の実践①|設計編
効果的な1on1を実現するには、「どのように設計するか」が何よりも重要です。設計が曖昧だと、1on1は単なる雑談や義務的な面談になってしまいます。
設計のポイント
1:目的や意義を明確にする
👉 なぜ行うのか、どんな変化を期待するのかを共有
2:組織全体で共通認識をもつ
👉 頻度やテーマの基準をそろえることで、不公平感を防ぐ
3:話しやすいテーマを用意する
👉 「最近気になっていること」など、話のきっかけを設ける
4:対話の蓄積と活用を設計する
👉 メモやトピック履歴を活かした“つながりのある対話”を続ける
心理的安全性を高める1on1の実践②|運用編
設計だけでなく、実際の進め方やふるまいが1on1の成否を左右します。心理的安全性を育む1on1では、「どう話すか」「どう聴くか」が特に大切です。
運用のポイント
1:安心感をつくる“はじまり”の工夫
👉 アイスブレイクを取り入れ、上司も自分の話をする
2:対話の質を高める聴き方・問いかけ
👉 遮らずに聴き、沈黙も受け入れ、問いを投げかける
3:メンバーが抱える明確な言葉にならない感情も扱う
👉 「どう感じた?」と感情に触れる言葉を意識
4:次回につながる終わり方
👉 「また聞かせてね」「ありがとう」と自然につなげる
心理的安全性を高める1on1の実践③|定着編
心理的安全性を高めるには、1on1を「一過性の取り組み」ではなく、組織文化として定着させることが必要です。
定着のポイント
1:目的や意義の継続的な共有
👉 繰り返し「なぜやるのか」を伝え、形骸化を防ぐ
2:マネジャー間での学び合い
👉 良かった事例や困ったことを共有し、ノウハウを高める
3:成果や変化の“見える化”
👉 実施率だけでなく、対話の質や気づきをデータで共有
4:定期的な振り返りとアップデート
👉 メンバーに1on1の感想を聞き、テーマや進め方を改善
最後に:マネジャーにも心理的安全性が必要です
1on1では、部下の悩みや重たい本音に直面することもあります。そのとき、「一人で解決しなければ」と思い詰めると、マネジャー自身の心理的負担が高まり、1on1が苦痛な時間になってしまうことも。
だからこそ、マネジャー同士が支え合える場や対話の機会も欠かせません。
💬 「こんなテーマで悩んだ」
💬 「どう声をかければいいか分からなかった」
そんな会話を重ねることで、マネジャーもまた“聴いてもらえる場”を持つことができ、1on1の質を継続的に高めていくことができます。
心理的安全性とは?|定義と注目される理由
心理的安全性とは、「このチームでは、失敗や疑問を口にしたり、意見を述べても非難されたり恥をかくことはない」とメンバーが感じられる状態を指します。
これは単に「仲が良い」ということではなく、立場に関係なく発言ができ、異なる意見を尊重し合える、健全なチームの状態を意味します。
なぜ心理的安全性が重要なのか?
組織が成長し、変化に柔軟に対応するためには、心理的安全性が不可欠です。具体的には、以下のような効果が期待されます。
📌 学習と成長の促進
→ 失敗を恐れずに新たなことへ挑戦できる環境が、イノベーションを生み出します。
📌 問題解決力の向上
→ 意見を自由に出し合えることで、多様な視点から課題の本質にアプローチできます。
📌 エンゲージメントの向上
→ 自分の意見が受け入れられる経験が、組織への信頼と貢献意欲につながります。
📌 離職率の低下
→ 安心して働ける職場は、メンバーの定着率を高め、優秀な人材の流出を防ぎます。
📌 生産性の向上
→ 円滑なコミュニケーションが無駄を減らし、業務効率を高めます。
このように、心理的安全性は、組織の土台として機能します。しかし、実際の現場では「大事なのは分かっているけれど、どうすればいいか分からない」という声が多く聞かれます。次項では、心理的安全性を妨げている“静かな壁”の正体について掘り下げていきます。
心理的安全性を妨げる“静かな壁”とは?
💬 「心理的安全性の重要性は理解している。でも、なぜか声が出てこない」
実際、多くの職場ではこうした“言いにくさ”が日常に潜んでいます。一見、表面的にはコミュニケーションが成立しているようでも、会議のあとに「言いたいことを言えなかった」と感じるメンバーは少なくありません。
こうした「心理的安全性の低下」は、以下のような無意識の要因から生まれます。
心理的安全性を損なう主な原因
原因内容結果としての行動学習された慎重さ過去に発言を否定されたり、スルーされた経験がある発言を控え、自分を守るようになる構造的な抑制評価制度や意思決定の“暗黙のルール”が発言を妨げている無難な意見しか出ず、沈黙が増える認知バイアス「自分が話す立場じゃない」と思い込んでしまう弱い立場の人ほど発言しづらくなる
これらが日々の中で積み重なると、職場には「何も言わない方が安全」という空気が広がります。これは心理学でいう学習性無力感に近く、「どうせ何も変わらない」と感じることで、声をあげる意欲そのものが失われていきます。
日常に潜む“無意識のつまずき”が対話を壊す
心理的安全性の低下は、突然起きるわけではありません。多くの場合、小さなつまずきの積み重ねによって静かに進行します。
安全性低下の要因起きていること結果としての影響表面的な会話業務連絡や進捗確認だけで終わり、本音や雑談が出にくい対話が深まらず、信頼関係が築かれない上下関係の力学上司が話すと場が静まり、意見が出なくなる議論が単調になり、創造性が失われる失敗の記憶過去の否定体験により再び挑戦することを避けるようになる沈黙や守りの姿勢が強まる新しい提案への抵抗前例主義や「無理そう」という反応が繰り返される提案が出にくくなり、改善が形骸化する
心理的安全性のある組織とない組織の違い
“静かな壁”があるかどうかで、職場の雰囲気やメンバーの行動は大きく異なります。以下に心理的安全性の有無による違いを整理しました。
観点心理的安全性が高い組織心理的安全性が低い組織対話の質自由に意見交換ができ、未完成な考えも共有される本音が出づらく、報告や確認で終わる挑戦と失敗失敗も学びと捉えて挑戦を後押しするミスが恐れられ、守りに入りやすい関係性困ったときに「助けて」が言える信頼関係がある遠慮が強く、問題を抱え込むフィードバック建設的で率直なやりとりができる否定・回避・沈黙に偏りがち雰囲気前向きで柔らかく、自発的な行動が生まれやすい緊張感や閉塞感が漂い、指示待ちの空気になる
心理的安全性を育て直すために必要なのは「継続的な対話」
心理的安全性は、一朝一夕で築けるものではありません。信頼関係とは、日々の接し方・環境・対話の積み重ねによって育まれるものです。
そのためには、以下の二つの視点からのアプローチが欠かせません。
① リーダーのふるまいを変える
📌 「ありがとう」「その視点、面白いね」と肯定的なリアクション
📌 ミスを責めず、「次にどうするか」を一緒に考える
📌 「違う」ではなく「もっと良くするには?」と建設的な対話
📌 「なんでも聞いて」「聞いてくれてうれしい」など、相談歓迎の姿勢
② 組織としての“対話を育てる土壌”をつくる
📌 会議に自由発言の時間を設ける(例:3分トーク、雑談タイム)
📌 傾聴・質問・フィードバックなどの対話スキルを共有・学習
📌 匿名アンケートや声を拾う仕組みの整備
📌 対話や関わりそのものを成果と同様に評価する文化づくり
なぜ1on1が、心理的安全性を育てるのか?
対話を促進する工夫を組み込んでも、信頼は一度きりの言葉や対応では育ちません。だからこそ、1on1という「継続的な対話の場」を定期的に設けることが、心理的安全性を高める上で極めて効果的です。
1on1によって得られる心理的安全性の効果
📌 信頼関係の構築
→ 継続的に話すことで、相互理解が深まる
📌 率直な意見が言える場
→ 周囲を気にせず、不安や迷いを表現できる
📌 一人ひとりに向き合う対応が可能
→ 状況に応じたフィードバックや承認がしやすくなる
📌 課題の早期発見と解決
→ トラブルが深刻化する前に対処できる
📌 挑戦や成長を後押しする
→ キャリアの話題を扱うことで、意欲を引き出す
このように、1on1は単なる制度ではなく、「信頼と対話を育て続ける仕組み」です。次項では、1on1によって実際に心理的安全性が高まったチームの事例を紹介しながら、どのような変化が起きるのかを具体的に見ていきます。
実例で見る:1on1が心理的安全性を高めたチームの変化
ある企業のチームでは、1on1を導入して継続的に運用することで、心理的安全性の状態が「低→中→高」へと段階的に変化していきました。
そのプロセスを通じて、メンバーが1on1に求めるものや、感じる価値も大きく変化していったのです。
▷ 初期段階:心理的安全性が低い状態
導入直後は「話を聞いてもらえるだけでもありがたい」と感じる段階。メンバーは不安を抱えやすく、人間関係の安心感を得ることが目的となりがちでした。1on1の内容は雑談が中心で、「とりあえず話す場」というレベルにとどまっていました。
▷ 中期段階:心理的安全性が中程度に向上
1on1が一定のリズムで定着すると、メンバーの信頼感も育ちはじめ、業務に関する相談や進捗の確認といった“具体的な対話”が増加。「この時間で仕事が前に進む」と実感する声も多く聞かれるようになりました。
▷ 現在:心理的安全性が高まった状態
継続的な1on1を通じて、チーム内の信頼関係が深まり、会話のテーマもキャリアや成長、未来の挑戦といった中長期的な視点へと進化。メンバー自身が「自分を理解してくれる時間」として1on1を捉えるようになりました。
心理的安全性の“段階”によって、1on1の焦点は変わる
心理的安全性のレベルによって、メンバーが1on1に求めることや、効果的な対話の焦点は大きく異なります。チームの状態を見極めながら、1on1のあり方を調整することが重要です。
心理的安全性が低いチーム
目的:人間関係の安心感づくり
特徴:緊張感が強く、フィードバックへの恐れがある
対応:雑談や日常会話からスタートし、「話しても大丈夫」と感じられる空気をつくる
心理的安全性が中程度のチーム
目的:業務の進め方や成果の明確化
特徴:タスクの優先順位や進捗相談のニーズが高い
対応:アドバイスや承認を明確に伝え、「見ているよ」と声をかけることで信頼を醸成
心理的安全性が高いチーム
目的:成長やキャリアの対話、組織づくりへの参画
特徴:未来志向の会話が自然に出てくる
対応:中長期的な目標、挑戦意欲、チーム全体のビジョンなどをテーマに深く語り合う
心理的安全性を高める1on1の実践①|設計編
効果的な1on1を実現するには、「どのように設計するか」が何よりも重要です。設計が曖昧だと、1on1は単なる雑談や義務的な面談になってしまいます。
設計のポイント
1:目的や意義を明確にする
👉 なぜ行うのか、どんな変化を期待するのかを共有
2:組織全体で共通認識をもつ
👉 頻度やテーマの基準をそろえることで、不公平感を防ぐ
3:話しやすいテーマを用意する
👉 「最近気になっていること」など、話のきっかけを設ける
4:対話の蓄積と活用を設計する
👉 メモやトピック履歴を活かした“つながりのある対話”を続ける
心理的安全性を高める1on1の実践②|運用編
設計だけでなく、実際の進め方やふるまいが1on1の成否を左右します。心理的安全性を育む1on1では、「どう話すか」「どう聴くか」が特に大切です。
運用のポイント
1:安心感をつくる“はじまり”の工夫
👉 アイスブレイクを取り入れ、上司も自分の話をする
2:対話の質を高める聴き方・問いかけ
👉 遮らずに聴き、沈黙も受け入れ、問いを投げかける
3:メンバーが抱える明確な言葉にならない感情も扱う
👉 「どう感じた?」と感情に触れる言葉を意識
4:次回につながる終わり方
👉 「また聞かせてね」「ありがとう」と自然につなげる
心理的安全性を高める1on1の実践③|定着編
心理的安全性を高めるには、1on1を「一過性の取り組み」ではなく、組織文化として定着させることが必要です。
定着のポイント
1:目的や意義の継続的な共有
👉 繰り返し「なぜやるのか」を伝え、形骸化を防ぐ
2:マネジャー間での学び合い
👉 良かった事例や困ったことを共有し、ノウハウを高める
3:成果や変化の“見える化”
👉 実施率だけでなく、対話の質や気づきをデータで共有
4:定期的な振り返りとアップデート
👉 メンバーに1on1の感想を聞き、テーマや進め方を改善
最後に:マネジャーにも心理的安全性が必要です
1on1では、部下の悩みや重たい本音に直面することもあります。そのとき、「一人で解決しなければ」と思い詰めると、マネジャー自身の心理的負担が高まり、1on1が苦痛な時間になってしまうことも。
だからこそ、マネジャー同士が支え合える場や対話の機会も欠かせません。
💬 「こんなテーマで悩んだ」
💬 「どう声をかければいいか分からなかった」
そんな会話を重ねることで、マネジャーもまた“聴いてもらえる場”を持つことができ、1on1の質を継続的に高めていくことができます。