
皆川恵美
管理職育成・組織開発コンサルティングに携わった後、KAKEAIを共同創業
【キャリア自律を促す1on1メソッド】“自分の道を選ぶ力”を育む対話とは
キャリア自律とは、自らの価値観や志向性をもとに、キャリアを選択し行動できる状態を指します。言い換えれば、「与えられた役割にただ従う」のではなく、「自分がどうありたいか」を起点に、主体的に未来を選び取っていく力を得ることとも言えます。
不確実性の高い時代において、職業人生が“会社任せ”では立ち行かなくなりつつある今、個人がキャリアに対して自律的な視点を持つことは、組織にとっても大きな価値となります。人材が“自走する”状態は、マネジメントの効率化にもつながり、組織の活力にもなります。
とはいえ、キャリアの方向性を考えることは、一人では難しいものです。これまでの経験をどう意味づけるか、今の仕事がどんな意味を持つのか、将来にどんな可能性があるのか──。こうした問いに向き合うには支援が必要ですが、一方的な研修や情報提供では、本人の内にある答えを引き出すのは難しいでしょう。
そこで有効なのが、1on1という対話の場です。1on1では、マネジャーの問いかけによって、本人が過去の経験を振り返り、現在の状況を整理し、未来への道筋を見出していく。マネジャーはこの「内省と問い」のプロセスを通じて、本人の気づきや選択を支援することができます。言葉にすることで「なんとなく思っていたこと」が整理され、行動の一歩が明確になります。
キャリア自律を促す1on1とは、「指導の場」でも「答え合わせの場」でもなく、自分の人生をどう歩みたいかを、安心して言葉にできる場です。その場の力を活かすことで、個人と組織の関係性もより成熟したものへと変わっていくはずです。

課長の時間を取り戻せ。1on1が変えるマネジメント構造
人材の流動化、リモートワーク、複雑化する組織構造。こうした変化の中で、管理職──特に課長層が担う負荷は、かつてないほどに増加しています。
「部下に目を配りたいが、手が回らない」
「育成より、進捗確認と火消しで精一杯」
「指示は出しているのに、部下が自律的に動かない」
このような悩みは、決してマネジメントスキルが不足しているわけではなく、そうならざるを得ない構造になっているというのが実態のようです。
こうした負荷を真に軽減するには、スキルや制度以前に、マネジメント構造そのものを見直す必要があります。
そして、その構造改革の第一歩が「1on1の再定義」にあると考えられます。

デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術
「この人になら、メンバーやチームを任せられる」。そう思える“デキる上司”に共通する特徴とは何でしょうか。
部下の活躍や成長を、安心して任せられる上司。そんな存在に求められているのは、圧倒的な指導力や経験ではなく、日々の対話の中で発揮される、一見すると気づきづらい技術です。
今、1on1は多くの企業で制度化され、導入が進んでいます。背景にあるのは、従業員の自律や上司と部下の関係性の質が、組織の成果に直結する時代になったこと。変化が激しく、答えが一つではない時代においては、指示命令ではなく「問いかけ」「寄り添い」「支援する力」が求められているのです。
私たちKakeaiが150万回以上の1on1データを通じて見出したのは、そうした時代において信頼される上司が実践している、「感情の受け止め」「言語化の支援」「成果と成長の橋渡し」という三つの対話の技術です。
単に話すのではなく、“どう向き合い、どう聴き、どう残すか”。これらを意識した対話が、部下からの厚い信頼を生み、行動へと駆り立てる原動力となるのです。

1on1が組織を変える。エンゲージメント向上の成功事例
急速に変化するビジネス環境において、企業が競争力を維持するには、社員一人ひとりの主体的な行動と自律的な成長を促す組織づくりが不可欠です。その実現に欠かせないのが、社員と組織の心理的なつながり、すなわち「エンゲージメント」です。
しかし、制度や仕組み(ハード施策)を整備するだけでは、社員の納得や自発的な行動にはつながりません。組織文化やコミュニケーション(ソフト施策)を促進しても声がけに終わってしまうことも多いです。
そこで注目されているのが「1on1」です。上司と部下が定期的に対話を重ね、制度や方針の意図を丁寧に伝え、信頼関係を築く場としての1on1は、エンゲージメントを高める実践的な手段です。
本記事では、1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」の事例をもとに、エンゲージメント向上に効果的な1on1の設計・運用・定着方法を解説します。

心理的安全性を高める組織づくりと1on1の実践
「なぜ、部下が本音を言ってくれないのか」「雰囲気は悪くないのに、会議がかみ合わない」「頑張ってフィードバックしても、反応が薄い」ーー。
このような悩みを抱えるリーダーが増えています。職場における「心理的安全性」の重要性は広く認知されてきましたが、実際に高めようとすると、どこから手をつけるべきか分からず、漠然としたモヤモヤを抱えたまま日々のコミュニケーションが続いている組織も多いのではないでしょうか。
信頼や本音が育ちにくい背景には、職場に無意識のうちに積み重なる“静かな壁”が存在します。たとえば、報われなかった経験や、対話が設計されていない状態は、知らず知らずのうちに「声をあげない方が安全だ」という空気を生んでしまいます。
こうした課題に対して、いま注目されているのが、1on1ミーティングという「継続的な対話の仕組み」です。
上司と部下が定期的に向き合う1on1は、安心して話せる関係性を築く土台となり、心理的安全性を育て直すための有効なアプローチとして導入する企業が増えています。
本記事では、心理的安全性がなぜ損なわれるのかという根本要因から、1on1が信頼と対話をどう再構築するのかまでを、実際の事例も交えながら解説します。

なぜあなたのフィードバックは受け入れられないのか? 知っておきたい”部下の期待”
部下へのフィードバックは、個人の成長や組織のパフォーマンス向上に不可欠です。しかし、部下の性格や心理状態によっては、フィードバックが困難になるケースがあります。
「フィードバックがしやすい・しにくい」という問題の根本には、「部下が上司に期待する役割の違い」が大きく影響しています。
この期待役割のズレを上司が理解し、望ましい方向へ調整することが、フィードバックを円滑化させ、組織全体の成長や生産性向上につながります。
本記事では、フィードバックが難しい部下の5パターンを分析し、それぞれの心理状況と上司が取るべき対応策を解説します。

挑戦しないメンバーに効く! マネジャーの1on1対応ガイド
とある事業部門で、若手メンバーの育成に取り組むマネジャーから「自分のできることしかやらないメンバーがいて困っている」という悩みを聞きました。
「自分のできることしかやらない」とは一体どのような状況なのでしょうか。マネジャーの期待とメンバーの言動にギャップが存在することは前提ですが、メンバーのスタンスや意欲の問題として捉えても状況は改善しません。
この課題の背景には、マネジャーがメンバーの心理や状況を十分に理解できず、「やる気がない」といった誤った解釈をしてしまうことや、期待していることがうまく伝わっていないといったコミュニケーションのズレがあることが少なくありません。
本コンテンツでは、こうした課題に対して組織としてどう向き合うかをテーマに、実際のディスカッションから整理・汎用化した考え方をもとに、状況の捉え方や分解の仕方、そして具体的な対応のヒントをご紹介していきます。

個人と組織の成長が加速。マネジャーのための「1on1完全ガイド」
「会社で1on1を始めることになったが、正直どうやって進めたらいいかわからない」「忙しい日常業務に追われ、気がつけば1on1がただの報告会になってしまっている」
「部署やマネジャーごとにやり方が違い、何が正解かわからない」……こうした悩みを抱えている管理職の方は多いのではないでしょうか。
経営環境や働き方が急速に変化する中、従来の画一的な管理や指示だけでは、社員一人ひとりのやる気や力を引き出すことが難しくなっています。社員がもっと活躍し、チームで成果を出すためには、何かを変える必要があります。
このような変化に対応するためには近道はなく、メンバーとの丁寧な対話が不可欠です。その機会として「1on1ミーティング」が求められています。
しかし、実際には「形だけの導入」や「手応えが感じられない」といった声も少なくありません。
このガイドでは、マネジャーの皆さんが今日からすぐに使えるよう、1on1の取り組み方を詳しく解説します。メンバーもマネジャーも小さな進化や手応えを感じられるヒントが詰まっていますので、ぜひ取り組んでみてください。
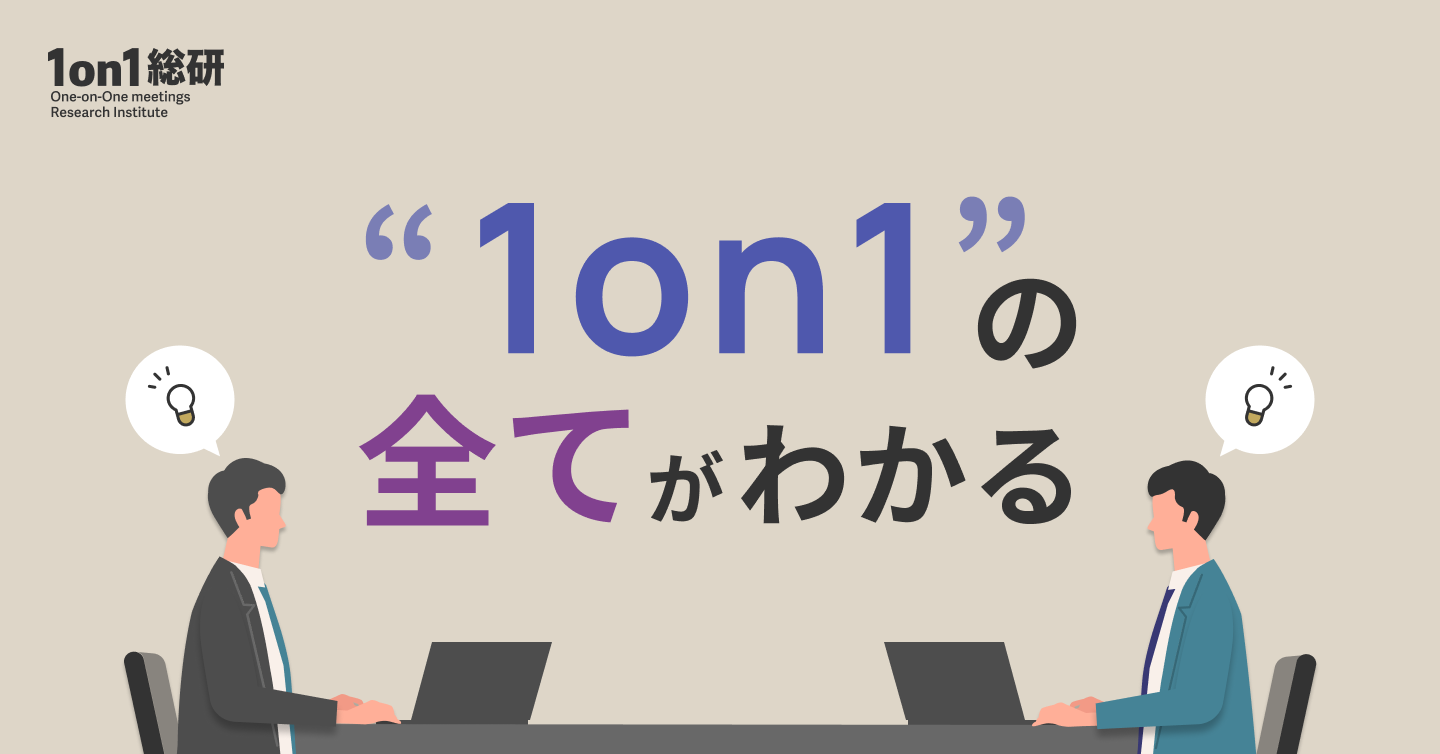
「フォロワーシップ」を知れば、会社が変わる
「組織の成果の8〜9割は、リーダーではなくフォロワーが決める」―この衝撃的な事実が、現代の組織論を根底から覆しています。
リーダーシップ偏重の経営に限界を感じていませんか?実は組織の大半を占めるフォロワーの質こそが、企業の成功を左右する最重要要素なのです。Google、Spotify、トヨタ記念病院など先進企業は、フォロワーの主体性と創造性を引き出す仕組みで圧倒的な成果を上げています。本記事では、ロバート・ケリー教授が提唱する5つのフォロワータイプから、各業界の革新的な活用事例、そして組織を変革する実践的な育成方法まで、フォロワーシップの全貌を解説します。

あなたの会社を変える魔法の言葉!MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の作り方
「なぜ、うちの会社は方向性がバラバラなのか」―その答えは、MVVの不在にあるかもしれません。
ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)は、組織の存在意義と進むべき道を示す羅針盤です。Microsoft、Amazon、メルカリなど成功企業は例外なく明確なMVVを掲げ、それを経営の軸として成長を続けています。本記事では、MVVの基本概念から、成功企業の事例分析、8つの策定ステップ、7つの分析フレームワーク、そして組織への浸透方法まで、MVVを効果的に活用するための実践的な知識を体系的に解説します。



