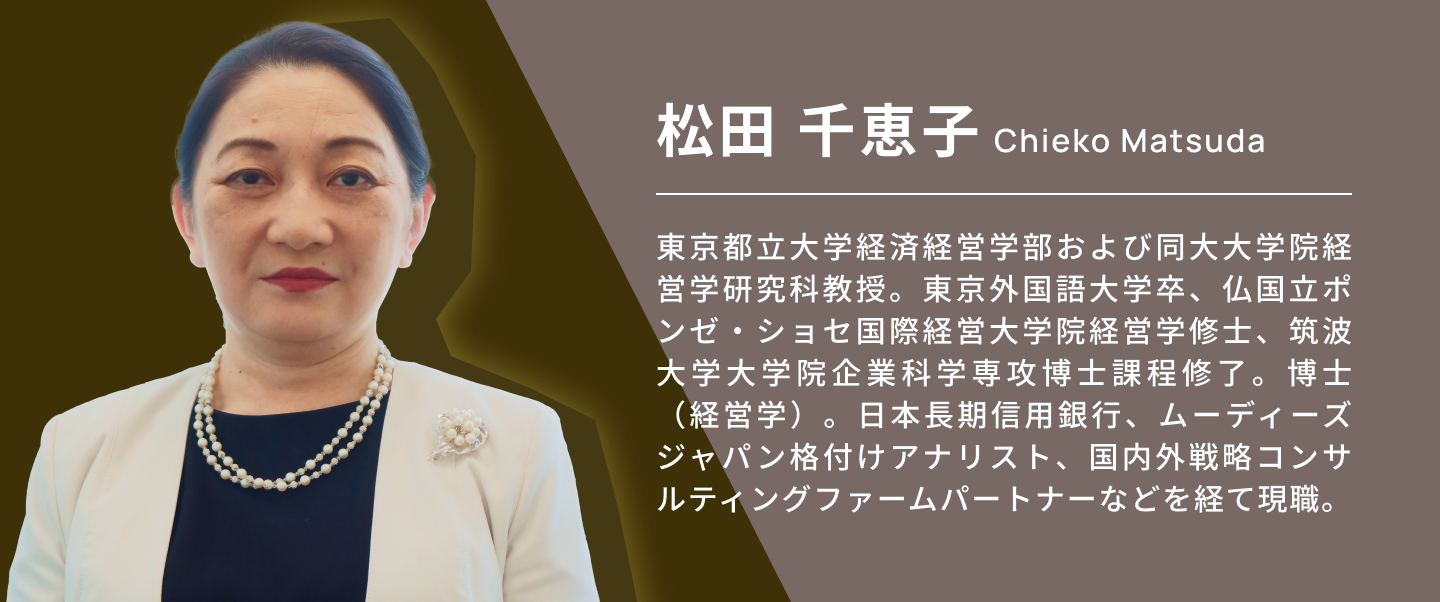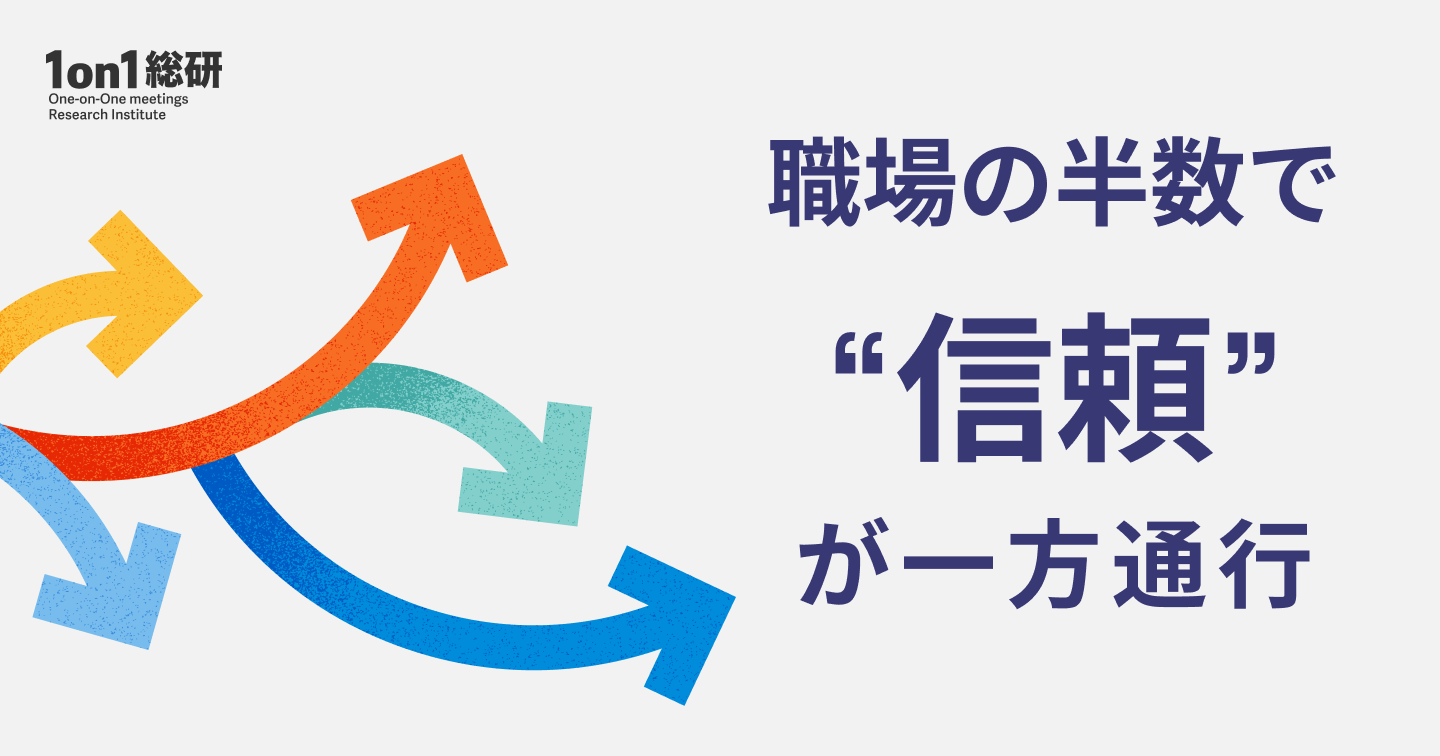組織風土
チーム全員が幸福であることが成果を最大にする。ゆめみCHRO太田氏が語る“関係性のマネジメント”
ティール組織の実践企業として知られる株式会社ゆめみ。
全員CEO制や助言プロセスなど、自律を支える仕組みを取り入れてきたが、その根底にあるのは「関係性をどう築くか」という問いである。コーチング専門部隊の設置、リモートから出社への転換、そして2025年に始まった1on1制度——。
同社CHROの太田昂志氏は、試行錯誤の末に見出したのは「聴くこと」ではなく「関係性を機能させること」だと語る。幸福と成果を両立させるチームをいかに設計するのか。その思想と実践を聞いた。

株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO
システムインテグレーター等を経て、株式会社ゆめみに入社。CHRO、取締役、上席執行役員を歴任し、DX・内製化支援の分野でリーディングカンパニーとしての成長に貢献。「働きがいのある会社」アワード各賞の受賞にも導いた。共著に『職場を上手にモチベートする科学的方法 無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社)がある。

「お客様化」する若手社員と、感情ケアに疲弊するミドルマネジャー。井上慎平氏が指摘する「上司の役割」の問題点
「新人のエンゲージメントの低さについて、ミドルマネジャーの管理能力が問われることは正しいのでしょうか」――話題の書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の著者・井上慎平氏は、今日の「上司の役割」に疑問を呈する。
部下の感情ケアで疲弊する中間管理職、「お客様化」する若手社員、誰も傷つかない対話、そして組織が持つ残酷さ――。
現代組織が抱える構造的な問題について、1on1総研編集長・下元陽が井上氏に話を聞くと、「綺麗事」を突き放す言葉が次々と返ってきた。
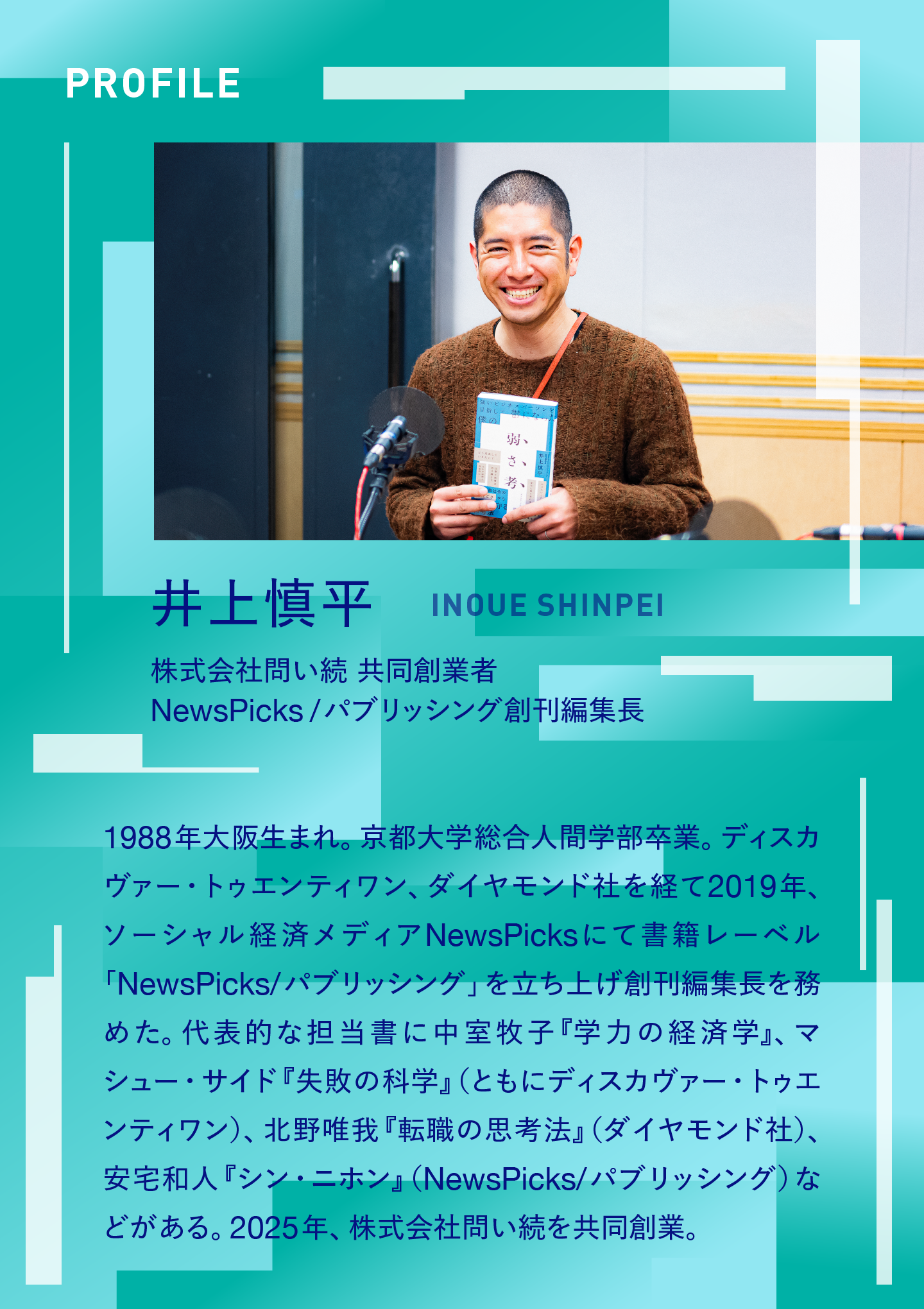

【社員のタイプ別】「静かな退職」への現実的マネジメント術
辞めるわけではないが、仕事への意欲を失い、必要最低限の業務しかしなくなる──。そんな「静かな退職(Quiet Quitting)」が組織課題として注目されている。黙って与えられた仕事だけをこなす姿勢は、短期的には問題が表面化しづらいが、放置すればチームの熱量を奪い、組織の推進力を損なうリスクがある。
働き方の多様化やキャリア観の変化を背景に、「静かな退職」に至る理由は一様ではなくなっている。マネジャーは、こうしたメンバーとどう向き合えばいいのか。必要なのは、価値観を否定せず、現実的な対話と実務的な工夫によって、チーム全体の熱量を維持することだ。この記事では、その考え方と具体的なアプローチを提案する。
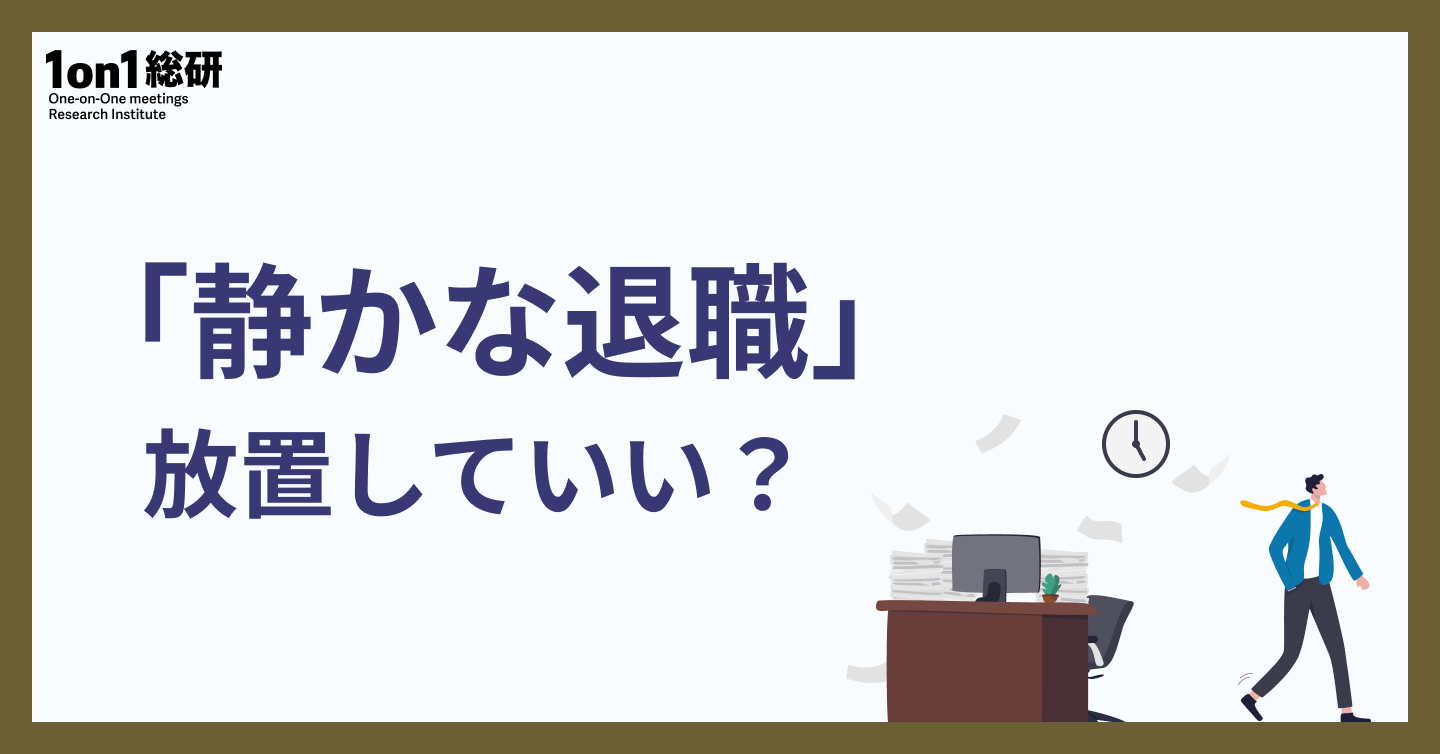
【アルムナイ採用完全ガイド】メリット・導入手順・成功事例を徹底解説
少子高齢化による人手不足、終身雇用モデルの変化、そして人的資本経営の広がりを受け、いま注目されているのが「アルムナイ採用」です。
退職者を単なる過去の人材ではなく、新たな「資源」として迎え入れることで、採用コストやミスマッチを抑制できるうえ、元社員が築いたネットワークを通じて新規ビジネスや顧客開拓にもつなげられます。
本記事では、アルムナイ採用の基礎知識からメリット・デメリット、導入の具体手順、成功企業の事例、そして導入前に押さえておきたいFAQまで、幅広く解説します。ぜひ自社の採用戦略にお役立てください。

【発想転換】「社員は会社のものではない」から考える人的資本経営
人的資本経営が広がっています。
「人が中心」、「人が輝く」といったきらびやかな印象もある人的資本経営。しかしながら、よく見ると「人」的・「資本」・「経営」の三つの要素で構成されています。人を中心としながらも、資本という財務視点を伴う「経営」であると踏まえるべきでしょう。
したがって、エンゲージメントが向上して組織の雰囲気も良くなったものの、業績が低迷しているのなら人的資本経営の本質とはかけ離れています。求められているのは、企業の価値を高めるための人的資本経営なのです。
そこでコーポレート・ガバナンスや事業ポートフォリオ戦略などに詳しい東京都立大学の松田千恵子教授に、企業経営の本質に則った人的資本経営の何たるかを訊きました。