
人事のAI導入の現在地 ~失敗の要点と成功の条件~
人事部門でのAI導入が加速する今、現場では二極化が進んでいます。「作業量が従来の30分の1になった」という企業あれば、「結局、手作業に戻した」という企業も。同じAI活用でなぜここまで差が生まれてしまうのでしょうか。
本連載は人事図書館館長・吉田洋介さんが様々な人事部門の実践者から収集した「普通の会社における生成AI活用の実例」を、時にプロンプトまで含めて詳細に紹介していきます。連載初回となる今回は、人事のAI導入の現在地を俯瞰しながら、典型的な失敗パターンと成功企業に共通する三つの条件を、具体例と共に解説します。
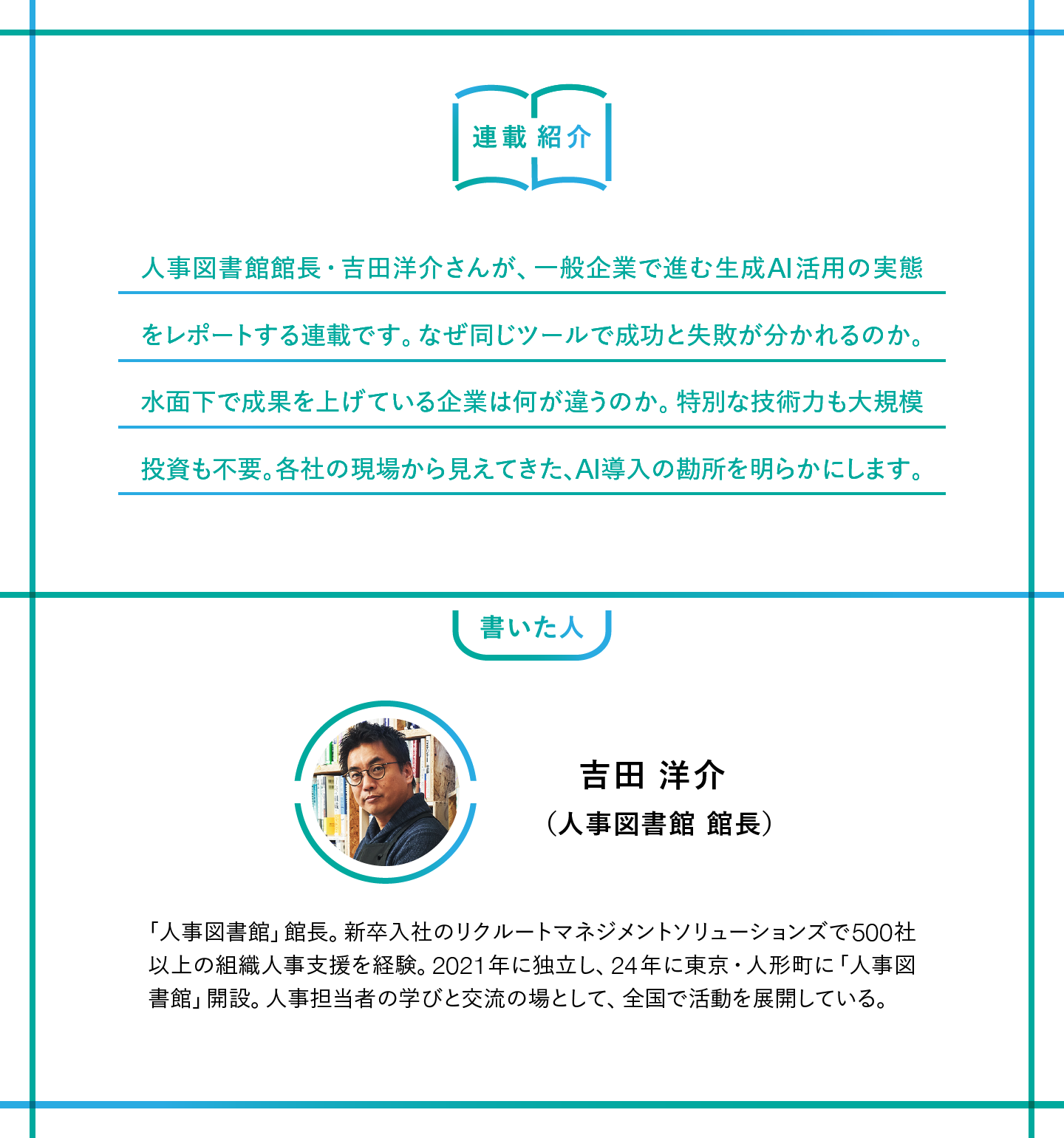
各社で起きている状況
2022年のChatGPT登場から生成AIの活用は大きく進んでいます。仕事に限らず日常でもAIを活用したサービスが毎日のようにあらわれ、人間では出来なかった大量の個別対応やチャットボットでは感じられなかった自然なやりとりなど、様々なことが実現し始めています。
人事の世界でもAIの活用がうたわれるようになって久しいですが、まだまだ慎重な企業と積極的に活用している企業に分かれているようです。カオナビ『人事担当者の生成AI活用に関する実態調査』(2025)によると、活用しているのが44%程度、使用していないが56%程度となっています。他にも日本の人事部『人事白書2025』では66.5%の企業がAIを業務で活用していると回答。取得元データによる違いはありますが、どのデータを見ても概ね半々程度に分かれている状況は間違いなさそうです。
具体的にどう活用しているのかという調査も様々行われていますが、代表的には採用関連(スカウト文面や求人文面の作成など)、各種レポート作成、データ分析などがあがっています。各社の中でも経営からAI活用を強く求められたり、毎日のように「AI活用で業務効率化!」といった記事や広告を見て、人事業務でのAI活用に必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。
典型的な失敗パターンと要因
有用性を期待されているAI活用ですが、実際の成果はどうなっているのでしょうか。人事図書館ではAI活用を進めている企業から話を聞くことも多いのですが、「実際のところうまくいっていない」という声も少なくありません。
例えば率先してAIを活用しようと、様々な社内文章をAIに作成してもらっていたA社では作成された文章の手直しが多く発生し、「結局0から手で作ったほうが早い」となってしまいました。B社ではAIを使って研修と投影スライドを設計しようとしましたが、うまく形にならず「AIはまだまだ現場では使えない」と結論付けています。また、C社では新人研修でAIを習得してもらおうとカリキュラムに入れましたが、配属後の上長から「新人が上司や先輩よりもAIの言うことを正しいと考えているようで育成の手間が増している」という声があがっています。
このように積極的にAIを使おうとしているにも関わらず失敗してしまい、元のやり方に回帰してしまうケースも少なくありません。しかし、みなさんも感じているように今から完全にAI無しの業務に戻すのは事業上で大きなビハインドとなりかねません。
成功企業の共通条件
一方で成功している企業ではどのようにAIが導入されているのでしょうか。
例えば研修設計でのAI導入で大きな工数削減と効果の向上に至っている事例があります。ある企業では、研修に関係する受講者の課題感、研修の目的、得てほしい気づき、踏んでほしいプロセスなどの設計に必要な要素をAIにインプットすることで、自社にあった研修を短時間で概ね組みあげています。また、研修終了後のフォローアップでもAIを活用しています。研修内容を学習したAIが受講者の実践を支援し、学びと実践のサイクルを促進することで、従来以上の研修効果を実現しています。
他にも就業規則や人事制度、社内の様々なガイドラインをAIに読み込ませておくことで、人事に対する社内問合せを大幅に削減している事例も数多くあがってきています。
今までは「就業規則のここに書いてあります」と伝えても、また時間が経ったら「どうなってるんでしたっけ」と問い合わせが繰り返されてしまうということが続いていましたが、AIに問い合わせる形式に変えることで、質問する側も気兼ねなく確認ができ、人事側も毎回説明する工数がとられず、より重要な業務に時間を振り分けられるようになったといいます。
実はここで紹介したものを含め、失敗している企業と成功している企業のやろうとしていること自体に大きな差はありません。生産性を高めたい、AIに代替してほしい、自動化していきたい、などのねらいは同じにも関わらず、どこで大きな差がつくのでしょうか?
私が見てきた中で成功している企業には共通の要件があります。
1.AIの特性(出来ること、限界等)を理解している人事担当者がいる
AIの機能や特性は日々進化しています。ある時に出来なかったことが、今日できるようになったり、目覚ましく反応速度があがったり、芯を食ったやりとりが続くようになることも多々あります。一方でAIの苦手とする処理や理解しづらい情報というのも存在しています。成功している企業ではエンジニアに限らずそのようなAIの特性を理解している人事担当者がいて、社内の展開をサポートしています。
2.実験的に小さく始めている
AIへの期待は大きく、出来るだけレバレッジを利かせたい、という思いから全社導入などを大きく進めてしまいがちです。しかし、社員のリテラシーも様々であったり、まだまだAIの挙動も不安定さを持っているため、一部の社員が「これは使えない」「結局役に立たない」と言い出してしまうことが少なくありません。成功している企業では、積極的に活用してくれそうな部署や本当に困っている部署から小さく実験を始め、改善を重ね成果を上げ、その評判をもとに徐々に他部署に展開しています。 この段階的なアプローチが成功の確率を高めます
3.問題意識>AIの活用
このズレが一番よく発生しています。AI活用そのものが目的となり、「AIを使って何ができるか」から発想してしまっているケースです。もちろんその発想が悪いわけではないのですが、「ハンマーを持つとすべて釘に見える」という逸話と同じようにAIは非常に有用なため様々な課題に活用できてしまいます。しかし、本当に困っている当事者がいなかったり、問題意識がそこまで強くない部分にまでAIを活用しても、結果として積極的に使われない、価値を感じてもらえないという結果に繋がることも少なくありません。
AI導入に向けて
AIに限らず便利なツールが現れる際には典型的に「ツールを使って何とかしよう」という力学が生まれやすくなります。PCの展開した1995年前後、通信速度が大幅に向上した2000年前後、スマホの普及した2010年前後などにも同様の展開がありました。技術者観点でいえば種から発想していくことも非常に重要なのですが、今のところ成功している企業を見るとAIの発展を起点に発想するのではなく、事業上・業務上の問題意識から活用を進めることが近道と言えそうです。
次回は人事のAI導入を具体的にどう進めたら良いのか、いま成果が出やすいのはどの領域なのか、について考えを深めていきます。
各社で起きている状況
2022年のChatGPT登場から生成AIの活用は大きく進んでいます。仕事に限らず日常でもAIを活用したサービスが毎日のようにあらわれ、人間では出来なかった大量の個別対応やチャットボットでは感じられなかった自然なやりとりなど、様々なことが実現し始めています。
人事の世界でもAIの活用がうたわれるようになって久しいですが、まだまだ慎重な企業と積極的に活用している企業に分かれているようです。カオナビ『人事担当者の生成AI活用に関する実態調査』(2025)によると、活用しているのが44%程度、使用していないが56%程度となっています。他にも日本の人事部『人事白書2025』では66.5%の企業がAIを業務で活用していると回答。取得元データによる違いはありますが、どのデータを見ても概ね半々程度に分かれている状況は間違いなさそうです。
具体的にどう活用しているのかという調査も様々行われていますが、代表的には採用関連(スカウト文面や求人文面の作成など)、各種レポート作成、データ分析などがあがっています。各社の中でも経営からAI活用を強く求められたり、毎日のように「AI活用で業務効率化!」といった記事や広告を見て、人事業務でのAI活用に必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。
典型的な失敗パターンと要因
有用性を期待されているAI活用ですが、実際の成果はどうなっているのでしょうか。人事図書館ではAI活用を進めている企業から話を聞くことも多いのですが、「実際のところうまくいっていない」という声も少なくありません。
例えば率先してAIを活用しようと、様々な社内文章をAIに作成してもらっていたA社では作成された文章の手直しが多く発生し、「結局0から手で作ったほうが早い」となってしまいました。B社ではAIを使って研修と投影スライドを設計しようとしましたが、うまく形にならず「AIはまだまだ現場では使えない」と結論付けています。また、C社では新人研修でAIを習得してもらおうとカリキュラムに入れましたが、配属後の上長から「新人が上司や先輩よりもAIの言うことを正しいと考えているようで育成の手間が増している」という声があがっています。
このように積極的にAIを使おうとしているにも関わらず失敗してしまい、元のやり方に回帰してしまうケースも少なくありません。しかし、みなさんも感じているように今から完全にAI無しの業務に戻すのは事業上で大きなビハインドとなりかねません。
成功企業の共通条件
一方で成功している企業ではどのようにAIが導入されているのでしょうか。
例えば研修設計でのAI導入で大きな工数削減と効果の向上に至っている事例があります。ある企業では、研修に関係する受講者の課題感、研修の目的、得てほしい気づき、踏んでほしいプロセスなどの設計に必要な要素をAIにインプットすることで、自社にあった研修を短時間で概ね組みあげています。また、研修終了後のフォローアップでもAIを活用しています。研修内容を学習したAIが受講者の実践を支援し、学びと実践のサイクルを促進することで、従来以上の研修効果を実現しています。
他にも就業規則や人事制度、社内の様々なガイドラインをAIに読み込ませておくことで、人事に対する社内問合せを大幅に削減している事例も数多くあがってきています。
今までは「就業規則のここに書いてあります」と伝えても、また時間が経ったら「どうなってるんでしたっけ」と問い合わせが繰り返されてしまうということが続いていましたが、AIに問い合わせる形式に変えることで、質問する側も気兼ねなく確認ができ、人事側も毎回説明する工数がとられず、より重要な業務に時間を振り分けられるようになったといいます。
実はここで紹介したものを含め、失敗している企業と成功している企業のやろうとしていること自体に大きな差はありません。生産性を高めたい、AIに代替してほしい、自動化していきたい、などのねらいは同じにも関わらず、どこで大きな差がつくのでしょうか?
私が見てきた中で成功している企業には共通の要件があります。
1.AIの特性(出来ること、限界等)を理解している人事担当者がいる
AIの機能や特性は日々進化しています。ある時に出来なかったことが、今日できるようになったり、目覚ましく反応速度があがったり、芯を食ったやりとりが続くようになることも多々あります。一方でAIの苦手とする処理や理解しづらい情報というのも存在しています。成功している企業ではエンジニアに限らずそのようなAIの特性を理解している人事担当者がいて、社内の展開をサポートしています。
2.実験的に小さく始めている
AIへの期待は大きく、出来るだけレバレッジを利かせたい、という思いから全社導入などを大きく進めてしまいがちです。しかし、社員のリテラシーも様々であったり、まだまだAIの挙動も不安定さを持っているため、一部の社員が「これは使えない」「結局役に立たない」と言い出してしまうことが少なくありません。成功している企業では、積極的に活用してくれそうな部署や本当に困っている部署から小さく実験を始め、改善を重ね成果を上げ、その評判をもとに徐々に他部署に展開しています。 この段階的なアプローチが成功の確率を高めます
3.問題意識>AIの活用
このズレが一番よく発生しています。AI活用そのものが目的となり、「AIを使って何ができるか」から発想してしまっているケースです。もちろんその発想が悪いわけではないのですが、「ハンマーを持つとすべて釘に見える」という逸話と同じようにAIは非常に有用なため様々な課題に活用できてしまいます。しかし、本当に困っている当事者がいなかったり、問題意識がそこまで強くない部分にまでAIを活用しても、結果として積極的に使われない、価値を感じてもらえないという結果に繋がることも少なくありません。
AI導入に向けて
AIに限らず便利なツールが現れる際には典型的に「ツールを使って何とかしよう」という力学が生まれやすくなります。PCの展開した1995年前後、通信速度が大幅に向上した2000年前後、スマホの普及した2010年前後などにも同様の展開がありました。技術者観点でいえば種から発想していくことも非常に重要なのですが、今のところ成功している企業を見るとAIの発展を起点に発想するのではなく、事業上・業務上の問題意識から活用を進めることが近道と言えそうです。
次回は人事のAI導入を具体的にどう進めたら良いのか、いま成果が出やすいのはどの領域なのか、について考えを深めていきます。






