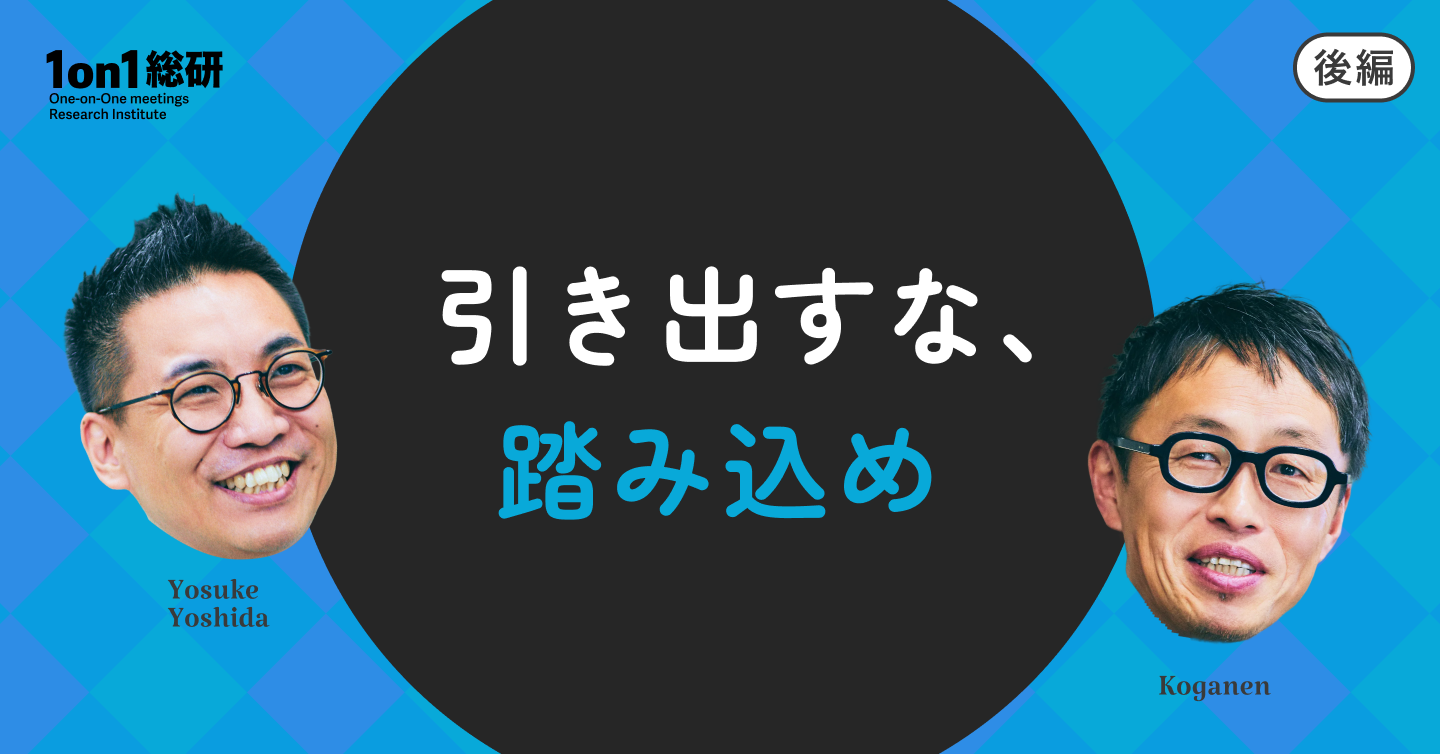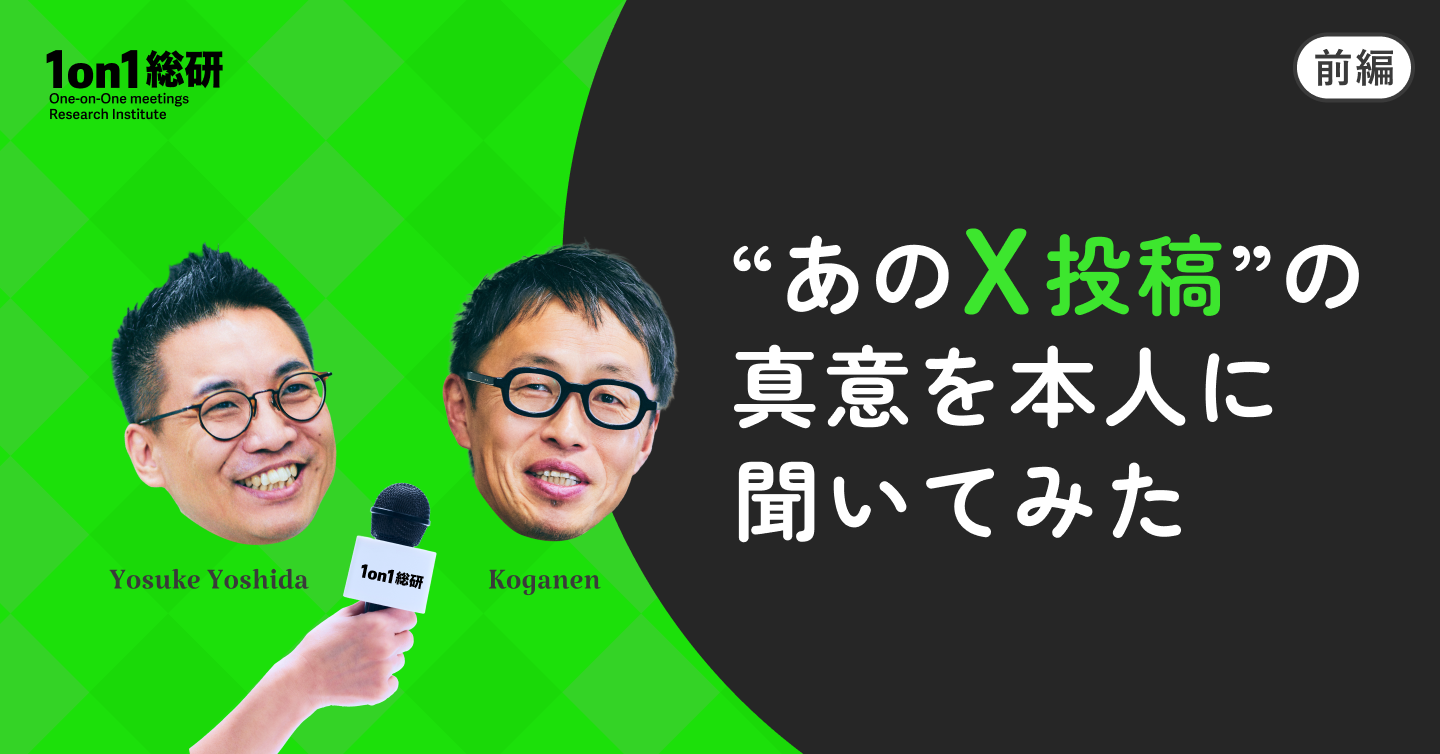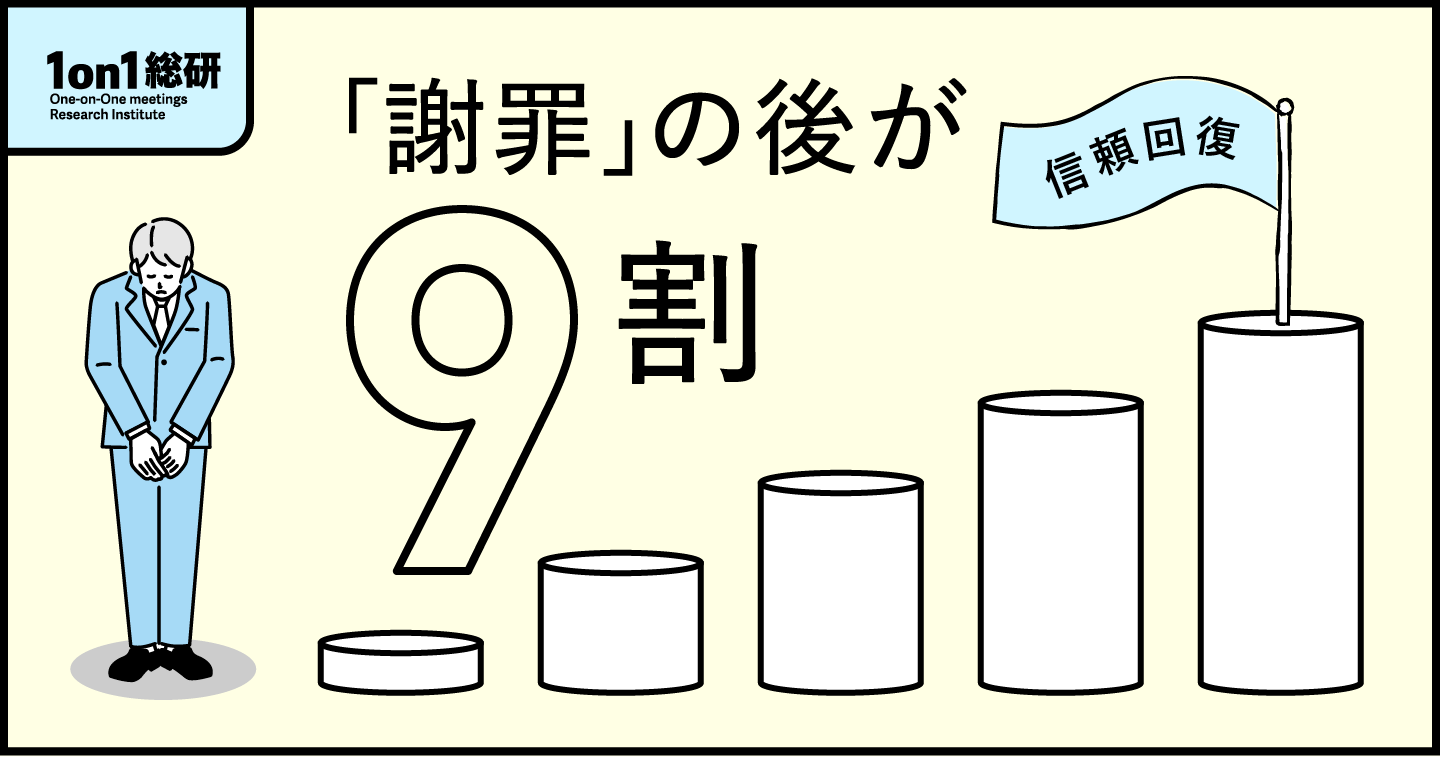自律性を育む1on1 。富士通が選んだ「職場起点」の組織変革
富士通の人事部門は、国内約8万人の従業員に対して1on1を強制しない。月1回30分の対話を推奨し、双方向のコミュニケーションを通じて自律性を育む支援をするが、積極的な介入はしない。「やらされ感でやっても意味がない」――この言葉に、ジョブ型転換を進める同社の人事哲学が凝縮されている。
1on1導入から4年。従業員一人当たりの年間実施回数は平均12.8回まで増加した。一方で、組織文化の変革が一朝一夕には進まない現実も見えてきている。
富士通の組織開発を担う野村哲也氏、同部門でコミュニケーション変革をリードする成田富男氏、秋田依里香氏に、「職場起点」で進める1on1の理想と現実を聞いた。
制度改革で高まる「新たな対話」の必要性
2019年、富士通は国内約8万人の従業員を擁する巨大組織でジョブ型人事制度への全面転換を決定した。2020年に幹部社員、2022年に一般社員へと段階的に導入。平松浩樹CHRO(最高人事責任者)が掲げた「フルモデルチェンジ」の号令の下、従来のメンバーシップ型からの大転換が始まった。
――富士通はこの数年で大きな制度改革を進め、1on1も開始しています。なぜ1on1が必要になったのでしょうか。
野村 まず、事業構造の転換が背景にあります。SI(システムインテグレーション)中心のビジネスモデルから社会課題解決型へとシフトしています。正解のない課題に挑むには、部門を超えた深い対話が欠かせません。実際、今はSE、営業、人事、デザイナーといった多様な職種がプロジェクトで協働しています。こうした働き方の変化が、1on1の必要性を大きく高めました。
また、人事制度の根本的な転換を進める中で、キャリアオーナーシップ、つまり自律的なキャリア形成が重要テーマに浮上しました。従来は年2回の評価面談のみ。期初の目標設定と期末のフィードバックだけで、それ以外に会社として定めた対話の仕組みはありませんでした。しかし、自律的なキャリアを促すには、評価とは切り離された、継続的な対話の場が不可欠でした。

――1on1を社内でどのように定義し、どんな仕組みとして設計したのですか。
成田 1on1の必要性を現場に伝えるため、1on1の理解を促進することからスタートしました。そして、まず、1on1を「メンバーの成長支援の場」と定義しました。主役はあくまでメンバー。自分のキャリアを見つめ直し、上司と対話しながら次のステップを描く。評価面談のような一方通行ではなく、メンバーがこの場をフル活用するくらいの主体性が理想です。
月1回30分の1on1を推奨し、3カ月に1回は「Connect Conversations*」として”中長期的”な観点での個人のパフォーマンスとキャリアについて語り合う場にしました。
人事が積極的に介入しない理由
――新しい仕組みである1on1の導入にあたり、8万人組織への浸透は容易ではなかったと思います。
成田 導入当初は習慣化に注力しました。説明会を繰り返し行い、認知度を上げるとともに、コミュニケーションの重要性を改めて認識してもらう機会を多く作るようにしました。コロナ禍以降は、コミュニケーションの頻度が下がったこともあり、現場でもその重要性がより実感されるようになりました。

――具体的にどのような推進策を実施したのですか。
秋田 1on1の促進・定着のため、1on1支援ツール「Kakeai」を導入し、1on1の準備から対話の記録、実施状況の管理まで一元管理できる環境を整えました。並行して、全社イベントでの登壇やオンラインセミナーを通じて、ツールの活用方法や1on1の本質的な意義など伝えました。
成田 現場から個別に相談を受けた時は、現場のニーズに合わせて個別訪問し、セミナーやワークショップを実施しています。
外部の有識者を招く場合もありますが、社内で実施する場合は、参加者同士で1on1の課題を共有し合い、どのようにアプローチすればよいかを対話型で考える場を設けています。
――実施状況はどのようにモニタリングしているのでしょうか。
成田 日々の1on1については、職場が実施状況を確認できるように、Kakeaiのデータを元に弊社独自のダッシュボードを構築し、社内に公開しています。また、Connect Conversationsの際にサーベイを実施し、1on1の課題も可視化しています。
――人事部門としてKPIは設定していますか。
成田 7〜8割程度の実施率を維持したいと考えていますが、明確な目標設定はしていません。実施状況はダッシュボードで見える化して、各組織が自主的に判断する形です。
――人事部門が直接管理せず、現場に任せているのはなぜですか。
野村 やらされ感でやっても意味がありません。変化の激しいビジネス環境で新たなビジネスを生み出すために従来のメンバーシップ型人事制度からジョブ型人事制度へのフルモデルチェンジを進めてきており、コミュニケーションのあり方も「職場起点」の取り組みに大きく舵を切っています。

従来は全社の課題を踏まえ人事部門が制度・仕組みを作り、全社に展開するケースが大半でした。しかし今は、事業単位ごとに組織長が権限を持ち、自らの組織をどうマネジメントしていくかを主体的に考えています。1on1を含めた組織内のコミュニケーションのあり方についても、この職場起点の考え方を基本としています。
組織長が自部門にコミュニケーションの課題があると判断し、1on1がその課題改善に有効であれば、自らメッセージを発信する。私たち人事の役割は、それをサポートする。
――全社統一のルールと各部門の裁量のバランスは。
野村 月1回の1on1は会社が推奨している基準です。それ以上、週1でやってもいいし、月1回で十分というならそれでもいい。基本的に、上司とメンバーで自律的に決めることが大事です。
秋田 実際、富士通は大きい組織で、数百人の社員が所属している部門もあります。そういった組織では独自にエンゲージメント向上策を考えたり、1on1の実施率をKPIに設定したりしています。
また、各組織にはエンゲージメント推進担当者もいて、現場から「1on1を活性化させたい」「うまくいかないので支援してほしい」といった要望が寄せられることも。そういう時は私たちが出向いて、1on1の意義や進め方についてその事業部の方々と一緒に考える場を設けています。

目指すべき「受動的な対応力と能動的な創造力」の両立
導入から4年。富士通の有価証券報告書によれば、1on1は組織に着実に定着している。従業員1人あたりの年間実施回数は、2022年度の9.4回から2023年度は11.7回、2024年度には12.8回と継続的に増加している。

――実際に4〜5年間の実践を経て、どのような変化がありましたか。
秋田 1on1はまず「やってもらう」ところからスタートし、定期的な実施は定着しました。現在は「質」の向上に注力する段階に来ています。
野村 エンゲージメントサーベイの結果を分析すると、コミュニケーションに関する課題が見えてきました。1on1の定着により量は確保されましたが、質はまだ十分ではありません。上司が話しやすい場を作るだけでなく、メンバー側も明確な目的を持って臨む必要がある。1on1を意味のあるものにするのは、上司とメンバー双方が1on1で何を実現したいのかを意識し、積極的なコミュニケーションをとることが第一歩だと考えています。
――なぜそのような課題が生まれるのでしょうか。
野村 まだまだ上司が良い1on1をやってくれることを期待している「待ち」の姿勢の人が多いと感じています。ただ、これは個人の問題というより、私たちの組織文化が影響しているのかもしれません。
当社の強みは、お客様の課題解決に最後まで伴走する「やり切る力」と、常にお客様のために最善を尽くす「顧客志向のカルチャー」です。
SIビジネスにおいては、お客様の多様な要望や要件をシステムで実現すること。この過程で培われた、目標達成への強いコミットメントと、困難な状況でも諦めずにやり遂げる姿勢は、当社の強みだと考えています。
しかしながら、これからのビジネス環境においては、既存の枠組みにとらわれない新たな価値創造が求められます。私たちは、お客様の要望に確実に応える「受動的な対応力」と、市場や社会の変化を先読みし、積極的に新しい提案を行う「能動的な創造力」の両方を高めていく必要があると考えております。

――成田さん、秋田さんはどのような課題を感じていますか。
成田 環境面では、1人の上司が数十人の部下を見ているケースがあります。内容面では、上司の一方的な話や業務報告のみで、建設的なフィードバックがもらえないという声も。メンバー自身が1on1を活用するマインドになっていない場合もあり、ひとりひとりのオーナーシップが不足していると感じます。
秋田 人事として主体的な活用を促していますが、全ての社員が実践できているわけではありません。価値観や考え方が合わないケースもあり、1on1自体に苦しさを感じている人もいます。そういった状況の中で、社員のマインドを変えていくことは決して簡単なことではないと痛感しています。
――課題が見えてきた一方で、発展的な動きも生まれていますか。
成田 現場主導で「斜めの1on1」が広がっています。上司とだけではキャリアについて深く話せないケースもあり、上司以外の人との1on1や、横の1on1を推進している部門もあります。メンバーが自発的に別部門の方と1on1を実施するケースも出てきました。
また、ポスティング制度*との連動も一般化しました。応募前に希望部署の人と1on1をして、実際の仕事内容や雰囲気を確認する。そういう活用法も広がりつつあります。

――1on1は短期的には効果が見えづらいと言われます。投資対効果をどう考えますか。
野村 その点は私たちも課題として認識しています。組織風土の変革は1、2年でできる話ではなく、効果が現れるまでに時間がかかります。
人事施策は短期の成果を求められがちですが、私たちは長期的な視点で1on1がもたらす変化を追跡し、その効果を可視化しようと試みています。
長期的には、1on1でコミュニケーションを取ることが当たり前になって、それが上司・メンバーだけでなく、社内の横の関係や斜めの関係、さらには社外にまで広がっていってほしい。1on1は、富士通の大きな課題である縦割りや組織の壁を壊し、ビジネスモデル変革を推進する可能性を秘めていると思います。
制度改革で高まる「新たな対話」の必要性
2019年、富士通は国内約8万人の従業員を擁する巨大組織でジョブ型人事制度への全面転換を決定した。2020年に幹部社員、2022年に一般社員へと段階的に導入。平松浩樹CHRO(最高人事責任者)が掲げた「フルモデルチェンジ」の号令の下、従来のメンバーシップ型からの大転換が始まった。
――富士通はこの数年で大きな制度改革を進め、1on1も開始しています。なぜ1on1が必要になったのでしょうか。
野村 まず、事業構造の転換が背景にあります。SI(システムインテグレーション)中心のビジネスモデルから社会課題解決型へとシフトしています。正解のない課題に挑むには、部門を超えた深い対話が欠かせません。実際、今はSE、営業、人事、デザイナーといった多様な職種がプロジェクトで協働しています。こうした働き方の変化が、1on1の必要性を大きく高めました。
また、人事制度の根本的な転換を進める中で、キャリアオーナーシップ、つまり自律的なキャリア形成が重要テーマに浮上しました。従来は年2回の評価面談のみ。期初の目標設定と期末のフィードバックだけで、それ以外に会社として定めた対話の仕組みはありませんでした。しかし、自律的なキャリアを促すには、評価とは切り離された、継続的な対話の場が不可欠でした。

――1on1を社内でどのように定義し、どんな仕組みとして設計したのですか。
成田 1on1の必要性を現場に伝えるため、1on1の理解を促進することからスタートしました。そして、まず、1on1を「メンバーの成長支援の場」と定義しました。主役はあくまでメンバー。自分のキャリアを見つめ直し、上司と対話しながら次のステップを描く。評価面談のような一方通行ではなく、メンバーがこの場をフル活用するくらいの主体性が理想です。
月1回30分の1on1を推奨し、3カ月に1回は「Connect Conversations*」として”中長期的”な観点での個人のパフォーマンスとキャリアについて語り合う場にしました。
人事が積極的に介入しない理由
――新しい仕組みである1on1の導入にあたり、8万人組織への浸透は容易ではなかったと思います。
成田 導入当初は習慣化に注力しました。説明会を繰り返し行い、認知度を上げるとともに、コミュニケーションの重要性を改めて認識してもらう機会を多く作るようにしました。コロナ禍以降は、コミュニケーションの頻度が下がったこともあり、現場でもその重要性がより実感されるようになりました。

――具体的にどのような推進策を実施したのですか。
秋田 1on1の促進・定着のため、1on1支援ツール「Kakeai」を導入し、1on1の準備から対話の記録、実施状況の管理まで一元管理できる環境を整えました。並行して、全社イベントでの登壇やオンラインセミナーを通じて、ツールの活用方法や1on1の本質的な意義など伝えました。
成田 現場から個別に相談を受けた時は、現場のニーズに合わせて個別訪問し、セミナーやワークショップを実施しています。
外部の有識者を招く場合もありますが、社内で実施する場合は、参加者同士で1on1の課題を共有し合い、どのようにアプローチすればよいかを対話型で考える場を設けています。
――実施状況はどのようにモニタリングしているのでしょうか。
成田 日々の1on1については、職場が実施状況を確認できるように、Kakeaiのデータを元に弊社独自のダッシュボードを構築し、社内に公開しています。また、Connect Conversationsの際にサーベイを実施し、1on1の課題も可視化しています。
――人事部門としてKPIは設定していますか。
成田 7〜8割程度の実施率を維持したいと考えていますが、明確な目標設定はしていません。実施状況はダッシュボードで見える化して、各組織が自主的に判断する形です。
――人事部門が直接管理せず、現場に任せているのはなぜですか。
野村 やらされ感でやっても意味がありません。変化の激しいビジネス環境で新たなビジネスを生み出すために従来のメンバーシップ型人事制度からジョブ型人事制度へのフルモデルチェンジを進めてきており、コミュニケーションのあり方も「職場起点」の取り組みに大きく舵を切っています。

従来は全社の課題を踏まえ人事部門が制度・仕組みを作り、全社に展開するケースが大半でした。しかし今は、事業単位ごとに組織長が権限を持ち、自らの組織をどうマネジメントしていくかを主体的に考えています。1on1を含めた組織内のコミュニケーションのあり方についても、この職場起点の考え方を基本としています。
組織長が自部門にコミュニケーションの課題があると判断し、1on1がその課題改善に有効であれば、自らメッセージを発信する。私たち人事の役割は、それをサポートする。
――全社統一のルールと各部門の裁量のバランスは。
野村 月1回の1on1は会社が推奨している基準です。それ以上、週1でやってもいいし、月1回で十分というならそれでもいい。基本的に、上司とメンバーで自律的に決めることが大事です。
秋田 実際、富士通は大きい組織で、数百人の社員が所属している部門もあります。そういった組織では独自にエンゲージメント向上策を考えたり、1on1の実施率をKPIに設定したりしています。
また、各組織にはエンゲージメント推進担当者もいて、現場から「1on1を活性化させたい」「うまくいかないので支援してほしい」といった要望が寄せられることも。そういう時は私たちが出向いて、1on1の意義や進め方についてその事業部の方々と一緒に考える場を設けています。

目指すべき「受動的な対応力と能動的な創造力」の両立
導入から4年。富士通の有価証券報告書によれば、1on1は組織に着実に定着している。従業員1人あたりの年間実施回数は、2022年度の9.4回から2023年度は11.7回、2024年度には12.8回と継続的に増加している。

――実際に4〜5年間の実践を経て、どのような変化がありましたか。
秋田 1on1はまず「やってもらう」ところからスタートし、定期的な実施は定着しました。現在は「質」の向上に注力する段階に来ています。
野村 エンゲージメントサーベイの結果を分析すると、コミュニケーションに関する課題が見えてきました。1on1の定着により量は確保されましたが、質はまだ十分ではありません。上司が話しやすい場を作るだけでなく、メンバー側も明確な目的を持って臨む必要がある。1on1を意味のあるものにするのは、上司とメンバー双方が1on1で何を実現したいのかを意識し、積極的なコミュニケーションをとることが第一歩だと考えています。
――なぜそのような課題が生まれるのでしょうか。
野村 まだまだ上司が良い1on1をやってくれることを期待している「待ち」の姿勢の人が多いと感じています。ただ、これは個人の問題というより、私たちの組織文化が影響しているのかもしれません。
当社の強みは、お客様の課題解決に最後まで伴走する「やり切る力」と、常にお客様のために最善を尽くす「顧客志向のカルチャー」です。
SIビジネスにおいては、お客様の多様な要望や要件をシステムで実現すること。この過程で培われた、目標達成への強いコミットメントと、困難な状況でも諦めずにやり遂げる姿勢は、当社の強みだと考えています。
しかしながら、これからのビジネス環境においては、既存の枠組みにとらわれない新たな価値創造が求められます。私たちは、お客様の要望に確実に応える「受動的な対応力」と、市場や社会の変化を先読みし、積極的に新しい提案を行う「能動的な創造力」の両方を高めていく必要があると考えております。

――成田さん、秋田さんはどのような課題を感じていますか。
成田 環境面では、1人の上司が数十人の部下を見ているケースがあります。内容面では、上司の一方的な話や業務報告のみで、建設的なフィードバックがもらえないという声も。メンバー自身が1on1を活用するマインドになっていない場合もあり、ひとりひとりのオーナーシップが不足していると感じます。
秋田 人事として主体的な活用を促していますが、全ての社員が実践できているわけではありません。価値観や考え方が合わないケースもあり、1on1自体に苦しさを感じている人もいます。そういった状況の中で、社員のマインドを変えていくことは決して簡単なことではないと痛感しています。
――課題が見えてきた一方で、発展的な動きも生まれていますか。
成田 現場主導で「斜めの1on1」が広がっています。上司とだけではキャリアについて深く話せないケースもあり、上司以外の人との1on1や、横の1on1を推進している部門もあります。メンバーが自発的に別部門の方と1on1を実施するケースも出てきました。
また、ポスティング制度*との連動も一般化しました。応募前に希望部署の人と1on1をして、実際の仕事内容や雰囲気を確認する。そういう活用法も広がりつつあります。

――1on1は短期的には効果が見えづらいと言われます。投資対効果をどう考えますか。
野村 その点は私たちも課題として認識しています。組織風土の変革は1、2年でできる話ではなく、効果が現れるまでに時間がかかります。
人事施策は短期の成果を求められがちですが、私たちは長期的な視点で1on1がもたらす変化を追跡し、その効果を可視化しようと試みています。
長期的には、1on1でコミュニケーションを取ることが当たり前になって、それが上司・メンバーだけでなく、社内の横の関係や斜めの関係、さらには社外にまで広がっていってほしい。1on1は、富士通の大きな課題である縦割りや組織の壁を壊し、ビジネスモデル変革を推進する可能性を秘めていると思います。