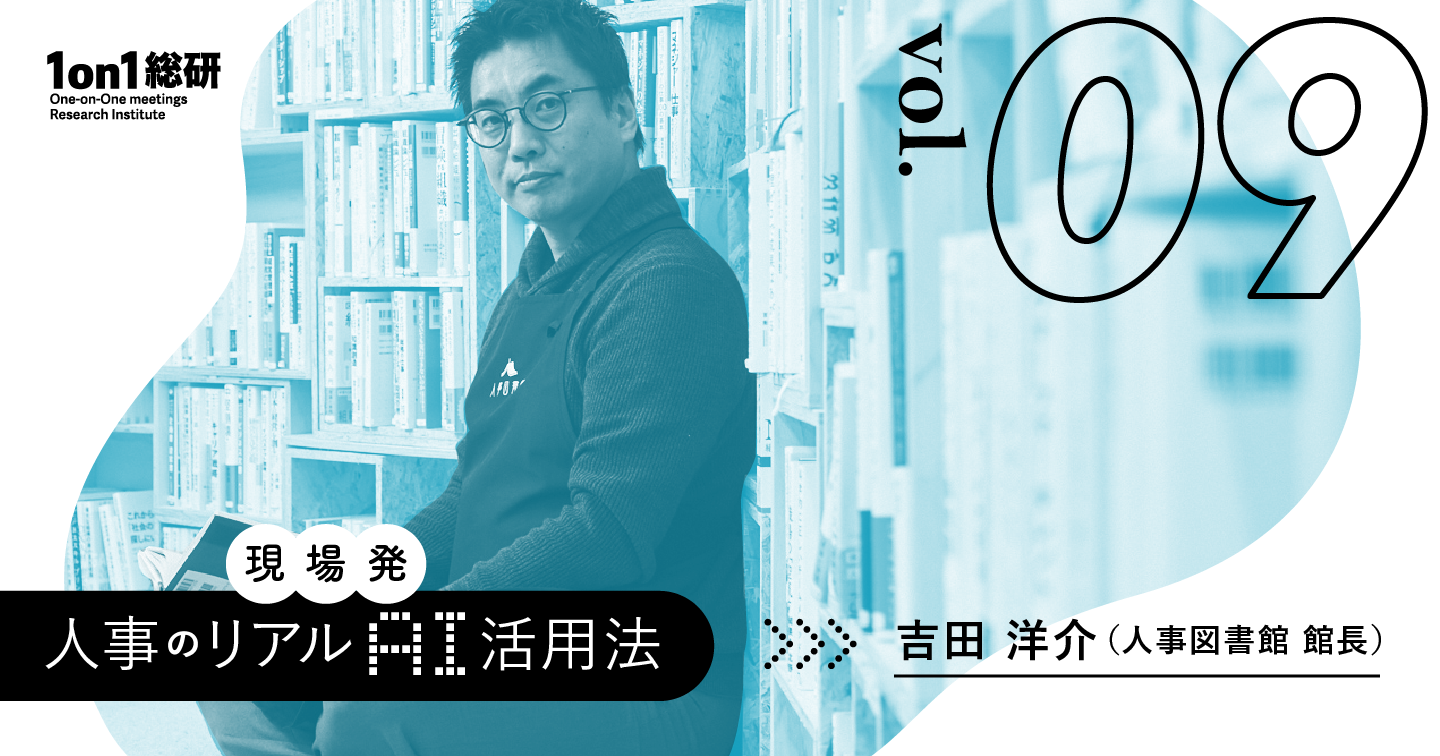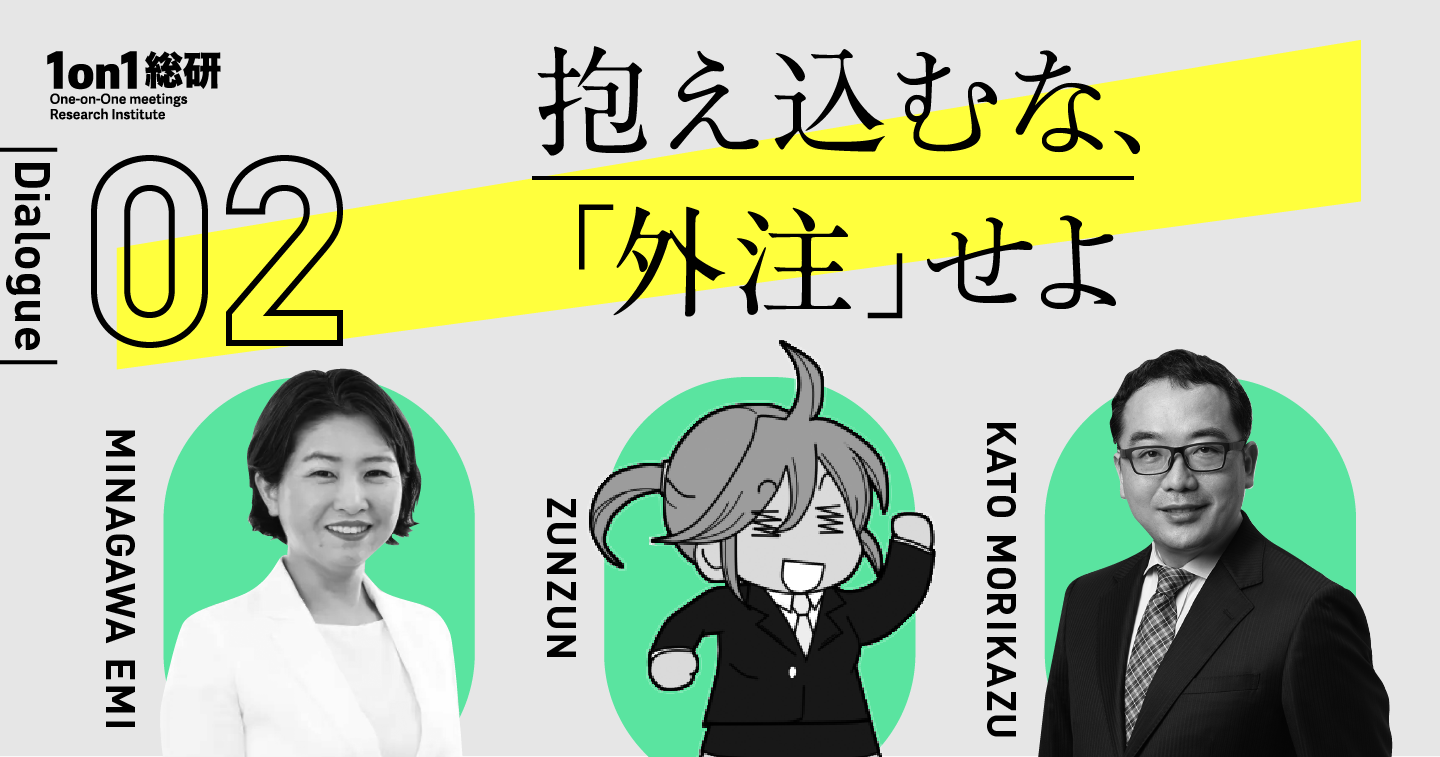人的資本経営が創る未来――従業員の力を最大化する投資と1on1の活用法
市場環境が大きく変化する中、時代の要請に応える経営手法として注目を集めているのが「人的資本経営」です。本記事では人的資本経営の本質をわかりやすく解説します。
人的資本経営とは何か
人的資本経営は、企業価値向上の鍵を握るのは「人材」であるという視点から、従業員の能力・経験・モチベーションを“資本”として捉え、積極的に投資を行っていく経営手法です。
従来は「人件費」というコスト発想で捉えられがちだった人材を、企業の長期的成長を担う重要な資本として位置付ける点が特徴といえます。
この考え方の根底には、18世紀のアダム・スミスや、ノーベル経済学賞を受賞したゲーリー・ベッカーなどが唱えた「人的資本論」があります。
人的資本論では、教育やトレーニングを通じて人が獲得した能力は、企業や社会に大きな付加価値をもたらすとされてきました。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)やグローバル化が加速する中、企業が競争優位を築く上でも、“人への投資”が不可欠という考え方が再注目されています。
従来の人事との違いー「人的資源」から「人的資本」へ
これまでの人事・経営手法では、従業員を「人的資源(Human Resource)」と呼び、コストや配置効率の観点から管理・最適化する傾向が強く見られました。
一方、人的資本経営では、従業員一人ひとりがもつ潜在能力や専門性を“価値創造の源泉”と捉え、あえて投資を行い、最大限の成果を引き出そうとします。
この違いは、経営視点にも大きく影響します。短期利益の確保を最優先とし、必要以上のコスト削減や人員削減に走るのではなく、長期的・戦略的視野で人材育成やエンゲージメント向上にリソースを振り向ける。その結果、企業カルチャーの革新や持続的なイノベーション創出が期待できるようになるのです。
なぜ今「人的資本経営」が注目されているのか
📍 人への投資が競争力を左右する時代
世界的な技術革新と激化するグローバル競争の中で、企業の競争力は「どれだけ優秀な人材を引き付け、育成し、定着させるか」に大きく左右されるようになりました。
モノや設備に投資するだけでは差別化が難しい時代において、人の知恵や創造力こそが新たな付加価値を生み出す原動力です。
さらに、AIやビッグデータ解析など高度なデジタル技術を活用できる人材の獲得は、多くの企業の急務となっています。人材市場が流動化し、多様な働き方が広がる中で、一度採用した優秀な人材をいかに企業の成長に活かし続けられるかが、企業の命運を握るようになってきました。
📍 SDGs・ESGの潮流
企業は、財務指標だけでなくSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)を念頭に置いた経営が求められています。特にESG投資の拡大によって、社会課題の解決や従業員の働きがい創出といった「S(Social)」の要素が企業評価に大きく影響を及ぼしています。
「人的資本経営」の取り組みは、そのままESGの“Social”部分に深く関わるため、投資家やステークホルダーからの評価を上げる手段としても注目度を増しています。
📍 ポストコロナ時代の組織課題
コロナ禍でリモートワークが普及し、従業員同士のコミュニケーションが希薄になったり、エンゲージメントが低下したりするリスクが顕在化しました。また、オンライン環境に適応できない組織体制や評価制度の不備も浮き彫りになり、離職率の上昇が経営課題となる企業も少なくありません。
こうした状況を打開し、従業員のモチベーションや健康(ウェルビーイング)を保ちながら企業としての競争力を維持するには、人的資本経営が欠かせないという認識が急速に広まっています。
📍 国内外のルール整備
海外でも規制強化やガイドライン策定が進んでいます。米国ではSEC(米国証券取引委員会)が上場企業に対して人的資本情報の開示を義務付けています(具体的な開示項目は企業の裁量に任されている)。
日本でも2023年度から有価証券報告書において「人的資本投資に関する方針・指標」の開示が求められるようになりました。
さらに、「人的資本経営コンソーシアム」の設立や経団連の提言など、政府や経済団体が一体となって人的資本経営を推進する流れも強まっています。このような制度面の後押しが、企業の「人への投資」を加速させる理由のひとつとなっているのです。
人的資本経営に取り組むメリット
📍 企業イメージ・評価の向上
人的資本経営を積極的に進める企業は、従業員を大切にする姿勢を内外に示すことができます。これは採用マーケットにおいて優秀な人材を引き寄せる要因となるのはもちろん、顧客や取引先からの信頼獲得にも寄与します。また、ESG投資を行う機関投資家や株主にとっても、人的資本を重視する企業は投資先として魅力的な存在となります。
📍 従業員エンゲージメント・生産性の向上
従業員を企業成長の主役と捉え、キャリア開発やリスキリング(学び直し)の機会を提供したり、多様性を尊重する職場環境を整えたりすることで、従業員のエンゲージメントが高まります。モチベーションを持って働ける組織では自然と生産性も上がり、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなるでしょう。
📍 業績・財務面での恩恵
人的資本経営は、短期的な人件費削減とは対極に位置しますが、長期的には企業の収益力や利益率を高めることが期待できます。従業員定着率の向上やイノベーション創出、顧客満足度の向上など、さまざまな形で「人への投資」がリターンを生み出すからです。
また、人的資本に注力する企業はESG投資資金を呼び込みやすいとも言われており、株価評価においてプラスに作用する可能性も高まっています。
📍 法令対応のスムーズ化
人的資本経営を行うことで、人材戦略の明確化や人事データの整備が進みます。これらは、有価証券報告書や各種開示資料での情報提供に役立つだけでなく、労働関連法令の遵守やハラスメント対策の推進など、法令対応の面でもスムーズに進める下地となります。
人的資本経営に関する国内外の動向・ガイドライン
米国の事例
米国の上場企業は、SEC(米国証券取引委員会)のRegulation S‑K改正に基づき、人的資本資源に関する情報を開示するよう求められています。ただし、具体的な指標は、企業のビジネス特性に応じて重要と判断された情報を自社で選定して報告する形式となっています。投資家はそれらの開示情報を基に企業の長期的成長の可能性を評価する傾向が強まっています。
日本の事例
日本では、2023年度から上場企業の有価証券報告書において、人的資本投資や人材戦略に関する情報の開示が義務化されています。
具体的には、採用や離職の状況、多様性に関する指標(例:女性管理職比率)や、リスキリングへの投資額などが報告され、これらの情報は投資家やその他のステークホルダーによる企業評価の材料となっています。
また、企業が人的資本の情報開示を行う際の参考フレームワークとして、内閣官房や経済産業省が示す「人的資本可視化指針」などが挙げられます。
これらの指針では、一般的に以下の七つの分野(合計19項目程度)を参考にして人的資本の状況を整理するケースが多いです(なお、各社が採用する具体的な指標や分類は、自社の事情に応じて異なる場合があります)。
✅ 人的資本戦略・方針(企業のビジョンや経営戦略との連動性など)
✅ 組織構造・制度(雇用形態やジョブ型制度の導入状況など)
✅ 報酬・評価制度(報酬ポリシーや業績連動型インセンティブなど)
✅ 多様性とインクルージョン(女性管理職比率、国籍・年齢構成、障がい者雇用など)
✅ 人材育成・キャリア支援(研修制度、リスキリング支援、キャリアパスの透明性など)
✅ エンゲージメント・ウェルビーイング(離職率、労働時間、健康管理施策など)
✅ コーポレートガバナンス・コンプライアンス(リーダーシップの透明性、内部通報制度など)
各分野では、例えば研修受講率、離職率、女性管理職比率などのKPI(主要業績評価指標)を定量的および定性的に評価し、PDCAサイクルに基づく継続的な改善活動を通じて、従業員エンゲージメントや企業価値の向上が図られています。
人的資本経営を実践するためのステップ
人的資本経営を成功させるには、以下のステップで計画的に取り組むことが重要です。
1.経営戦略と人材戦略の連動
まずは、自社のビジョンや経営方針を改めて整理し、それを支えるための人材戦略を策定します。伊藤レポートでも指摘されているように、人的資本への投資は経営戦略とワンセットで考えないと、効果が断片化してしまいがちです。トップマネジメントと人事部門、各事業部門が連携し、同じゴールを共有することが大切です。
2.現状と理想像のギャップ把握
次に、自社の人的資本に関する定量データや定性情報を収集し、現状を客観的に把握します。たとえば、スキルマップの作成やエンゲージメント調査を行うことで、どの部門がどのスキルセットを必要としているのか、従業員が抱えている不満や課題は何か、といった具体的な問題点が浮き彫りになります。そのうえで「理想像(目指すべき姿)」とのギャップを測定し、優先すべき施策を見極めます。
3.KPI設定と施策の立案・実行
ギャップを明らかにしたら、解消するため、下記のような具体的な目標(KPI)を設定します。
<例>
📍「従業員エンゲージメントスコアを2年後に10%向上させる」
📍「女性管理職比率を3年後に30%にする」
📍「年間のリスキリング研修受講率をXX%以上にする」
この時、測定可能な形で目標を定義することが重要です。その目標に基づき、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の推進や企業カルチャー改革、エンゲージメント向上施策、働き方改革・ウェルビーイング向上施策など、複数の施策を組み合わせて実行していきます。
4.モニタリングと改善(PDCAサイクル)
施策を実行し始めたら、定期的にKPIをモニタリングし、その進捗や効果を測定します。結果が思わしくない場合は原因を分析し、アプローチを改善するというPDCAサイクルを回すことが欠かせません。長期視点で取り組む人的資本経営だからこそ、柔軟かつ継続的な検証プロセスが成果を左右します。
人的資本経営の成功事例
企業の成長を支える「人的資本経営」は、多くの企業で注目されています。以下で、先進的な取り組みを行う日本企業の事例を紹介。社員の活力を最大化しながら企業価値を向上させる戦略を探ります。
富士通
富士通は2020年7月に「Work Life Shift」というコンセプトを掲げて、ニューノーマル時代の新しい働き方に挑戦しています。これは「Smart Working」「Borderless Office」「Culture Change」の3つを柱とし、テレワーク環境の整備や仮想デスクトップの活用、コミュニケーションの新しい文化づくりを推進してきた結果、社員の通勤時間の大幅削減や育児との両立、副業による知見拡大など、仕事と生活の両面でエンゲージメント向上に成果を上げています。せ
その1年間の実践を踏まえ、2021年10月に発表された「Work Life Shift 2.0」では、「WorkとLifeの融合」に目を向け、社員一人ひとりのWell-Being実現を重視しています。具体的には、男性育児参加率100%を目指す取り組みや、ワーケーションを通じた創造性の向上、副業の積極推奨によるスキルや視野の拡大などを推進中です。また、オフィスを情報交換や雑談の場として活用する「Hybrid Work」を進め、リアルとオンラインを組み合わせた効率的で豊かな働き方を追求しています。
参考:「働き方改革の本質とは。Work Life Shift 2.0で富士通が目指すもの」
オムロン
「Shaping the Future 2030(SF2030)」のビジョンのもと、人的資本経営を推進し、社員の多様性と成長を企業の原動力と位置づけています。特に「ダイバーシティ&インクルージョン」の加速を掲げ、国籍・性別・障がいの有無を問わず、すべての社員が活躍できる環境づくりに注力しています。
社員の能力開発では、個々の成長を支援する研修やキャリア支援プログラムを充実させ、リーダー人財の育成にも力を入れています。さらに、ワークライフバランスを尊重し、フレキシブルな働き方を推奨。育児・介護支援制度の拡充や、育児休暇の取得推進により、仕事と家庭の両立を支援しています。
また、グローバルな人財配置を推進し、各地域でのリーダー登用を強化することで、多様な視点を取り入れた経営を実現。社員の成長とイノベーション創出を両立し、持続可能な社会への貢献を目指しています。
参考:「人財アトラクション」
花王
花王は中期経営計画「K27」のビジョン「未来のいのちを守る」を実現するため、経営戦略と連動した人財戦略を公表しました。「脱マトリックス型組織運営」を軸に、人財・組織を「グローバル・シャープトップ」として磨き上げ、社員活力を最大化する狙いがあります。公平な機会の提供と意欲ある人材への重点投資を目指し、DX教育を含むリスキリングや社内公募制度などでキャリア形成を促進しています。さらにスクラム型運営の導入や360度評価を整え、現場での継続的対話を重視して社員エンゲージメントを高める施策を展開しています。
参考:「花王、ビジョンである「未来のいのちを守る」実現に向け、経営戦略と連動した人財戦略を公表」
人的資本経営における課題と人事がすべきこと
データの可視化・活用不足
人的資本経営には、従業員のスキルやエンゲージメント、配置状況などを定量的に把握し、戦略的に活用するためのデータ管理が不可欠です。しかし、システム連携が進んでいなかったり、部署ごとにデータが散在していたりすると、正確な分析や意思決定ができません。
👉解決案
✅ HRテックの導入や人事システムの統合によりデータを一元管理
✅ 分析に長けた人材や外部コンサルタントを起用し、データを経営層へ迅速かつ明瞭に提示
経営層と従業員のコミュニケーション不足
人的資本経営の重要性を経営陣が理解していても、現場との温度差が大きいと施策が空回りしてしまいます。また、従業員が意見を自由に言えない風土では、イノベーションは生まれにくくなります。
👉解決案
✅ 経営トップや役員、人事担当者が定期的にタウンホールミーティングを開催し、方針や成果を丁寧に共有
✅ 上司と部下が双方向で話し合う機会を設けるなど、従業員の声を吸い上げる仕組みを整備
多様性の受容体制の不足
女性活躍やシニアの活用、外国人の登用などが表面的な取り組みにとどまり、社内文化や評価制度が従来のままでは、せっかく採用しても辞めてしまうケースも少なくありません。
👉解決策
✅ DEI推進のための専門チームや責任者を設置し、トップダウンで制度改革と意識改革を進める
✅ 無意識のバイアスやハラスメントを防ぐための研修や、心理的安全性を高める施策を導入
リスキリング(学び直し)の機会不足
急速に変化する市場ニーズや技術革新に対応するためには、従業員が継続的にスキルアップできる環境が欠かせません。しかし、現場は日々の業務に忙殺され、学習の時間や予算が確保されないといった課題があります。
👉解決案
✅ オンライン学習プラットフォームやeラーニングを整備し、空き時間でも学べる環境を作る。
✅ 学習成果を評価制度に反映するなど、従業員の学びを高めてインセンティブを設計する。
柔軟な働き方への対応
リモートワークやフレックスタイム、ジョブシェアなど多様な働き方を求める従業員が増えています。特にコロナ以降、この流れは不可逆的といえるでしょう。柔軟な働き方を認めることはエンゲージメント向上につながりますが、同時にコミュニケーション不足や評価制度の不備といった問題も生じやすくなります。
👉解決案
✅ オンラインでも綿密なコミュニケーションを行うためのツール活用や会議ルールの整備
✅ 評価制度に関して、成果物やプロセス指標を明確に設定し、在宅勤務やオフィス勤務の代わりに公平に評価体制を確立
1on1(ワンオンワン)は人的資本経営にどう役立つか
1on1とは、上司と部下が定期的に1対1で行う対話です。従業員一人ひとりの声を丁寧に汲み取り、成長やキャリア志向を明確にしエンゲージメントを高める手段として、人的資本経営の推進においても非常に重要な役割を果たします。
個々のキャリア開発と企業戦略の橋渡し
人的資本経営の基本にあるのは、「企業の成長戦略と従業員のキャリア成長をいかに結びつけるか」という視点です。1on1は、この“橋渡し”の場として非常に有効です。
📍 キャリア目標の共有
上司と部下が対話を重ねる中で、部下が目指すキャリア像や現在のスキルセットを把握し、企業が求める人材像と擦り合わせることができます。これにより、部下の能力開発計画を企業戦略と整合させやすくなり、投資(研修・教育プログラムなど)の効果を最大化できます。
📍スキル・コンピテンシーの把握
人的資本経営では、組織全体のスキルマップや人材アセスメントが重要ですが、その土台となる「現場レベルでのスキル評価や課題認識」を得やすいのが1on1です。上司が部下の業務上の強み・弱みを定期的にヒアリング・フィードバックすることで、組織的なスキルギャップの早期発見につながります。
エンゲージメント向上と離職率低減
人的資本経営において「従業員のエンゲージメント」は企業価値向上の大きな鍵を握ります。1on1は、エンゲージメントを高め、人材の流出を防ぐための打ち手にもなります。
📍パーソナライズドなサポート
月1回や週1回といった定期的な1on1を通じて、従業員が抱える悩み・課題を早期に把握し、個別にフォローできます。こうしたきめ細かい支援を通じて、従業員が「自分は大切にされている」と実感できるようになります。
📍心理的安全性の醸成
1対1の対話の場は、上司が適切にリードしながら、部下が本音を言いやすい環境をつくることができます。これによって職場でのストレス要因や改善要望を表に出しやすくなり、結果的に早期対応と組織改善、そして離職率の抑制につながります。
DEIの促進
人的資本経営では、DEIは欠かせないテーマです。特に職場にはジェンダーや世代、国籍、障がいの有無、ライフステージなど多様なバックグラウンドをもつ従業員が在籍しています。
📍個々の背景・ニーズに合わせた対応
1on1の対話を通じて、多様な背景を持つ従業員が仕事上で感じている課題やサポートニーズを的確人で把握できます。D&Iを「組織全体の理念」だけにとどめず、一人ひとりの具体的アクションに落としこむうえでも1on1は効果的です。
📍バイアスの早期発見と解消
管理職自身が持つ無意識のバイアスに気付くきっかけにもなるのが1on1です。個別にヒアリングすることで、従業員にとって不公平と感じられる慣習や制度を認識し、改善に繋げやすくなります。
イノベーション創出と組織学習の加速
人的資本経営が目指す最終ゴールの一つは、従業員の主体性や創造力を高め、新たな付加価値を生み出す“イノベーション体質”を企業文化として根付かせることです。
📍アイデアの活性化
1on1は、業務報告や評価目的の場だけでなく、「新しいアイデアを試すにはどうすればいいか」「部署をまたいだコラボレーションを進めるには?」といった自由な発想の相談やブレストの場にもなり得ます。こうした積み重ねが組織内のイノベーションを活性化します。
📍組織学習とナレッジ共有
部下から吸い上げた学びや成功事例を、上司が組織の会議や他部署との連携の中で広めることで、個人の知見を組織全体に展開できます。人的資本経営の観点で見ると「個人の成長=組織の成長」へとスムーズに繋げる重要な鍵となるのが1on1です。
パフォーマンスマネジメントとデータ活用
人的資本経営では、定量的・定性的なデータを活用して従業員の成長度合いや組織課題を可視化し、経営戦略に反映することが求められます。1on1の定期実施は、そうしたデータを蓄積するうえでも有効な手段です。
📍KPIや目標のフォローアップ
1on1の中で、前回設定した目標やKPIの進捗を確認し合い、具体的な障壁や改善策を話し合うことで、行動ベースのデータが蓄積されていきます。これらのデータは、組織的な人材育成方針や人事評価制度のブラッシュアップに直接活かせます。
📍定性情報と従業員満足度の測定
1on1で得られるのは数字だけではありません。従業員の意欲や不満、組織に対する信頼感など、アンケートだけでは拾いにくい“定性情報”も収集しやすくなります。人事部門や経営陣がこの情報を組み合わせ、改善策を打ち出すことで人的資本への投資効率がさらに高まります。
管理職研修と企業文化の醸成
1on1の成果を引き出すには、上司と部下双方の目的意識や組織文化の醸成が不可欠です。トップダウンで「人的資本経営」を推進している会社であっても、現場の上司がその趣旨を理解し、1on1を実践しなければ効果は限定的です。
📍コーチングスキルの習得
1on1で上司が問うべきは「部下が何を求めているのか」「どんな成長機会が必要なのか」であり、指示・命令型の一方的なコミュニケーションではありません。管理職向けにコーチングの基礎を学ぶ研修を行い、組織全体で1on1の質を高めることが重要です。
📍心理的安全性と失敗許容文化
1on1が形骸化せず、部下が本音で語れるようにするためには、失敗や意見の相違を認める組織文化が欠かせません。これにより、学習と試行錯誤を歓迎する風土が生まれ、人的資本経営の要である“自律型人材”を育てやすくなります。
まとめ
人的資本経営は、急激に変化するビジネス環境と労働市場に対応し、企業が持続的に成長するための不可欠なアプローチです。人をコストとして捉えるのではなく、企業価値を高める源泉として位置づけ、戦略的に育成・活用していく。この考え方は、一部の先進企業だけの取り組みではなく、広く一般的に求められる時代になりつつあります。
人的資本経営とは何か
人的資本経営は、企業価値向上の鍵を握るのは「人材」であるという視点から、従業員の能力・経験・モチベーションを“資本”として捉え、積極的に投資を行っていく経営手法です。
従来は「人件費」というコスト発想で捉えられがちだった人材を、企業の長期的成長を担う重要な資本として位置付ける点が特徴といえます。
この考え方の根底には、18世紀のアダム・スミスや、ノーベル経済学賞を受賞したゲーリー・ベッカーなどが唱えた「人的資本論」があります。
人的資本論では、教育やトレーニングを通じて人が獲得した能力は、企業や社会に大きな付加価値をもたらすとされてきました。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)やグローバル化が加速する中、企業が競争優位を築く上でも、“人への投資”が不可欠という考え方が再注目されています。
従来の人事との違いー「人的資源」から「人的資本」へ
これまでの人事・経営手法では、従業員を「人的資源(Human Resource)」と呼び、コストや配置効率の観点から管理・最適化する傾向が強く見られました。
一方、人的資本経営では、従業員一人ひとりがもつ潜在能力や専門性を“価値創造の源泉”と捉え、あえて投資を行い、最大限の成果を引き出そうとします。
この違いは、経営視点にも大きく影響します。短期利益の確保を最優先とし、必要以上のコスト削減や人員削減に走るのではなく、長期的・戦略的視野で人材育成やエンゲージメント向上にリソースを振り向ける。その結果、企業カルチャーの革新や持続的なイノベーション創出が期待できるようになるのです。
なぜ今「人的資本経営」が注目されているのか
📍 人への投資が競争力を左右する時代
世界的な技術革新と激化するグローバル競争の中で、企業の競争力は「どれだけ優秀な人材を引き付け、育成し、定着させるか」に大きく左右されるようになりました。
モノや設備に投資するだけでは差別化が難しい時代において、人の知恵や創造力こそが新たな付加価値を生み出す原動力です。
さらに、AIやビッグデータ解析など高度なデジタル技術を活用できる人材の獲得は、多くの企業の急務となっています。人材市場が流動化し、多様な働き方が広がる中で、一度採用した優秀な人材をいかに企業の成長に活かし続けられるかが、企業の命運を握るようになってきました。
📍 SDGs・ESGの潮流
企業は、財務指標だけでなくSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)を念頭に置いた経営が求められています。特にESG投資の拡大によって、社会課題の解決や従業員の働きがい創出といった「S(Social)」の要素が企業評価に大きく影響を及ぼしています。
「人的資本経営」の取り組みは、そのままESGの“Social”部分に深く関わるため、投資家やステークホルダーからの評価を上げる手段としても注目度を増しています。
📍 ポストコロナ時代の組織課題
コロナ禍でリモートワークが普及し、従業員同士のコミュニケーションが希薄になったり、エンゲージメントが低下したりするリスクが顕在化しました。また、オンライン環境に適応できない組織体制や評価制度の不備も浮き彫りになり、離職率の上昇が経営課題となる企業も少なくありません。
こうした状況を打開し、従業員のモチベーションや健康(ウェルビーイング)を保ちながら企業としての競争力を維持するには、人的資本経営が欠かせないという認識が急速に広まっています。
📍 国内外のルール整備
海外でも規制強化やガイドライン策定が進んでいます。米国ではSEC(米国証券取引委員会)が上場企業に対して人的資本情報の開示を義務付けています(具体的な開示項目は企業の裁量に任されている)。
日本でも2023年度から有価証券報告書において「人的資本投資に関する方針・指標」の開示が求められるようになりました。
さらに、「人的資本経営コンソーシアム」の設立や経団連の提言など、政府や経済団体が一体となって人的資本経営を推進する流れも強まっています。このような制度面の後押しが、企業の「人への投資」を加速させる理由のひとつとなっているのです。
人的資本経営に取り組むメリット
📍 企業イメージ・評価の向上
人的資本経営を積極的に進める企業は、従業員を大切にする姿勢を内外に示すことができます。これは採用マーケットにおいて優秀な人材を引き寄せる要因となるのはもちろん、顧客や取引先からの信頼獲得にも寄与します。また、ESG投資を行う機関投資家や株主にとっても、人的資本を重視する企業は投資先として魅力的な存在となります。
📍 従業員エンゲージメント・生産性の向上
従業員を企業成長の主役と捉え、キャリア開発やリスキリング(学び直し)の機会を提供したり、多様性を尊重する職場環境を整えたりすることで、従業員のエンゲージメントが高まります。モチベーションを持って働ける組織では自然と生産性も上がり、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなるでしょう。
📍 業績・財務面での恩恵
人的資本経営は、短期的な人件費削減とは対極に位置しますが、長期的には企業の収益力や利益率を高めることが期待できます。従業員定着率の向上やイノベーション創出、顧客満足度の向上など、さまざまな形で「人への投資」がリターンを生み出すからです。
また、人的資本に注力する企業はESG投資資金を呼び込みやすいとも言われており、株価評価においてプラスに作用する可能性も高まっています。
📍 法令対応のスムーズ化
人的資本経営を行うことで、人材戦略の明確化や人事データの整備が進みます。これらは、有価証券報告書や各種開示資料での情報提供に役立つだけでなく、労働関連法令の遵守やハラスメント対策の推進など、法令対応の面でもスムーズに進める下地となります。
人的資本経営に関する国内外の動向・ガイドライン
米国の事例
米国の上場企業は、SEC(米国証券取引委員会)のRegulation S‑K改正に基づき、人的資本資源に関する情報を開示するよう求められています。ただし、具体的な指標は、企業のビジネス特性に応じて重要と判断された情報を自社で選定して報告する形式となっています。投資家はそれらの開示情報を基に企業の長期的成長の可能性を評価する傾向が強まっています。
日本の事例
日本では、2023年度から上場企業の有価証券報告書において、人的資本投資や人材戦略に関する情報の開示が義務化されています。
具体的には、採用や離職の状況、多様性に関する指標(例:女性管理職比率)や、リスキリングへの投資額などが報告され、これらの情報は投資家やその他のステークホルダーによる企業評価の材料となっています。
また、企業が人的資本の情報開示を行う際の参考フレームワークとして、内閣官房や経済産業省が示す「人的資本可視化指針」などが挙げられます。
これらの指針では、一般的に以下の七つの分野(合計19項目程度)を参考にして人的資本の状況を整理するケースが多いです(なお、各社が採用する具体的な指標や分類は、自社の事情に応じて異なる場合があります)。
✅ 人的資本戦略・方針(企業のビジョンや経営戦略との連動性など)
✅ 組織構造・制度(雇用形態やジョブ型制度の導入状況など)
✅ 報酬・評価制度(報酬ポリシーや業績連動型インセンティブなど)
✅ 多様性とインクルージョン(女性管理職比率、国籍・年齢構成、障がい者雇用など)
✅ 人材育成・キャリア支援(研修制度、リスキリング支援、キャリアパスの透明性など)
✅ エンゲージメント・ウェルビーイング(離職率、労働時間、健康管理施策など)
✅ コーポレートガバナンス・コンプライアンス(リーダーシップの透明性、内部通報制度など)
各分野では、例えば研修受講率、離職率、女性管理職比率などのKPI(主要業績評価指標)を定量的および定性的に評価し、PDCAサイクルに基づく継続的な改善活動を通じて、従業員エンゲージメントや企業価値の向上が図られています。
人的資本経営を実践するためのステップ
人的資本経営を成功させるには、以下のステップで計画的に取り組むことが重要です。
1.経営戦略と人材戦略の連動
まずは、自社のビジョンや経営方針を改めて整理し、それを支えるための人材戦略を策定します。伊藤レポートでも指摘されているように、人的資本への投資は経営戦略とワンセットで考えないと、効果が断片化してしまいがちです。トップマネジメントと人事部門、各事業部門が連携し、同じゴールを共有することが大切です。
2.現状と理想像のギャップ把握
次に、自社の人的資本に関する定量データや定性情報を収集し、現状を客観的に把握します。たとえば、スキルマップの作成やエンゲージメント調査を行うことで、どの部門がどのスキルセットを必要としているのか、従業員が抱えている不満や課題は何か、といった具体的な問題点が浮き彫りになります。そのうえで「理想像(目指すべき姿)」とのギャップを測定し、優先すべき施策を見極めます。
3.KPI設定と施策の立案・実行
ギャップを明らかにしたら、解消するため、下記のような具体的な目標(KPI)を設定します。
<例>
📍「従業員エンゲージメントスコアを2年後に10%向上させる」
📍「女性管理職比率を3年後に30%にする」
📍「年間のリスキリング研修受講率をXX%以上にする」
この時、測定可能な形で目標を定義することが重要です。その目標に基づき、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の推進や企業カルチャー改革、エンゲージメント向上施策、働き方改革・ウェルビーイング向上施策など、複数の施策を組み合わせて実行していきます。
4.モニタリングと改善(PDCAサイクル)
施策を実行し始めたら、定期的にKPIをモニタリングし、その進捗や効果を測定します。結果が思わしくない場合は原因を分析し、アプローチを改善するというPDCAサイクルを回すことが欠かせません。長期視点で取り組む人的資本経営だからこそ、柔軟かつ継続的な検証プロセスが成果を左右します。
人的資本経営の成功事例
企業の成長を支える「人的資本経営」は、多くの企業で注目されています。以下で、先進的な取り組みを行う日本企業の事例を紹介。社員の活力を最大化しながら企業価値を向上させる戦略を探ります。
富士通
富士通は2020年7月に「Work Life Shift」というコンセプトを掲げて、ニューノーマル時代の新しい働き方に挑戦しています。これは「Smart Working」「Borderless Office」「Culture Change」の3つを柱とし、テレワーク環境の整備や仮想デスクトップの活用、コミュニケーションの新しい文化づくりを推進してきた結果、社員の通勤時間の大幅削減や育児との両立、副業による知見拡大など、仕事と生活の両面でエンゲージメント向上に成果を上げています。せ
その1年間の実践を踏まえ、2021年10月に発表された「Work Life Shift 2.0」では、「WorkとLifeの融合」に目を向け、社員一人ひとりのWell-Being実現を重視しています。具体的には、男性育児参加率100%を目指す取り組みや、ワーケーションを通じた創造性の向上、副業の積極推奨によるスキルや視野の拡大などを推進中です。また、オフィスを情報交換や雑談の場として活用する「Hybrid Work」を進め、リアルとオンラインを組み合わせた効率的で豊かな働き方を追求しています。
参考:「働き方改革の本質とは。Work Life Shift 2.0で富士通が目指すもの」
オムロン
「Shaping the Future 2030(SF2030)」のビジョンのもと、人的資本経営を推進し、社員の多様性と成長を企業の原動力と位置づけています。特に「ダイバーシティ&インクルージョン」の加速を掲げ、国籍・性別・障がいの有無を問わず、すべての社員が活躍できる環境づくりに注力しています。
社員の能力開発では、個々の成長を支援する研修やキャリア支援プログラムを充実させ、リーダー人財の育成にも力を入れています。さらに、ワークライフバランスを尊重し、フレキシブルな働き方を推奨。育児・介護支援制度の拡充や、育児休暇の取得推進により、仕事と家庭の両立を支援しています。
また、グローバルな人財配置を推進し、各地域でのリーダー登用を強化することで、多様な視点を取り入れた経営を実現。社員の成長とイノベーション創出を両立し、持続可能な社会への貢献を目指しています。
参考:「人財アトラクション」
花王
花王は中期経営計画「K27」のビジョン「未来のいのちを守る」を実現するため、経営戦略と連動した人財戦略を公表しました。「脱マトリックス型組織運営」を軸に、人財・組織を「グローバル・シャープトップ」として磨き上げ、社員活力を最大化する狙いがあります。公平な機会の提供と意欲ある人材への重点投資を目指し、DX教育を含むリスキリングや社内公募制度などでキャリア形成を促進しています。さらにスクラム型運営の導入や360度評価を整え、現場での継続的対話を重視して社員エンゲージメントを高める施策を展開しています。
参考:「花王、ビジョンである「未来のいのちを守る」実現に向け、経営戦略と連動した人財戦略を公表」
人的資本経営における課題と人事がすべきこと
データの可視化・活用不足
人的資本経営には、従業員のスキルやエンゲージメント、配置状況などを定量的に把握し、戦略的に活用するためのデータ管理が不可欠です。しかし、システム連携が進んでいなかったり、部署ごとにデータが散在していたりすると、正確な分析や意思決定ができません。
👉解決案
✅ HRテックの導入や人事システムの統合によりデータを一元管理
✅ 分析に長けた人材や外部コンサルタントを起用し、データを経営層へ迅速かつ明瞭に提示
経営層と従業員のコミュニケーション不足
人的資本経営の重要性を経営陣が理解していても、現場との温度差が大きいと施策が空回りしてしまいます。また、従業員が意見を自由に言えない風土では、イノベーションは生まれにくくなります。
👉解決案
✅ 経営トップや役員、人事担当者が定期的にタウンホールミーティングを開催し、方針や成果を丁寧に共有
✅ 上司と部下が双方向で話し合う機会を設けるなど、従業員の声を吸い上げる仕組みを整備
多様性の受容体制の不足
女性活躍やシニアの活用、外国人の登用などが表面的な取り組みにとどまり、社内文化や評価制度が従来のままでは、せっかく採用しても辞めてしまうケースも少なくありません。
👉解決策
✅ DEI推進のための専門チームや責任者を設置し、トップダウンで制度改革と意識改革を進める
✅ 無意識のバイアスやハラスメントを防ぐための研修や、心理的安全性を高める施策を導入
リスキリング(学び直し)の機会不足
急速に変化する市場ニーズや技術革新に対応するためには、従業員が継続的にスキルアップできる環境が欠かせません。しかし、現場は日々の業務に忙殺され、学習の時間や予算が確保されないといった課題があります。
👉解決案
✅ オンライン学習プラットフォームやeラーニングを整備し、空き時間でも学べる環境を作る。
✅ 学習成果を評価制度に反映するなど、従業員の学びを高めてインセンティブを設計する。
柔軟な働き方への対応
リモートワークやフレックスタイム、ジョブシェアなど多様な働き方を求める従業員が増えています。特にコロナ以降、この流れは不可逆的といえるでしょう。柔軟な働き方を認めることはエンゲージメント向上につながりますが、同時にコミュニケーション不足や評価制度の不備といった問題も生じやすくなります。
👉解決案
✅ オンラインでも綿密なコミュニケーションを行うためのツール活用や会議ルールの整備
✅ 評価制度に関して、成果物やプロセス指標を明確に設定し、在宅勤務やオフィス勤務の代わりに公平に評価体制を確立
1on1(ワンオンワン)は人的資本経営にどう役立つか
1on1とは、上司と部下が定期的に1対1で行う対話です。従業員一人ひとりの声を丁寧に汲み取り、成長やキャリア志向を明確にしエンゲージメントを高める手段として、人的資本経営の推進においても非常に重要な役割を果たします。
個々のキャリア開発と企業戦略の橋渡し
人的資本経営の基本にあるのは、「企業の成長戦略と従業員のキャリア成長をいかに結びつけるか」という視点です。1on1は、この“橋渡し”の場として非常に有効です。
📍 キャリア目標の共有
上司と部下が対話を重ねる中で、部下が目指すキャリア像や現在のスキルセットを把握し、企業が求める人材像と擦り合わせることができます。これにより、部下の能力開発計画を企業戦略と整合させやすくなり、投資(研修・教育プログラムなど)の効果を最大化できます。
📍スキル・コンピテンシーの把握
人的資本経営では、組織全体のスキルマップや人材アセスメントが重要ですが、その土台となる「現場レベルでのスキル評価や課題認識」を得やすいのが1on1です。上司が部下の業務上の強み・弱みを定期的にヒアリング・フィードバックすることで、組織的なスキルギャップの早期発見につながります。
エンゲージメント向上と離職率低減
人的資本経営において「従業員のエンゲージメント」は企業価値向上の大きな鍵を握ります。1on1は、エンゲージメントを高め、人材の流出を防ぐための打ち手にもなります。
📍パーソナライズドなサポート
月1回や週1回といった定期的な1on1を通じて、従業員が抱える悩み・課題を早期に把握し、個別にフォローできます。こうしたきめ細かい支援を通じて、従業員が「自分は大切にされている」と実感できるようになります。
📍心理的安全性の醸成
1対1の対話の場は、上司が適切にリードしながら、部下が本音を言いやすい環境をつくることができます。これによって職場でのストレス要因や改善要望を表に出しやすくなり、結果的に早期対応と組織改善、そして離職率の抑制につながります。
DEIの促進
人的資本経営では、DEIは欠かせないテーマです。特に職場にはジェンダーや世代、国籍、障がいの有無、ライフステージなど多様なバックグラウンドをもつ従業員が在籍しています。
📍個々の背景・ニーズに合わせた対応
1on1の対話を通じて、多様な背景を持つ従業員が仕事上で感じている課題やサポートニーズを的確人で把握できます。D&Iを「組織全体の理念」だけにとどめず、一人ひとりの具体的アクションに落としこむうえでも1on1は効果的です。
📍バイアスの早期発見と解消
管理職自身が持つ無意識のバイアスに気付くきっかけにもなるのが1on1です。個別にヒアリングすることで、従業員にとって不公平と感じられる慣習や制度を認識し、改善に繋げやすくなります。
イノベーション創出と組織学習の加速
人的資本経営が目指す最終ゴールの一つは、従業員の主体性や創造力を高め、新たな付加価値を生み出す“イノベーション体質”を企業文化として根付かせることです。
📍アイデアの活性化
1on1は、業務報告や評価目的の場だけでなく、「新しいアイデアを試すにはどうすればいいか」「部署をまたいだコラボレーションを進めるには?」といった自由な発想の相談やブレストの場にもなり得ます。こうした積み重ねが組織内のイノベーションを活性化します。
📍組織学習とナレッジ共有
部下から吸い上げた学びや成功事例を、上司が組織の会議や他部署との連携の中で広めることで、個人の知見を組織全体に展開できます。人的資本経営の観点で見ると「個人の成長=組織の成長」へとスムーズに繋げる重要な鍵となるのが1on1です。
パフォーマンスマネジメントとデータ活用
人的資本経営では、定量的・定性的なデータを活用して従業員の成長度合いや組織課題を可視化し、経営戦略に反映することが求められます。1on1の定期実施は、そうしたデータを蓄積するうえでも有効な手段です。
📍KPIや目標のフォローアップ
1on1の中で、前回設定した目標やKPIの進捗を確認し合い、具体的な障壁や改善策を話し合うことで、行動ベースのデータが蓄積されていきます。これらのデータは、組織的な人材育成方針や人事評価制度のブラッシュアップに直接活かせます。
📍定性情報と従業員満足度の測定
1on1で得られるのは数字だけではありません。従業員の意欲や不満、組織に対する信頼感など、アンケートだけでは拾いにくい“定性情報”も収集しやすくなります。人事部門や経営陣がこの情報を組み合わせ、改善策を打ち出すことで人的資本への投資効率がさらに高まります。
管理職研修と企業文化の醸成
1on1の成果を引き出すには、上司と部下双方の目的意識や組織文化の醸成が不可欠です。トップダウンで「人的資本経営」を推進している会社であっても、現場の上司がその趣旨を理解し、1on1を実践しなければ効果は限定的です。
📍コーチングスキルの習得
1on1で上司が問うべきは「部下が何を求めているのか」「どんな成長機会が必要なのか」であり、指示・命令型の一方的なコミュニケーションではありません。管理職向けにコーチングの基礎を学ぶ研修を行い、組織全体で1on1の質を高めることが重要です。
📍心理的安全性と失敗許容文化
1on1が形骸化せず、部下が本音で語れるようにするためには、失敗や意見の相違を認める組織文化が欠かせません。これにより、学習と試行錯誤を歓迎する風土が生まれ、人的資本経営の要である“自律型人材”を育てやすくなります。
まとめ
人的資本経営は、急激に変化するビジネス環境と労働市場に対応し、企業が持続的に成長するための不可欠なアプローチです。人をコストとして捉えるのではなく、企業価値を高める源泉として位置づけ、戦略的に育成・活用していく。この考え方は、一部の先進企業だけの取り組みではなく、広く一般的に求められる時代になりつつあります。