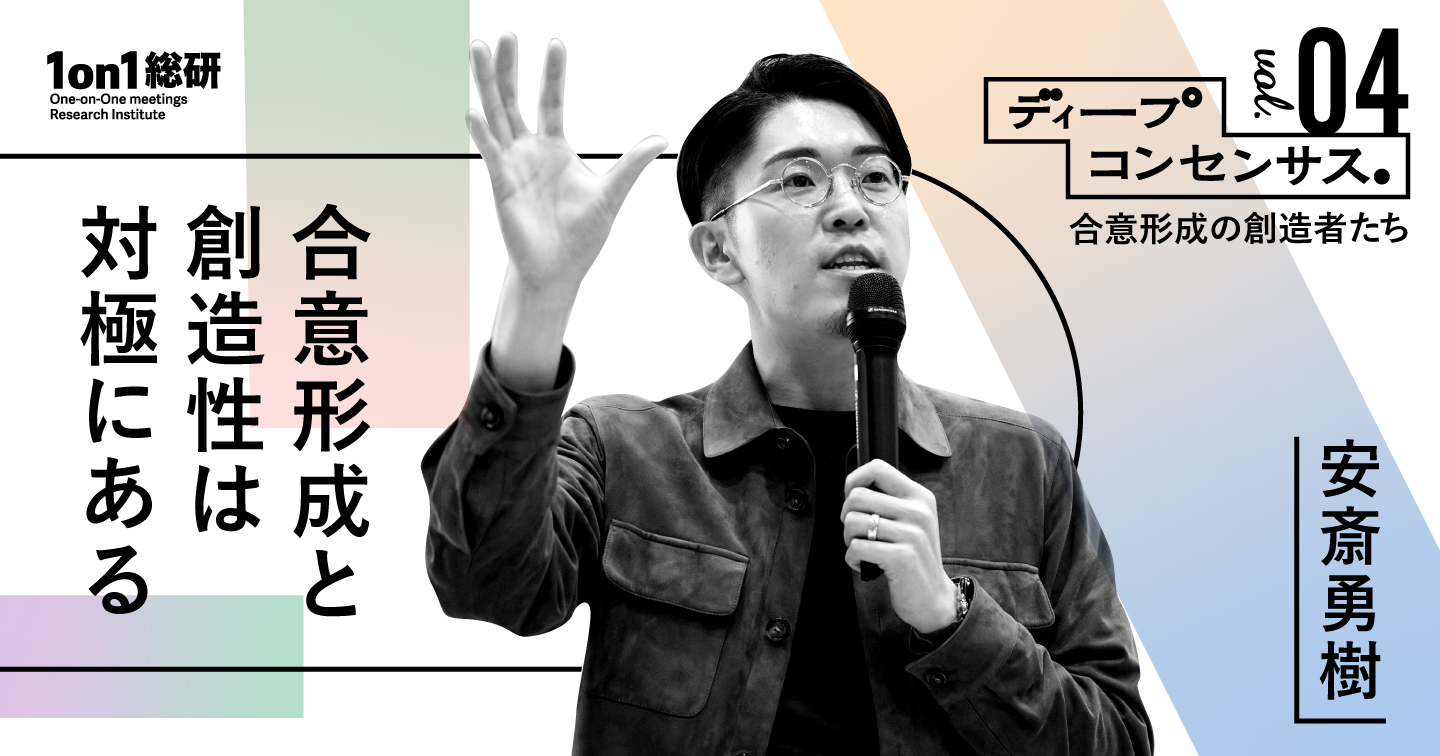
合意形成は遅らせろ。MIMIGURI安斎氏が教える「本質的な納得」のつくり方
「合意を形成するだけなら簡単です。誰にでもできますよ」——。経営コンサルティングファーム「MIMIGURI」共同代表の安斎勇樹氏は、そう語る。意味深な発言の裏にあるのは、対話が空洞化することへの警鐘だ。
理想のゴールは、すべての参加者が「自分たちで決めた」という実感を得られること。その目標に向けて、安斎氏は議論のプロセスを緻密にデザインしている。
日本を代表するウォッチブランド「CITIZEN」のデザインアイデンティティ構築プロジェクトを例に、「納得感が高い対話を生み出す方法」を解説してもらった。
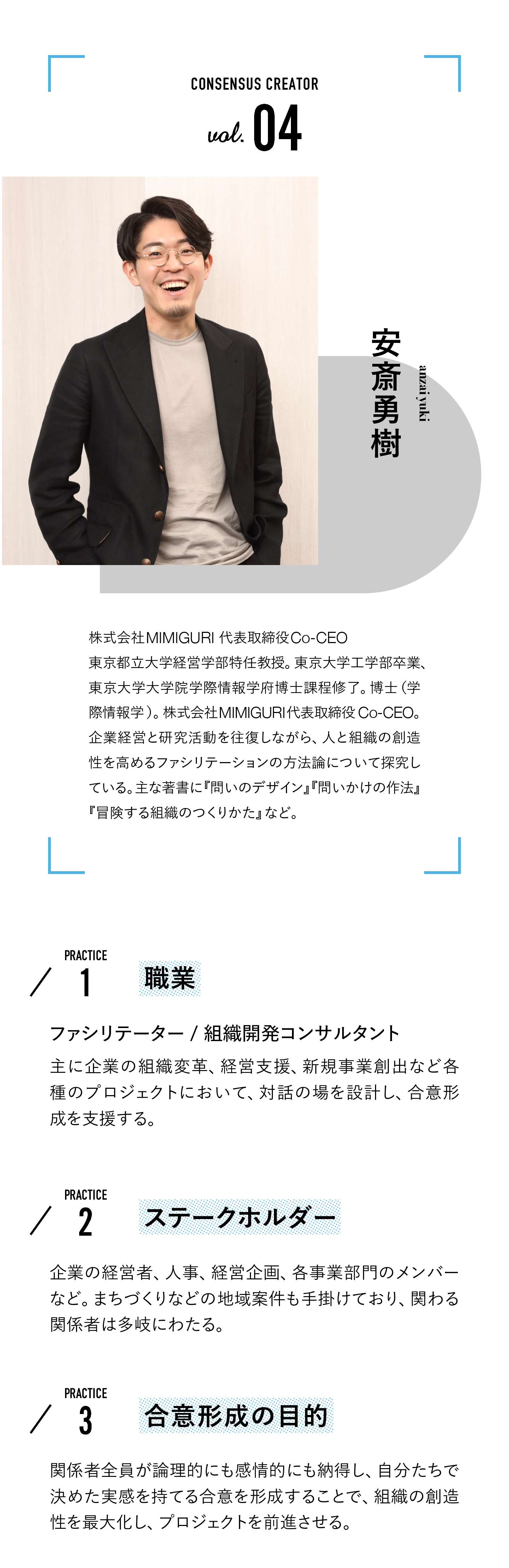
「全デザイナーが納得」を実現する方法
——安斎さんは様々な企業で議論のファシリテーターを担われています。「合意形成」というテーマで特に記憶に残っている案件はありますか。
安斎 シチズン時計の事例が印象的です。同社は創業100周年を迎えるにあたり、次の100年に残したい「シチズンらしいデザイン」を定義するプロジェクトに取り組んでいました。100年間に作られた膨大なモデルの中から、数十人のデザイナーが「シチズンらしい時計」100モデルを選び、図録を作る。そのプロセスのファシリテートを依頼されました。率直に「無理ゲー」だと思いました(笑)。
——なぜでしょうか。
安斎 多数決を採用すれば形式的な合意は作れます。でも、人間は感情的な生き物です。表面的には納得しても、心の中では腹落ちしていないことがある。そういう状態だと、後に合意が覆ったり、プロジェクトが頓挫したりする。全ての関係者が論理的にも感情的にも納得しないと、質の高い合意形成にはなりません。
それをシチズンのプロジェクトに当てはめると、6000を超えるモデルの中から、数十人に及ぶ全てのデザイナーが納得した状態で100本を選出することが求められます。かなりのハードルですよね。
——その難しさをどう乗り越えようとしたのでしょうか。
安斎 二つの観点から考えました。一つ目は、各デザイナーに「個人主語」で考えてもらうことです。

人には複数の主語がある。「私」もあれば、「課長」や「我が社」といった組織に基づく主語もある。そして多くの場合、人は「組織人格」を優先します。「個人的にはA案が良いと思うが、会社視点に立てばB案が妥当」。そんな忖度が生まれると、「自分たちで決めた」という実感は失われ、アウトプットも凡庸になります。
二つ目の観点は時間軸です。多くのデザイナーは担当モデルの翌年のアウトプットに集中しています。その短期的な視野のまま未来について尋ねても、「シチズンはこう歩んできたから、こうすべき」などと社内資料のような答えが返ってくるでしょう。
つまり、デザイナーに「短期視点の組織人格」から「長期視点の個人人格」へと切り替えてもらう必要があります。どうすればそれを実現できるか。
「現在」に集中するデザイナーに100年先を考えてもらうには、100年前から考える「助走」が必要ではないか。そして、その考えを個人主語で語る場を用意した方が良いのでは。そんな結論に至りました。
.webp)
——具体的にどのようなプロセスを設計したのでしょうか。
安斎 次の図のようなステップを提案をしました。

シチズン時計の本社にはミュージアムがあります。そこに6000モデルを展示し、「ワークショップ当日までにシチズンらしいと思う時計を三つ選んでください」とデザイナーに"宿題"を出しました。
数については、1本では狭すぎるが、5本以上では適当に選んでしまう恐れがある。3本なら「迷わず選んだ1本」「迷い抜いて入れた1本」「意外性のある1本」といった具合に、ほどよく厳選されると考えました。
——渾身の3本から多様な個人語りが生まれる、と。
安斎 実際、ワークショップは大盛り上がりでした。デザイナーが4、5人のグループに分かれ、せーので時計を見せ合うと、「そうきましたか!」「それ僕も迷ったんですよ〜!」といったやり取りがすぐに始まりました。
各自が選んだ理由を語り、聞き手はテーブルの模造紙にメモを残しながら耳を傾ける。僕が各テーブルを見回ると、様々なキーワードが書き込まれていて、それがすごく面白い。
あるテーブルでは、ベテランデザイナーが「シチズンらしさって、"キワモノ感"なんだよね」と力説していて驚きました(笑)。
——組織人格では出てこない表現ですね。
安斎 CITIZENには、デザインのセオリーより技術的挑戦を優先したモデルがいくつも存在しますが、それを「キワモノ感」と表現するのは、個人主語ならではですよね。

各テーブルの議論がある程度進んだ段階で、一度ストップをかけ、キーワードを全体で共有しました。その上で、「では、次の100年に残したいシチズンらしい要素とは何でしょうか」と問いを変える。
すると、キーワードを掘り下げる形で対話が進んでいく。「"キワモノ"という言葉は極端だが、"技術先行"はこれからも貫きたい」といった発言が出てくるなど、シチズンブランドとしてこの先も大事にしたい姿勢が言語化されていきました。
ワークショップ後、営業職などデザイナー以外の社員にも「シチズンらしさ」を尋ねる自由記述のアンケートを実施しました。その結果とワークショップのデータをテキストマイニングで分析すると、「シチズンらしさ」を構成する12のカテゴリーが見えてきた。
そこからプロジェクト事務局で各カテゴリーに入れるべき代表的なモデルを選定し、各デザイナーと相談しながら取捨選択を重ね、100モデルを選定しました。カテゴリへの納得度が高かったこともあり、モデルの選定は比較的スムーズに進みました。
——合意形成がうまく行った要因をどう考えますか。
安斎 主語の転換がうまく進み、デザイナーの皆さんに「自分たちで決めた」という感覚を持っていただけたことが大きかったと思います。
図録には、モデル別に「シチズンらしさ」の解説テキストと手書きのスケッチを掲載します。その作業はデザイナーの方々が日常業務の合間を縫って進めるもの。プロジェクトに当事者性を感じ、決定プロセスにも納得感があるからこそ、協力していただけたのでしょう。その協力を仰ぐために、デザイナー各位とコミュニケーションを重ねたプロジェクト事務局の皆さんの努力も素晴らしいと思います。
昨年、この100モデルを展示する「THE ESSENCE OF TIME」が九段ハウス(東京・千代田区)で開かれ、各デザイナーが自身が手がけたモデルについて熱心に説明されていました。シチズン側の責任者の方が「今回のプロセスを通じて、デザイナー陣が時計をデザインすることの面白味を再認識した」とおっしゃってくださり、非常に嬉しかったことを覚えています。
合意形成と創造性は対極にある
——シチズンの事例は対話の事前準備に良質な合意形成を生み出すためのヒントが隠されていましたが、対話のファシリテートにおいても、意識していることはありますか。
安斎 これは僕の博士論文の結論でもありますが、「合意形成」と「創造性」は、ある種対極にあると考えています。話し合いの初期段階でみんなが「あ、それいいね」という提案は、既視感があったり、当初の仮説に近かったりする。他方、イノベーティブなアイデアは賛否両論から生まれるもの。簡単には合意できないトピックを扱わないと、最終的に質の高いアウトプットにつながりません。
その意味で、僕は「合意形成をできるだけ遅延させること」がファシリテーターの仕事だと思っています。リソースの許す限りギリギリまで結論に向かわず、プロジェクトの後半に一気に合意形成を進める。
.png)
——迅速な合意形成が目的化すると、決定の質の低下を招いてしまう——そんな話に聞こえます。
安斎 実際、合意を取ること自体は簡単です。個人の思いを封殺してしまえばいいだけですから。例えば僕が『冒険する組織のつくりかた』でも批判している「軍事的組織」では、「仕事だろ。決まったんだからやれ」とトップダウンで指揮すれば、簡単に合意が取れてしまう。ただ、合意形成のコストは下がるかもしれませんが、働く人の主体性も下がってしまいます。
似たような観点で多数決もお勧めしません。形式的に合意した状態は作れますが、往々にして、過半数の人は納得していません。
——では、どうするのが良いのでしょうか。
安斎 投票で物事を決める場合、僕たちは「多様決」という方法を使います。投票者に「賛成票」と「モヤモヤ票」の2種類を与え、好きなアイデアに投票してもらう。この場合、賛成票がダントツの候補は、その質を疑った方が良い。一見優れているようで、その実、エッジが立っていないことが多いためです。他方、賛成票とモヤモヤ票をバランスよく集めた候補は、イノベーティブなポテンシャルを秘めている可能性が高い。

投票前に「賛成とモヤモヤの両方が集まる候補が良いアイデアです」と伝えておくのもお勧めします。そうすると、良質な候補にモヤモヤ票を投じた人が、「このアイデアは全体としては素晴らしいのですが、この文言だけが惜しくて……」といった具合に、嬉々として理由を語ってくれます。そうした発言には、ブレイクスルーのヒントがたくさん詰まっています。
(構成:下元陽、トップ写真:AOI Pro.提供、その他写真:三井実撮影)
🔹インタビュー後編では、ミドルマネジャーが部下に「本音」を語ってもらう方法を安斎さんに教えていただきました。こちらも併せてご覧ください。
『なぜ相手は本音を語らないのか。メンバーの「個人主語」を引き出す簡単な方法』
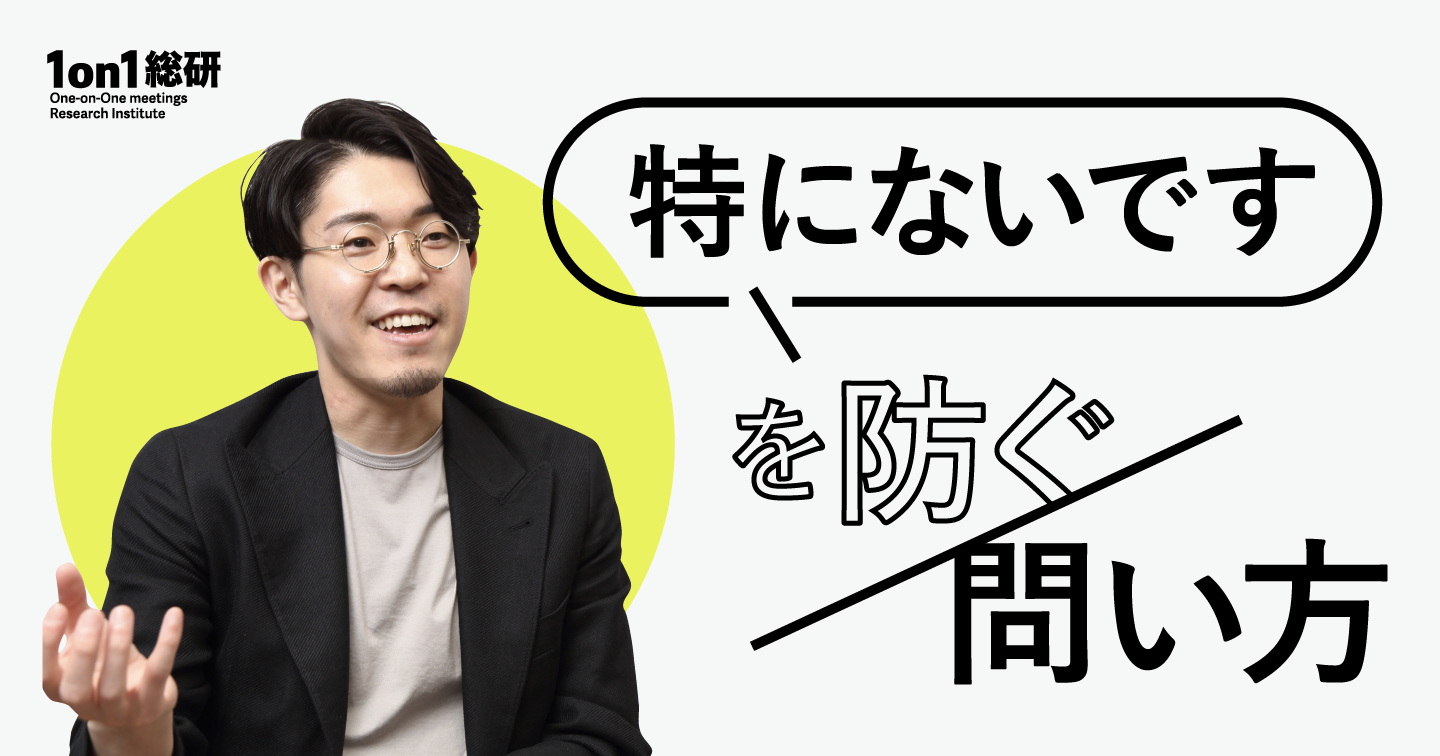
📕書籍紹介
「会議で意見が出ない」「メンバーが指示待ちになっている」——そんな悩みを抱えるリーダーへ。命令で動く「軍隊型チーム」を、メンバー一人ひとりが考え、判断し、行動する「冒険型チーム」に変える鍵が「問いかけ」である。本書では、相手の思考と行動を引き出す「見立てる」「組み立てる」「投げかける」の3つのサイクルを解説。1on1や会議で使える具体的な質問技法も充実している。中原淳氏、佐渡島庸平氏も推薦する、チームを動かすマネジャー必読書。

『新 問いかけの作法』
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
著者:安斎勇樹
書籍リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4799332252/
「全デザイナーが納得」を実現する方法
——安斎さんは様々な企業で議論のファシリテーターを担われています。「合意形成」というテーマで特に記憶に残っている案件はありますか。
安斎 シチズン時計の事例が印象的です。同社は創業100周年を迎えるにあたり、次の100年に残したい「シチズンらしいデザイン」を定義するプロジェクトに取り組んでいました。100年間に作られた膨大なモデルの中から、数十人のデザイナーが「シチズンらしい時計」100モデルを選び、図録を作る。そのプロセスのファシリテートを依頼されました。率直に「無理ゲー」だと思いました(笑)。
——なぜでしょうか。
安斎 多数決を採用すれば形式的な合意は作れます。でも、人間は感情的な生き物です。表面的には納得しても、心の中では腹落ちしていないことがある。そういう状態だと、後に合意が覆ったり、プロジェクトが頓挫したりする。全ての関係者が論理的にも感情的にも納得しないと、質の高い合意形成にはなりません。
それをシチズンのプロジェクトに当てはめると、6000を超えるモデルの中から、数十人に及ぶ全てのデザイナーが納得した状態で100本を選出することが求められます。かなりのハードルですよね。
——その難しさをどう乗り越えようとしたのでしょうか。
安斎 二つの観点から考えました。一つ目は、各デザイナーに「個人主語」で考えてもらうことです。

人には複数の主語がある。「私」もあれば、「課長」や「我が社」といった組織に基づく主語もある。そして多くの場合、人は「組織人格」を優先します。「個人的にはA案が良いと思うが、会社視点に立てばB案が妥当」。そんな忖度が生まれると、「自分たちで決めた」という実感は失われ、アウトプットも凡庸になります。
二つ目の観点は時間軸です。多くのデザイナーは担当モデルの翌年のアウトプットに集中しています。その短期的な視野のまま未来について尋ねても、「シチズンはこう歩んできたから、こうすべき」などと社内資料のような答えが返ってくるでしょう。
つまり、デザイナーに「短期視点の組織人格」から「長期視点の個人人格」へと切り替えてもらう必要があります。どうすればそれを実現できるか。
「現在」に集中するデザイナーに100年先を考えてもらうには、100年前から考える「助走」が必要ではないか。そして、その考えを個人主語で語る場を用意した方が良いのでは。そんな結論に至りました。
.webp)
——具体的にどのようなプロセスを設計したのでしょうか。
安斎 次の図のようなステップを提案をしました。

シチズン時計の本社にはミュージアムがあります。そこに6000モデルを展示し、「ワークショップ当日までにシチズンらしいと思う時計を三つ選んでください」とデザイナーに"宿題"を出しました。
数については、1本では狭すぎるが、5本以上では適当に選んでしまう恐れがある。3本なら「迷わず選んだ1本」「迷い抜いて入れた1本」「意外性のある1本」といった具合に、ほどよく厳選されると考えました。
——渾身の3本から多様な個人語りが生まれる、と。
安斎 実際、ワークショップは大盛り上がりでした。デザイナーが4、5人のグループに分かれ、せーので時計を見せ合うと、「そうきましたか!」「それ僕も迷ったんですよ〜!」といったやり取りがすぐに始まりました。
各自が選んだ理由を語り、聞き手はテーブルの模造紙にメモを残しながら耳を傾ける。僕が各テーブルを見回ると、様々なキーワードが書き込まれていて、それがすごく面白い。
あるテーブルでは、ベテランデザイナーが「シチズンらしさって、"キワモノ感"なんだよね」と力説していて驚きました(笑)。
——組織人格では出てこない表現ですね。
安斎 CITIZENには、デザインのセオリーより技術的挑戦を優先したモデルがいくつも存在しますが、それを「キワモノ感」と表現するのは、個人主語ならではですよね。

各テーブルの議論がある程度進んだ段階で、一度ストップをかけ、キーワードを全体で共有しました。その上で、「では、次の100年に残したいシチズンらしい要素とは何でしょうか」と問いを変える。
すると、キーワードを掘り下げる形で対話が進んでいく。「"キワモノ"という言葉は極端だが、"技術先行"はこれからも貫きたい」といった発言が出てくるなど、シチズンブランドとしてこの先も大事にしたい姿勢が言語化されていきました。
ワークショップ後、営業職などデザイナー以外の社員にも「シチズンらしさ」を尋ねる自由記述のアンケートを実施しました。その結果とワークショップのデータをテキストマイニングで分析すると、「シチズンらしさ」を構成する12のカテゴリーが見えてきた。
そこからプロジェクト事務局で各カテゴリーに入れるべき代表的なモデルを選定し、各デザイナーと相談しながら取捨選択を重ね、100モデルを選定しました。カテゴリへの納得度が高かったこともあり、モデルの選定は比較的スムーズに進みました。
——合意形成がうまく行った要因をどう考えますか。
安斎 主語の転換がうまく進み、デザイナーの皆さんに「自分たちで決めた」という感覚を持っていただけたことが大きかったと思います。
図録には、モデル別に「シチズンらしさ」の解説テキストと手書きのスケッチを掲載します。その作業はデザイナーの方々が日常業務の合間を縫って進めるもの。プロジェクトに当事者性を感じ、決定プロセスにも納得感があるからこそ、協力していただけたのでしょう。その協力を仰ぐために、デザイナー各位とコミュニケーションを重ねたプロジェクト事務局の皆さんの努力も素晴らしいと思います。
昨年、この100モデルを展示する「THE ESSENCE OF TIME」が九段ハウス(東京・千代田区)で開かれ、各デザイナーが自身が手がけたモデルについて熱心に説明されていました。シチズン側の責任者の方が「今回のプロセスを通じて、デザイナー陣が時計をデザインすることの面白味を再認識した」とおっしゃってくださり、非常に嬉しかったことを覚えています。
合意形成と創造性は対極にある
——シチズンの事例は対話の事前準備に良質な合意形成を生み出すためのヒントが隠されていましたが、対話のファシリテートにおいても、意識していることはありますか。
安斎 これは僕の博士論文の結論でもありますが、「合意形成」と「創造性」は、ある種対極にあると考えています。話し合いの初期段階でみんなが「あ、それいいね」という提案は、既視感があったり、当初の仮説に近かったりする。他方、イノベーティブなアイデアは賛否両論から生まれるもの。簡単には合意できないトピックを扱わないと、最終的に質の高いアウトプットにつながりません。
その意味で、僕は「合意形成をできるだけ遅延させること」がファシリテーターの仕事だと思っています。リソースの許す限りギリギリまで結論に向かわず、プロジェクトの後半に一気に合意形成を進める。
.png)
——迅速な合意形成が目的化すると、決定の質の低下を招いてしまう——そんな話に聞こえます。
安斎 実際、合意を取ること自体は簡単です。個人の思いを封殺してしまえばいいだけですから。例えば僕が『冒険する組織のつくりかた』でも批判している「軍事的組織」では、「仕事だろ。決まったんだからやれ」とトップダウンで指揮すれば、簡単に合意が取れてしまう。ただ、合意形成のコストは下がるかもしれませんが、働く人の主体性も下がってしまいます。
似たような観点で多数決もお勧めしません。形式的に合意した状態は作れますが、往々にして、過半数の人は納得していません。
——では、どうするのが良いのでしょうか。
安斎 投票で物事を決める場合、僕たちは「多様決」という方法を使います。投票者に「賛成票」と「モヤモヤ票」の2種類を与え、好きなアイデアに投票してもらう。この場合、賛成票がダントツの候補は、その質を疑った方が良い。一見優れているようで、その実、エッジが立っていないことが多いためです。他方、賛成票とモヤモヤ票をバランスよく集めた候補は、イノベーティブなポテンシャルを秘めている可能性が高い。

投票前に「賛成とモヤモヤの両方が集まる候補が良いアイデアです」と伝えておくのもお勧めします。そうすると、良質な候補にモヤモヤ票を投じた人が、「このアイデアは全体としては素晴らしいのですが、この文言だけが惜しくて……」といった具合に、嬉々として理由を語ってくれます。そうした発言には、ブレイクスルーのヒントがたくさん詰まっています。
(構成:下元陽、トップ写真:AOI Pro.提供、その他写真:三井実撮影)
🔹インタビュー後編では、ミドルマネジャーが部下に「本音」を語ってもらう方法を安斎さんに教えていただきました。こちらも併せてご覧ください。
『なぜ相手は本音を語らないのか。メンバーの「個人主語」を引き出す簡単な方法』
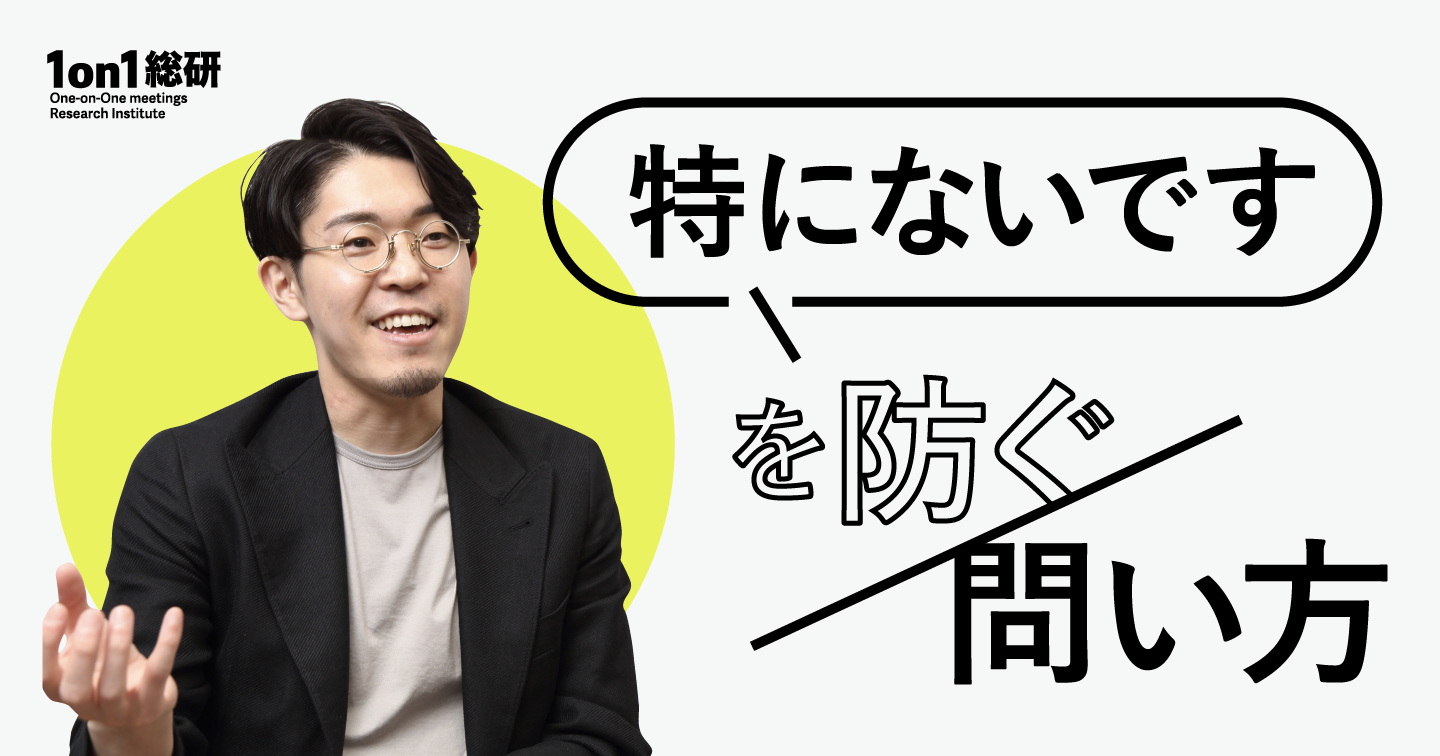
📕書籍紹介
「会議で意見が出ない」「メンバーが指示待ちになっている」——そんな悩みを抱えるリーダーへ。命令で動く「軍隊型チーム」を、メンバー一人ひとりが考え、判断し、行動する「冒険型チーム」に変える鍵が「問いかけ」である。本書では、相手の思考と行動を引き出す「見立てる」「組み立てる」「投げかける」の3つのサイクルを解説。1on1や会議で使える具体的な質問技法も充実している。中原淳氏、佐渡島庸平氏も推薦する、チームを動かすマネジャー必読書。

『新 問いかけの作法』
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
著者:安斎勇樹
書籍リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4799332252/






