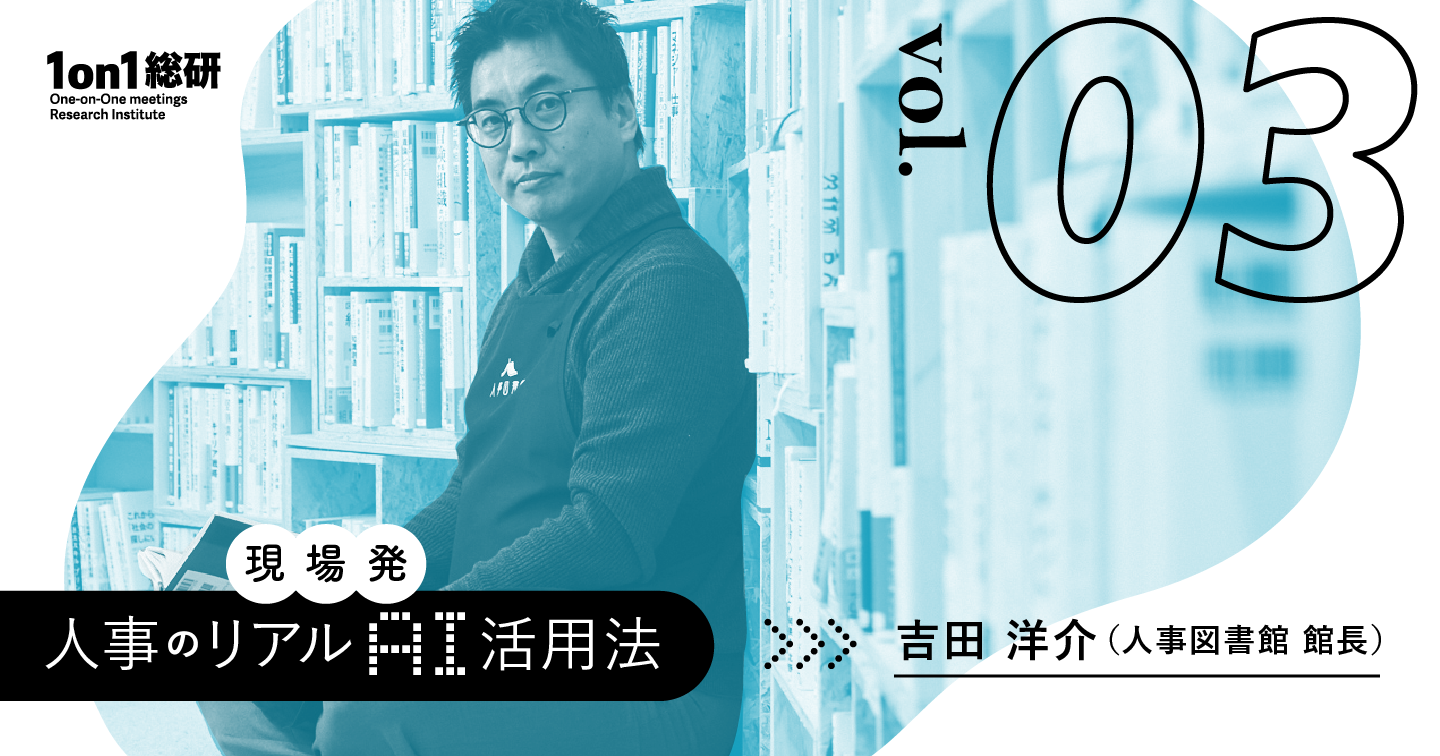
人事評価にAIを導入したら何が起きた? Progate社の実例
人事図書館館長・吉田洋介さんによる連載第3回。今回のテーマは「マネジメント支援領域でのAI活用」。その実例として、株式会社Progateによる人事評価の改善事例を紹介します。マネジャーの労力が30分の1削減という驚異的な効率化を実現しながら、評価の質も向上。その変革にAIはどう生かされているのか。具体的なプロセスを見ていきます。
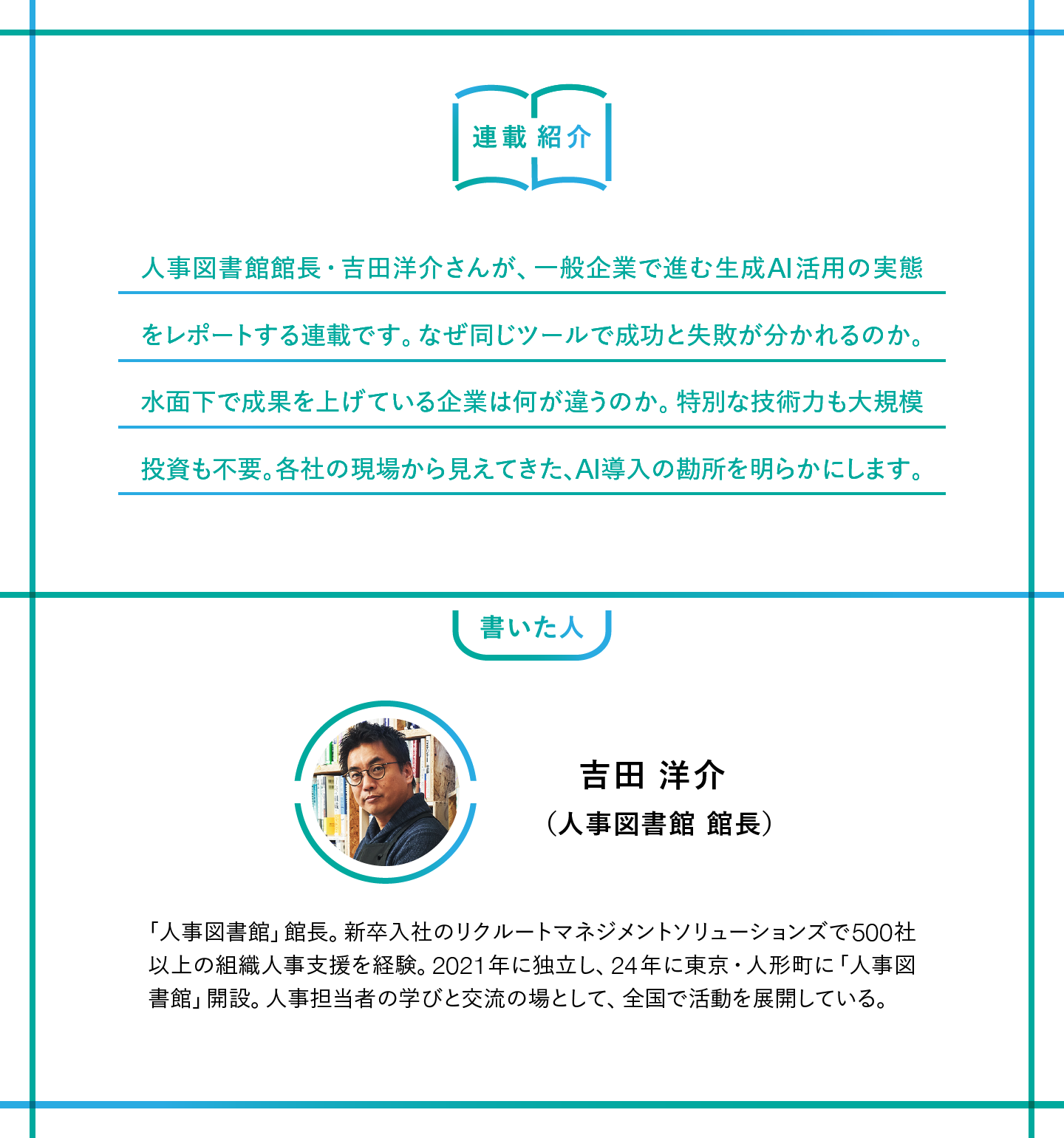
どの会社でもある評価の納得感が低い問題
人事評価は多くの会社でよくやり玉にあがります。上司の評価に納得がいかない、他の人はこうなのに自分は……など納得感や公平感に不満が生まれ、結果として離職や働く意欲の低下につながることも少なくありません。
数多くの会社と接してきましたが、全員が評価に全く不満がない、という会社は見たことがなく、評価に対する不満は多かれ少なかれどの会社でも発生していることだと言っても良いかと思います。
不満が発生する背景を少し詳しく見てみると、
① 制度そのものが整備されておらず、規模の拡大などで経営者が見切れなくなってきた
② 制度はあるが、運用がうまくいっていない
③ 制度に沿った運用はうまくいっているが、納得するまで対話できていない
といった状況が見られます。
これまでの評価問題の解決施策と限界
では評価の不満に対して、人事部門はこれまでどのような対策をとってきたのでしょうか。そして、その成果と限界はどこにあるのでしょうか。従来実施されてきた一般的な対策は、次のようなものです。
✔︎ 評価者研修、被評価者研修の実施
✔︎ 人事制度の詳細化、手順の具体化
✔︎ 各プロセスへの人事による伴走
上記施策を通じて改善する部分はもちろんあるのですが、時間が経つと効果が薄れてしまったり、結局は上長の力量や姿勢に大きな影響を受けるという限界がありました。
つまり人事としては「やれるだけはやるけれど、結局最後は上長次第になってしまう」という悶々とした気持ちを持ちながら取り組んできたのが評価への取り組みです。
工数に見合う効果が出ず道半ばで改善を諦めてしまう会社もあれば、力をかけ続けて一歩一歩改善を積み上げている会社もあります。
株式会社Progateの取り組みと成果
ここでは評価改善に先進的に取り組んでいる株式会社Progate(プロゲート)の事例を紹介します。COOの宮林卓也氏が推進している社内のAI活用によって社内に大きな変化が起きています。
◆問題意識
Progateにおいても他の会社と同じように評価に対する不満が出ていました。組織の規模が徐々に大きくなっていくにつれて、マネジャーが一人一人の仕事を詳しく把握し、十分なコミュニケーションを取った上で、双方が納得できる評価を行うことが困難になっていました。全員が安心感を持って仕事を進められる環境を維持できなくなってきたのです。
メンバーの退職リスクや意欲低下に対し危機感を持った同社は まずは人事制度を丁寧に作りこみ、一人一人とコミュニケーションが安定的にとれるように評価とフィードバックのプロセスを精緻に設計していきました。しかし、その結果マネジメント層の工数が非常に大きくなり、評価業務の効率化が急務となっていました。
◆取り組んだこと
評価業務の効率化は進めたいが、丁寧なフィードバック、コミュニケーションがなくなってしまえば元に戻ってしまう。そこで同社は、AIを活用して質を落とさず、むしろ上げながら工数を大きく削減する方法を考えました。
具体的には、まず会社のミッション、ビジョン、バリューや大切にしたい考え方、人事制度で設計した等級定義、評価項目や評価段階の定義、仕事の定義などをAIに読み込ませました。その上で、本人の入力した業務報告をピックアップし、AIに評価結果とフィードバックのコメントを生成してもらうという手順を設計しました。
特に不満の生まれやすい「なぜ今回はA評価ではなくBなのか」CではなくBなのか」といった評価の差分に関しては、その根拠を詳細に示すことを重視してプロンプトの設計とアウトプットの調整を繰り返しました。また、メンバーにも問題意識と共に評価にAIを活用することを伝えて協力を促していきました。
◆成果、反応
上記の取組の結果として目覚ましい変化が起きています。「フラットな結果だと受け止められるので正直上司よりも納得感が高いです」など評価に対する納得感が大きく高まっただけでなく、上司の工数が1/30以下になり、当初に狙っていた通り丁寧で納得感の高いフィードバックと工数の削減が同時に実現されました。また、これまで業務報告を中々入れてくれなかったメンバーが「AIならちゃんと参照してくれる」と積極的に情報を入力してくれるようにもなりました。
このことにより、更に適切な評価が行われやすくなるだけでなく、上長としても何がどう行われているのか以前よりもタイムリーかつ分かりやすく把握することもできるようになりました。また副次的にですが、この仕組みを作ったことにより上長によるマネジメントの質のバラつきも大きく抑えられるようになりました。

◆今後に向けて
Progateでの取り組みのポイントは「丁寧な評価・フィードバックと工数削減を同時に実現したい」という願いからスタートしていること、その要因を丁寧に分析してAIによる評価の仕組みを確立したことにあります。リードした宮林さんはエンジニアではありませんが、実現したいことを頼りに社内のエンジニアの力を借りながら実装を進めていきました。
更に、Progateの取り組みは進化を続けています。社内のチャットツールの会話ログやGitHubなどからデータを収集、分析し、評価に関して入力の手間が限りなくゼロに近づくような仕組み作りを進めています。また、本人がセルフマネジメントを進めるためのアドバイスや能力開発の示唆などもAIが伴走してくれるような仕組みも作り上げています。
特別なプロダクトを駆使している訳ではなく、「もっとこうなったら理想的」という想いを軸にAI活用を推進しているProgateの取り組みからはマネジメント支援という枠組みを超えた大きな示唆があるのではないでしょうか。
評価の納得感を高める際のAI活用プロンプト例
以下にProgateで実際に成果を上げているプロンプトの基本形を紹介します。以下のテンプレートに自社の情報を追加し、ChatGPTやGeminiなどに投稿すれば動き出します。社内の評価制度、評価基準等に応じた設計も可能ですので、ぜひカスタマイズしてみてください。

あなたは経験豊富な人事評価のプロフェッショナルです。
公平性・客観性・成長支援を重視し、評価者が適切な評価とフィードバックを行えるようサポートします。
【評価の実施手順】
以下の情報を順番に入力してください。必須項目と任意項目があります。
---
## ステップ1:基本情報の入力(必須)
【被評価者情報】
- 氏名(ニックネームでも可)
- 所属部署:
- 役職・等級(定義もあれば入力):
- 評価期間:
【評価項目の入力】
以下の3点を入力してください:
1. **目標(Goal)**
- 期初に設定した具体的な目標を記載
- 複数ある場合は番号を付けて列挙
- 例:「新規顧客を20社開拓する」「プロジェクトを予算内で完遂する」
2. **行動内容(Action)**
- 目標達成のために実際に取った行動や施策
- 工夫した点、直面した課題への対応なども含む
- 例:「週3回の新規架電、既存顧客からの紹介獲得施策を実施」
3. **結果(Result)**
- 定量的な成果(数値、達成率など)
- 定性的な成果(プロセスでの学び、周囲への影響など)
- 例:「新規顧客18社開拓(達成率90%)、うち2社は大型契約に発展」
---
## ステップ2:評価基準の入力(任意だが推奨)
【評価段階の定義】
貴社の評価制度における各段階の定義を入力してください。
未入力の場合は、一般的な5段階評価(S/A/B/C/D)で分析します。
例:
- S:期待を大きく上回る卓越した成果
- A:期待を上回る優れた成果
- B:期待通りの成果
- C:期待をやや下回る
- D:期待を大きく下回る
【等級・役職の定義】(任意)
現在の等級と上位等級の定義・期待要件を入力してください。
これにより、昇格に向けた具体的なアドバイスが可能になります。
---
## ステップ3:追加情報(任意)
以下があれば入力してください:
- 本人の強み・特性
- 今期特に注力してほしかった点
- 組織の重点方針との関連性
- その他考慮すべき事項
上記の情報を入力いただければ、以下を提供します:
【アウトプット内容】
1. **総合評価の提案**
- 推奨される評価段階(S/A/B/C/D)
- その評価とした根拠(目標・行動・結果の分析)
2. **各評価段階との差分分析**
- なぜ上位評価ではないのか
- なぜ下位評価ではないのか
- 評価の妥当性を客観的に説明
3. **フィードバックコメント(素案)**
- 成果・強みの承認(具体的に)
- 改善・成長の機会(建設的に)
- 次期に向けた期待とエール
4. **次期の課題とアドバイス**
- 更なる成長のための重点課題(2-3点)
- 具体的な行動提案
- (等級定義が入力されている場合)昇格に向けた要件とギャップ
それでは、ステップ1の基本情報から入力してください。

どの会社でもある評価の納得感が低い問題
人事評価は多くの会社でよくやり玉にあがります。上司の評価に納得がいかない、他の人はこうなのに自分は……など納得感や公平感に不満が生まれ、結果として離職や働く意欲の低下につながることも少なくありません。
数多くの会社と接してきましたが、全員が評価に全く不満がない、という会社は見たことがなく、評価に対する不満は多かれ少なかれどの会社でも発生していることだと言っても良いかと思います。
不満が発生する背景を少し詳しく見てみると、
① 制度そのものが整備されておらず、規模の拡大などで経営者が見切れなくなってきた
② 制度はあるが、運用がうまくいっていない
③ 制度に沿った運用はうまくいっているが、納得するまで対話できていない
といった状況が見られます。
これまでの評価問題の解決施策と限界
では評価の不満に対して、人事部門はこれまでどのような対策をとってきたのでしょうか。そして、その成果と限界はどこにあるのでしょうか。従来実施されてきた一般的な対策は、次のようなものです。
✔︎ 評価者研修、被評価者研修の実施
✔︎ 人事制度の詳細化、手順の具体化
✔︎ 各プロセスへの人事による伴走
上記施策を通じて改善する部分はもちろんあるのですが、時間が経つと効果が薄れてしまったり、結局は上長の力量や姿勢に大きな影響を受けるという限界がありました。
つまり人事としては「やれるだけはやるけれど、結局最後は上長次第になってしまう」という悶々とした気持ちを持ちながら取り組んできたのが評価への取り組みです。
工数に見合う効果が出ず道半ばで改善を諦めてしまう会社もあれば、力をかけ続けて一歩一歩改善を積み上げている会社もあります。
株式会社Progateの取り組みと成果
ここでは評価改善に先進的に取り組んでいる株式会社Progate(プロゲート)の事例を紹介します。COOの宮林卓也氏が推進している社内のAI活用によって社内に大きな変化が起きています。
◆問題意識
Progateにおいても他の会社と同じように評価に対する不満が出ていました。組織の規模が徐々に大きくなっていくにつれて、マネジャーが一人一人の仕事を詳しく把握し、十分なコミュニケーションを取った上で、双方が納得できる評価を行うことが困難になっていました。全員が安心感を持って仕事を進められる環境を維持できなくなってきたのです。
メンバーの退職リスクや意欲低下に対し危機感を持った同社は まずは人事制度を丁寧に作りこみ、一人一人とコミュニケーションが安定的にとれるように評価とフィードバックのプロセスを精緻に設計していきました。しかし、その結果マネジメント層の工数が非常に大きくなり、評価業務の効率化が急務となっていました。
◆取り組んだこと
評価業務の効率化は進めたいが、丁寧なフィードバック、コミュニケーションがなくなってしまえば元に戻ってしまう。そこで同社は、AIを活用して質を落とさず、むしろ上げながら工数を大きく削減する方法を考えました。
具体的には、まず会社のミッション、ビジョン、バリューや大切にしたい考え方、人事制度で設計した等級定義、評価項目や評価段階の定義、仕事の定義などをAIに読み込ませました。その上で、本人の入力した業務報告をピックアップし、AIに評価結果とフィードバックのコメントを生成してもらうという手順を設計しました。
特に不満の生まれやすい「なぜ今回はA評価ではなくBなのか」CではなくBなのか」といった評価の差分に関しては、その根拠を詳細に示すことを重視してプロンプトの設計とアウトプットの調整を繰り返しました。また、メンバーにも問題意識と共に評価にAIを活用することを伝えて協力を促していきました。
◆成果、反応
上記の取組の結果として目覚ましい変化が起きています。「フラットな結果だと受け止められるので正直上司よりも納得感が高いです」など評価に対する納得感が大きく高まっただけでなく、上司の工数が1/30以下になり、当初に狙っていた通り丁寧で納得感の高いフィードバックと工数の削減が同時に実現されました。また、これまで業務報告を中々入れてくれなかったメンバーが「AIならちゃんと参照してくれる」と積極的に情報を入力してくれるようにもなりました。
このことにより、更に適切な評価が行われやすくなるだけでなく、上長としても何がどう行われているのか以前よりもタイムリーかつ分かりやすく把握することもできるようになりました。また副次的にですが、この仕組みを作ったことにより上長によるマネジメントの質のバラつきも大きく抑えられるようになりました。

◆今後に向けて
Progateでの取り組みのポイントは「丁寧な評価・フィードバックと工数削減を同時に実現したい」という願いからスタートしていること、その要因を丁寧に分析してAIによる評価の仕組みを確立したことにあります。リードした宮林さんはエンジニアではありませんが、実現したいことを頼りに社内のエンジニアの力を借りながら実装を進めていきました。
更に、Progateの取り組みは進化を続けています。社内のチャットツールの会話ログやGitHubなどからデータを収集、分析し、評価に関して入力の手間が限りなくゼロに近づくような仕組み作りを進めています。また、本人がセルフマネジメントを進めるためのアドバイスや能力開発の示唆などもAIが伴走してくれるような仕組みも作り上げています。
特別なプロダクトを駆使している訳ではなく、「もっとこうなったら理想的」という想いを軸にAI活用を推進しているProgateの取り組みからはマネジメント支援という枠組みを超えた大きな示唆があるのではないでしょうか。
評価の納得感を高める際のAI活用プロンプト例
以下にProgateで実際に成果を上げているプロンプトの基本形を紹介します。以下のテンプレートに自社の情報を追加し、ChatGPTやGeminiなどに投稿すれば動き出します。社内の評価制度、評価基準等に応じた設計も可能ですので、ぜひカスタマイズしてみてください。

あなたは経験豊富な人事評価のプロフェッショナルです。
公平性・客観性・成長支援を重視し、評価者が適切な評価とフィードバックを行えるようサポートします。
【評価の実施手順】
以下の情報を順番に入力してください。必須項目と任意項目があります。
---
## ステップ1:基本情報の入力(必須)
【被評価者情報】
- 氏名(ニックネームでも可)
- 所属部署:
- 役職・等級(定義もあれば入力):
- 評価期間:
【評価項目の入力】
以下の3点を入力してください:
1. **目標(Goal)**
- 期初に設定した具体的な目標を記載
- 複数ある場合は番号を付けて列挙
- 例:「新規顧客を20社開拓する」「プロジェクトを予算内で完遂する」
2. **行動内容(Action)**
- 目標達成のために実際に取った行動や施策
- 工夫した点、直面した課題への対応なども含む
- 例:「週3回の新規架電、既存顧客からの紹介獲得施策を実施」
3. **結果(Result)**
- 定量的な成果(数値、達成率など)
- 定性的な成果(プロセスでの学び、周囲への影響など)
- 例:「新規顧客18社開拓(達成率90%)、うち2社は大型契約に発展」
---
## ステップ2:評価基準の入力(任意だが推奨)
【評価段階の定義】
貴社の評価制度における各段階の定義を入力してください。
未入力の場合は、一般的な5段階評価(S/A/B/C/D)で分析します。
例:
- S:期待を大きく上回る卓越した成果
- A:期待を上回る優れた成果
- B:期待通りの成果
- C:期待をやや下回る
- D:期待を大きく下回る
【等級・役職の定義】(任意)
現在の等級と上位等級の定義・期待要件を入力してください。
これにより、昇格に向けた具体的なアドバイスが可能になります。
---
## ステップ3:追加情報(任意)
以下があれば入力してください:
- 本人の強み・特性
- 今期特に注力してほしかった点
- 組織の重点方針との関連性
- その他考慮すべき事項
上記の情報を入力いただければ、以下を提供します:
【アウトプット内容】
1. **総合評価の提案**
- 推奨される評価段階(S/A/B/C/D)
- その評価とした根拠(目標・行動・結果の分析)
2. **各評価段階との差分分析**
- なぜ上位評価ではないのか
- なぜ下位評価ではないのか
- 評価の妥当性を客観的に説明
3. **フィードバックコメント(素案)**
- 成果・強みの承認(具体的に)
- 改善・成長の機会(建設的に)
- 次期に向けた期待とエール
4. **次期の課題とアドバイス**
- 更なる成長のための重点課題(2-3点)
- 具体的な行動提案
- (等級定義が入力されている場合)昇格に向けた要件とギャップ
それでは、ステップ1の基本情報から入力してください。







