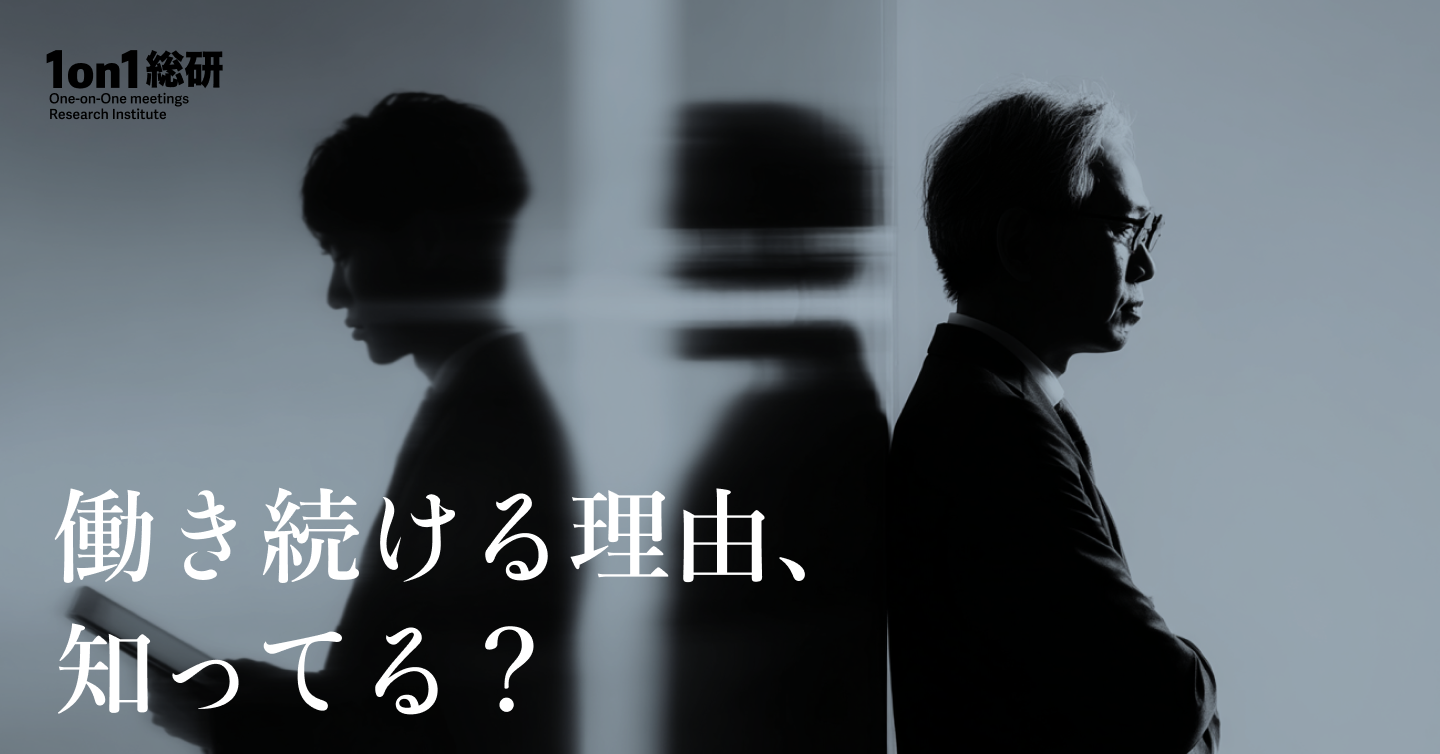
シニア社員との向き合い方——マネジャーに求められる対話と翻訳のスキル
定年延長や再雇用人材活用によってシニア人材の就業率が年々高まり、マネジャーが一回り以上年上の部下を持つことも珍しくなくなった。シニア社員に成果を出してもらうには、どんな対話が必要なのか。本稿では、世代を越えて協働するための対話のヒントと、そのために不可欠な“翻訳”の仕方を解説する。
シニア社員とすれ違う三つのパターン
シニア社員が増えるなか、現場では新たな課題が生まれている。賃金の下落や役割の縮小によってモチベーションが揺らぐシニア社員に対し、マネジャーは「やりにくさ」や「扱いづらさ」を感じているのである。しかし、モチベーション低下の背景を理解せずに接すると、互いに不信感が募り、チーム全体の成果を損なう結果となる。
では、年下のマネジャーは、どう向き合えばよいのか。まずは、シニア社員と年下上司がすれ違う典型的なパターンを押さえよう。
☑️ プライドによる衝突
長いキャリアを持つ社員は、「自分がこの会社を作ってきた」という自負と、「年下に指示されたくない」という感情が表に出やすい。そのプライドが、対話のすれ違いを生む。
☑️ キャリア観のズレ
若手は将来のキャリア形成を見据えているが、シニア社員は「もう先はない」と考えることが多い。そのため、マネジャーは「今この瞬間に貢献してもらう」ことに焦点を合わせなければ、一緒に進むことが難しくなる。
☑️ コミュニケーションの断絶
シニア社員が語る“武勇伝”や経験談は、世代背景の異なるマネジャーには受け止めにくい。一方、マネジャーが「面倒だから」と世代の違いを言葉にしないままでいると、断絶が深まり、組織は停滞してしまう。
これらは、世代や立場の非対称性が生む、組織上の構造的な難しさでもある。とはいえ、マネジャーには、誰と組んでもチームとして成果を出すことが求められる。そのためには、こうしたすれ違いが起こりうることを認識しておく必要がある。
敬意をもって共通言語に置き換える
プライドや価値観の違いをなくすことはできない。しかし、それらを乗り越えて対話を成立させる方法がある。鍵となるのは“翻訳のスキル”だ。まずは相手の背景や価値観を理解し、敬意を示すこと。そのうえで共通言語に置き換えて伝えることで、信頼関係を築くことができる。
💡「プライドによる衝突」には……
年上部下の自負やプライドは否定せず受け止める。「自分の経験を尊重してくれている」と感じてもらうことで、対話の土台ができる。そのうえで「今の状況ではこうです」と共通言語に翻訳して伝えることが大切だ。
💡「キャリア観のズレ」には……
「もう成長する気はない」と言われたら、まずはその考えを認める。そして「成長」ではなく「貢献」に軸を移す。「あなたの知見やスキルをチームに生かしてほしい」と伝えることで、役割への納得感を持ってもらえる。
💡「コミュニケーションの断絶」には……
「俺の時代はこうだった」と経験談を語られたら、一度は受け入れる。そのうえで「今の状況に照らすと、当時の考え方が役立つかもしれません」とつなげれば、相手の話が今のチームに生きる。ただし、一方的に聞くだけでは不十分だ。マネジャー側からも、「私たちの世代では○○と考えがちですが」と率直に世代間の認識の違いを言葉にし、共有することで、断絶を防ぐことができる。
ポイントは、相手の価値観に完全に合わせるのではなく、現在の組織基準で物事を進めることだ。
ただし、相手の経験や考えを否定してはならない。まずは尊重する姿勢を示し、信頼関係を築く。そうすれば、現在のチームの方針や目標に協力してもらえるようになる。
相手が理解できる表現に「翻訳」して伝える——。この意識だけで、対話の質は大きく変わるだろう。
1on1で聞くべき「働き続ける理由」
では、シニア社員のマネジメントに行き詰まったとき、どう関係性を見直していけばよいだろうか。整理の軸として、次の四つの視点が役立つ。

大切なのは「扱い方」ではなく、役割と貢献を軸に関係を再設計する姿勢だ。年齢差にとらわれず、相手の言葉を翻訳しながら対話を重ねる。それがマネジャーに求められる力なのである。
その実践において、特に重要なのが、1on1の場で「働き続ける理由」を尋ねることだ。この問いかけを通じて相手への理解を深めることが、心が近づく第一歩になる。
シニア社員との1on1の質問例
では、具体的にどのように話を進めるのが効果的だろうか。「働き続ける理由」を探るには、直接的に聞くよりも、以下のような角度から問いかけると本音を引き出しやすい。
① 選択の理由
Q:なぜ再雇用(定年延長)を選んだのですか。
……お金のために働く人ばかりではないし、辞めるという選択肢もあったはず。「なぜ辞めなかったのか」の回答には、今働いている目的や動機が見えてくる。
② 会社との関係性
Q:この会社のどこに魅力を感じていますか。
……他の会社で働くこともできたのに残ったからには、何らかの愛着や理由があるはず。「取り立てて好きなところはないが、居心地が良い」という答えなら、その「居心地」を大事にしていると考えられる。
③ 仕事観
Q:仕事を続けるうえで、譲れないことは何ですか。
……高い成長は望まなくても、働くからには譲れない価値観があるはず。回答から、その人が仕事に求める本質を読み取ろう。
これらをフラットに尋ねることで、相手の価値観や動機が見え、無用な思い込みを減らせる。食事をしながら自然に話を聞くようなスタンスで耳を傾けるのが理想である。
シニア社員の管理を任されることを「押し付けられた」と感じてしまう若手マネジャーもいるだろう。しかし、よく考えてみてほしい。マネジャーのほうが後から異動してきたケースも少なくないのだ。
シニア社員は社内に豊富な人脈を持ち、過去の成功・失敗に基づく経験値も有する非常に貴重な部下である。信頼関係を築ければ、若手には見えないリスクを事前に教えてくれる、大きな戦力となるはずだ。
シニア社員とすれ違う三つのパターン
シニア社員が増えるなか、現場では新たな課題が生まれている。賃金の下落や役割の縮小によってモチベーションが揺らぐシニア社員に対し、マネジャーは「やりにくさ」や「扱いづらさ」を感じているのである。しかし、モチベーション低下の背景を理解せずに接すると、互いに不信感が募り、チーム全体の成果を損なう結果となる。
では、年下のマネジャーは、どう向き合えばよいのか。まずは、シニア社員と年下上司がすれ違う典型的なパターンを押さえよう。
☑️ プライドによる衝突
長いキャリアを持つ社員は、「自分がこの会社を作ってきた」という自負と、「年下に指示されたくない」という感情が表に出やすい。そのプライドが、対話のすれ違いを生む。
☑️ キャリア観のズレ
若手は将来のキャリア形成を見据えているが、シニア社員は「もう先はない」と考えることが多い。そのため、マネジャーは「今この瞬間に貢献してもらう」ことに焦点を合わせなければ、一緒に進むことが難しくなる。
☑️ コミュニケーションの断絶
シニア社員が語る“武勇伝”や経験談は、世代背景の異なるマネジャーには受け止めにくい。一方、マネジャーが「面倒だから」と世代の違いを言葉にしないままでいると、断絶が深まり、組織は停滞してしまう。
これらは、世代や立場の非対称性が生む、組織上の構造的な難しさでもある。とはいえ、マネジャーには、誰と組んでもチームとして成果を出すことが求められる。そのためには、こうしたすれ違いが起こりうることを認識しておく必要がある。
敬意をもって共通言語に置き換える
プライドや価値観の違いをなくすことはできない。しかし、それらを乗り越えて対話を成立させる方法がある。鍵となるのは“翻訳のスキル”だ。まずは相手の背景や価値観を理解し、敬意を示すこと。そのうえで共通言語に置き換えて伝えることで、信頼関係を築くことができる。
💡「プライドによる衝突」には……
年上部下の自負やプライドは否定せず受け止める。「自分の経験を尊重してくれている」と感じてもらうことで、対話の土台ができる。そのうえで「今の状況ではこうです」と共通言語に翻訳して伝えることが大切だ。
💡「キャリア観のズレ」には……
「もう成長する気はない」と言われたら、まずはその考えを認める。そして「成長」ではなく「貢献」に軸を移す。「あなたの知見やスキルをチームに生かしてほしい」と伝えることで、役割への納得感を持ってもらえる。
💡「コミュニケーションの断絶」には……
「俺の時代はこうだった」と経験談を語られたら、一度は受け入れる。そのうえで「今の状況に照らすと、当時の考え方が役立つかもしれません」とつなげれば、相手の話が今のチームに生きる。ただし、一方的に聞くだけでは不十分だ。マネジャー側からも、「私たちの世代では○○と考えがちですが」と率直に世代間の認識の違いを言葉にし、共有することで、断絶を防ぐことができる。
ポイントは、相手の価値観に完全に合わせるのではなく、現在の組織基準で物事を進めることだ。
ただし、相手の経験や考えを否定してはならない。まずは尊重する姿勢を示し、信頼関係を築く。そうすれば、現在のチームの方針や目標に協力してもらえるようになる。
相手が理解できる表現に「翻訳」して伝える——。この意識だけで、対話の質は大きく変わるだろう。
1on1で聞くべき「働き続ける理由」
では、シニア社員のマネジメントに行き詰まったとき、どう関係性を見直していけばよいだろうか。整理の軸として、次の四つの視点が役立つ。

大切なのは「扱い方」ではなく、役割と貢献を軸に関係を再設計する姿勢だ。年齢差にとらわれず、相手の言葉を翻訳しながら対話を重ねる。それがマネジャーに求められる力なのである。
その実践において、特に重要なのが、1on1の場で「働き続ける理由」を尋ねることだ。この問いかけを通じて相手への理解を深めることが、心が近づく第一歩になる。
シニア社員との1on1の質問例
では、具体的にどのように話を進めるのが効果的だろうか。「働き続ける理由」を探るには、直接的に聞くよりも、以下のような角度から問いかけると本音を引き出しやすい。
① 選択の理由
Q:なぜ再雇用(定年延長)を選んだのですか。
……お金のために働く人ばかりではないし、辞めるという選択肢もあったはず。「なぜ辞めなかったのか」の回答には、今働いている目的や動機が見えてくる。
② 会社との関係性
Q:この会社のどこに魅力を感じていますか。
……他の会社で働くこともできたのに残ったからには、何らかの愛着や理由があるはず。「取り立てて好きなところはないが、居心地が良い」という答えなら、その「居心地」を大事にしていると考えられる。
③ 仕事観
Q:仕事を続けるうえで、譲れないことは何ですか。
……高い成長は望まなくても、働くからには譲れない価値観があるはず。回答から、その人が仕事に求める本質を読み取ろう。
これらをフラットに尋ねることで、相手の価値観や動機が見え、無用な思い込みを減らせる。食事をしながら自然に話を聞くようなスタンスで耳を傾けるのが理想である。
シニア社員の管理を任されることを「押し付けられた」と感じてしまう若手マネジャーもいるだろう。しかし、よく考えてみてほしい。マネジャーのほうが後から異動してきたケースも少なくないのだ。
シニア社員は社内に豊富な人脈を持ち、過去の成功・失敗に基づく経験値も有する非常に貴重な部下である。信頼関係を築ければ、若手には見えないリスクを事前に教えてくれる、大きな戦力となるはずだ。








