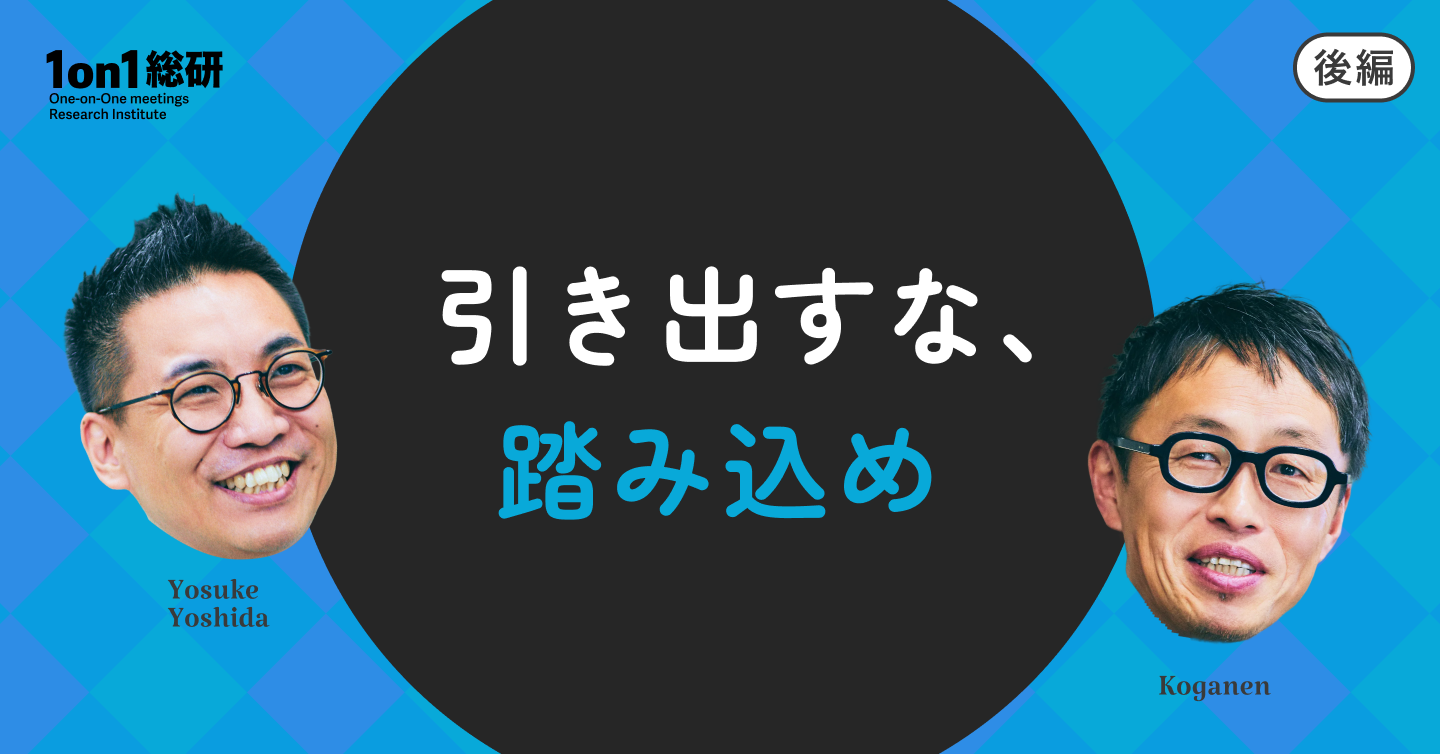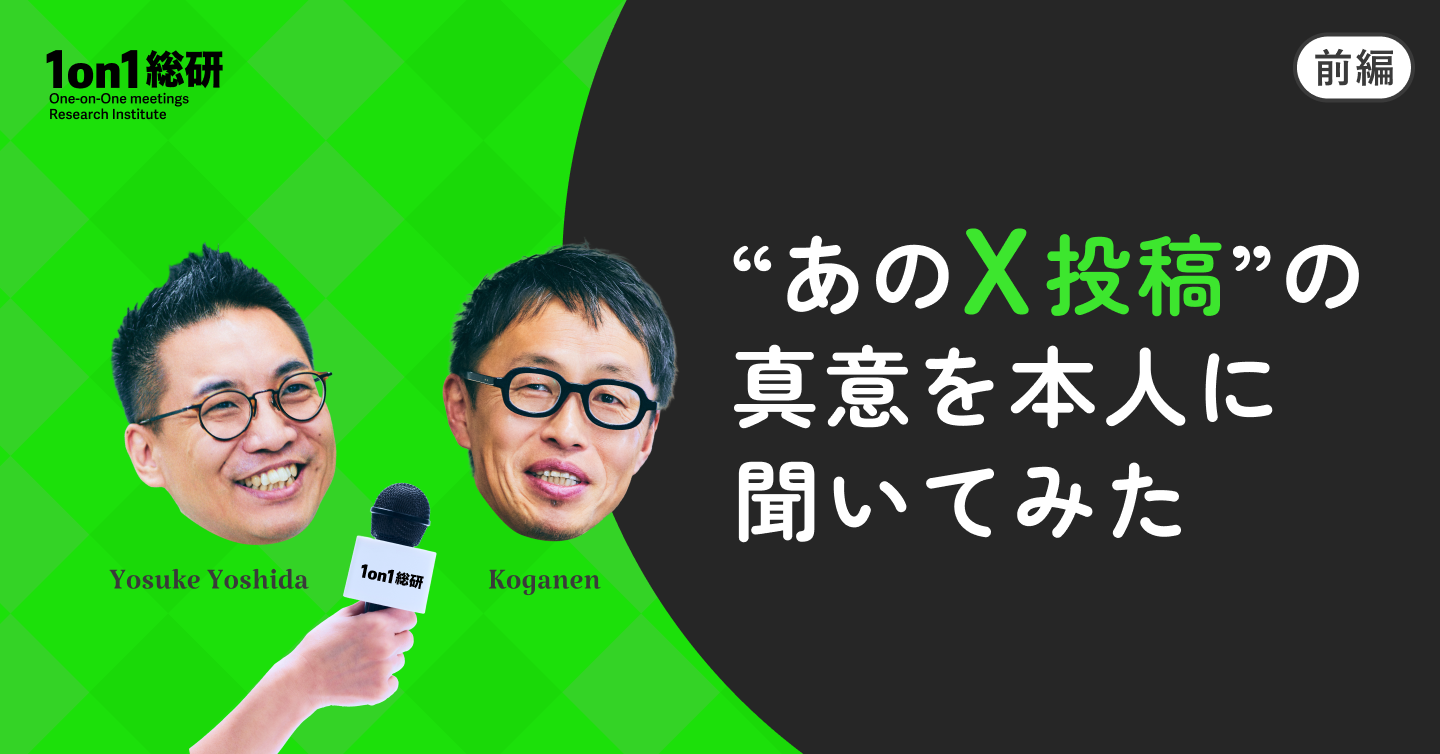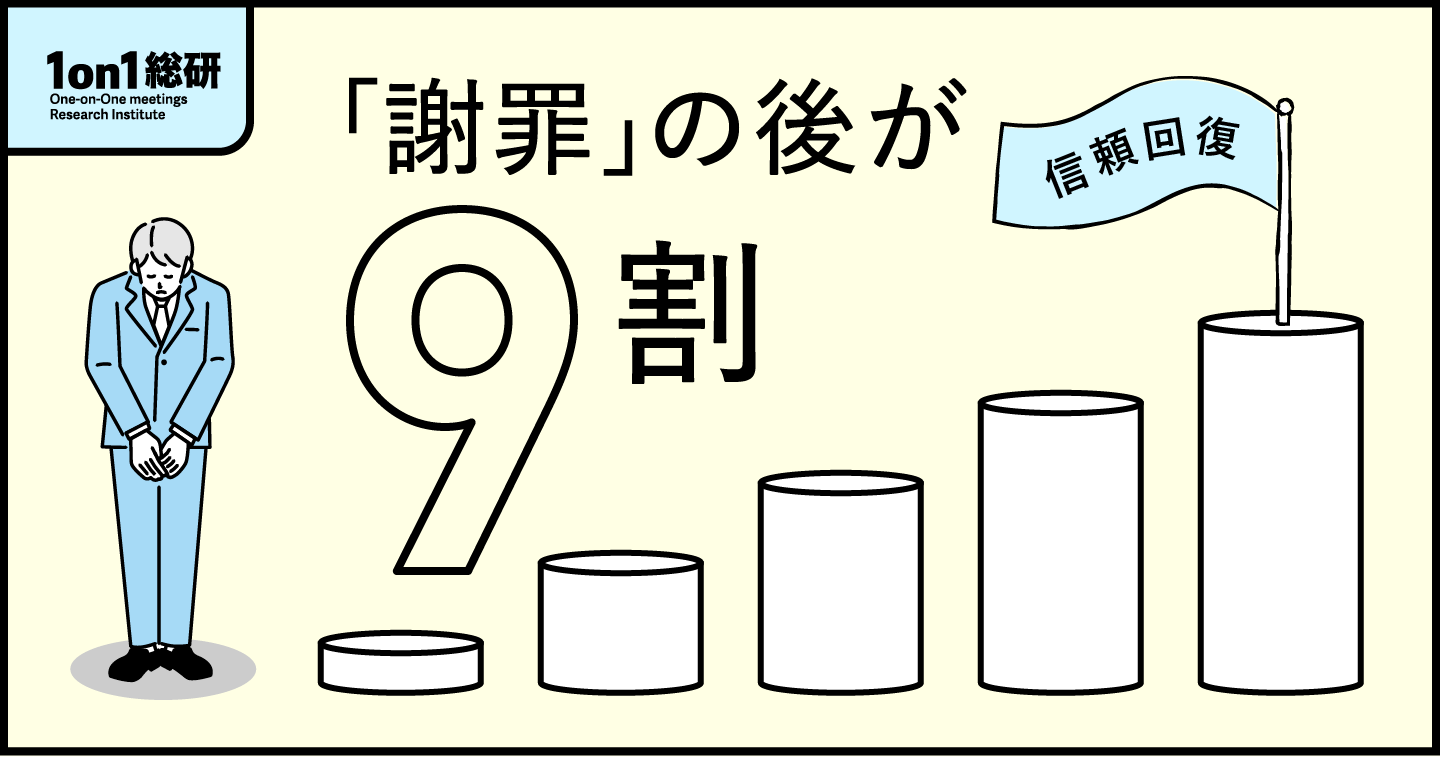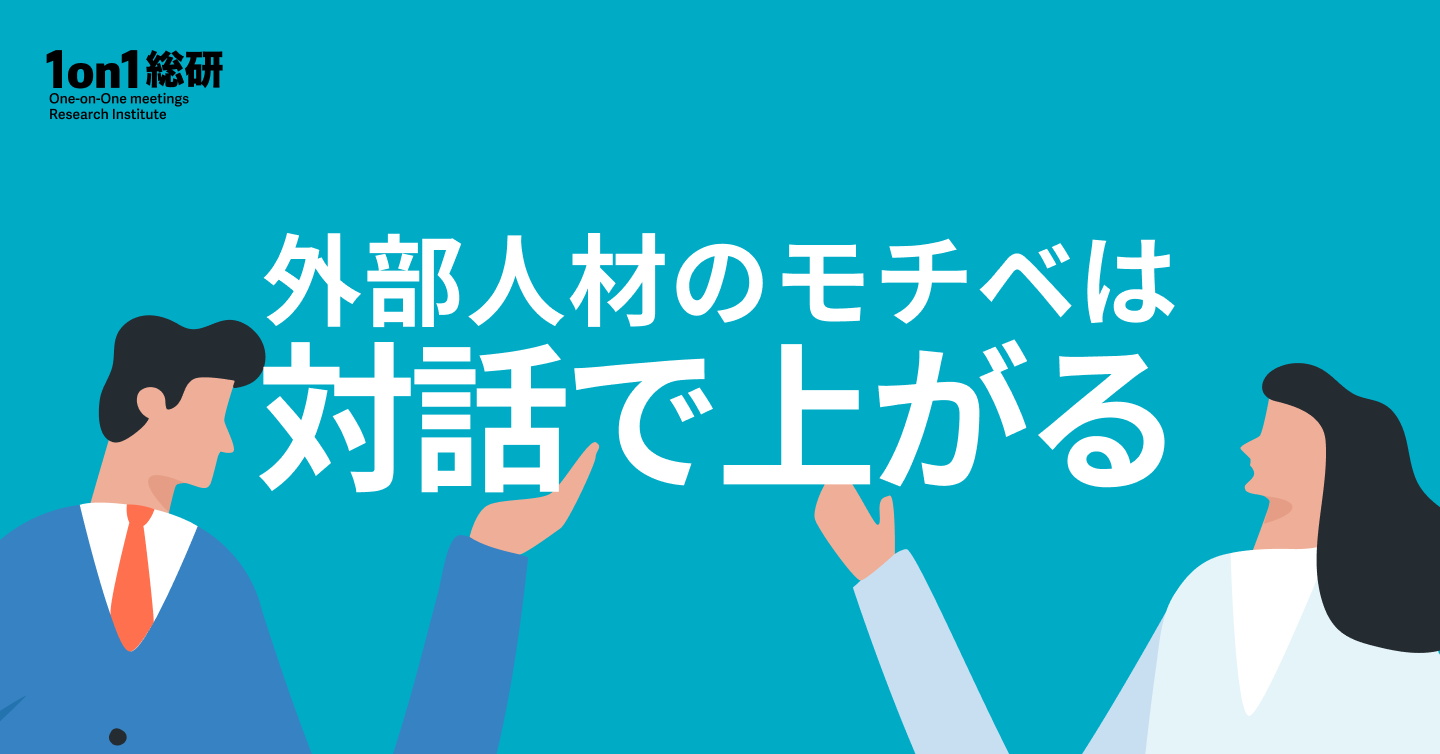
業務委託人材が真価を発揮する1on1実践法
マーケティングの高度化、複雑なプロダクト開発、AIを使った新規企画など、いまや社内人材だけではプロジェクトが回りづらい状況が広がっている。
こうした背景から、外部のプロ人材がプロジェクトに参画する機会は増えている。しかし、業務委託という雇用関係でも主従関係でもないからこそ、従来のマネジメントは通用しにくい。そのなかでエンゲージメントを高め、モチベーションを維持することは、チームの成果を大きく左右する。
この記事では、外部人材と信頼を築きながら成果を上げるためにマネジャーが取るべきアプローチを整理し、1on1の実践ヒントやチェックリストを紹介する。
求めているのは「貢献実感」
プロ人材は有期契約のため、期間内に明確な成果を出すことが求められる。このため多くのマネジャーは「発注側」の立場で接しがちで、想定通りのアウトカム(その成果による効果・価値)を求めて期待を一方的に伝えるだけになりがちだ。
しかし、プロ人材のモチベーションの源泉は、単なる成果の達成ではなく「貢献できている」という実感にある。つまり、自分のスキルが適切に活用され、組織の役に立っていると実感できることが重要なのだ。
ところが、発注側にプロ人材を活用するスキルが不足し、彼らの能力を十分に発揮できる体制が整っていないと、プロ人材は「自分の専門性が活かされていない」と感じてしまう。こうなると貢献実感を得ることができず、モチベーションが低下し、本来のパフォーマンスも発揮できなくなってしまう。
情報格差を埋める努力が不可欠
リモートで働くタイプの外部人材は、日々の雑談やオフィスでの文脈を共有できない。そのため情報格差が生まれやすく、そこに成果が影響されることもある。TeamsやSlackなど社内コミュニケーションツールのやり取りには限界があるため、背景情報や期待するアウトプットを丁寧に伝える工夫が欠かせない。
「外部人材はオフィスに来るのを嫌がるのではないか」と思い込みすぎないことも大切だ。フル出社でコミュニケーションを密に取ることでパフォーマンスを高めている会社であれば、その文脈や背景を積極的に伝えることで、外部人材も真価を発揮しやすくなる。交渉が必要な場面もあるが、あくまでも対等な関係であることを前提に進めたい。
例えば、定例会議の議事録を必ず共有する、Teams等の「社内の重要な変化や背景」をまとめたチャンネルに参加してもらう——、そんな小さな仕組みを整えるだけでも、外部人材の理解度と成果は大きく変わる。
対話で信頼とモチベーションを高める
外部人材が本当は何を考えているかを知るには、やはり対話が欠かせない。プロ人材とチームは「成果を求め、対価を払うだけのドライな関係」で終わる必要はない。互いの理解を深めるために、1on1の機会を積極的に設けたい。
発注者は「1on1は迷惑ではないか」と遠慮しがちだが、実際には、貢献にこだわるプロ人材の側こそ1on1を求めている。状況共有や期待役割の明確化、貢献実感の確認は、短時間でも定期的に行うほど成果につながりやすい。
ここで重要なのは「健全な緊張関係」を維持することだ。発注者とプロ人材の双方が期待値を調整し合い、たとえば、四半期ごとに「次の3カ月で何を達成するか」を話し合う場を設ければ、過剰な依存や一方的な命令関係に陥らず、互いに納得感を持って取り組める。
さらに、外部人材の考えや価値観を共有する場としても1on1は有効だ。価値観や仕事へのこだわりを理解し合うことで互いに仕事がしやすくなる。そのためには、仕事以外の話題も交えると良い。たとえば、最近の喜怒哀楽に関するエピソードを尋ねるだけでも、その人の心が動かされるポイントやモチベーションの源泉を垣間見ることができる。
ある経営者は契約しているプロ人材と3カ月ごとに30分の1on1を実施している。その場で経営者はプロ人材に評価を伝え、プロ人材は新しいアイデアを提案する。この仕組みにより経営者は外部人材から最新の知見を、プロ人材は定期的な自己プレゼンの機会を得られ、両者の信頼関係が深まっているという。
マネジャーのための外部人材1on1チェックリスト
外部人材との1on1ではどんな点に気を付けるべきか。以下のチェックリストを参考にしてほしい。

外部人材との1on1に特別なスキルは必要ない。重要なのは、対話を通じて信頼関係を築くことだ。それにより、一方的な指示だけの関係から、チームの力を共に高める協働関係へと発展させることができるだろう。
求めているのは「貢献実感」
プロ人材は有期契約のため、期間内に明確な成果を出すことが求められる。このため多くのマネジャーは「発注側」の立場で接しがちで、想定通りのアウトカム(その成果による効果・価値)を求めて期待を一方的に伝えるだけになりがちだ。
しかし、プロ人材のモチベーションの源泉は、単なる成果の達成ではなく「貢献できている」という実感にある。つまり、自分のスキルが適切に活用され、組織の役に立っていると実感できることが重要なのだ。
ところが、発注側にプロ人材を活用するスキルが不足し、彼らの能力を十分に発揮できる体制が整っていないと、プロ人材は「自分の専門性が活かされていない」と感じてしまう。こうなると貢献実感を得ることができず、モチベーションが低下し、本来のパフォーマンスも発揮できなくなってしまう。
情報格差を埋める努力が不可欠
リモートで働くタイプの外部人材は、日々の雑談やオフィスでの文脈を共有できない。そのため情報格差が生まれやすく、そこに成果が影響されることもある。TeamsやSlackなど社内コミュニケーションツールのやり取りには限界があるため、背景情報や期待するアウトプットを丁寧に伝える工夫が欠かせない。
「外部人材はオフィスに来るのを嫌がるのではないか」と思い込みすぎないことも大切だ。フル出社でコミュニケーションを密に取ることでパフォーマンスを高めている会社であれば、その文脈や背景を積極的に伝えることで、外部人材も真価を発揮しやすくなる。交渉が必要な場面もあるが、あくまでも対等な関係であることを前提に進めたい。
例えば、定例会議の議事録を必ず共有する、Teams等の「社内の重要な変化や背景」をまとめたチャンネルに参加してもらう——、そんな小さな仕組みを整えるだけでも、外部人材の理解度と成果は大きく変わる。
対話で信頼とモチベーションを高める
外部人材が本当は何を考えているかを知るには、やはり対話が欠かせない。プロ人材とチームは「成果を求め、対価を払うだけのドライな関係」で終わる必要はない。互いの理解を深めるために、1on1の機会を積極的に設けたい。
発注者は「1on1は迷惑ではないか」と遠慮しがちだが、実際には、貢献にこだわるプロ人材の側こそ1on1を求めている。状況共有や期待役割の明確化、貢献実感の確認は、短時間でも定期的に行うほど成果につながりやすい。
ここで重要なのは「健全な緊張関係」を維持することだ。発注者とプロ人材の双方が期待値を調整し合い、たとえば、四半期ごとに「次の3カ月で何を達成するか」を話し合う場を設ければ、過剰な依存や一方的な命令関係に陥らず、互いに納得感を持って取り組める。
さらに、外部人材の考えや価値観を共有する場としても1on1は有効だ。価値観や仕事へのこだわりを理解し合うことで互いに仕事がしやすくなる。そのためには、仕事以外の話題も交えると良い。たとえば、最近の喜怒哀楽に関するエピソードを尋ねるだけでも、その人の心が動かされるポイントやモチベーションの源泉を垣間見ることができる。
ある経営者は契約しているプロ人材と3カ月ごとに30分の1on1を実施している。その場で経営者はプロ人材に評価を伝え、プロ人材は新しいアイデアを提案する。この仕組みにより経営者は外部人材から最新の知見を、プロ人材は定期的な自己プレゼンの機会を得られ、両者の信頼関係が深まっているという。
マネジャーのための外部人材1on1チェックリスト
外部人材との1on1ではどんな点に気を付けるべきか。以下のチェックリストを参考にしてほしい。

外部人材との1on1に特別なスキルは必要ない。重要なのは、対話を通じて信頼関係を築くことだ。それにより、一方的な指示だけの関係から、チームの力を共に高める協働関係へと発展させることができるだろう。