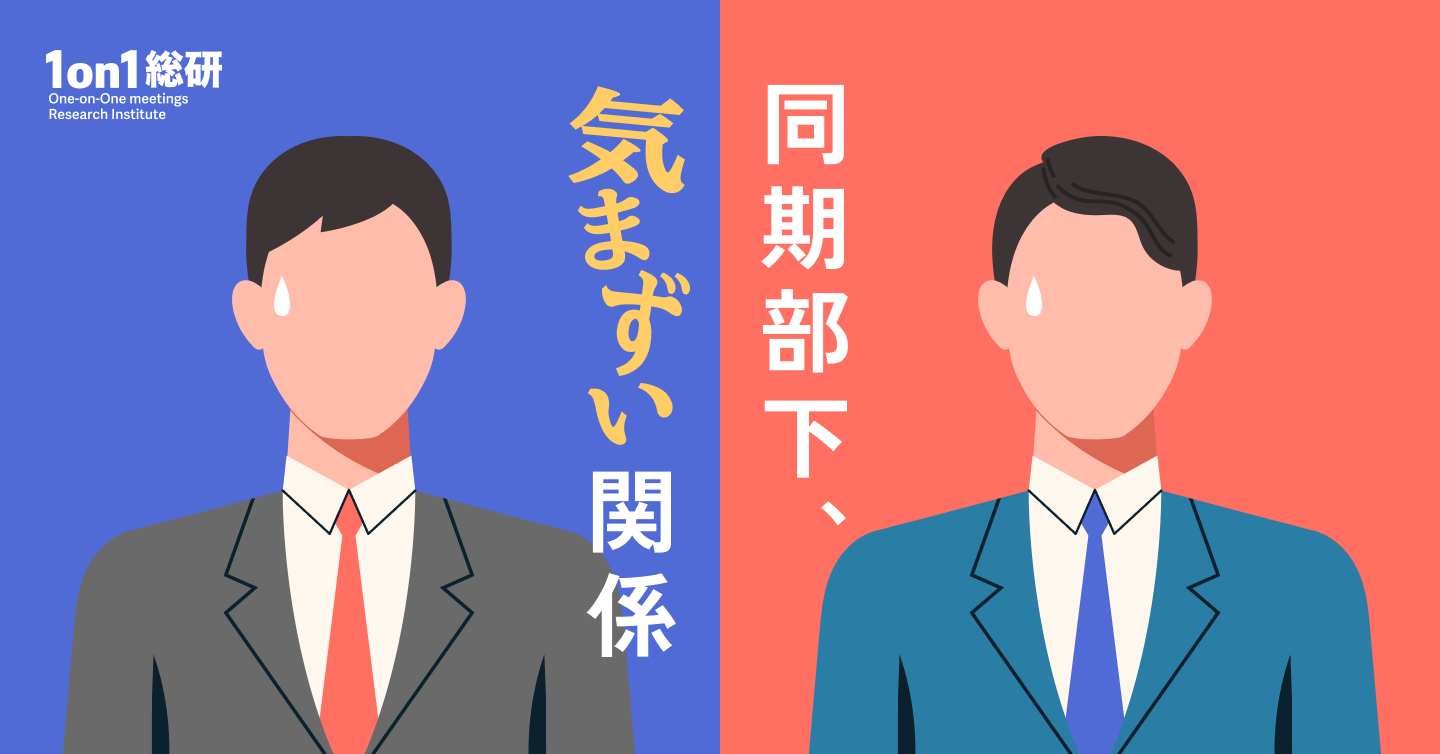組織を動かす
【驚愕のデータ】優秀な若手が逃げ出す「ゆるブラック」という現実
人間の考えや志向は実に多様です。その環境を好む人もいれば嫌う人も現れます。
かつて日本企業では、多くの人が望まぬ長時間労働を強いられ、心身の不調をきたす人もいました。「働きすぎ」問題は、「ブラック企業」という言葉として悪評がSNSを通じて広まったこと、また政府による本格的な介入も奏功し、ある程度の解消に向かいました。
しかしながら、今度は別の問題に直面しました。
逆に仕事が楽過ぎてやりがいを感じられない、または望むような成長ができないと思う人が出てきます。そうした人は、強制的に楽な仕事しかさせない環境を問題視し、表面的にはホワイトながらもやりがいや成長機会に乏しい会社を、いつからか「ゆるブラック」企業と認定するようになりました。
ゆるブラックな環境は、やる気のある若手が流出する要因にもなっています。
過酷な労働環境はご法度、されど仕事が緩いのもダメ……一体どうすればいいのでしょうか。そこで2回にわたって、データ分析も踏まえながら、以下の三つの問いに迫ります。
📌「働きやすさ」と「働きがい」をもたらす要因
📌「働きやすさ」および「働きがい」と、企業業績との関係性
📌人生100年時代における「働きやすさ」と「働きがい」の両立
初回となる今回は、働きやすさの改善の裏で急速に失われた働きがいについて驚愕のデータを交えて深掘りします。

心理的安全性を高める組織づくりと1on1の実践
「なぜ、部下が本音を言ってくれないのか」「雰囲気は悪くないのに、会議がかみ合わない」「頑張ってフィードバックしても、反応が薄い」ーー。
このような悩みを抱えるリーダーが増えています。職場における「心理的安全性」の重要性は広く認知されてきましたが、実際に高めようとすると、どこから手をつけるべきか分からず、漠然としたモヤモヤを抱えたまま日々のコミュニケーションが続いている組織も多いのではないでしょうか。
信頼や本音が育ちにくい背景には、職場に無意識のうちに積み重なる“静かな壁”が存在します。たとえば、報われなかった経験や、対話が設計されていない状態は、知らず知らずのうちに「声をあげない方が安全だ」という空気を生んでしまいます。
こうした課題に対して、いま注目されているのが、1on1ミーティングという「継続的な対話の仕組み」です。
上司と部下が定期的に向き合う1on1は、安心して話せる関係性を築く土台となり、心理的安全性を育て直すための有効なアプローチとして導入する企業が増えています。
本記事では、心理的安全性がなぜ損なわれるのかという根本要因から、1on1が信頼と対話をどう再構築するのかまでを、実際の事例も交えながら解説します。

【話題沸騰】「配属ガチャ」は消滅するのか。今問う人事異動の価値
「配属ガチャ」という言葉が広がっています。入社時の配属先をはじめ、会社によって一方的に決められる人事異動やジョブローテーションを指すネットスラング発祥の用語。今や一般紙でも使われるなど、市民権を獲得しています。
自身のキャリアが「運任せ」となってしまう配属ガチャという、かつて「当たり前」の人事慣行が今となっては若手社員の離職要因になっています。
それを受けて配属ガチャを廃止し、入社時に配属先を確定させる採用へと切り替える企業が相次いでいます。
配属ガチャは絶滅するのでしょうか。そうとも言いきれません。
むしろ、ポスティング(手挙げ式)の異動が広がり、配属ガチャが減っている今だからこそ、会社主導による人事異動が再評価されるようになりました。
そこで各社の動向を踏まえながら、改めて人事異動の意義を深掘りしていきます。

【結局】「ジョブ型」で日本企業は変わるのか
ジョブ型雇用・人事が浸透してから、はや5年。
昨今でも、「ジョブ型によって30代の管理職抜擢が増えた」といったニュースをよく見かけます。2024年夏には政府が「ジョブ型人事指針」を公表するなど、官民挙げての「ジョブ型推し」の様相を呈しています。
人事の領域では珍しく(失礼!)、一時のブームで終わらずに浸透しつつあるジョブ型。ジョブ型によって本当に日本の雇用・人事は変わるのでしょうか。
もっとも、その前に踏まえておくべきことがあります。それはジョブ型ほど勘違いされている概念はないということです。「ジョブ型で実力主義が加速する」といった表層的な理解よりもはるかに深い、日本の雇用・人事にまつわる核心を掘り下げる必要があります。
そこで今回登場する極めて重要な概念が「単線キャリアパス」というもの。おそらく聞いたことがない言葉でしょう。その知名度の低さとは裏腹に、日本の人事課題を理解するうえで最も重要な概念となります。この単線キャリアパスを軸に日本型雇用・人事のあるべき未来を紐解きます。

【核心】若手が辞めて、シニアが残る「本当の理由」
「働かないおじさん」という言葉が生まれてどれだけの月日が経つでしょうか。この問題がいっこうに解消されない理由は極めてシンプルです。
中高年の「個人の問題」だと決めつけて、原因の究明について真剣に考えてこなかったからです。そもそも働かなくなるのは、中高年社員がモチベーションを維持できない深い理由があるからです。
「企業風土が悪い」の類も本質的な理由にはなりません。あらゆる業界にも横たわる課題であることから、「中高年社員が輝けない」のは、風土いかんによらず日本企業に共通する構造的な問題です。
現在、人的資本経営の名の下、若手・中堅社員向けのエンゲージメント向上策などに力を入れている企業が増えています。対照的に、中高年に対してはエンゲージメントのてこ入れをするどころか、「管理職下ろし」に邁進している企業が少なくありません。
しかし、人的資本経営の本丸は、中高年社員の活性化にほかなりません。
なぜなら、長年その会社で働いてきたシニアが輝けない企業が「人を大切にしている」はずがないからです。今の時代、輝いていないシニアを見た若手が退職するという負の連鎖反応も起こり得ます。
中高年社員の輝けない仕組みは、日本的人事の課題で一番根深い根源そのもので、日本企業が長らく放置してきたもの。その最深部に迫ることで、「ジョブ型」などの今の人事トレンドの本質を理解する一助にもなります。

【真偽】日本企業は本当に「人を大切」にしてきたのか
「胡蝶(こちょう)の夢」という中国の故事があります。
夢を見ているときの方が現実ではないかと、現実と夢の区別ができなくなる境地のこと。人生の儚さを暗示することもあります。大ヒットしたSF映画「マトリックス」では、現代社会が実は夢の世界に過ぎないというシナリオが強烈な印象を与えました。
現実と夢の境が揺れていることの一つといえば、日本の伝統的なサラリーマン像でしょう。
多くの日本企業はこれまで、「人を大切にする」ことを強調してきました。ところが、「現実」として起きていること、それは中高年社員を中心としたリストラ(人員整理)の話、あるいは若手から中堅にかけての社員の離職増加でしょう。
人を大切にする日本の人事慣行は、もはや現実ではなく儚い夢なのかもしれません。最近広がっているジョブ型雇用や人的資本経営などの人事改革も、「人を大切にする」の概念が揺らいでいたら元も子もありません。
そこで本記事は、社会からほぼ意識されることなく今日まで受け継がれてきた日本的雇用の「暗黙の了解」に迫り、その再考に迫ります。

「30代クライシス」に見る、日本企業の「すでに起こった」課題
自らを「社会生態学者」と名乗ったピーター・ドラッカーは、「すでに起こった未来」という概念を提唱しました。
多くの場合、未来の予測は困難です。とはいえ、短期的な変動はあれど、長期的には一定の方向に進むことがほぼ確実なこともあります。例えば、出生率の低下に伴う人口動態や、社会のデジタル化などがそれに該当します。
ただし、そうした未来(変化)は、初期の頃には社会からはほとんど認知されません。変化の萌芽から世間からの認知までにタイムラグがあることを踏まえ、ドラッカーは「すでに起こった未来」と表現したのです。
現在の日本企業におけるすでに起こった未来はなんでしょうか。その一つが「30代離職」の増加ではないでしょうか。
業績そのものは堅調な企業であっても、「中堅社員」と呼ばれるこの層の流出が進行しているケースも。まるでボディーブローのように時間をかけてじわじわと効いてくる、忍び寄る危機です。
日本企業がずっと掲げてきた「人を大切にする」という標語。今ほどその標語の意味を再考することを迫られている時代はありません。そこで本連載を通じて、企業の成長の源泉である人事・雇用における「すでに起こった未来」を深掘りしていきます。
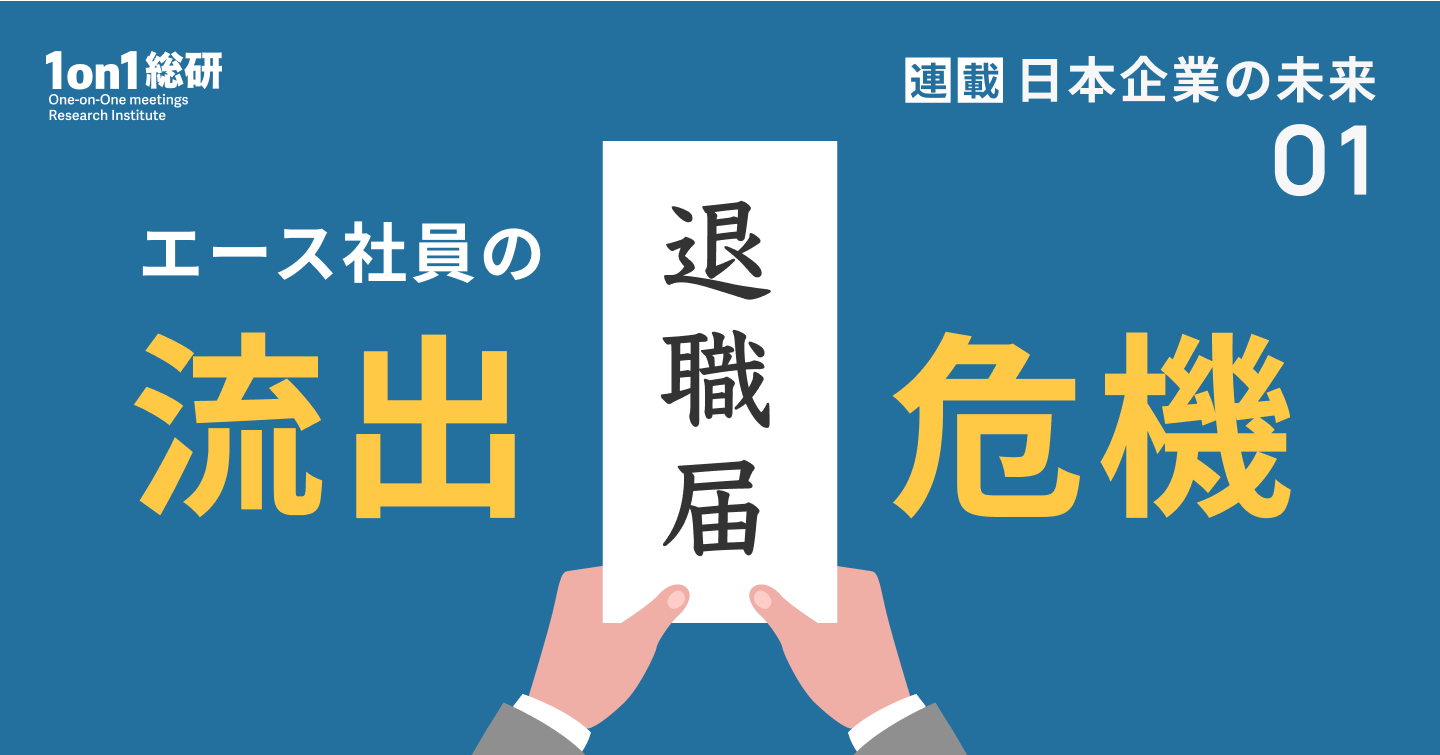
【失敗の本質】「勤勉な国」日本では世界に通用しない
2025年1月に永眠された野中郁次郎氏。共著「知識創造論」(東洋経済新報社)や知識マネジメントを扱った「SECIモデル」のみならず、「失敗の本質」(ダイヤモンド社)の共同著者としても有名です。ロングセラーとなった「失敗の本質」は、太平洋戦争での日本の敗戦について分析したものです。
野中郁次郎氏の功績を多角的に深掘りする本特集の前編と中編では、高度経済成長期の日本の製造業の強みが、野中氏が確立した知識創造モデルを通じて、アメリカのソフトウエア開発やスタートアップビジネスにも応用されてきたことを紹介しました。
ということは、日本のものづくり企業の強みが、時代を超えて海を越えて業種を超えても通用する。つまり、本質的な強みには業種などを問わずに「普遍性」があるということです。
逆に、日本が抱える普遍的な弱みや課題とは何でしょうか。そのヒントが書籍「失敗の本質」に眠っているのです。
先にその一端を紹介すると、日本の課題とは、人材の「質の高さ」や「勤勉性」への過剰な依存です。本来は「強み」であるはずが、場合によっては「弱み」に転じるのです。
今でいうと、「人が中心」を標語とする人的資本経営に対する一つの警鐘ともいえるこのテーマを深掘りします。

【世界標準】米国は日本から生産性の本質を学んだ、さて日本はどうする
経営学者の野中郁次郎氏が2025年1月に永眠されました。竹内弘高ハーバード・ビジネス・スクール元教授・現国際基督教大学理事長と共に、かつての日本企業が「暗黙知」を含めた知識を創造し続ける仕組みを「SECI(セキ)モデル」にまとめました。
このモデルはアメリカで注目され、ソフトウェア開発モデルの発展にも貢献しました。
アメリカの経営の進展に大きく貢献した、もう一人の日本人をご存じでしょうか。トヨタ自動車元副社長の大野耐一氏です。
「トヨタ生産方式の父」としてご存じの人も多いでしょう。トヨタ生産方式もまた、アメリカの経営に多大な影響を与えました。それも、アメリカの自動車産業だけでなく、ソフト開発やスタートアップの経営に対してもです。
日本が培ってきたものづくりの力は、単に技術の範疇にとどまりません。国も業界も問わずに普遍的に応用できるマネジメントの要諦が詰まっています。巷で聞く「日本のものづくり思考は限界」といった意見はあまりに表層的です。
野中郁次郎氏の功績を多角的に深掘りする本特集の第二回は、知識労働としてのモノづくりのエッセンスに迫ります。あなたがどのような職種や業種に属していようとも、必ず役立つマネジメントの王道がそこにあります。