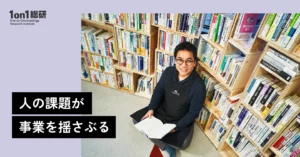部下には学びを求めるのに、自分は学んでいない——、そんな管理職は少なくない。
スキルベースで組織をつくる流れが加速し、リスキリングは企業にとって避けられないテーマになっている。しかし、部下の成長を促す立場にあるマネジャー自身が「学ぶこと」から距離を置いてはいないだろうか。
「学んでいない上司に、部下はついてこない」。そう語るのは、リスキリング支援を通じて数多くの企業変革に携わってきた後藤宗明氏だ。経営と現場をつなぐマネジャーこそが、変化の先頭に立たなければならない。
本記事では、管理職がなぜ・何を・どう学ぶべきかを掘り下げるとともに、リスキリングによって事業構造を変えた中小企業の実例や、組織に働きかける具体的なアクションまで、実践的な処方箋を紹介する。

後藤 宗明(ごとう むねあき)
一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事 SkyHive Technologies 日本代表
2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。現在日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。
目次
マネジャーが学ぶ姿が「背中で語る」メッセージになる
——後藤さんは、部下にリスキリングをしてもらうためには、マネジャー自身にがリスキリングの経験が必要だと考えているとのことでした。マネジャークラスとメンバークラスとを比較したとき、リスキリングに違いはありますか。
マネジャークラスは出世に関わるため、メンバークラスとはリスキリングへのインセンティブが異なります。また、マネジャーには「『部下の手本となる」』という独特の責任もあります。子どもに「勉強しなさい」と言うだけでは動かないのと同じで、部下も“学んでいない上司”にはついてきません。
——マネジャーはどのようなタイミングでリスキリングを考えるべきなのでしょうか。
マネジャーの役割は、経営の意思決定を理解し、現場に落とし込むことです。その過程で人事と協働しながら自部門に求められるスキルを明確化する際、自身のリスキリングも併せて検討するのがよいでしょう。
——マネジャー層には、ゼネラリストとして育っている人も多いと思います。どういう視点で学ぶべきスキルを考えればよいのでしょうか。
日々の業務の中に考えるきっかけはたくさんあります。競合サービスにAIが実装され、自社の脅威になりそうなら、マネジャー自身もAI分野を学ばなくてはなりません。コーポレート部門も同様で、採用業務にAIを取り入れる企業が増えたと聞いたら、AIによるオペレーション業務の自動化のスキルを獲得したほうがいいわけです。
ただし、リスキリングの必要性に気づいても実行に移せないケースが多く、その原因は主に会社側にあります。経営者がテクノロジーに疎い、業務時間内のリスキリングは認めないなど、理由はさまざまです。
しかし、会社が支援しなければ、学習意欲の高い人はその努力を認める会社に転職してしまいます。リスキリングは転職のために行うものではなく、会社のために必要な学びです。したがって、業務時間内に行うべきだということを、経営者は肝に銘じておくべきだと思います。
社員のリスキリングが事業構造を変える例も
——マネジャーのリスキリングが、実際に会社に成果をもたらした事例はありますか。
石川県にある石川樹脂工業を例に取りましょう。6年前、創業家の3代目である専務・石川勤氏が、社員全員に対してデジタル分野のリスキリングを実施し、事業構造を大きく転換させました。具体的には、もともと外食チェーン向けの食器などを製造する樹脂製品のOEMメーカーでしたが、リスキリングによってデザイン性の高い食器を自社ブランドとして開発・販売し、大ヒットさせました。現在では、自社ブランドが売上の7割を占めています。
製品名は「ARAS」(エイラス)。「1000回落としても割れない食器」というキャッチコピーのもと、デザイン面のDXだけでなく、まったく手つかずだったWebマーケティングの分野も強化しました。ブランドのInstagramのフォロワー数は30万アカウントを超えています。
——エンジニア以外の方もリスキリングにチャレンジしたのですね。

はい。ブランドマネジャーを務める女性は、リスキリング前は金型の設計を担当していました。コロナ禍で技能実習生が来日できなくなったタイミングで、工場にロボットを導入したことがリスキリングのきっかけでした。彼女はその後、配置転換によってデジタルマーケティングを任され、AmazonでのEC販売を担当。Amazonのカスタマーサクセスチームから学ぶことで、売上をわずか3カ月で倍増させました。そこから外部の方々と仕事をしながらリスキリングをしていき、現在は部下を3人抱えるリーダーとして活躍しています。
——リスキリングで、人も会社も成長したのですね。
リスキリングを人事任せにしてはいけない
——マネジャーがリスキリングをするときのポイントは。
まず、上司である部長や執行役員が、部門内でのリスキリング時間を確保する意思決定をすることが大切です。就業時間外の自主的な学習は転職リスクにもつながりかねません。
マネジャーは、最新のテクノロジーを学ぶことが、いかに自社に影響を与えるかをしっかりと現場に伝えるのが良いでしょう。あえて強調するならば、「リスキリングを人事任せにしない」ことこそが最大のポイントだと思います。
——マネジャーは、上司にリスキリングがしたいと伝える必要がありますね。
はい。部長との1on1で「なぜ今その分野を学ぶべきなのか」「それが会社にどんな影響を与えるのか」をしっかり伝え、業務としての位置付けを理解してもらうことが重要です。
ただし、経営者自身がリスキリングに関心を持っていない企業では、社員の要望だけでは動きにくいのが実情です。
経営者は自社が所属する経済団体などで他社の成功事例を聞いて初めてスイッチが入ることが多いものです。そのため、経営層の理解を得るには、外部の成功事例を社内に持ち込む方法が有効です。たとえば、社内でその分野の専門家を招いた勉強会を開き、社長にも参加してもらうことで、リスキリングの重要性を実感してもらえるでしょう。
——マネジャーの中には、リスキリングに消極的な人もいると思います。

既存業務の多くは遅かれ早かれAIやヒューマノイドロボットに置き換わっていきます。マイクロソフトでは、自社製品のプログラミングの約4割をすでにAIが担っており、下級エンジニアの解雇も始まっています。今後はあらゆる仕事の性質が変わっていく。ただし全てが変わりきるまでには猶予があります。その間に自身の役割の変化と向き合い、できるだけ早い段階でリスキリングに取り組むべきです。
リスキリングに前向きな方には、組織の学習環境整備を主導していただきたい。そのような役割を担える人材が、今後、会社の中でチェンジメーカーになっていくはずです。
📕あわせて読みたい
「部下はなぜ学ばないのか? 日本企業のリスキリングがうまくいかないこれだけの理由」
⇨なかなか進まない日本企業のリスキリング。その根本原因をリスキリングの第一人者・後藤宗明氏が徹底解説。部下が学ばない理由から、マネジャーが果たすべき新たな役割、そして成功する企業の共通点まで、具体的な事例とともに明かします。