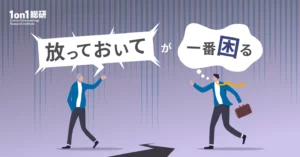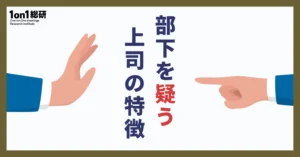名選手の影に名コーチあり。名経営者の影にも名コーチがいます。
世界のデジタル産業革命をけん引し続けているシリコンバレーの地で、アップルのCEO、スティーブ・ジョブズやグーグルの元CEO、エリック・シュミットをはじめ、数多くの企業経営者に深い影響を及ぼした人物がいます。
それがビル・キャンベル。彼がコーチングした企業の時価総額を合わせるとトリリオン(1兆)ドルに達するとのことで、「1兆ドルコーチ」と呼ばれるようになりました。
そのコーチング哲学と生き様をまとめたのが「1兆ドルコーチ(著者:エリック・シュミットほか、発行:ダイヤモンド社)」。日本でも発行部数が17万部を超え、アマゾンには2000件以上ものレビューが付いています。
そんな希代の名コーチは、元々はラグビーのコーチをしていました。そこで養った人間と組織への観察眼、そして人たらしの術がビジネス界でいかんなく発揮されたのです。
シリコンバレーといえば「デジタル」や「テクノロジー」、そして「戦略」に長けた印象があります。しかし、ビルが重視したのが「コミュニティ(人間関係など)」や「誠実さ」、「実行力」でした。
これらは、猫も杓子も「DX」と口にする今の時代からすると泥臭いテーマ。でも、そこに古今東西不変のチームマネジメントの神髄があります。今こそ名コーチに学んでみませんか。
プロフィール:ビル・キャンベル(ウィリアム・ヴィンセント・キャンベル・ジュニア、1940年8月31日 – 2016年4月18日)。アメリカンフットボールの選手とコーチを経て実業界へ。1997~2014年アップル取締役。2001年にグーグルのコーチ就任。ツイッター(現X)やアンドリーセン・ホロウィッツ、元米副大統領アル・ゴアのコーチも務めた。
目次
問題は「戦略」ではない
シリコンバレーの成功企業を支えているのは、華々しい経営戦略だけではない——。
ビル・キャンベルの功績は、この意外な事実を私たちに教えてくれます。経営者なら「戦略」、それも「長期的な戦略」に関心が向くと考えられています。しかし、ビルのアプローチは違いました。
本書によれば、グーグル幹部(執筆者ら)がビルに会うと、本題で真っ先に話すのはオペレーション(日常業務)やタクティクス(短期的な戦術)などに関することだったそうです。ビルが長期的な経営戦略の問題を取り上げることはめったになく、たとえあったとしても、その戦略を支える強力な行動計画があるかどうかを確かめるためにすぎませんでした。
また、ビルは「やるべきこと」を指示しませんでした。プロダクトに対して思うところがあっても、口を出さない。むしろ、組織の状態を何よりも注視していました。
そして、ビルはチームのコミュニケーションが取れているかどうか、(また組織内の)緊張や対立が明るみに出され、話し合われているかどうかに気を配り、大きな決定が下されるときは、賛成しようがしまいが全員がそれを受け入れていることを確認しました。
このように、「1兆ドルコーチ」が大切にしてきたのは、経営戦略そのものよりも、コミュニティ(組織の健全性)と実行力の徹底でした。この洞察は、現代のビジネスリーダーにとって価値ある教訓です。
組織の「ひび」がいつか「ゾウ」になる
英語のイディオム(慣用句)に「部屋の中のゾウ(The elephant in the room)」があります。ゾウという巨大な存在に気が付かない人はいないはずなのに、誰もその存在を言い出せない状況を指します。この皆が「見て見ぬふり」をしていることが重大な経営課題となります。
部屋の中に象がいるかどうかを調べる「リトマス試験紙」は、ある問題に対して、チームが率直に話し合えているかどうかです。それができていない時には、組織にある種の「緊張」があります。
緊張の要因は組織内の「政治」にあります。すでに人間同士の駆け引きが始まっているのです。ビルはこうした状況に我慢がなりませんでした。
例えば、プロダクトリーダー同士が揉めた時のこと。当初は技術的な問題とみなされていましたが、データや理論と照らし合わせても解決策が見つかるどころか、むしろ問題がこじれました。

この時、ビルは問題に介入しました。もちろん、問題の解決について明確な意見を持っていたわけではありません。「緊張見つけ人」としての自らの出番だと理解していたからです。
そしてビルは、対立の根源的な要因(本書には明記されていないが、おそらく人間同士またはチーム間での社内政治的な駆け引き)を探し当てて、対処を迫りました。こうして実施されたミーティングは「グーグル史上最も白熱したものの一つになったが」、部屋の中のゾウを追い払う企業文化の醸成へとつながったようです。
人間同士の軋轢(あつれき)は些細なことがきっかけで起こります。「ちょっとさすっただけで直せるような、組織の小さな『ひび』に気づくこと」が、コーチの役目だとビルは言いました。
例えば、ある時、グーグルCEOのシュミットが、ミーティングで誰かの発言を悪く(批判や否定的意見だと)受け取りました。それは一週間もの間、彼の心に刺さり、「今度は相手を言い負かしてやろう」と、臨戦態勢で次回のミーティングに臨んでしまったそうです。こうした態度を諫めるのもビルの役目でした。
私たちの仕事を振り返っても、戦略がうまく機能しない時には、多くの場合、実行に支障があります。ただし、実行を担うメンバーの能力が不足しているとは限りません。むしろ、人間関係の悪化や利害のぶつかり合いによって実行がないがしろにされていることがあります。しかも、こうした問題の方が当事者が話しにくいものです。
組織にできた小さな「ひび」を放置するとゆくゆくは「部屋の中のゾウ」に発展しかねないという、私たちへの戒めでもあります。
「意見の一致」は重要ではない
ビルはまた、多数決のような「民主主義」を好みませんでした。なぜなら下される意思決定が最適解ではなく、権力者へのロビイング活動の産物だからです。言い換えれば「政治が勝利を収める」とビル。
人間というものはボスへの忖度が避けられない社会的動物であり、特段に工夫をしないと、まともな意思決定すらままならないとも解釈できます。
そこで彼は「即興コメディ」のようなアンサンブル、つまり、適材適所でリーダーたちが有機的に入れ替わり適宜チームを率いていく状態を好みました。こうして、駆け引きのない環境が保たれるように常に気を配っていました。
駆け引きのない関係で欠かせないのが「信頼」。「ギブ・アンド・テイク」の考えが根強いビジネスにおいて、いくら経済的メリットが見込めそうであっても、ビルは信頼できない相手とは決して付き合おうとしませんでした。

信頼の基礎となるのは率直さです。約束を守るという、当たり前のようでいて簡単ではないことをちゃんと実現するのに必要な能力や勤勉さなどを持ち合わせていなければなりません。
また「関係の透明性」も欠かせません。これは、相手に耳を傾け、正直なフィードバックを与え、相手にも率直であることを求めること。「偽りのない(Authentic)リーダーシップ」に必須の姿勢です。
IT大手の米サン・マイクロシステムズの共同創業者(ビノッド・コースラ)のコメントが全てを物語っています。それが、「ビルと僕は意見が合うときも合わないときも、信頼をもとに関係を深めた」です。
信頼関係があるとは、常に意見が合う状態ではありません。むしろ、信頼している相手には異を唱えやすいものです。
「ボール持たぬ人」にも目をやる
実際、ビルは「コンセンサス(意見の一致)なんかクソくらえだ!」とよく怒鳴ったそうです。実際、多くの学術研究が、最適解ではなくコンセンサスを目指すと「グループ・シンク(集団浅慮)」に陥り、意思決定の質が低下しがちなことを示しています。
コンセンサスではなく、信頼を原動力に組織を動かすために具体的にビルが最重要原則としたことがあります。
それが「1on1を正しくやる」、「スタッフミーティングを正しくやる」こと。全員から忌憚(きたん)なき意見を引き出すために、ビルはミーティングの前にメンバー一人ひとりとひざを交えて彼らの胸の内を知ろうとしたそうです。
加えて、1on1で解決できそうな問題であっても複数人のミーティングで話し合うこともありました。重要な問題のほとんどは複数の部門にまたがる問題です。他のチームで起きていることを皆で議論することで共通認識が芽生え、部署の垣根を越えた協力関係へと発展します。
ミーティング中には、「試合に出ない」コーチだからこそ持てる視点を生かしました。
部屋全体の様子を俯瞰(ふかん)して、特に「ボールを持たない人」、つまり物言わぬ人たちの反応を見ていました。こうして、チームメンバー間のコミュニケーションと理解のギャップを見出し、それらを埋める役割を請け負いました。

何よりも「達成する文化」
ビルがコミュニティと並んで重視したことがあります。それが「オペレーショナル・エクセレンス(卓越した実務遂行力)」でした。
彼らしいエピソードがあります。彼が1990年代後半、会計ソフトを手がける米インテュイットのCEOを務めていた時のことです。
ある時、四半期の収益・利益目標の達成が危うくなりました。取締役会では「今投資を抑制すれば長期的な成長力が失われるので、短期的な利益目標は未達でもしたかない」との意見が大半でした。おそらく、日本企業でも同様の意見がほとんどを占めるでしょう。
ところが、CEOのビルは反対しました。「スリム化を図ってでも数字を達成したい。それが自分たちの目指す文化だ」と。
注目すべきは、ビルにとって重要なのが目標達成そのものではないこと。「オペレーショナル・エクセレンス」が少しでも欠けた状態を許さない「文化」を維持するためです。ラグビーのコーチ経験があるビルからすれば、組織に「負け癖」を付けさせたくなかったのでしょう。
ビルにとって、経営陣の仕事とは「結果を出すこと」です。それは株主のためだけでなく、チームや顧客のためでもあると考えていました。
長期目線が重要なのは間違いありません。しかし、「今日の勝敗」の積み重ねが、最終的な結果として現れるのも事実です。
特に長期目線という言葉を誤って解釈し、短期的な収益目標をおろそかにしてしまう組織も存在します。それは「ダイエットは来年から頑張る」と毎年言い続ける人にも相通じるものがあります。
厳しくて親身な「愛のムチ」
目標達成にこだわりを見せるビルは、周囲にも決して「優しい人」ではありませんでした。結果を出せない人はもちろん、メンツやプライドを優先してチームに貢献しない人には厳しい声をぶつけました。
興味深いエピソードがあります。ある時、ビルがクラリスという企業の幹部の油を絞る(叱る)ことになりました。ところが驚いたことに、当人は叱責されて落ち込んでいるかと思いきや、かえって元気づけられて清々しい姿を見せました。
ビルの人柄があってこそ、厳しい指摘が「応援」として受け取られたのでしょう。なお、ビルのインテュイット時代の同僚曰く、ビルとうまくやっていくコツは、「ごまかすな。聞かれたことに答えられなくても、適当にはぐらかすな。分からないと言うんだ!」だそうです。
そんなビル・キャンベルの原点は、アメフトのコーチ時代の「大失敗」にあります。
ある試合で手痛い敗北を喫した時、チームを鼓舞して誠意を示す代わりに、ロッカールームでチームメンバーに罵声を浴びせ、本気でつるし上げました。本書に記載はないものの、ビルとメンバーとの信頼関係は崩壊したのでしょう。
後にビル本人が、「私がチームを失った瞬間」と振り返るシーンです。試合で負けた以上に「真に敗北した」瞬間をずっと胸に刻み、「敗北しているときは、大義に改めて向き合え」という教訓へと昇華されました。

著名な組織心理学者のアダム・グラントは、リーダーシップを持つべきマネジャーが他者と接する際に「親身になるべきか、厳しくすべきか」といった問いを持つことを「誤った二分法」と断じ、本来は「高い基準と期待を示し、それに到達できるよう励ましを与える。いわば愛のムチ」が必要だと説きます。
自分の弱みに正直になる
ビルは、どのような人を卓越した人材と見ていたのでしょうか。彼によると4つの資質があります。それらは「知性」、「勤勉」、「誠実」、そして、打ちのめされても立ち上がって再び挑戦する情熱と根気強さを意味する「グリット(GRIT)」。
ビルはこの4つの資質があると思える人には、他に欠点があっても目をつぶりました。候補者に対して何を成し遂げたかではなく、どうやって成し遂げたかを尋ねることでその資質があるかどうか判断しました。
これら4つの要素を絡めると、自己を理解する力という資質も浮かび上がってきます。
ラグビーの名将トム・ランドリーの名言に、「コーチとは、自分がなれると思っている人になれるように、(選手に)聞きたくないことを聞かせ、見たくないものを見せてくれる人だ」というものがあります。もちろん、選手が高い理想や目標を達成するために必要だからです。
かくしてコーチたるもの、教える相手の「自己認識力」、すなわち自身の強みと弱みをどれだけ認識しているかを把握しなくてはなりません。ビルが嘘つきを嫌ったのは、他人にだけでなくて自分にも不正直だからです。
私たちへの教訓として、仮に著名なコーチを雇うとしても、そのコーチングを実りあるものにするためには、何よりも残酷なまでに自分自身に正直にならなくてはなりません。それはスポーツであろうがビジネスであろうが同じです。