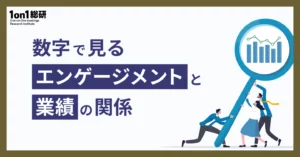人的資本経営が広がっています。
「人が中心」、「人が輝く」といったきらびやかな印象もある人的資本経営。しかしながら、よく見ると「人」的・「資本」・「経営」の三つの要素で構成されています。人を中心としながらも、資本という財務視点を伴う「経営」であると踏まえるべきでしょう。
したがって、エンゲージメントが向上して組織の雰囲気も良くなったものの、業績が低迷しているのなら人的資本経営の本質とはかけ離れています。求められているのは、企業の価値を高めるための人的資本経営なのです。
そこでコーポレート・ガバナンスや事業ポートフォリオ戦略などに詳しい東京都立大学の松田千恵子教授に、企業経営の本質に則った人的資本経営の何たるかを訊きました。
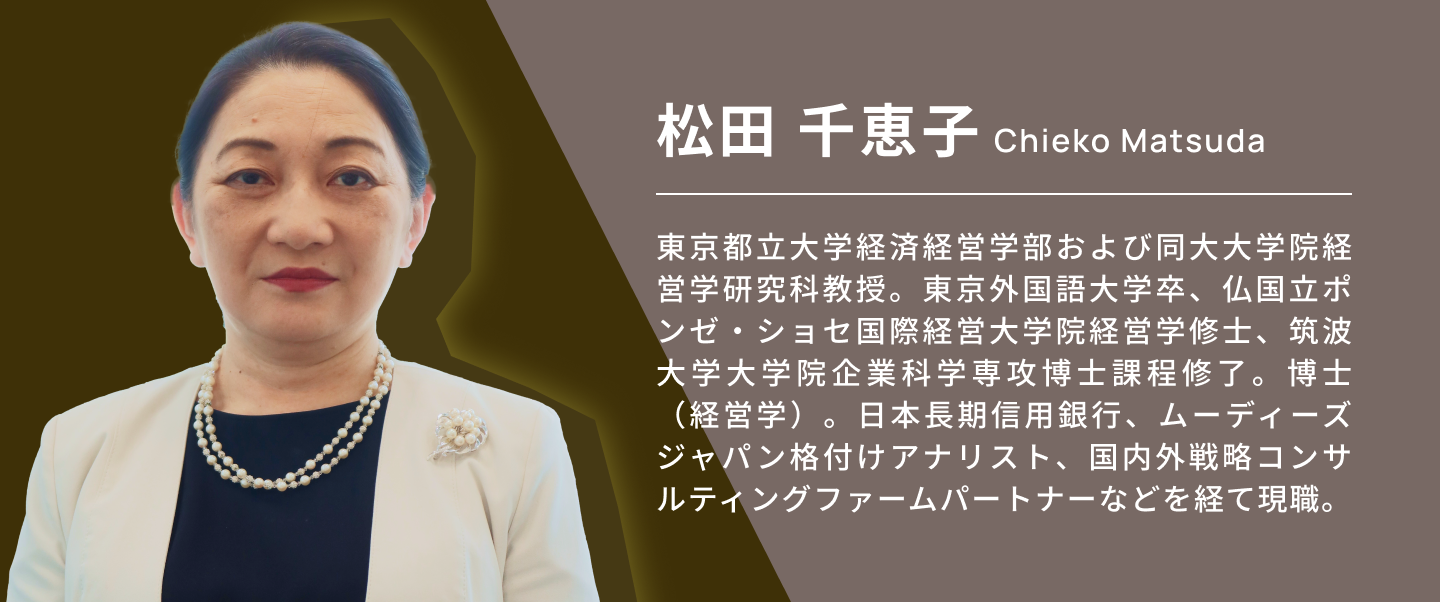
目次
社員は「会社のもの」ではない
──近年ブームとなっている人的資本経営について、企業経営を広く研究している松田教授から見て、気になる点はありますか。
人的資本経営について、日本にはある誤解が根強く残っています。それは人材を「会社のもの」、つまり会社の所有物だと思い込んでいることです。
かつての日本企業における財務の発想と似ています。「自己資本」というと、かつては多くの経営者が「会社のもの」、つまり「自分たちのお金」だと勘違いしていましたよね。
正しくは株主に帰属するお金であり、有効な投資先を見いだせないのなら、株主に返すべきものです。その会社で死蔵しているお金は株主に返し、成長産業の投資に向かわせる方が有効活用されているといえます。
──小説やドラマなどで社長や会長が「俺の会社に何をする!」というセリフが出てきます。創業者のみならず、サラリーマン社長ですら会社は自分のものと思ってきた節があります。
会社には株主というオーナーがいます。上場会社であれば一般的にはオーナーと経営者は別です。社長は株主から経営を託された存在であり、会社の所有者ではありません。こうした当たり前のことが理解されてないのが実情です。

また事業活動には先立ってお金と人が必要になります。お金は投資家や銀行から調達し、事業に先行投資をして、得られたリターンを株主や銀行に還元します。同様に、人材も労働市場を通じて外から調達し、事業に人を配属することで事業活動は成り立ちます。
企業は、調達したお金に対して株主が期待する資本コストを上回る投資リターンが求められるのと同様に、人がそこで働くことに価値を感じられるような仕事環境や機会を提供し、事業成長をさせていかなければなりません。
──となると、雇用を維持することが一概に「素晴らしい」とは限らず、停滞している事業に“塩漬け”にしていることは人材の無駄遣いということになるのですね。
昔のように「雇用を守らなければならないから、この事業は収益性が低いけどやめるわけにはいかない」という理由は通じなくなりました。成長投資がほとんどなされない「ノンコア(非中核)事業」は、働く人にとっても魅力的ではないですよね。
成長しない事業には資金だけでなく人も集まりませんので、人的資本の観点からしてもノンコア事業をいつまでも持ち続けるわけにはいきません。
別の観点から言うと、ビジネスで高い成長を遂げたら、その事業の資産価値が大きく高まります。同様に将来性の高い事業で働く方が成功や失敗の経験が多く得られ、その学びから成長していくので、人的資本の価値も高まります。逆に停滞していて投資もできない事業を放置していたら、人的資本を高めることは難しくなります。
管理職ではなく経営職だ
──人的資本に代表される無形資産が企業価値に直結すると言われて久しい中、松田教授は人的資本のどのような項目に注目していますか。
エンゲージメントや管理職の男女比率など以上に開示すべき重要項目は、「人的投資」だと私は考えています。それも人材育成として「具体的に何にどれだけのお金をかけているか」という情報です。
日本企業は総じて人的投資が少ないことで知られます。その少ない投資の中身も、年功序列の下で昔ながらにやってきた全員ジェネラリストを目指す「階層別研修」が大半を占めます。将来経営を担う人材を選抜して特訓することや、それ以外の分野で高いレベルのプロフェッショナルを目指せるよう鍛錬することにはこれまで消極的でした。
日本ではいわゆるマネジャーのことを「管理職」と呼んできました。私は「経営職」と呼ぶべきだと思っています。
組織のリーダーに求められるのは管理ではなく、経営です。経営とは、組織で発生する難しい意思決定、それもコンフリクトがある難題を解決し、組織を目指す方向に向かって率いるのが仕事です。そうした高度な意思決定能力や、統率に必要なコミュニケーションやリーダーシップの力を身に付けるためには訓練が必要です。

形式的な階層別研修だけでは経営職は育ちません。いわゆる修羅場体験も必要ですし、座学レベルの経営知識でさえなかなか身に付いていない場合が多いです。そうした育成の場を十分に備えたうえで、日頃のチームリーダーとしての仕事自体を、経営職として行うことも必要です。
プレイングマネジャーはよく使われる言葉です。しかし、この場合、どうしてもプレイヤーとしての仕事が先に立ち、マネジャーとしての意識やスキルは身に付きにくい。どんなに小さくてもチームリーダーであれば、「経営」を行う機能なのであるという位置づけが必要です。
国際比較すると、日本企業に圧倒的に欠けていることがリーダー人材を育てること。日本企業が人的資本経営を標榜するなら、一番力を入れるべきは経営職の育成です。
──日本企業の場合、花形部門で活躍した「プレイヤー」から先に管理職に昇進していきます。その際、経営や人材育成の素養が問われることはあまりありません。
日本企業の管理職への昇進は「ところてん方式」。これは、年功序列によって画一的なジェネラリスト人材が管理職へと押し出されていく慣行のこと。部長という型書きこそあれど、部長が何をする役職なのか具体的に決められていません。
本来であれば、課長であれ部長であれ「長」が付く役職については、組織のリーダーとして求められる役割と資質をきちんと定義すべきです。
加えて、こうした役職に就く前に、仕事の仕方や習性、気質などにおいてリーダーとしての素養がある人には、若いうちからリーダーとしての能力を伸ばす環境を提供することです。
もちろん経営に向かない、あるいはやりたくない人もいるでしょう。
そういう人には、その道のプロフェッショナルを目指せるキャリアが開かれていることも必要です。ここで言うプロフェッショナルとは、単なる作業のスペシャリストではありません。研究開発に没頭したいのであればノーベル賞を目指してほしい、というレベルのプロフェッショナルです。
日本の経営は「無免許運転」
──何事も無難であることをよしとするのが「管理職」だとすると、上級管理職である経営者も痛みを伴う構造改革には手を付けずに3、4年程度の在任期間を大過なくやり過ごそうとする傾向があると言われています。
これまでの日本企業は、本当の意味での経営をしなくてもよかった面がありました。
事業環境は今よりも安定していたし、メインバンクから安定して資金を調達できたので財務面の悩みは少なかった。しかも、資本コストを超えるリターンを求める株主もほぼ皆無でした。
人材供給量も圧倒的に多かったので、人材確保においても悩みも少なかった。そうなると、経営者は事業に専念できました。
──経営者であってもやることは「事業部長」の延長線上であった、と。
昔は外部環境も内部資源も安定していたので、それでも問題が起こらなかったかもしれません。しかし、今は環境がまったく違います。外部環境は不確定性を増し、内部資源も安定的な確保が難しくなってきました。こうした中で、経営者が判断を間違えたら会社は潰れかねません。
そんな中で経営者として育成されていない人が経営に携わるのは危険でさえあります。いわば「無免許運転」をしているようなものです。
しかも、日本企業では50歳を過ぎてからようやく経営者としての育成が始まるケースがあります。高齢になってからハンドルを初めて握ったようなものです。それではあまりに遅いです。
年齢に関係なく経営に向いた人材を選抜して訓練すべきです。また、若い時期に選抜されれば、その後ファストトラックからいったん降りることも当然出てきます。その時に再度挑戦できるような道筋を作っておくことも重要です。
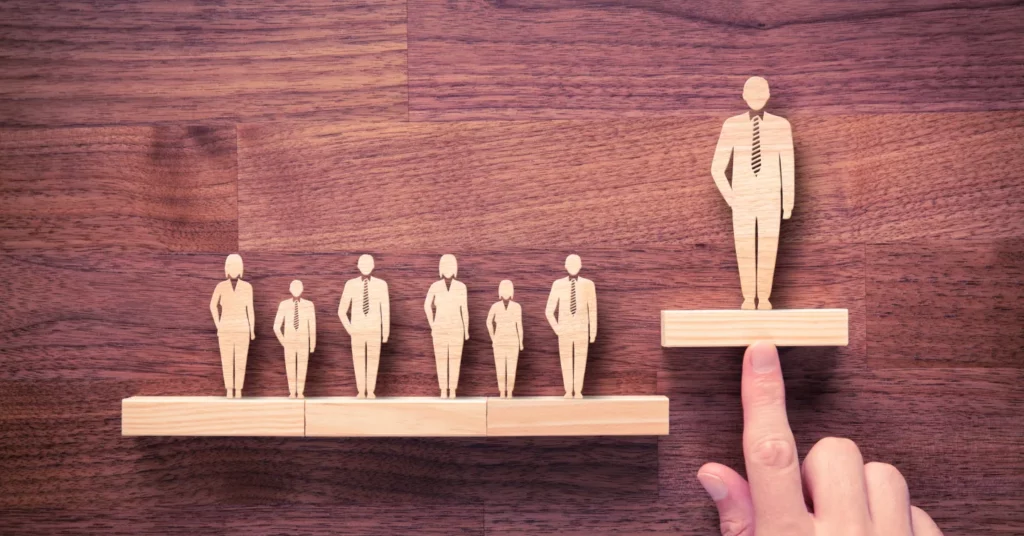
経営者育成のうってつけのポジションとして、子会社のトップというものがあります。さすがに今では少なくなってきたものの、従前の日本企業では経営の一線を退いた経営幹部が子会社トップに就くケースがよくありました。本来は、これから経営者になる人に子会社の経営を任せるべきです。親会社出身なのか、子会社出身なのかなどということは関係ありません。
CHROはCEOになれる人
──松田教授は日本CFO(最高財務責任者)協会や日本CHRO(最高人事責任者)協会にも長らく関わっています。最近はCHROに注目する企業が日本でも増えてきました。
今のCHROの状況は、四半世紀前に日本CFO協会が創立された頃の状況と既視感を覚えるくらい似ています。当時(1990年代後半~2000年代)、CFOという役職名が日本で使われるようになりました。
*CFOは1995年にソニーが日本で初めて導入
しかし、その当時はまだ中身が伴っていませんでした。多くの場合、CFOといってもせいぜい経理担当役員や経理部長の認識だったのではないでしょうか。そうした特定領域の担当者ではなく、経営者として十分にやっていける人材であることがCxOといわれる存在には求められます。今のCHROについてもまさに当てはまることです。
──最近ではソニーやNEC、ルネサスエレクトロニクスのようにCFOを経てCEOを務めるケースが増え、CFOは単に「金庫番」ではなく経営者と認識されつつあります。CHROもそのようになっていくのでしょうか。
CFOについても四半世紀かかっています。本当のCHROがいる会社は未だ一握りであることからして、日本企業に広く浸透するには時間を要するでしょう。
これまでの人事部というと「奥の院」として、独自の組織理論の下で動いており、一方で行っていることは労務、あるいは終身雇用や年功序列といった旧来の制度を前提とした採用や育成ばかりでした。これらの動きは企業全体の全社戦略や事業戦略とは繋がっていません。これまで話したように、労務などといった管理主体の仕事と、CHROが担うべき経営には乖離があります。
──NEC、レゾナックのように人事畑ではなく、子会社トップや経営企画部門などで経営の経験を積んだ人がCHROに就任するケースが増えています。
まさに人事畑のように「畑」といった言葉が旧来の日本企業を象徴しています。その範疇にとどまっている「●●畑」の発想では本来のCxOを務めることはできません。CxOは経営層として機能を横断して全社視点で意思決定することが求められるからです。
CHROとは単に人事領域の専門家ではなく、会社の経営が分かる人。人的資本経営を標榜するなら、全社の方向性や戦略を十分に理解したうえで、それを実現するのに必要な経営資源についてCFOやCEOと対等に議論できることが必要です。
言い換えるとCHROは「やろうと思えばCEOも務められる人」であるべきです。
あわせて読みたい
・人事バズワード30年史を紐解く、日本型雇用の向かう先
・【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り方
・【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か