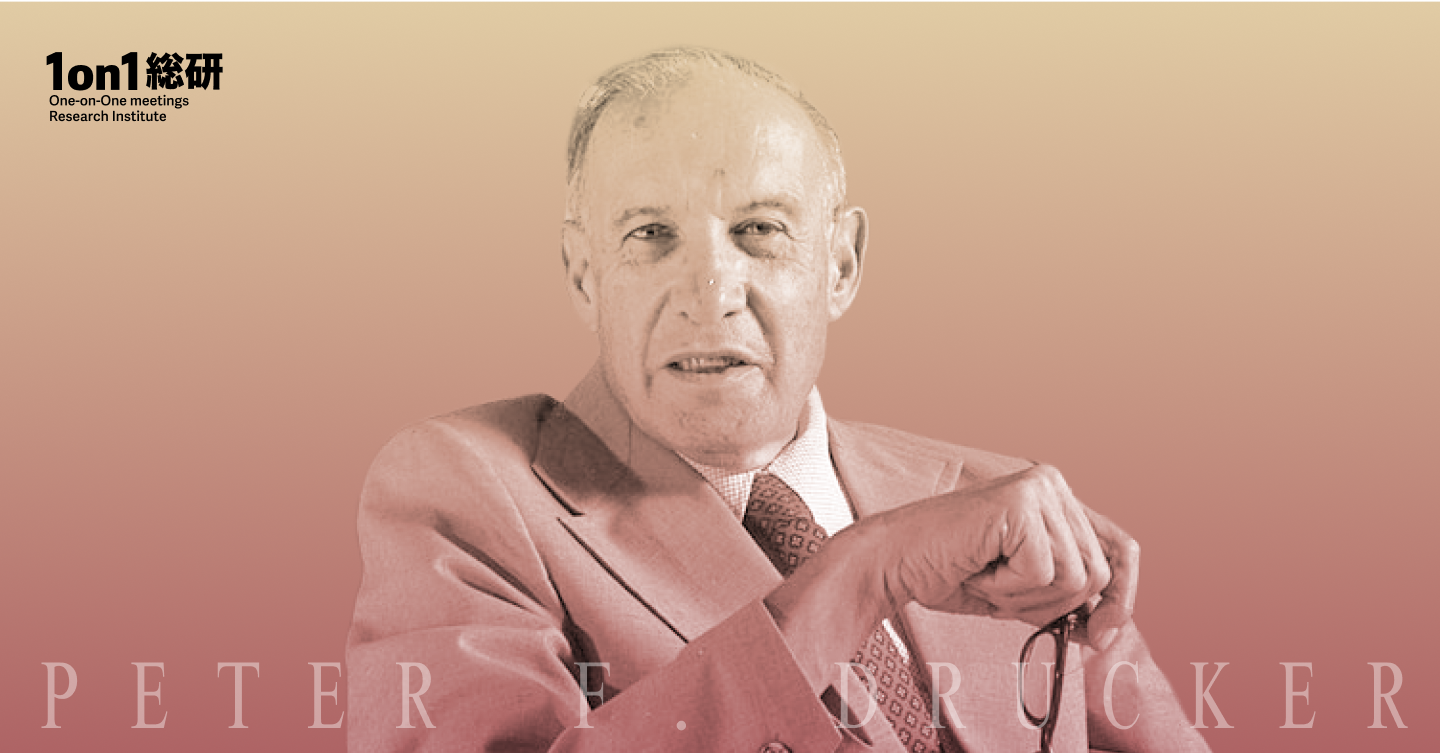アサーティブ・コミュニケーション完全解説|アサーションで職場のハラスメントを防ぎ、人間関係を変える方法
多様性が進み、リモートワークが当たり前となった今、コミュニケーションの“質”が仕事の成果や人間関係に直結しています。
強く言えばハラスメント、黙っていれば伝わらない──そんなジレンマを解決するカギが「アサーション」。
自分も、相手も大切にする伝え方として、今あらためて注目されているこのスキルを、基礎から実践まで解説します。
1. アサーションとは?
アサーション(Assertion)は一見「自己主張」と訳されがちですが、その真髄は単に自分の意見を押し付けることではありません。むしろ「自分も相手も尊重する」というコミュニケーションの姿勢を示す言葉であり、「アサーティブ・コミュニケーション(Assertive Communication)」とも呼ばれています。
私たちが人間関係を築くとき、つい「遠慮しすぎて本音を言えなくなる」「言いづらいことを強引に押し付けてしまう」など極端な態度を取りがちです。
しかし、アサーションでは「自分の感情や意見を大切にしながら、同時に相手の感情や意見にも配慮する」というスタンスを保ちます。そのため、会話の両当事者が対等に話し合いを進められる環境を生み出しやすいのが特徴です。
2. アサーションの歴史的背景
アサーションのルーツを探ると、1950年代から60年代にかけてアメリカで行われた行動療法や、公民権運動(Civil Rights Movement)に行き着きます。
当時のアメリカでは、人種差別や社会的な格差が顕在化しており、「自分たちの権利を正当に主張しよう」という機運が高まっていました。そこから派生して、「主張が苦手な人や社会的弱者が、自分の意見をきちんと伝える権利を取り戻す」という支援が行われるようになったのです。
とりわけ、女性やマイノリティといった立場の人たちが、自分の意思をしっかりと発信しながら、相手を不必要に攻撃せずに建設的な交渉を行うための技法が重視されました。これらの活動を通じて生まれたのが「アサーション・トレーニング」であり、心理学の研究者たちが「人間はどのようにすれば自己主張と他者尊重を両立できるのか」を理論化・実践化する流れを作っていったのです。
当初は「自分の立場が弱い人」に向けて「正しく声を上げる方法」を提供する色合いが強かったアサーションですが、やがては教育現場や企業研修、医療・福祉の現場など、あらゆるコミュニケーションの場面で使えるスキルとして広がっていきました。弱者支援から始まった理念が、現代の多様な組織や社会においても「相互尊重」のコミュニケーションを実現するうえで重要なアプローチとして注目されているのです。
3. ビジネスシーンでアサーションが注目される理由
①組織の多様化・グローバル化への対応
一つ目の理由として挙げられるのは、組織や人材の多様化です。現代のビジネスシーンは、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が集まり、国内外を問わずグローバルなコミュニケーションを行う場面が増えています。性別、年齢、国籍、文化、ライフスタイルなどの違いにより、仕事観やコミュニケーションのスタイルが大きく異なるケースも少なくありません。
例えば、海外支社の同僚や外国籍のメンバーと協働する際、「相手の文化を尊重しながら自分の要求をどう伝えるか」「英語で自分の考えを遠慮なく言うと、失礼にならないか」など、悩むシーンが増えました。
アサーションの考え方を身につけることで、相手の意図や背景を踏まえたうえで自分の意見を伝えられるようになり、誤解や対立を最小限に抑えることが期待されます。
②リモートワーク・ハイブリッドワーク下でのコミュニケーション不足
二つ目は、リモートワークやハイブリッドワークの普及です。
顔が見えにくいオンライン環境では、ちょっとした言葉選びやチャットメッセージの書き方一つで、相手に「冷たい」「突き放された」と感じさせてしまうリスクがあります。
例えば部下がプロジェクトの進捗報告をしている時、上司が「それは遅すぎる」と言ったら、自分が責められているように感じて落ち込んでしまうかもしれません。

もしアサーティブコミュニケーションの考えが浸透していれば、上司は「進行が少し遅れているようですが、何か困っていることはありませんか?」と相手を気遣う発言ができます。
部下の方も「実はここが苦手で……。手助けしてもらえませんか?」と素直に相談でき、モヤモヤをため込まずに済むはずです。
チャットツールでおなじみのSlack Technologies社も、公式サイトで「テレワークや時差勤務が増える中では、お互いの意見を尊重し合うアサーティブなコミュニケーションが大切です」と呼びかけ、その意義を伝えています。
参照先:https://slack.com/intl/ja-jp/blog/collaboration/what-is-assertive-communication
③成果重視の風潮とハラスメント防止の同時進行
三つ目として、成果重視の風潮とハラスメント防止の要請が同時に高まっていることも大きな要因です。
企業は厳しい競争環境の中で、生産性向上や新規事業の創出などを求められる一方、社内でのパワハラ・セクハラを防止し、従業員の心理的安全性を確保することが社会的責務になりつつあります。
経営者や人事担当者にとって、「結果を出してほしいけれど、過剰なプレッシャーでメンタル不調者や離職者を増やしてはいけない」というジレンマは深刻です。そこでアサーションのスキルを導入し、自他ともに尊重するコミュニケーションを実践すれば、必要な指導やフィードバックは適切に行いつつ、相手を追い詰めすぎないバランスを保ちやすくなります。
例えば、営業成績が伸び悩んでいる部下に対して、上司が「何やってるんだ、もっと頑張れよ!」と一方的に叱責するだけでは、部下は萎縮してモチベーションが下がってしまうかもしれません。逆に、言いたいことを言えずに放置すれば、部下は問題を自覚しないまま業績を下げ続けるリスクもあります。
アサーションの姿勢であれば、「あなたの現状を心配している」「こうした結果が出ると、どんなメリットがあるか」「困っている部分があるなら一緒に対策を考えたい」というように、お互いが納得できる形で課題を共有し、協力して解決策を探ることが可能になります。
④組織のエンゲージメント向上とイノベーション創出
さらに、「風通しの良い職場づくり」が重視される昨今では、エンゲージメント向上やイノベーション創出のためにもアサーションが効果を発揮すると言われています。
厳しい競争下では、既存のやり方に固執せず、新しいアイデアやスピード感のある意思決定が必要とされます。ところが、人間関係において心理的安全性が欠けていると、新しい提案や意見が出しにくくなり、組織全体の成長スピードを阻害してしまいます。
アサーションを土台にしたコミュニケーション文化が根付くことで、「怖がらずに意見を言える」「ネガティブな情報も早めに共有して対策を取れる」という土壌ができあがります。
企業によっては、新規事業立ち上げのブレスト会議や社内ハッカソンで「何を言っても否定されない」空気をつくるために、あえて「アサーションの原則」を共有してから議論をスタートさせるケースも増えているようです。
アサーションの4つの原則
アサーションの原則とは、自分と相手の権利を尊重しながら、率直で誠実に、自分の考えや気持ちを表現するための基本ルールや考え方のことを指します。代表的なものとしては、以下の4つが挙げられます。
✅ 自己と他者の尊重
アサーションにおいては、自分が我慢して相手を優先したり、逆に相手を無視して自己主張をするのではなく、双方が尊重されるコミュニケーションを目指すことが大切です。
✅ 率直で誠実な表現
遠回しや曖昧な言い方ではなく、自分が何を感じ、何を望んでいるのかを明確に伝えることも重要なポイントです。相手の言葉を素直に受け取り、相手にも率直に意見を伝えます。
✅ 責任の明確化
自分の感情や意見に責任を持つこと。「あなたが〜」ではなく「私は〜」を主語にして伝えることも大切です。(アイメッセージで伝える)
✅ 対等
相手の役割や役職や年齢、性別などに関係なく、すべての人の意見や感情を等しく尊重し、お互いに「言うべきことは言える」関係性を築きます。
アサーティブではないタイプとは?
アサーティブなコミュニケーションができないと、職場の人間関係や仕事の成果に悪影響が出る可能性があります。あなたや周囲の人が以下のような傾向を持っていないか、チェックしてみましょう。
🙅♀️ 攻撃的タイプ(アグレッシブ)
感情的で自分の意見を一方的に主張し、相手の感情や意見を無視しがちなタイプ。相手の反発を招きやすくなります。
🙅♀️ 受け身タイプ(ノンアサーティブ)
他人に嫌われないよう相手に合わせすぎて、本音を伝えられないタイプ。無理をして仕事を抱え込む傾向があります。
🙅♀️ 作為的タイプ
本音を直接言わず、態度や陰口など間接的に不満を表現するタイプ。一見穏やかですが、不満が蓄積し、やる気や仕事の質が低下しやすいところがあります。
4. 「アサーションを身につけるトレーニング方法」
アサーションは「知っている」だけでは身につきません。自分の感情を整理し、相手との関係を損なわずに伝えるためには、実践的なトレーニングが必要です。ここでは、現場で効果的とされている3つの手法をご紹介します。
① DESC法×ロールプレイ
アサーションの基本フレームワーク「DESC法(Describe/Express/Specify/Consequence)」は、研修や自己学習の現場で最も多く使われています。
たとえば、「会議中に話を遮られてしまった」というシーンを想定し、次のように発言を組み立てます。

・D(Describe/事実)
👩🦰 「私が意見を言い始めたときに、声をかぶせて話し始めましたよね」
・E(Express/感情)
👩🦰 「そのとき、最後まで意見を伝えられなくて悲しかったです」
・S(Specify/要望)
👩🦰 「もし途中で意見を追加したい場合は、一度声をかけてもらってから話してもらえるとうれしいです」
・C(Consequence/結果)
👩🦰 「そうしてもらえると、お互いの考えが十分に共有できるので、より良いアイデアが生まれると思います」
このような例を使いながら、研修では参加者同士が役割を交代しながらロールプレイを行います。実際に言葉にしてみることが、アサーションの理解と定着をぐっと深めます。
②ワークシート活用
アサーションのワークシートは、頭の中でぼんやりしている“もやもや”を、紙に書き出して整理するためのツールです。
たとえば、「あの人の態度が引っかかるけど、何が嫌なのかうまく言えない……」というとき。このシートに沿って書くだけで、意外なほどスムーズに気持ちと言葉がつながり、自分でも気づいていなかった本音が見えてくることがあります。
基本の記入項目(DESC法に対応)
<項目 書き方のヒント>
【D】状況の事実:客観的に、事実のみを書く(例:「昨日の会議で……」)
【E】自分の気持ち:感情を単語でなく、文章で表す(例:「〜と感じて悲しかった」)
【S】してほしいこと:相手にどうしてほしいか、具体的に書く
【C】そうなるとどうなるか:その行動によってどう良くなるか、ポジティブな結果を書く
企業のアサーショントレーニングでは、このワークシートを使って「言葉にする練習」を行います。ワークシートは、ロールプレイの前に発言を組み立てるための準備として。ロールプレイの後は、フィードバックを受けて、感情や表現を整理することに活用できます。
こうしたプロセスを通じて、理論だけでは身につかない“アサーティブな言葉選び”が、少しずつ自分の中に染み込んでいくのです。
5. 1on1におけるアサーション活用
人事施策として導入する企業が増えている1on1ミーティングでも、アサーションの概念は非常に有効です。
1on1は上司と部下が対等に話し合い、業務の進捗や悩み、キャリア目標を共有するとされていますが、上司が一方的に指示・命令をする場になってしまうと、部下が本音を言えずに本音の対話のチャンスを失うおそれがあります。
アサーションのポイントを踏まえた上司は、まず「私はあなたの成長を心から応援しているし、あなたの意見を大事に思っている」という気持ちを言葉にして伝えます。
これによって部下は、自分の意見が尊重されると安心して話しやすくなり、率直に「実は新しいプロジェクトの進め方がよく分からず困っています」「顧客対応で行き詰まっている点があるんです」といった困り事を共有してくれるようになるのです。
部下の考えや想いをスムーズに引き出すためにも、「あなたはどう感じている?」「あなたの思う理想の働き方は?」といったオープンな質問を投げかけながら、「私はこう感じた」「私はこう受け取った」といったアイメッセージを交えて伝えることで、相手の防衛心を和らげ、対話がより深まります。
6. アサーション導入で得られるメリット
アサーションを導入した組織では、ハラスメントの減少や心理的安全性の向上など、さまざまなポジティブな効果が確認されています。
なぜハラスメント防止に効果的かというと、アサーションは自分の感情や要望を明確に伝えるスキルを高めるので、不快な言動に対して早めに問題を伝えることができるからです。また、社員が日頃から率直にコミュニケーションをとるようになると、不適切な言動そのものが発生しにくくなります。
アサーションが文化として根付くことで、ミスや課題を早めに共有し合う風土が生まれ、トラブルを未然に防いだり、より良い改善策を短いサイクルで打ち出せる可能性も高まるとされています。
例えば、ANAグループでは2008年より、飛行乗務員向けの訓練にアサーション・プログラムを取り入れています。これは、「運航中に疑問や違和感を抱いたときに、上下関係にとらわれず率直に声を上げ合うことが人為的ミスを防ぐうえで欠かせない」という考え方に基づくものです。
「階級に関係なく疑問を伝え合う」姿勢が、今では整備士・客室乗務員を含む全職種に広がり、安全・品質・人間関係のすべてを支える基盤として定着しています。
参考:https://www.ana.co.jp/group/recruit/ana-recruit/interview/talk89.html
7. アサーションを学ぶには?
アサーションを本格的に導入したい企業向けには、以下のような外部研修サービスを活用するのもおすすめです。
①ANAビジネスソリューション株式会社
コミュニケーション課題を抱える企業・団体向けのアサーション研修です(基本6時間、カスタマイズ可能)。自己表現のタイプを理解し、カードゲーム等の体験型学習を通してアサーティブなコミュニケーションスキル(DESC法など)を習得します。
参照:https://www.abc.jp/service/anakenshu/communication/assertion
②日本・精神技術研究所(NSGK)
1947年設立の専門機関で、人間関係改善に特化した研修実績を豊富に持つ老舗。アサーションの研修では、ロールプレイや自己開示を通じて「伝える・聴く・関わりあう」力を高め、職場のストレス軽減やハラスメント予防にも貢献。教育・福祉・医療現場への導入も多く、内容のカスタマイズも可能。
参照:https://www.nsgk.co.jp/houjin/customize
③株式会社ビジネスコンサルタント(BCon)
人材育成と組織開発を専門とするBConは、アサーションを軸にした職場の対話促進プログラムを多数提供。DESC法やアイメッセージをベースに、「言いづらいことを建設的に伝える技術」を実践的に指導。管理職研修や女性活躍支援にも対応し、人間関係と成果の両立を支える研修として高く評価されています。
参照:https://www.bcon.jp/service/human_resource_development/assertion/
おすすめの書籍
アサーションは、実践してこそ身につくスキルですが、研修とあわせて書籍や教材で体系的に学ぶことで、より深い理解と応用力が育まれます。ここでは、アサーションの基本を押さえたい方から、職場で実践したい方におすすめの良書・教材をご紹介します。
① 『アサーション・トレーニング』(平木典子/金子書房)
アサーション・トレーニングの第一人者・平木典子先生によるロングセラー。「言えない」「言いすぎる」人のための中庸な表現方法を、豊富な事例とともに解説。理論と実践のバランスがよく、研修の補助教材としても使われています。
https://amzn.asia/d/35jPh67
②『マンガでやさしくわかるアサーション』(平木典子・ 星井博文・サノマリナ/日本能率協会マネジメントセンター)
アサーションを気軽に学ぶなら、①と同じ作者による『マンガでやさしくわかるアサーション 』もおすすめです。著者によるわかりやすい解説とストーリーマンガのサンドイッチ形式でアサーションの基礎を楽しく学べます。
https://amzn.asia/d/6fQG7n6
③『アサーティブ・コミュニケーション』(戸田久実/日経文庫)
アサーションの基本から、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)への気づき方、在宅勤務やメール主体の職場で起こりがちな“攻撃的”または“萎縮的”な伝え方への対処まで、現代のビジネスシーンに即した具体例で解説。職場のリアルな事例が多く、コンパクトに実践ポイントがまとまっており、入門書としても再学習用としてもおすすめです。
https://amzn.asia/d/2EEnuEg
アサーションを実務に根付かせるためのポイント
アサーションを実際のビジネス現場に根付かせるには、「段階的な研修の実施」と「導入後のフォロー体制」が欠かせません。まずは管理職を対象に研修を行い、彼らがアサーティブなコミュニケーションを実践してみせることで、部下たちも安心して自分の意見を言える空気ができあがります。
そのうえで、社内勉強会やロールプレイ、ワークシートなどを取り入れて、若手からベテランまで幅広く実践の機会を設けると定着率が高まります。
導入初期には「わざわざこんな手間をかける必要があるのか」という声が上がるかもしれません。
しかし、実際にアサーションを行うことで、「衝突してもおかしくない場面をスムーズに乗り切れた」「お互い嫌な思いをせずに仕事の質を高められた」という体験を重ねると、その意義が自然と社内に浸透していきます。
まとめ
多様化・リモート化・成果主義の進行により、職場のコミュニケーションは今、かつてないほど複雑さを増しています。
「どう言えばいいかわからない」「本音を言えずに我慢してしまう」「言ったことで関係がこじれるのが怖い」──。そんな葛藤を抱える人が増える中、アサーションは、自己主張と他者尊重のバランスを取るための確かなヒントを与えてくれるはずです。
1. アサーションとは?
アサーション(Assertion)は一見「自己主張」と訳されがちですが、その真髄は単に自分の意見を押し付けることではありません。むしろ「自分も相手も尊重する」というコミュニケーションの姿勢を示す言葉であり、「アサーティブ・コミュニケーション(Assertive Communication)」とも呼ばれています。
私たちが人間関係を築くとき、つい「遠慮しすぎて本音を言えなくなる」「言いづらいことを強引に押し付けてしまう」など極端な態度を取りがちです。
しかし、アサーションでは「自分の感情や意見を大切にしながら、同時に相手の感情や意見にも配慮する」というスタンスを保ちます。そのため、会話の両当事者が対等に話し合いを進められる環境を生み出しやすいのが特徴です。
2. アサーションの歴史的背景
アサーションのルーツを探ると、1950年代から60年代にかけてアメリカで行われた行動療法や、公民権運動(Civil Rights Movement)に行き着きます。
当時のアメリカでは、人種差別や社会的な格差が顕在化しており、「自分たちの権利を正当に主張しよう」という機運が高まっていました。そこから派生して、「主張が苦手な人や社会的弱者が、自分の意見をきちんと伝える権利を取り戻す」という支援が行われるようになったのです。
とりわけ、女性やマイノリティといった立場の人たちが、自分の意思をしっかりと発信しながら、相手を不必要に攻撃せずに建設的な交渉を行うための技法が重視されました。これらの活動を通じて生まれたのが「アサーション・トレーニング」であり、心理学の研究者たちが「人間はどのようにすれば自己主張と他者尊重を両立できるのか」を理論化・実践化する流れを作っていったのです。
当初は「自分の立場が弱い人」に向けて「正しく声を上げる方法」を提供する色合いが強かったアサーションですが、やがては教育現場や企業研修、医療・福祉の現場など、あらゆるコミュニケーションの場面で使えるスキルとして広がっていきました。弱者支援から始まった理念が、現代の多様な組織や社会においても「相互尊重」のコミュニケーションを実現するうえで重要なアプローチとして注目されているのです。
3. ビジネスシーンでアサーションが注目される理由
①組織の多様化・グローバル化への対応
一つ目の理由として挙げられるのは、組織や人材の多様化です。現代のビジネスシーンは、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が集まり、国内外を問わずグローバルなコミュニケーションを行う場面が増えています。性別、年齢、国籍、文化、ライフスタイルなどの違いにより、仕事観やコミュニケーションのスタイルが大きく異なるケースも少なくありません。
例えば、海外支社の同僚や外国籍のメンバーと協働する際、「相手の文化を尊重しながら自分の要求をどう伝えるか」「英語で自分の考えを遠慮なく言うと、失礼にならないか」など、悩むシーンが増えました。
アサーションの考え方を身につけることで、相手の意図や背景を踏まえたうえで自分の意見を伝えられるようになり、誤解や対立を最小限に抑えることが期待されます。
②リモートワーク・ハイブリッドワーク下でのコミュニケーション不足
二つ目は、リモートワークやハイブリッドワークの普及です。
顔が見えにくいオンライン環境では、ちょっとした言葉選びやチャットメッセージの書き方一つで、相手に「冷たい」「突き放された」と感じさせてしまうリスクがあります。
例えば部下がプロジェクトの進捗報告をしている時、上司が「それは遅すぎる」と言ったら、自分が責められているように感じて落ち込んでしまうかもしれません。

もしアサーティブコミュニケーションの考えが浸透していれば、上司は「進行が少し遅れているようですが、何か困っていることはありませんか?」と相手を気遣う発言ができます。
部下の方も「実はここが苦手で……。手助けしてもらえませんか?」と素直に相談でき、モヤモヤをため込まずに済むはずです。
チャットツールでおなじみのSlack Technologies社も、公式サイトで「テレワークや時差勤務が増える中では、お互いの意見を尊重し合うアサーティブなコミュニケーションが大切です」と呼びかけ、その意義を伝えています。
参照先:https://slack.com/intl/ja-jp/blog/collaboration/what-is-assertive-communication
③成果重視の風潮とハラスメント防止の同時進行
三つ目として、成果重視の風潮とハラスメント防止の要請が同時に高まっていることも大きな要因です。
企業は厳しい競争環境の中で、生産性向上や新規事業の創出などを求められる一方、社内でのパワハラ・セクハラを防止し、従業員の心理的安全性を確保することが社会的責務になりつつあります。
経営者や人事担当者にとって、「結果を出してほしいけれど、過剰なプレッシャーでメンタル不調者や離職者を増やしてはいけない」というジレンマは深刻です。そこでアサーションのスキルを導入し、自他ともに尊重するコミュニケーションを実践すれば、必要な指導やフィードバックは適切に行いつつ、相手を追い詰めすぎないバランスを保ちやすくなります。
例えば、営業成績が伸び悩んでいる部下に対して、上司が「何やってるんだ、もっと頑張れよ!」と一方的に叱責するだけでは、部下は萎縮してモチベーションが下がってしまうかもしれません。逆に、言いたいことを言えずに放置すれば、部下は問題を自覚しないまま業績を下げ続けるリスクもあります。
アサーションの姿勢であれば、「あなたの現状を心配している」「こうした結果が出ると、どんなメリットがあるか」「困っている部分があるなら一緒に対策を考えたい」というように、お互いが納得できる形で課題を共有し、協力して解決策を探ることが可能になります。
④組織のエンゲージメント向上とイノベーション創出
さらに、「風通しの良い職場づくり」が重視される昨今では、エンゲージメント向上やイノベーション創出のためにもアサーションが効果を発揮すると言われています。
厳しい競争下では、既存のやり方に固執せず、新しいアイデアやスピード感のある意思決定が必要とされます。ところが、人間関係において心理的安全性が欠けていると、新しい提案や意見が出しにくくなり、組織全体の成長スピードを阻害してしまいます。
アサーションを土台にしたコミュニケーション文化が根付くことで、「怖がらずに意見を言える」「ネガティブな情報も早めに共有して対策を取れる」という土壌ができあがります。
企業によっては、新規事業立ち上げのブレスト会議や社内ハッカソンで「何を言っても否定されない」空気をつくるために、あえて「アサーションの原則」を共有してから議論をスタートさせるケースも増えているようです。
アサーションの4つの原則
アサーションの原則とは、自分と相手の権利を尊重しながら、率直で誠実に、自分の考えや気持ちを表現するための基本ルールや考え方のことを指します。代表的なものとしては、以下の4つが挙げられます。
✅ 自己と他者の尊重
アサーションにおいては、自分が我慢して相手を優先したり、逆に相手を無視して自己主張をするのではなく、双方が尊重されるコミュニケーションを目指すことが大切です。
✅ 率直で誠実な表現
遠回しや曖昧な言い方ではなく、自分が何を感じ、何を望んでいるのかを明確に伝えることも重要なポイントです。相手の言葉を素直に受け取り、相手にも率直に意見を伝えます。
✅ 責任の明確化
自分の感情や意見に責任を持つこと。「あなたが〜」ではなく「私は〜」を主語にして伝えることも大切です。(アイメッセージで伝える)
✅ 対等
相手の役割や役職や年齢、性別などに関係なく、すべての人の意見や感情を等しく尊重し、お互いに「言うべきことは言える」関係性を築きます。
アサーティブではないタイプとは?
アサーティブなコミュニケーションができないと、職場の人間関係や仕事の成果に悪影響が出る可能性があります。あなたや周囲の人が以下のような傾向を持っていないか、チェックしてみましょう。
🙅♀️ 攻撃的タイプ(アグレッシブ)
感情的で自分の意見を一方的に主張し、相手の感情や意見を無視しがちなタイプ。相手の反発を招きやすくなります。
🙅♀️ 受け身タイプ(ノンアサーティブ)
他人に嫌われないよう相手に合わせすぎて、本音を伝えられないタイプ。無理をして仕事を抱え込む傾向があります。
🙅♀️ 作為的タイプ
本音を直接言わず、態度や陰口など間接的に不満を表現するタイプ。一見穏やかですが、不満が蓄積し、やる気や仕事の質が低下しやすいところがあります。
4. 「アサーションを身につけるトレーニング方法」
アサーションは「知っている」だけでは身につきません。自分の感情を整理し、相手との関係を損なわずに伝えるためには、実践的なトレーニングが必要です。ここでは、現場で効果的とされている3つの手法をご紹介します。
① DESC法×ロールプレイ
アサーションの基本フレームワーク「DESC法(Describe/Express/Specify/Consequence)」は、研修や自己学習の現場で最も多く使われています。
たとえば、「会議中に話を遮られてしまった」というシーンを想定し、次のように発言を組み立てます。

・D(Describe/事実)
👩🦰 「私が意見を言い始めたときに、声をかぶせて話し始めましたよね」
・E(Express/感情)
👩🦰 「そのとき、最後まで意見を伝えられなくて悲しかったです」
・S(Specify/要望)
👩🦰 「もし途中で意見を追加したい場合は、一度声をかけてもらってから話してもらえるとうれしいです」
・C(Consequence/結果)
👩🦰 「そうしてもらえると、お互いの考えが十分に共有できるので、より良いアイデアが生まれると思います」
このような例を使いながら、研修では参加者同士が役割を交代しながらロールプレイを行います。実際に言葉にしてみることが、アサーションの理解と定着をぐっと深めます。
②ワークシート活用
アサーションのワークシートは、頭の中でぼんやりしている“もやもや”を、紙に書き出して整理するためのツールです。
たとえば、「あの人の態度が引っかかるけど、何が嫌なのかうまく言えない……」というとき。このシートに沿って書くだけで、意外なほどスムーズに気持ちと言葉がつながり、自分でも気づいていなかった本音が見えてくることがあります。
基本の記入項目(DESC法に対応)
<項目 書き方のヒント>
【D】状況の事実:客観的に、事実のみを書く(例:「昨日の会議で……」)
【E】自分の気持ち:感情を単語でなく、文章で表す(例:「〜と感じて悲しかった」)
【S】してほしいこと:相手にどうしてほしいか、具体的に書く
【C】そうなるとどうなるか:その行動によってどう良くなるか、ポジティブな結果を書く
企業のアサーショントレーニングでは、このワークシートを使って「言葉にする練習」を行います。ワークシートは、ロールプレイの前に発言を組み立てるための準備として。ロールプレイの後は、フィードバックを受けて、感情や表現を整理することに活用できます。
こうしたプロセスを通じて、理論だけでは身につかない“アサーティブな言葉選び”が、少しずつ自分の中に染み込んでいくのです。
5. 1on1におけるアサーション活用
人事施策として導入する企業が増えている1on1ミーティングでも、アサーションの概念は非常に有効です。
1on1は上司と部下が対等に話し合い、業務の進捗や悩み、キャリア目標を共有するとされていますが、上司が一方的に指示・命令をする場になってしまうと、部下が本音を言えずに本音の対話のチャンスを失うおそれがあります。
アサーションのポイントを踏まえた上司は、まず「私はあなたの成長を心から応援しているし、あなたの意見を大事に思っている」という気持ちを言葉にして伝えます。
これによって部下は、自分の意見が尊重されると安心して話しやすくなり、率直に「実は新しいプロジェクトの進め方がよく分からず困っています」「顧客対応で行き詰まっている点があるんです」といった困り事を共有してくれるようになるのです。
部下の考えや想いをスムーズに引き出すためにも、「あなたはどう感じている?」「あなたの思う理想の働き方は?」といったオープンな質問を投げかけながら、「私はこう感じた」「私はこう受け取った」といったアイメッセージを交えて伝えることで、相手の防衛心を和らげ、対話がより深まります。
6. アサーション導入で得られるメリット
アサーションを導入した組織では、ハラスメントの減少や心理的安全性の向上など、さまざまなポジティブな効果が確認されています。
なぜハラスメント防止に効果的かというと、アサーションは自分の感情や要望を明確に伝えるスキルを高めるので、不快な言動に対して早めに問題を伝えることができるからです。また、社員が日頃から率直にコミュニケーションをとるようになると、不適切な言動そのものが発生しにくくなります。
アサーションが文化として根付くことで、ミスや課題を早めに共有し合う風土が生まれ、トラブルを未然に防いだり、より良い改善策を短いサイクルで打ち出せる可能性も高まるとされています。
例えば、ANAグループでは2008年より、飛行乗務員向けの訓練にアサーション・プログラムを取り入れています。これは、「運航中に疑問や違和感を抱いたときに、上下関係にとらわれず率直に声を上げ合うことが人為的ミスを防ぐうえで欠かせない」という考え方に基づくものです。
「階級に関係なく疑問を伝え合う」姿勢が、今では整備士・客室乗務員を含む全職種に広がり、安全・品質・人間関係のすべてを支える基盤として定着しています。
参考:https://www.ana.co.jp/group/recruit/ana-recruit/interview/talk89.html
7. アサーションを学ぶには?
アサーションを本格的に導入したい企業向けには、以下のような外部研修サービスを活用するのもおすすめです。
①ANAビジネスソリューション株式会社
コミュニケーション課題を抱える企業・団体向けのアサーション研修です(基本6時間、カスタマイズ可能)。自己表現のタイプを理解し、カードゲーム等の体験型学習を通してアサーティブなコミュニケーションスキル(DESC法など)を習得します。
参照:https://www.abc.jp/service/anakenshu/communication/assertion
②日本・精神技術研究所(NSGK)
1947年設立の専門機関で、人間関係改善に特化した研修実績を豊富に持つ老舗。アサーションの研修では、ロールプレイや自己開示を通じて「伝える・聴く・関わりあう」力を高め、職場のストレス軽減やハラスメント予防にも貢献。教育・福祉・医療現場への導入も多く、内容のカスタマイズも可能。
参照:https://www.nsgk.co.jp/houjin/customize
③株式会社ビジネスコンサルタント(BCon)
人材育成と組織開発を専門とするBConは、アサーションを軸にした職場の対話促進プログラムを多数提供。DESC法やアイメッセージをベースに、「言いづらいことを建設的に伝える技術」を実践的に指導。管理職研修や女性活躍支援にも対応し、人間関係と成果の両立を支える研修として高く評価されています。
参照:https://www.bcon.jp/service/human_resource_development/assertion/
おすすめの書籍
アサーションは、実践してこそ身につくスキルですが、研修とあわせて書籍や教材で体系的に学ぶことで、より深い理解と応用力が育まれます。ここでは、アサーションの基本を押さえたい方から、職場で実践したい方におすすめの良書・教材をご紹介します。
① 『アサーション・トレーニング』(平木典子/金子書房)
アサーション・トレーニングの第一人者・平木典子先生によるロングセラー。「言えない」「言いすぎる」人のための中庸な表現方法を、豊富な事例とともに解説。理論と実践のバランスがよく、研修の補助教材としても使われています。
https://amzn.asia/d/35jPh67
②『マンガでやさしくわかるアサーション』(平木典子・ 星井博文・サノマリナ/日本能率協会マネジメントセンター)
アサーションを気軽に学ぶなら、①と同じ作者による『マンガでやさしくわかるアサーション 』もおすすめです。著者によるわかりやすい解説とストーリーマンガのサンドイッチ形式でアサーションの基礎を楽しく学べます。
https://amzn.asia/d/6fQG7n6
③『アサーティブ・コミュニケーション』(戸田久実/日経文庫)
アサーションの基本から、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)への気づき方、在宅勤務やメール主体の職場で起こりがちな“攻撃的”または“萎縮的”な伝え方への対処まで、現代のビジネスシーンに即した具体例で解説。職場のリアルな事例が多く、コンパクトに実践ポイントがまとまっており、入門書としても再学習用としてもおすすめです。
https://amzn.asia/d/2EEnuEg
アサーションを実務に根付かせるためのポイント
アサーションを実際のビジネス現場に根付かせるには、「段階的な研修の実施」と「導入後のフォロー体制」が欠かせません。まずは管理職を対象に研修を行い、彼らがアサーティブなコミュニケーションを実践してみせることで、部下たちも安心して自分の意見を言える空気ができあがります。
そのうえで、社内勉強会やロールプレイ、ワークシートなどを取り入れて、若手からベテランまで幅広く実践の機会を設けると定着率が高まります。
導入初期には「わざわざこんな手間をかける必要があるのか」という声が上がるかもしれません。
しかし、実際にアサーションを行うことで、「衝突してもおかしくない場面をスムーズに乗り切れた」「お互い嫌な思いをせずに仕事の質を高められた」という体験を重ねると、その意義が自然と社内に浸透していきます。
まとめ
多様化・リモート化・成果主義の進行により、職場のコミュニケーションは今、かつてないほど複雑さを増しています。
「どう言えばいいかわからない」「本音を言えずに我慢してしまう」「言ったことで関係がこじれるのが怖い」──。そんな葛藤を抱える人が増える中、アサーションは、自己主張と他者尊重のバランスを取るための確かなヒントを与えてくれるはずです。




.webp)