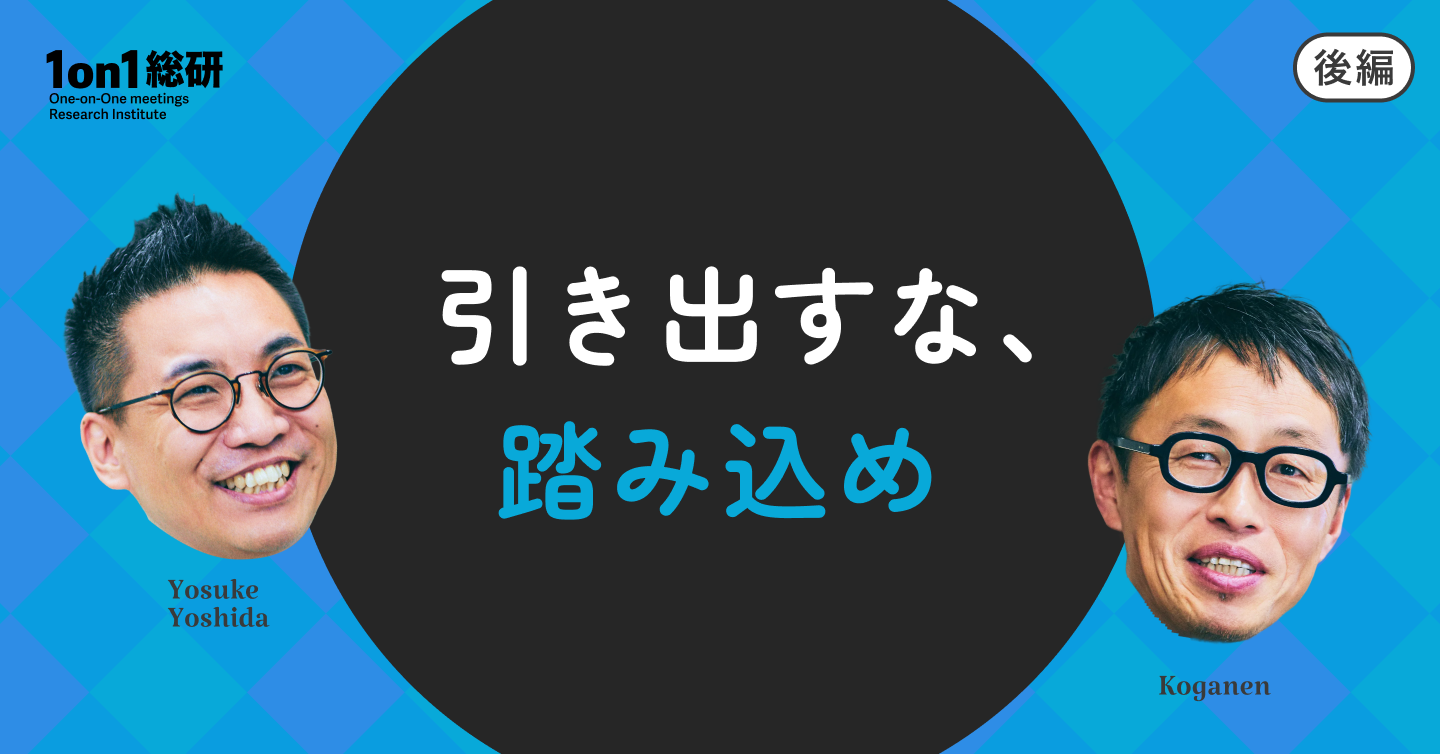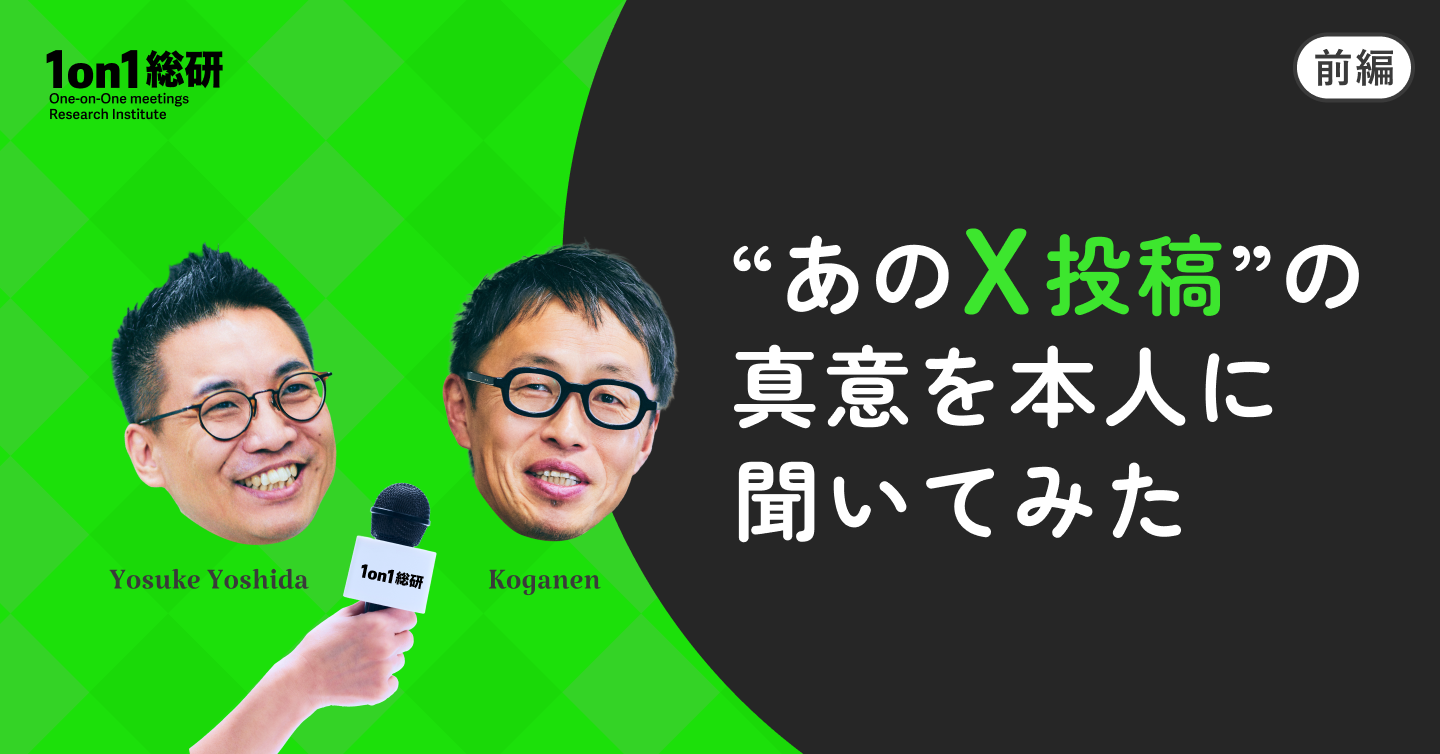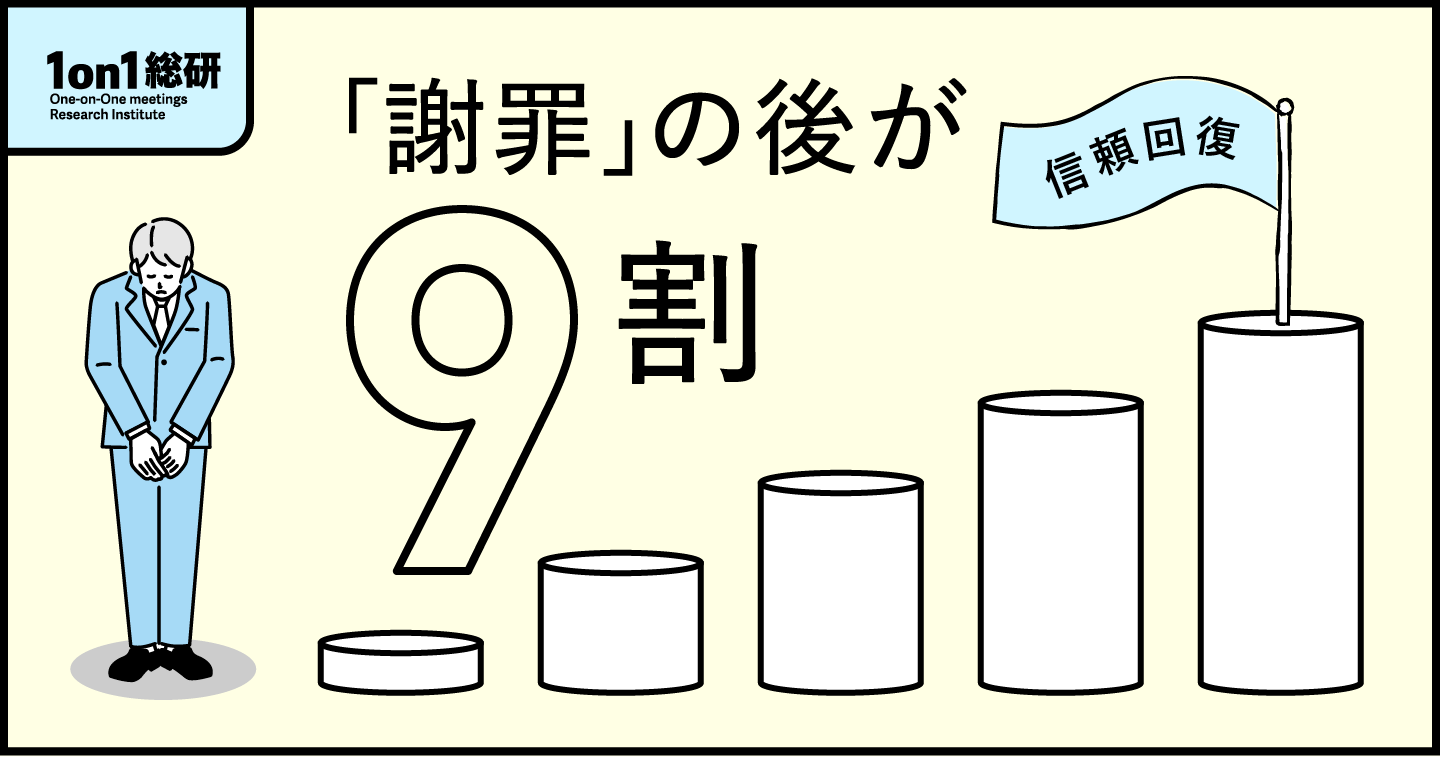なぜ1on1で悩み相談ができるようになったのか? エンジニアの心境を変えた上司の対応
「部下は私との1on1に価値を感じているだろうか」——多くのマネジャーはこんな疑問を抱えているだろう。そしてその答えはメンバーの声に隠されている。
自動車部品サプライヤー「アイシン」のグループ会社「アイシン・デジタルエンジニアリング」。エンジニアとして働く同社メンバーの森宏樹氏は、かつて1on1に懐疑的だったが、今では「部下のためのアルコールなしの飲み会」と表現するほどその価値を実感している。
ある上司の姿勢が森氏の心境を大きく変えた。業務報告で終わっていた30分が、なぜ本音を話せる場へと変わっていったのか。その過程からは多くのマネジャーが心得るべき重要な洞察が見えてくる。
「話すことが見当つかない」からのスタート
──御社では2021年から1on1を始めています。導入当初の印象は?
森 「何をやるんだろう」というのが率直な感想でした。上司から言われるがまま時間を設定したものの、会話に困り、中身がないまま30分を過ごしたこともあります。
キャリアについて聞かれても壮大すぎて答えられず、上司が定期的に変わる環境では深い関係性を築く必要性もあまり感じられませんでした。結果、業務進捗や打ち合わせの延長として時間を使うことが多かったように思います。

──そこから1on1の捉え方は変わったのでしょうか?
森 変わりました。きっかけはコロナ禍のテレワークです。自宅で週4、5日作業をしているうちにモチベーションが徐々に下がり、仕事に前向きになれなくなりました。そこで、出社して同僚や上司と話す機会を増やそうと思いました。雑談や何気ない会話が知らず知らずのうちに心の支えになっていたことに気付かされたからです。
──1on1ではどのような話をすることが多いですか?
森 新任上司との1on1では、いきなり深い話はできないので、雑談や軽めの話題から始めています。うまくコミュニケーションが取れるようになった上司とは、回を重ねるごとに、自分のキャリアや専門性、仕事のやりがいといった本質的な対話へと変化していきます。
──現在の上長との1on1でも、そのような変化がありましたか?
森 はい。現在の上司は2024年1月からお世話になっていて、これまで1on1を10回以上重ねています。最初の3、4回は趣味や育児の話題ばかり。はっきり言って純粋な雑談です(笑)。
こうした何気ない対話を積み重ねるうちに、徐々に仕事の話を持ち出せるようになっていきました。転機となったのは5回目くらいの1on1です。「解析技術の開発を一人でやることが多くて、業務が属人化している。正直、モチベーションが下がっています」と打ち明けました。
中堅社員である私は、多くの業務を一人で自走することが求められているため、サポートを求めることには少なからずためらいがありました。
それでも思い切って相談し、そこから業務のあるべき姿について1on1や日常業務のなかで上司と議論を重ねた結果、日々アドバイスをもらえる先輩社員をつけてもらえることになりました。
会社のリソースが限られている中、私一人のために先輩をつけてもらえるなんて本当にありがたかったです。

──その経験は仕事との向き合い方や心境に変化をもたらしましたか?
森 大きな変化がありましたね。以前は「どうせ上司はまだ変わるんだし」と思って、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)は最低限にしておこうと考えていました。
しかし、1on1を通じて「上司に困りごとや課題を共有すると、解決に動いてくれる」と実感してからは、些細なことでも相談するようになりました。しょうもないことばかり話すようになったかもしれませんが(笑)、上司とのコミュニケーションが増えたことは間違いありません。
──踏み込んだ相談ができるかどうかは、上司との信頼関係次第と言えそうです。現在の上司に対して「この人なら悩みを相談できる」と思えたのはなぜでしょう?
森 何より大きいのは、現在の上司が私の考えを否定せずに受け止めてくれることです。自分の不安や悩みを話したとき、「それは違うよ」と頭ごなしに否定するのではなく、「それは難しいよね」と共感してくれる。このような姿勢があると、自然と前向きな対話ができるようになります。
上司に対する信頼感は、1on1以外の日常でも育まれました。特に印象的だったのは、あるお客様との打ち合わせの後のこと。会議室を出た直後、上司が「今日の内容、正直、俺にも難しかった」と率直に打ち明けてくれたのです(笑)。
「上司も完璧ではない」と知ることで、自分の弱みや不安も見せられる安心感が生まれます。こうした共有が、私たちの間にフラットな対話の土壌を育んでいると感じます。

──1on1の時間を有意義にするために、何か工夫されていることはありますか?
森 基本的なことかもしれませんが、準備が何より大切だと思います。その場の思いつきだけで対話を始めると、どうしても表面的な会話で終わってしまう。自分の考えも整理できず、本当に相談したい悩みも上手く言語化できないんですよね。
この問題を解決するために、日々の業務中に「これは1on1で話そう」と思ったことをメモしておき、事前に話題を整理しています。また、1on1支援ツールを活用して話したいテーマを記録し、実施後も対話内容を振り返るようにしています。こうした習慣によって、対話のPDCAを回せている実感があります。
また、午後の方が人は社交的になりやすいという話を聞いたので、昼以降に1on1の時間を設定するようにしています。少し変わった工夫かもしれませんが、そういった細部にもこだわっています(笑)。
1on1がエンジニアにもたらす価値
──森さんはエンジニアです。エンジニア目線で感じる1on1の価値があれば教えてください。
森 エンジニアの世界では当然ながら技術力が重視されますが、実は「心理面」が思いのほか重要なんです。私たちが開発の壁にぶつかるとき、表面的には技術的な課題に見えても、実際は「自信の欠如」や「挑戦する勇気の不足」であることが少なくありません。
現在の自動車産業は、海外メーカーとの熾烈な競争の中で、より短期間・低コストでの開発が求められています。私たちの会社でも先進的な解析技術開発のプレッシャーが常にあります。こうした環境では「もっと良い解析手法があるはず」「もっと効率的な方法を見つけないと」という前向きな思いと、「失敗したらどうしよう」という不安が背中合わせです。
1on1はそんな不安を和らげ、一歩踏み出す勇気を与えてくれる貴重な場。一人だと「失敗するかもしれないからやめておこう」と思うことも、信頼できる上司のサポートがあれば「試してみよう」と前に進めます。
こうした「挑戦する勇気をくれる対話」こそが、技術革新が求められる現場のエンジニアにとって、1on1の最も価値ある側面なのかもしれません。

──そのような内面的な話は1on1のような場の方が持ち出しやすいのでしょうか?
森 そう思います。私たちの日常的な会議は業務計画の進捗報告が中心です。そういった公の場で「最近モチベーションが下がっていて……」とか「自分はお客様に価値を提供できている自信がありません……」といった個人の内面を話すのは、やはりためらわれます。
1on1の素晴らしい点は、そうした本音を安心して話せ、上司がきちんと耳を傾けてくれる時間が保証されていること。悩みを相談しようと思い立ったときにいつでも上司の時間を押さえられるわけではないので、定期的な対話の場が存在することに、いちメンバーとしてありがたさを感じます。
この1on1に対して、私は数年前から意識的に捉え方を変えるようにしました。会社が公式に推奨している取り組みなのだから、無用な遠慮はせず、「自分のための30分」と受け止め、積極的に活用すべきと考えるようになりました。
日常業務では「これは言いづらいかも」と自己検閲してしまいがちですが、「1on1なら本音を話して構わない」という気持ちで臨むようにしています。そのほうが断然、実りある対話になります。あえて過激な言い方をしますが、1on1は「部下のためのアルコールなし飲み会」と捉えるのが、ちょうど良いと思います(笑)。
(撮影:小島マサヒロ)
「話すことが見当つかない」からのスタート
──御社では2021年から1on1を始めています。導入当初の印象は?
森 「何をやるんだろう」というのが率直な感想でした。上司から言われるがまま時間を設定したものの、会話に困り、中身がないまま30分を過ごしたこともあります。
キャリアについて聞かれても壮大すぎて答えられず、上司が定期的に変わる環境では深い関係性を築く必要性もあまり感じられませんでした。結果、業務進捗や打ち合わせの延長として時間を使うことが多かったように思います。

──そこから1on1の捉え方は変わったのでしょうか?
森 変わりました。きっかけはコロナ禍のテレワークです。自宅で週4、5日作業をしているうちにモチベーションが徐々に下がり、仕事に前向きになれなくなりました。そこで、出社して同僚や上司と話す機会を増やそうと思いました。雑談や何気ない会話が知らず知らずのうちに心の支えになっていたことに気付かされたからです。
──1on1ではどのような話をすることが多いですか?
森 新任上司との1on1では、いきなり深い話はできないので、雑談や軽めの話題から始めています。うまくコミュニケーションが取れるようになった上司とは、回を重ねるごとに、自分のキャリアや専門性、仕事のやりがいといった本質的な対話へと変化していきます。
──現在の上長との1on1でも、そのような変化がありましたか?
森 はい。現在の上司は2024年1月からお世話になっていて、これまで1on1を10回以上重ねています。最初の3、4回は趣味や育児の話題ばかり。はっきり言って純粋な雑談です(笑)。
こうした何気ない対話を積み重ねるうちに、徐々に仕事の話を持ち出せるようになっていきました。転機となったのは5回目くらいの1on1です。「解析技術の開発を一人でやることが多くて、業務が属人化している。正直、モチベーションが下がっています」と打ち明けました。
中堅社員である私は、多くの業務を一人で自走することが求められているため、サポートを求めることには少なからずためらいがありました。
それでも思い切って相談し、そこから業務のあるべき姿について1on1や日常業務のなかで上司と議論を重ねた結果、日々アドバイスをもらえる先輩社員をつけてもらえることになりました。
会社のリソースが限られている中、私一人のために先輩をつけてもらえるなんて本当にありがたかったです。

──その経験は仕事との向き合い方や心境に変化をもたらしましたか?
森 大きな変化がありましたね。以前は「どうせ上司はまだ変わるんだし」と思って、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)は最低限にしておこうと考えていました。
しかし、1on1を通じて「上司に困りごとや課題を共有すると、解決に動いてくれる」と実感してからは、些細なことでも相談するようになりました。しょうもないことばかり話すようになったかもしれませんが(笑)、上司とのコミュニケーションが増えたことは間違いありません。
──踏み込んだ相談ができるかどうかは、上司との信頼関係次第と言えそうです。現在の上司に対して「この人なら悩みを相談できる」と思えたのはなぜでしょう?
森 何より大きいのは、現在の上司が私の考えを否定せずに受け止めてくれることです。自分の不安や悩みを話したとき、「それは違うよ」と頭ごなしに否定するのではなく、「それは難しいよね」と共感してくれる。このような姿勢があると、自然と前向きな対話ができるようになります。
上司に対する信頼感は、1on1以外の日常でも育まれました。特に印象的だったのは、あるお客様との打ち合わせの後のこと。会議室を出た直後、上司が「今日の内容、正直、俺にも難しかった」と率直に打ち明けてくれたのです(笑)。
「上司も完璧ではない」と知ることで、自分の弱みや不安も見せられる安心感が生まれます。こうした共有が、私たちの間にフラットな対話の土壌を育んでいると感じます。

──1on1の時間を有意義にするために、何か工夫されていることはありますか?
森 基本的なことかもしれませんが、準備が何より大切だと思います。その場の思いつきだけで対話を始めると、どうしても表面的な会話で終わってしまう。自分の考えも整理できず、本当に相談したい悩みも上手く言語化できないんですよね。
この問題を解決するために、日々の業務中に「これは1on1で話そう」と思ったことをメモしておき、事前に話題を整理しています。また、1on1支援ツールを活用して話したいテーマを記録し、実施後も対話内容を振り返るようにしています。こうした習慣によって、対話のPDCAを回せている実感があります。
また、午後の方が人は社交的になりやすいという話を聞いたので、昼以降に1on1の時間を設定するようにしています。少し変わった工夫かもしれませんが、そういった細部にもこだわっています(笑)。
1on1がエンジニアにもたらす価値
──森さんはエンジニアです。エンジニア目線で感じる1on1の価値があれば教えてください。
森 エンジニアの世界では当然ながら技術力が重視されますが、実は「心理面」が思いのほか重要なんです。私たちが開発の壁にぶつかるとき、表面的には技術的な課題に見えても、実際は「自信の欠如」や「挑戦する勇気の不足」であることが少なくありません。
現在の自動車産業は、海外メーカーとの熾烈な競争の中で、より短期間・低コストでの開発が求められています。私たちの会社でも先進的な解析技術開発のプレッシャーが常にあります。こうした環境では「もっと良い解析手法があるはず」「もっと効率的な方法を見つけないと」という前向きな思いと、「失敗したらどうしよう」という不安が背中合わせです。
1on1はそんな不安を和らげ、一歩踏み出す勇気を与えてくれる貴重な場。一人だと「失敗するかもしれないからやめておこう」と思うことも、信頼できる上司のサポートがあれば「試してみよう」と前に進めます。
こうした「挑戦する勇気をくれる対話」こそが、技術革新が求められる現場のエンジニアにとって、1on1の最も価値ある側面なのかもしれません。

──そのような内面的な話は1on1のような場の方が持ち出しやすいのでしょうか?
森 そう思います。私たちの日常的な会議は業務計画の進捗報告が中心です。そういった公の場で「最近モチベーションが下がっていて……」とか「自分はお客様に価値を提供できている自信がありません……」といった個人の内面を話すのは、やはりためらわれます。
1on1の素晴らしい点は、そうした本音を安心して話せ、上司がきちんと耳を傾けてくれる時間が保証されていること。悩みを相談しようと思い立ったときにいつでも上司の時間を押さえられるわけではないので、定期的な対話の場が存在することに、いちメンバーとしてありがたさを感じます。
この1on1に対して、私は数年前から意識的に捉え方を変えるようにしました。会社が公式に推奨している取り組みなのだから、無用な遠慮はせず、「自分のための30分」と受け止め、積極的に活用すべきと考えるようになりました。
日常業務では「これは言いづらいかも」と自己検閲してしまいがちですが、「1on1なら本音を話して構わない」という気持ちで臨むようにしています。そのほうが断然、実りある対話になります。あえて過激な言い方をしますが、1on1は「部下のためのアルコールなし飲み会」と捉えるのが、ちょうど良いと思います(笑)。
(撮影:小島マサヒロ)