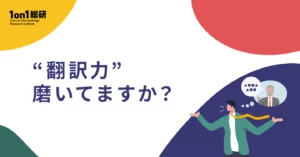目次
はじめに
近年、多くの業種で有効求人倍率が高止まりし、人材確保が難しい状況です。加えて新卒や若年層を中心に早期離職が続いており、「人材不足」と「人材の定着」が大きな課題となっています。その一方で、新しい知識や視点を持つ若手社員・多様なバックグラウンドを持つメンバーをうまく活かしきれず、現場に“もやもや”した空気が漂っている、という声もよく聞かれます。
こうした状況を打開するヒントとして、「傾聴力(アクティブリスニング)」が今改めて注目されています。
傾聴は、ただ相手の言葉を聞くのではなく、本音や背景にある感情にまで耳を傾けるコミュニケーションスキルです。これにより、職場での摩擦を減らし、メンバー同士の信頼関係を築き、組織としてのパフォーマンスを高めることが期待できます。
ここではコーチングの視点を交えつつ、傾聴のエモーショナルな効果や具体的なテクニックを紹介していきましょう。
傾聴とは何か? ビジネスでの重要性
傾聴の定義と意味
「聞く」ではなく「聴く」。この違いは想像以上に大きな意味を持ちます。耳に入ってくる情報を受け流すのではなく、相手が何を感じ、どのような思いを抱えているのかに意識を向けるのが「聴く」行為です。
心理学者カール・ロジャーズの来談者中心療法でも、クライアント(相手)を無条件に受容し、共感を重視することで自己成長を促すアプローチが重要視されてきました。
ビジネスにおいても、上司・部下間やチームメンバー間でしっかりと「聴く」姿勢を持つことで、一人ひとりの考え方や価値観を正しく理解し、最適なサポートやアドバイス、さらには信頼関係の土台を築くことができます。
なぜ今、傾聴が必要なのか?
①雇用環境の変化
かつては「上司の指示に従うこと」が当たり前だった職場も、今や多様な価値観が共存する場に変わっています。キャリア観、ライフスタイル、働く動機も人によってさまざまです。こうした個々のニーズや感情を汲み取り、対話の中から本人の“やる気のスイッチ”を見つけるには、表面的な会話ではなく「傾聴」の姿勢が欠かせません。
②事業環境の変化
市場は日々変化し、顧客ニーズも一層複雑・多様になっています。こうした時代においては、経営層だけでなく、最前線の現場で働くメンバーの気づきやアイデアこそが競争力の源泉になります。そうした中、上司がただ「聞く」のではなく、「耳を傾けて受け止める」姿勢を持つことが、組織の創造性や提案力を引き出す鍵になります。
③働き方の変化
リモートワークやハイブリッドワークの普及により、ちょっとした雑談や相づちといった“空気感”でつながる機会が激減しました。その結果、気づかぬうちにメンバーのモチベーションが下がったり、孤立感を抱えるケースも増えています。画面越しの会話でも、相手の表情や言葉の裏にある感情に目を向け、共感的に聴く力=傾聴が、関係性を維持・深化させる大きな力となります。
傾聴力を深める実践テクニック
傾聴はテクニックだけでなく、相手に寄り添う意識が大切です。しかし、具体的な方法を知ることで「実践しやすくなる」「スキルを伸ばしやすくなる」側面もあります。ここでは、コーチングの考え方も交えながら取り入れたい代表的なテクニックをご紹介します。
傾聴の基本要素
✅ アクティブリスニング(積極的傾聴)
相槌や要約を交えながら相手の話を深く受け止める態度を指します。話を遮らず、相手が自己開示しやすい雰囲気を作るのが大切です。
✅ 共感・受容
「つらかったね」「そう感じるのは自然だね」という具合に、相手の感情を否定しない姿勢。話し手は「分かってもらえた」と感じると、より深い本音を引き出せます。
✅ 非言語コミュニケーション
視線・うなずき・表情など、言語以外の部分でも「聴いていますよ」というサインを送ると、安心感を高められます。
明日から使える七つの「傾聴」テクニック
以下では、コミュニケーションを円滑にし、相手の自己開示を促す「傾聴テクニック」を七つ紹介します。どれもシンプルなものですが、意識して使うと会話の質が大きく変わってきます。ぜひ明日からの対話に取り入れてみてください。
① オープンクエスチョン
「はい/いいえ」で答えられない問いかけのことです。相手が自由に考えや感情を表現できるよう促します。
(例)
🧒「それをどう思った?」「背景にはどんなことがあるの?」
(ポイント)
👉 質問した後はすぐに話を遮らず、相手が考えるのを待つと自己探索が深まります。
②シグナル(非言語情報)を読み解く
声のトーンや姿勢、表情などから相手の感情や状態を汲み取る技術です。
(例)
🧒「いつもより元気がないように見えるけど、何かあった?」とさりげなく聞いてみる。
(ポイント)
👉「気づいてくれた」という安心感が相手の自己開示を促します。ただし、思い込みで断定しないよう気をつけることが大事です。
③オウム返し(パラフレーズ)
相手の話を要約して返すことで、自分の理解度を確認しつつ、相手がさらに話しやすくなるよう促す方法です。
(例)
🧒「つまり〇〇ということがいちばんの課題なんだね?」
(ポイント)
👉 相手は自分の考えを俯瞰でき、自然と会話の深掘りへ繋がりやすくなります。
④ミラーリング
相手の声のトーンや話すスピード、ジェスチャーを自然に合わせることで心理的な親近感を高める技術です。
(例)
💡 早口の人には少しテンポを上げて話す、落ち着いた口調の人にはゆっくり合わせる、など。
(ポイント)
👉 やり過ぎると不自然なので、あくまで「自然に少し似せる」程度がコツです。
⑤感情ラベリング
相手が口にしない感情を代わりに言葉にしてあげることで、「自分の気持ちを理解してもらえている」と感じてもらう技術です。
(例)
🧒「それはすごく悔しい気持ちになるよね」「もしかして不安が大きいんじゃないかな」
(ポイント)
👉 決めつけにならないよう、相手が「そうなんです」と答えやすい柔らかい表現を心がけましょう。
⑥沈黙と待つ力
すぐにアドバイスや解決策を示すのではなく、相手が考えを整理する時間を与えることで、思考の深掘りをサポートする方法。
(例)
🧒 相手が言葉につまったら、あえてすぐには話をつなげず、目線で「ゆっくり考えて大丈夫だよ」と伝える。
(ポイント)
👉 相手が話したそうな仕草を見せたら、再びオープンクエスチョンで促すなど、呼吸を合わせてコミュニケーションを続ける。
⑦ 自己開示
自己開示は、自分の体験や気持ちをあえて少しだけ打ち明けることで、相手が「話していいんだ」と安心し、本音を言いやすくなる技法です。
(例)
🧒 「実は自分も新人の頃、よく同じことで悩んでいたんだよね。もしかしたら似た気持ちかもしれないね」
(ポイント)
👉 相手を主役にすること。自己開示はあくまで相手のハードルを下げるためです。長々と自分の話をせず、「あなたはどう思う?」と対話に戻しましょう。相手が戸惑っているときや言葉に詰まったときに軽く話すと効果的です。自分の体験を強要せず、「こういう考え方もあるかも」くらいのスタンスで伝えると受け止められやすくなります。
よくある「ダメな聞き方」5選
以下では、相手の話を聞くつもりがあっても、ちょっとした対応のまずさで信頼を損ねてしまうケースを五つ紹介します。
よくある「ダメな聞き方」の事例を知り、対策や代わりの表現を押さえておくことで、傾聴力の向上につなげましょう。
❌ 相手の気持ちを矮小化する
(NGフレーズ例)
🙅 「それくらい大したことないよ」「みんな同じだよ、気にしすぎ」
このように相手の気持ちを矮小化すると、話し手が「自分のつらさをわかってもらえていない」と感じ、さらに心を閉ざしてしまいます。代わりに、「そう感じるのも無理ないね」「たしかに大変だったね」と受け止めると良いでしょう。
❌ 話題を急に自分の話にすり替える
(NGフレーズ例)
🙅 「それなら自分の場合はこうだったよ」「俺のときはもっと大変だった」
1on1などでせっかく部下が相談しているのに、それを遮って上司が昔の苦労話をすることがあります。話し手は「自分の問題よりあなたの話が大事なの?」と感じ、モチベーションが下がるので控えましょう。「もし参考になれば私の経験談を話すこともできるけど、まずはあなたの気持ちをもっと聞かせてほしい」というふうに、自分は一歩下がるのが傾聴の視点では大切です。
❌ 解決策をすぐに押しつける
(NGフレーズ例)
🙅 「こうすればいいのに」「そんなの○○でしょ」
すぐに答えを言ってしまうのは、話し手が自分で考えを整理し、納得感を得るプロセスを奪う結果になります。「もし必要なら一緒に案を出し合えるけど、まずはあなた自身はどう感じてる?」というふうに寄り添い、思考の壁打ち役になることに徹しましょう。
❌ 感情を否定する・揚げ足を取る
(NGフレーズ例)
🙅 「そんなの甘えだよ」「それはわがままだよ」
話し手の感情を否定されると、会話がストップしてしまいます。代わりに「それだけ真剣に考えてるんだね」「そう思わざるを得ない状況だったのかな」と相手の気持ちを重んじた発言をしましょう。
❌ ノンバーバルを軽視して話を聞いていない雰囲気を出す
(NG行為例)
🙅 スマホをチラチラ見る、腕組みしながらそっぽを向く
このような資格情報は、「聞いていないのかな」と思わせ、「話す気をなくす」原因になりやすいもの。話している時はスマホの画面を伏せたり、体を相手の方に向ける、適度なうなずきで関心を示すなど非言語の情報にも気を配りましょう。
3. 傾聴と1on1
1on1ミーティングの目的と意義
1on1は、マネジャーとメンバーが定期的に対話を行い、業務の進捗やキャリア、メンタル面などを共有するための仕組みです。単なる指示やフィードバックの場ではなく、メンバーが本音や悩みを話しやすい「安全地帯」として機能させることが重要です。
ここで傾聴のスキルを活かせると、相手が安心して心の内を話せるようになり、新しいアイディアの創出や離職を未然に防ぐことにも繋がります。
(参考:個人と組織の成長が加速。マネジャーのための「1on1完全ガイド」)
以下では、1on1を通じて相手の成長や課題解決をサポートするための基本フローを示します。単なる業務報告ではなく、「相手が自発的に考え、気づきを得られる対話」にすることが大きなポイントです。各ステップで傾聴のテクニックをバランスよく活用しながら、安心して話せる雰囲気づくりを意識しましょう。
傾聴を活用した1on1の基本フロー
①始め方
いきなり本題に入るのではなく、「最近どう?」「この前の仕事はどんな感じだった?」など、身近な話題から会話を始め、自然で話しやすい雰囲気をつくります。
💡ポイント
・軽い雑談や近況確認でリラックスムードを作る。
・「今日はどんなことを話したい?」などオープンクエスチョンでテーマを確認。
・「先週は忙しそうだったけど大丈夫?」など相手の様子を気遣いつつ、自然に話題を広げる。
②対話中
対話の核となる段階では、様々な傾聴のスタンスを維持しながら「相手に考えてもらう時間」をしっかり確保します。急いで解決策を押しつけず、沈黙や相槌、オウム返しをうまく使って相手の言語化を促しましょう。
💡ポイント
・オープンクエスチョンやオウム返し、感情ラベリングなどで相手の言語化を流す。
・相手が考え込みそうなときは「沈黙」を活かして自己探索を促す。
・必要以上にアドバイスを与えず、「あなたはどう思う?」と問いかける姿勢を大切にする。
③終わり方
1on1の目的は「その場だけの相談」で終わらせないこと。最後に具体的な行動や次回までの目標を明確にしておくと、モチベーション維持と継続的なフォローがしやすくなります。
💡ポイント
・「次回までにどんなアクションを取ってみたい?」と投げかけ、相手に具体的な目標・行動を言語化してもらう。
・フォローアップや次回の予定を確認し、継続的なサポートを続ける。
・必要があれば定期的に進捗を確認し、小さな成功体験を積み重ねによる成長を後押しする。
1on1を効果的に活用するには、相手を受け入れる傾聴の姿勢が大前提になります。相手の言葉に耳を傾けながら問いかけることで、部下やメンバー自身が新たな気づきや解決策を生み出せるようになります。
最後にアクションプランを言語化し、上司やチームがフォローする体制を整えることで、1on1が「日常的な対話→行動→成長」の好循環を生み出す場へと進化するでしょう。
【ケーススタディ】
職場でパフォーマンスが落ちている時に「何かあったの?」と聞いても、「特に問題ありません」といった無難な返事だけで本音を語らないメンバーも少なくありません。
そこで、どのように相手の声を引き出せるのか、以下のケーススタディを通じて学んでいきましょう。
(状況)
中堅企業で働くメンバーAさんは、会議や1on1でも本音を話さず、深い話を避けがちでした。上司BさんはAさんの様子から、何か悩みがあるのではと感じています。
(対話例)
👦 Bさん(上司):「最近大変そうに見えるけど、大丈夫? 実は私も以前、誰にも相談できず辛かった時期があったよ。もし困っていることがあれば言ってほしい」 ⇨ (自己開示で安心感を与える)
👩 Aさん(メンバー):「Bさんは忙しいし、細かいことまで言うのは気が引けて……」
👦 Bさん:「遠慮してくれてたんだね。でも実際には、モヤモヤしてるのかな?」⇨ (感情ラベリングで「遠慮」「モヤモヤ」を言語化)
👦 Bさん:「もし差し支えなければ、具体的に何がいちばんやりづらいか教えてくれる?」⇨ (オープンクエスチョンで深掘り)
👩 Aさん:「実は業務が複数重なると、どこから手をつければいいのか分からなくなるんです」
(ポイント)
まず「上司が先に自己開示をすることで、相手が安心して本音を言いやすい雰囲気をつくる」ことが大切です。「自分も似たような苦労をしたことがある」と話すだけで、相手は「相談しても大丈夫なんだ」と思いやすくなります。
次に、「感情ラベリング」で相手の気持ちを具体的に言葉にしてあげると、話し手は「自分の思いを理解してもらえた」と感じ、より深い部分を打ち明けやすくなります。
最後に、締めくくりとして「オープンクエスチョン」を使い、具体的な悩みや困りごとを引き出すことで、本音に近づいていく流れを自然に作れます。
傾聴文化を育てる施策と事例
大手コーヒーチェーンの「スターバックス」は、同社で働くパートナーを「ブランドを形づくる存在」と捉え、組織のベースに「多様性を認め合うこと」と「温かく迎え入れること」を位置づけています。
これは、単に「受け入れるだけ」ではなく、それぞれが抱えている思いを受容・理解する姿勢を持ち、「自分らしさ」を表現できる余白を提供するということです。そのためには、相手の話を否定せず、まず耳を傾けて寄り添う“傾聴”が欠かせません。
具体的には、定期的なパートナーミーティングやアンケートを通じて、パートナー一人ひとりの声を吸い上げる仕組みを整え、そこから出てきた意見やアイデアを尊重しあう風土が築かれています。
年齢や性別、バックグラウンドといった属性に捉われず、お互いを“対等な存在”として扱うことで、多様化するライフスタイルやライフステージに応じた働き方を可能にしているのです。
組織が取り入れるべきポイント
✅ 定期的な対話の場づくり
日頃から1on1やチームミーティング、アンケートなどを通じて社員の声を吸い上げる仕組みを用意します。特に“定期的”に開催することで、気軽に話せる空気が育まれやすくなります。
✅ フラットな関係性を意識する
スターバックスのように、上司・部下の垣根を越えて相手を“パートナー”と捉える姿勢が鍵です。役職や雇用形態に関係なく、一人ひとりが対等に意見を言える文化を形成しましょう。
✅ 多様性を尊重し、受容する
年齢や性別、ライフステージなどの違いが生むアイデアや働き方を前向きに受け入れることで、新たな発想が生まれやすくなります。相手の言葉をまず受け止める“傾聴”は、この多様性を活かすための基盤です。
✅ 意見を反映するフィードバックループ
せっかく吸い上げた声をそのままにせず、改善策や取り組みに繋げることで社員のモチベーションが高まります。経営層や管理職は結果をオープンに共有し、次のアクションへ活かす姿勢を示すことが重要です。
傾聴力がアップするトレーニング例
傾聴は、一朝一夕で習得できるスキルではありません。「ちゃんと聞いているつもり」でも、無意識のうちに相手の話を遮ったり、自分の価値観で解釈してしまっていることも少なくありません。だからこそ、「体験」と「振り返り」を通じて、日常のクセに気づき、より良い聞き方を自分のものにしていくことが大切です。ここでは、すぐに実践できて学びが深まるトレーニング方法をご紹介します。
(1) ロールプレイ
まず、二人一組でペアを組みます。Aさんが“話し役”、Bさんが“聴き役”とし、3~5分ごとに役割を交替します。話し役のトピックは、小さな悩みや最近あった出来事、職場で気になることなど、程よく話しやすいテーマを選びましょう。聴き役は、オープンクエスチョン、オウム返し、感情ラベリングなどのツールを使って聴きます。
(2)フィードバックセッション
ロールプレイ終了後、AさんがBさんに対して「もっとこうしてほしかった」「ここの反応は安心できた」など、具体的にフィードバックします。役割を交替した場合は、BさんからAさんへも同様にコメントを行います。グループで実施している場合は、観察していた第三者(Cさん)のコメントも加わるとさらに客観的な視点が得られるでしょう。
「聴く」姿勢や言葉選びに関して、相手から率直な感想をもらうことで、自分の弱点や改善点を把握できるメリットがあります。ほかの参加者のロールプレイを観察することも、学びの大きなヒントになることでしょう。
まとめ
傾聴は、一見地味なスキルのように思えますが、実は組織のコミュニケーションを劇的に変え、メンバーの意欲や能力を最大限に引き出す力があります。
オープンクエスチョンで相手の考えを広げ、シグナルを読み解いて気持ちを汲み取り、オウム返しや感情ラベリングで相手の心に寄り添う。このような一連のプロセスによって「この人になら何でも話せる」「この職場でなら自分を活かせる」という心理的安全性が醸成されます。
これらを継続的に行うことで、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下だけでなく、イノベーションの創出やチームワークの強化にも大きく寄与するでしょう。忙しいビジネスシーンの中だからこそ、「相手の話を聴き切る」時間を意識的に確保してみてください。