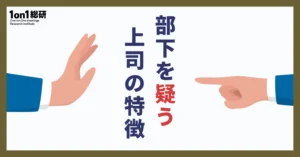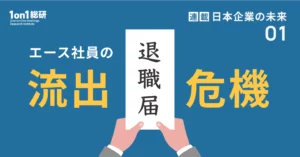今あなたの目の前にいる部下は、「『目標設定』という名の茶番に付き合わされている」と思っているかもしれない――。
上司と部下で毎年繰り返される「目標設定」。ここで決められた「目標」は本当に部下の成長のためになっているとあなたは言い切れるか。形骸化したMBO(目標管理制度)が企業の競争力を奪う時代に、部下の成長と事業成果を同時に実現する「勝てるマネジメント」のフレームワークを考える。
目次
MBOはもはや「儀式」!?
目標設定という行為、評価面談というものは、本来は目標を通じて部下の成長機会を作り、成果につなげるためのものである。しかし、現実には、「人事から言われてやらなくてはならないこと」「部下を評価すること」が目的になりがちだ。
部下の目標設定が日常業務と切り離された「儀式」になり、評価をすること自体が目的になってしまい、日常の業務とは関係ない目標や抽象的な目標を決めてしまう。形骸化したMBOによる目標は、達成しようがしまいが、チームにとってはもはやどうでもいいものである。
大半の大企業がMBOを導入していると考えられるが、MBOをすべての組織が生かし切れているわけではなく、目標を“決める”ことが仕事になっているケースもあるだろう。そんなMBOはむしろ、百害あって一利なしだ。
そもそも、ピーター・ドラッカーが提唱したMBOとは、会社の方針と社員自身が目指したい方向性を擦り合わせることで一人ひとりに目標を設定し、成果までの道のりを管理するマネジメントの概念だ。つまり、目標とその達成が主眼ではなく、達成までのプロセスを重要視している。その目標に向けて従業員が主体的に行動する「自己管理」こそが、彼らの成長につながるということがMBOの核心だ。MBOというものは、進捗管理が目的ではなく、組織と部下個人の成長を同時に実現することが目的だということを、マネジャーは理解しておく必要がある。
では、目標設定や面談を、部下の成果につなげていくためには、どんな方法があるのだろうか。次のセクションから詳しく見ていこう。
本当のMBOは評価と成長機会を結び付けるもの
MBOではどんな目標を立てるべきか。理想は、その人に合わせた難易度のチャレンジを設定し、その部下の人がどういうふうに自分の力を身に付けていくのかを考えた目標設計だ。
たとえば、キャリアプランを考える際の重要なフレームワーク「Will(本人が実現したいこと)・Can(生かしたい強みや克服したい課題)・Must(能力開発につながるミッション)」のうち、部下のCanを増やすのか、それとも特定のMustをクリアさせることで、より責任のある新しいMustへのチャレンジを促すのか。MBOで設定した目標は、部下自身が「自分にとって意味のある目標」と捉え、主体的に取り組みたいと思えるものでなければならない。個人のストーリーとして納得し、実際の行動に移せる状態にすることが重要だ。
これはつまり、仕事を使ってスキルを向上させ、次の難易度のチャレンジをさせていくということだ。会社からすれば、等級の高い人が難易度の高いこと、インパクトの大きいことができるようになるということである。そうした人材を生み出すために、MBOは非常に重要なのだ。
数値+○○=目標
今まで話してきたことを、もう少し詳しく解説していこう。MBOが儀式化し、形骸化してしまわないように、どんな工夫をするとよいだろうか。
まず、評価方法を明文化しておこう。基本的に等級(グレードなど)に合わせた難易度相当の目標を立てるわけだが、結果を点数化することを見越して、あらかじめ上司と部下で評価方法を決めておくことが大切だ。目標を決めて、どう評価するかを決めていれば、評価の際に上司と部下で話の食い違いが起きることを避けられる。
この目線合わせができていないと、評価面談のときに、部下が前期比120%の成果を残したのに、上司の評価では60点になっていた、ということが起きる。期待されていた領域や到達基準を踏まえずにアウトプットしても、それは評価につながらない。しかし、部下はその結果だけを見て、頑張っていたことを全否定されたように受け止め、つらい思いをするだろう。
次は、目標の立て方の工夫だ。目標設定プロセスには階層性がある。会社の目標が組織レベルに展開され、各組織の成果がマネジャーの評価基準になり、さらに組織目標が個人に割り当てられる。そのような構造を踏まえ、上司は組織としてやってほしいことを盛り込みながら、部下が意欲的に取り組める目標を立てる必要がある。
前提として、「何の課題もない」人はいない。そのため、数値目標を設定する際には、部下固有の課題を考慮し、その解決も組み込んだ「こういう状態を作る」という統合的な目標を設計するとよい。この「こういう状態」は、「○○ができるようになる」という能力開発の側面と、「数字を達成するためのプロセスを磨く」という方法論の側面、どちらかに重点を置いて設計するのが望ましい。
目標設定面談では、単に目標を決めるだけでなく、どうすれば本人の成長につながるかを具体的に話し合うことが非常に大切である。つまり、形式的な目標設定よりも、その目標に対して上司が期待することを明確に伝えることこそが最も重要なのである。
MBOは、目標設定して終わりではなく、そのプロセスが大切だ。目標は部下が次のステップに進むための道しるべであり、目標設定面談や評価面談、定期的な1on1は、上司と部下が目標に向かって上手に進んでいくためのコミュニケーションの場である。いうなれば、部下の成長のための作戦会議なのだ。
「部下の成長を促すMBO」実践チェックシート
今までの話をまとめると、MBOの形骸化を防ぐために、運用に関して特に注意しておきたいポイントは以下の四つとなる。
① 成果が測定できないような目標にしない
② 「目標設定したら終わり」にせず、進捗確認やフィードバックを定期的に行う
③ 部下任せにしすぎず、上司が適度なサポートをして活動に落とし込む
④ プロセスや行動を含めた評価がなければ本来の成長が促されないため結果だけで評価しない
最後に、目標設定において部下のモチベーションを下げ、成長の芽を摘むコミュニケーションにならないよう、「部下の成長を促すMBOチェックシート」をまとめておく。次回の目標設定面談では、ぜひ役立ててほしい。
■部下の成長を促す目標設定(MBO)実践的チェックシート
【目標設定時】
✅ 目標が会社やチームの方向性・戦略に明確にリンクしているか?
✅ 部下自身が達成したいと思える目標になっているか?
✅ 目標の具体的な成功イメージを部下が言語化できるか?
✅ 目標達成に向けて、最初の行動ステップが明確か?
✅ 目標達成を支援するために、上司として具体的な支援策(フィードバックの頻度や方法、必要なリソース)を提示したか?
【運用時】
✅ 目標の進捗状況を定期的(最低月1回)に具体的に確認しているか?
✅ 部下が困難や問題に直面した場合、早期に相談しやすい環境を作っているか?
✅ 部下の行動や取り組みをリアルタイムで具体的に認識しているか?
【振り返り時】
✅ 目標達成の結果だけでなく取り組んだプロセス・行動の質を深く掘り下げ評価しているか?
✅ 部下自身が達成・未達成の要因を具体的に自己分析できているか?
✅ 次の目標設定につながる具体的な改善点や成功要因を一緒に整理しているか?
✅ 成果や課題が次期以降の成長につながるよう部下自身が納得感を持って振り返れているか?

上司と部下が話し合い、部下の納得のいく目標を定め、そのプロセスによって部下の成長を促していくMBOのサイクルがつかめただろうか。タイミングごとにチェックリストを確認し、「儀式」ではない本質的なMBOを行ってみてほしい。