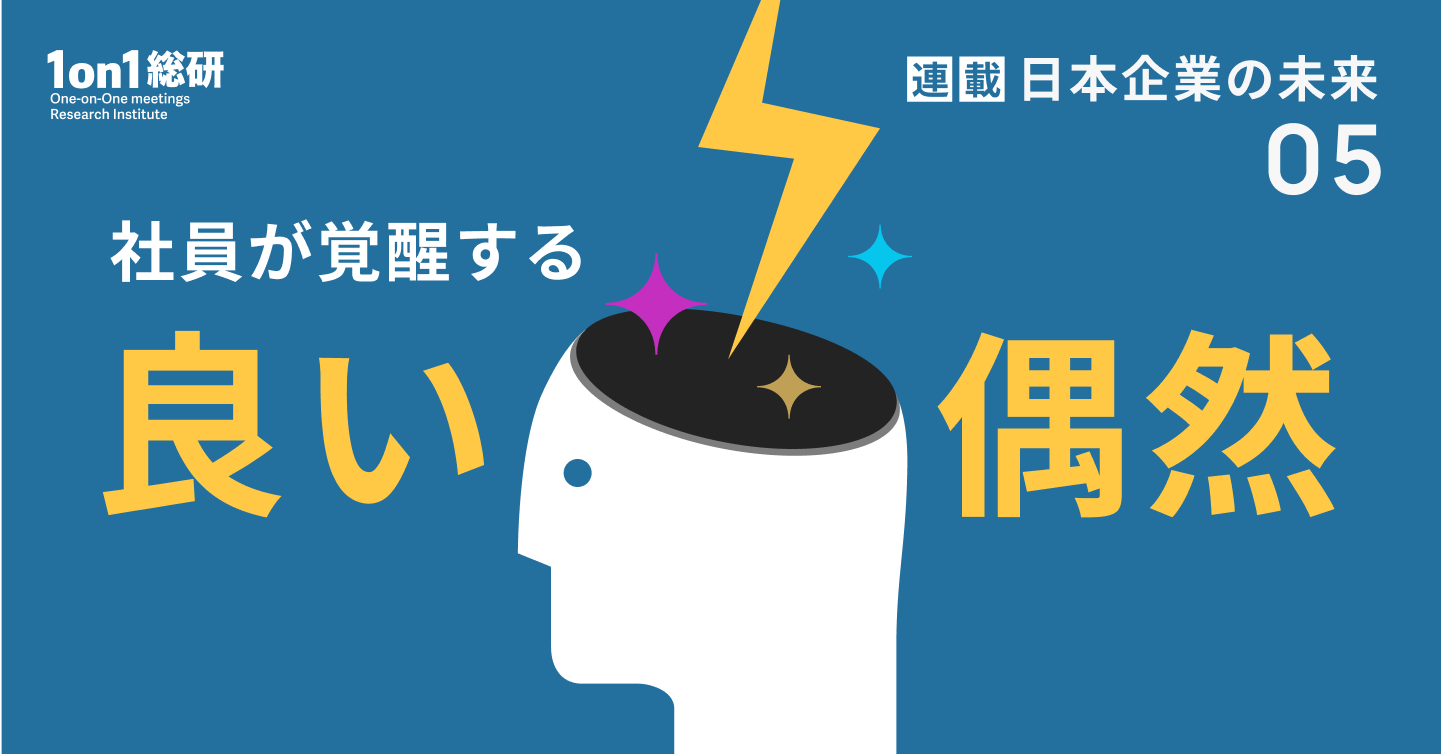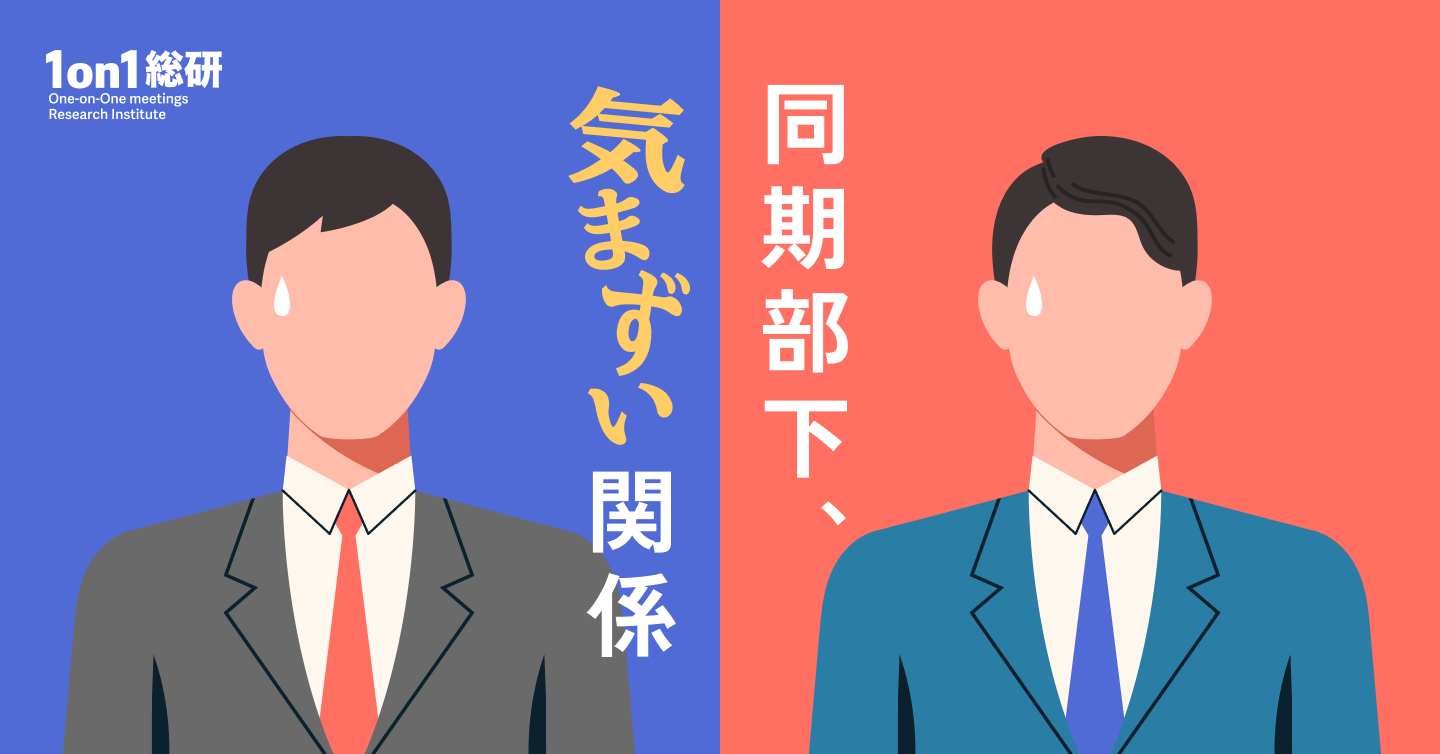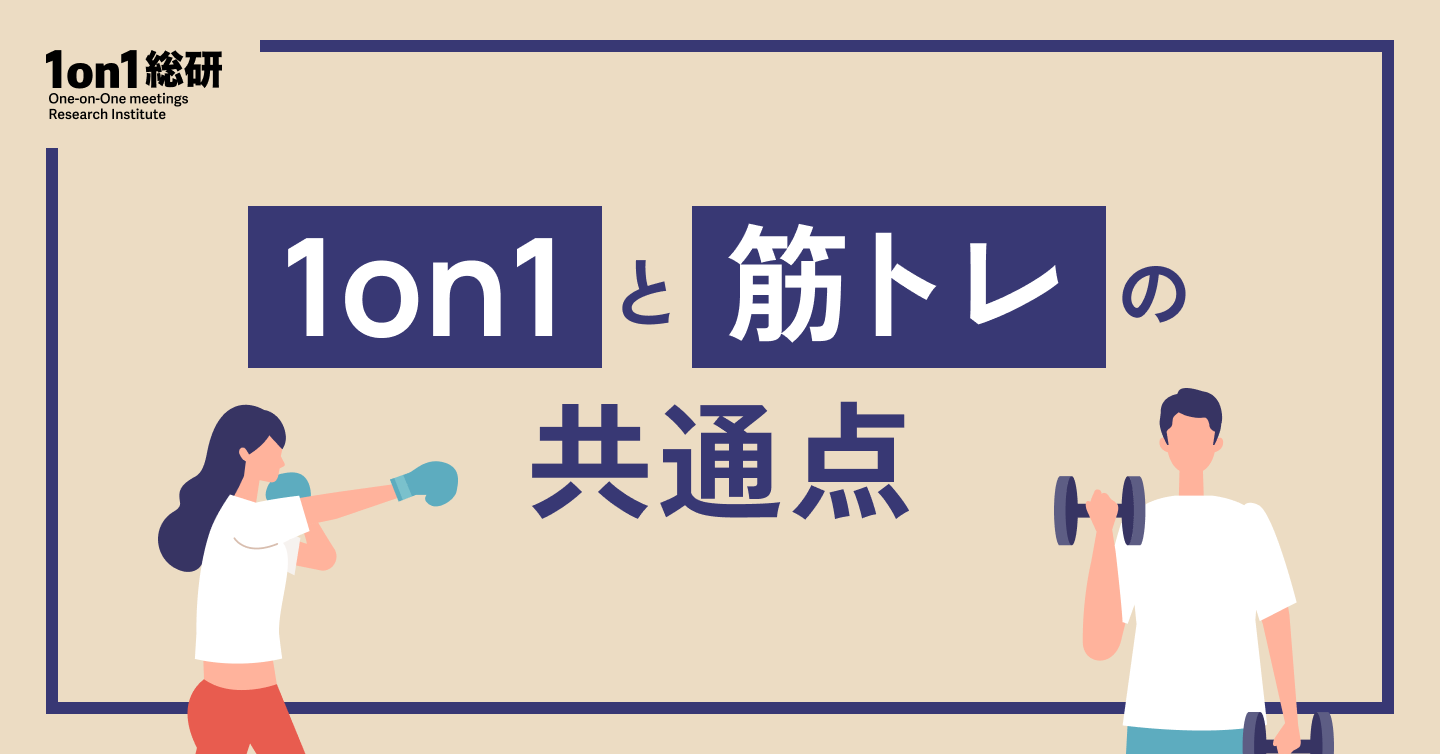記事一覧
その「聞き方」はNG! 明日から使える傾聴テクニック
近年、多くの業種で有効求人倍率が高止まりし、人材確保が難しい状況です。加えて新卒や若年層を中心に早期離職が続いており、「人材不足」と「人材の定着」が大きな課題となっています。その一方で、新しい知識や視点を持つ若手社員・多様なバックグラウンドを持つメンバーをうまく活かしきれず、現場に“もやもや”した空気が漂っている、という声もよく聞かれます。
こうした状況を打開するヒントとして、「傾聴力(アクティブリスニング)」が今改めて注目されています。
傾聴は、ただ相手の言葉を聞くのではなく、本音や背景にある感情にまで耳を傾けるコミュニケーションスキルです。これにより、職場での摩擦を減らし、メンバー同士の信頼関係を築き、組織としてのパフォーマンスを高めることが期待できます。
ここではコーチングの視点を交えつつ、傾聴のエモーショナルな効果や具体的なテクニックを紹介していきましょう。

【驚愕のデータ】優秀な若手が逃げ出す「ゆるブラック」という現実
人間の考えや志向は実に多様です。その環境を好む人もいれば嫌う人も現れます。
かつて日本企業では、多くの人が望まぬ長時間労働を強いられ、心身の不調をきたす人もいました。「働きすぎ」問題は、「ブラック企業」という言葉として悪評がSNSを通じて広まったこと、また政府による本格的な介入も奏功し、ある程度の解消に向かいました。
しかしながら、今度は別の問題に直面しました。
逆に仕事が楽過ぎてやりがいを感じられない、または望むような成長ができないと思う人が出てきます。そうした人は、強制的に楽な仕事しかさせない環境を問題視し、表面的にはホワイトながらもやりがいや成長機会に乏しい会社を、いつからか「ゆるブラック」企業と認定するようになりました。
ゆるブラックな環境は、やる気のある若手が流出する要因にもなっています。
過酷な労働環境はご法度、されど仕事が緩いのもダメ……一体どうすればいいのでしょうか。そこで2回にわたって、データ分析も踏まえながら、以下の三つの問いに迫ります。
📌「働きやすさ」と「働きがい」をもたらす要因
📌「働きやすさ」および「働きがい」と、企業業績との関係性
📌人生100年時代における「働きやすさ」と「働きがい」の両立
初回となる今回は、働きやすさの改善の裏で急速に失われた働きがいについて驚愕のデータを交えて深掘りします。
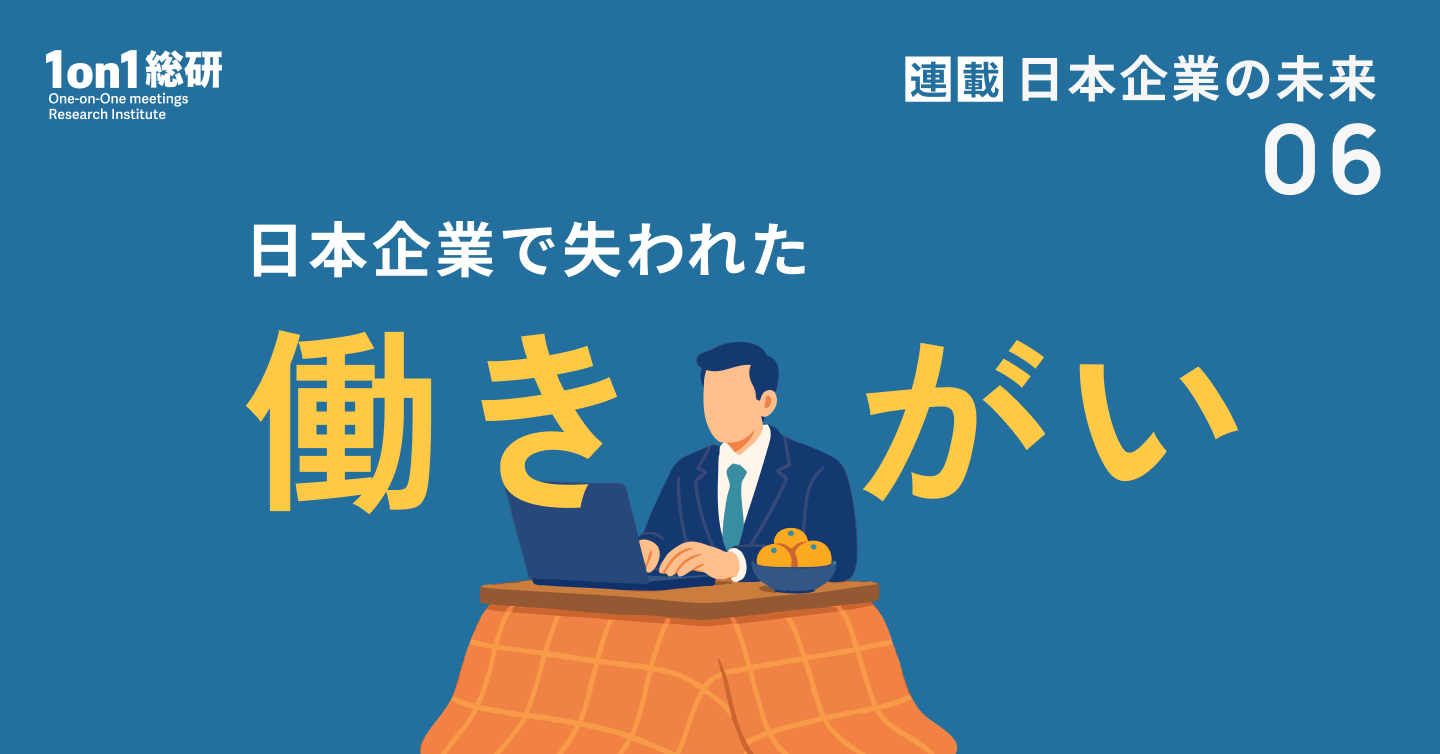
1on1が組織を変える。エンゲージメント向上の成功事例
急速に変化するビジネス環境において、企業が競争力を維持するには、社員一人ひとりの主体的な行動と自律的な成長を促す組織づくりが不可欠です。その実現に欠かせないのが、社員と組織の心理的なつながり、すなわち「エンゲージメント」です。
しかし、制度や仕組み(ハード施策)を整備するだけでは、社員の納得や自発的な行動にはつながりません。組織文化やコミュニケーション(ソフト施策)を促進しても声がけに終わってしまうことも多いです。
そこで注目されているのが「1on1」です。上司と部下が定期的に対話を重ね、制度や方針の意図を丁寧に伝え、信頼関係を築く場としての1on1は、エンゲージメントを高める実践的な手段です。
本記事では、1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」の事例をもとに、エンゲージメント向上に効果的な1on1の設計・運用・定着方法を解説します。

4年間の1on1がエンジニア組織を変えた ── 実施率100%の秘密に迫る
エンジニア組織に1on1は必要か? この問いに一つの解を示す企業がある。
世界有数の自動車部品サプライヤー、アイシングループの「アイシン・デジタルエンジニアリング」(ADE)。社員の8割がエンジニアという技術者集団が1on1を始めたのは2021年だった。
コロナ禍でのテレワーク移行により会話の機会を奪われた技術者たちは、仕事に対する不安を抱えながら、それを伝える場所を持たずにいた。また、メンバーの個性を活かした人材育成を進めるためにも、組織は対話の場を必要としていた。
顕在化した組織課題に向き合うべく同社は1on1を始め、2024年からは1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入。今では「実施率100%」を達成するなど組織に対話が定着している。
今年で5年目となる同社の1on1はなぜ形骸化しないのか。2人のキーパーソンの話から技術者集団を動かす対話の本質を探る。


心理的安全性を高める組織づくりと1on1の実践
「なぜ、部下が本音を言ってくれないのか」「雰囲気は悪くないのに、会議がかみ合わない」「頑張ってフィードバックしても、反応が薄い」ーー。
このような悩みを抱えるリーダーが増えています。職場における「心理的安全性」の重要性は広く認知されてきましたが、実際に高めようとすると、どこから手をつけるべきか分からず、漠然としたモヤモヤを抱えたまま日々のコミュニケーションが続いている組織も多いのではないでしょうか。
信頼や本音が育ちにくい背景には、職場に無意識のうちに積み重なる“静かな壁”が存在します。たとえば、報われなかった経験や、対話が設計されていない状態は、知らず知らずのうちに「声をあげない方が安全だ」という空気を生んでしまいます。
こうした課題に対して、いま注目されているのが、1on1ミーティングという「継続的な対話の仕組み」です。
上司と部下が定期的に向き合う1on1は、安心して話せる関係性を築く土台となり、心理的安全性を育て直すための有効なアプローチとして導入する企業が増えています。
本記事では、心理的安全性がなぜ損なわれるのかという根本要因から、1on1が信頼と対話をどう再構築するのかまでを、実際の事例も交えながら解説します。

なぜ1on1で悩み相談ができるようになったのか? エンジニアの心境を変えた上司の対応
「部下は私との1on1に価値を感じているだろうか」——多くのマネジャーはこんな疑問を抱えているだろう。そしてその答えはメンバーの声に隠されている。
自動車部品サプライヤー「アイシン」のグループ会社「アイシン・デジタルエンジニアリング」。エンジニアとして働く同社メンバーの森宏樹氏は、かつて1on1に懐疑的だったが、今では「部下のためのアルコールなしの飲み会」と表現するほどその価値を実感している。
ある上司の姿勢が森氏の心境を大きく変えた。業務報告で終わっていた30分が、なぜ本音を話せる場へと変わっていったのか。その過程からは多くのマネジャーが心得るべき重要な洞察が見えてくる。

【話題沸騰】「配属ガチャ」は消滅するのか。今問う人事異動の価値
「配属ガチャ」という言葉が広がっています。入社時の配属先をはじめ、会社によって一方的に決められる人事異動やジョブローテーションを指すネットスラング発祥の用語。今や一般紙でも使われるなど、市民権を獲得しています。
自身のキャリアが「運任せ」となってしまう配属ガチャという、かつて「当たり前」の人事慣行が今となっては若手社員の離職要因になっています。
それを受けて配属ガチャを廃止し、入社時に配属先を確定させる採用へと切り替える企業が相次いでいます。
配属ガチャは絶滅するのでしょうか。そうとも言いきれません。
むしろ、ポスティング(手挙げ式)の異動が広がり、配属ガチャが減っている今だからこそ、会社主導による人事異動が再評価されるようになりました。
そこで各社の動向を踏まえながら、改めて人事異動の意義を深掘りしていきます。