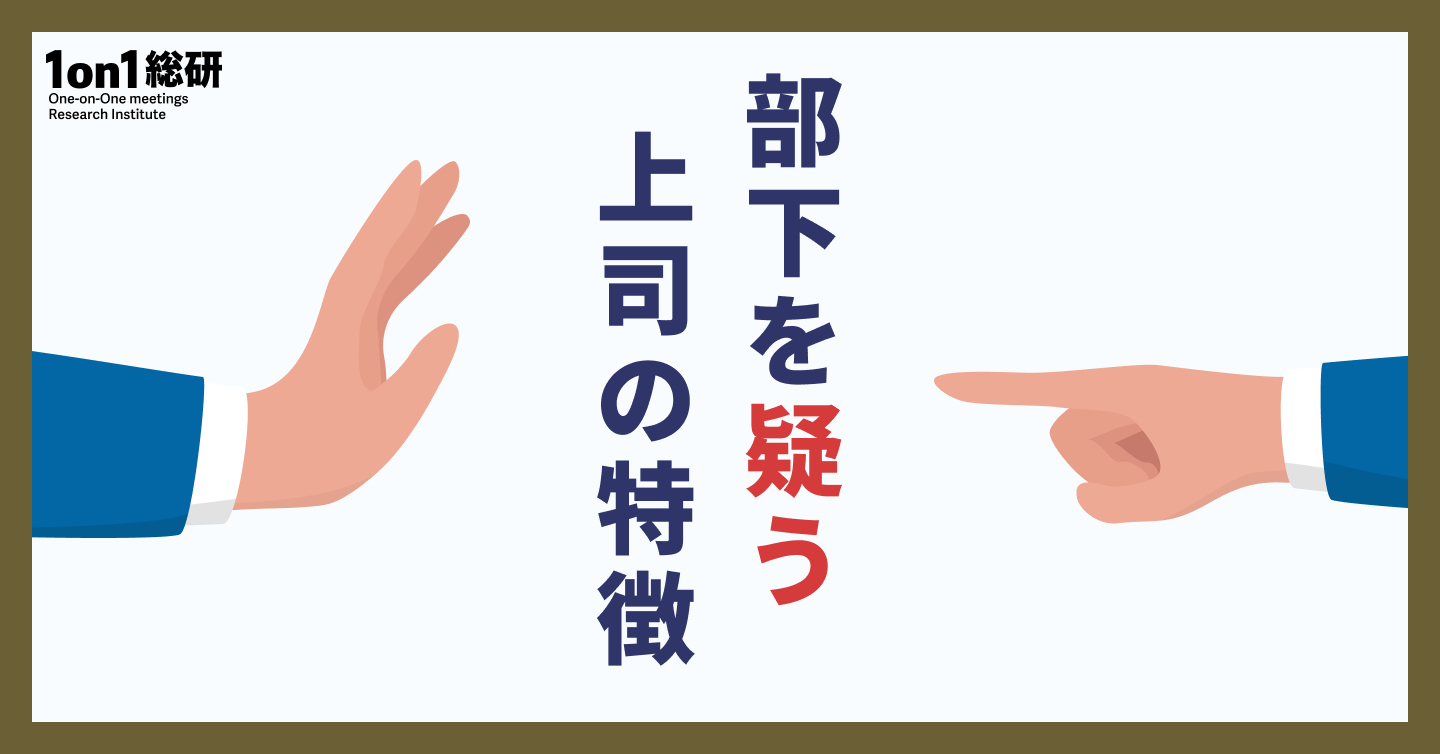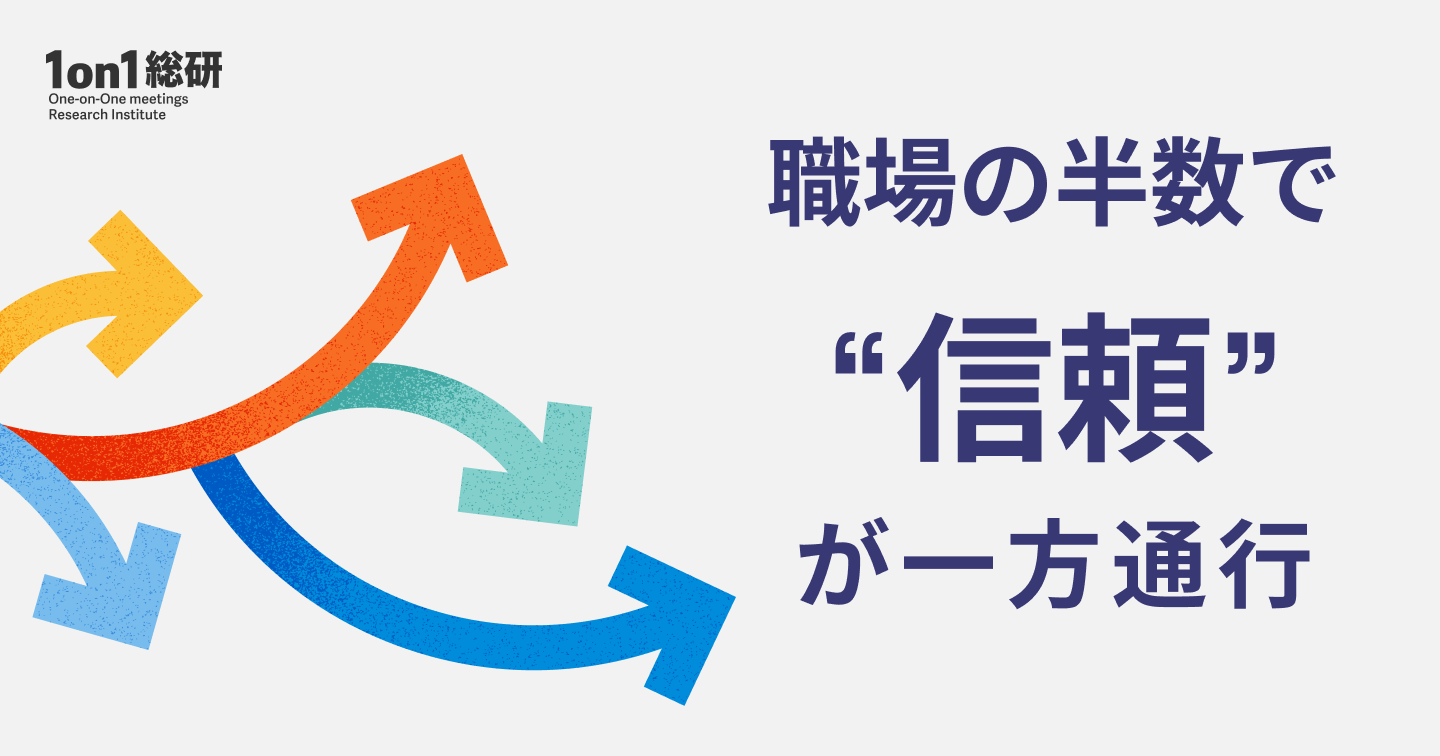組織を動かす
“役割の見直し”では、もう足りない──マネジャーを苦しめる構造の正体~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(前編)
「マネジャーとはこうあるべきだ」——そうした理想にふりまわされ、現場を支えるマネジャーが、多忙と疲弊にさらされている。多くの企業がこの状況に危機感を覚え、マネジャーの役割や業務の見直しに着手しているものの、現場の抜本的な変化につながっていないのはなぜか。
リクルートワークス研究所による報告書『マネジメントを編みなおす』では、その原因を「機能」への視点が抜け落ちていることに求めている。本記事では、同報告書の調査内容と、本研究プロジェクトを主導した辰巳哲子氏(リクルートワークス研究所・主任研究員)へのインタビューをもとに、マネジメントの再定義に向けた視座を提示する。
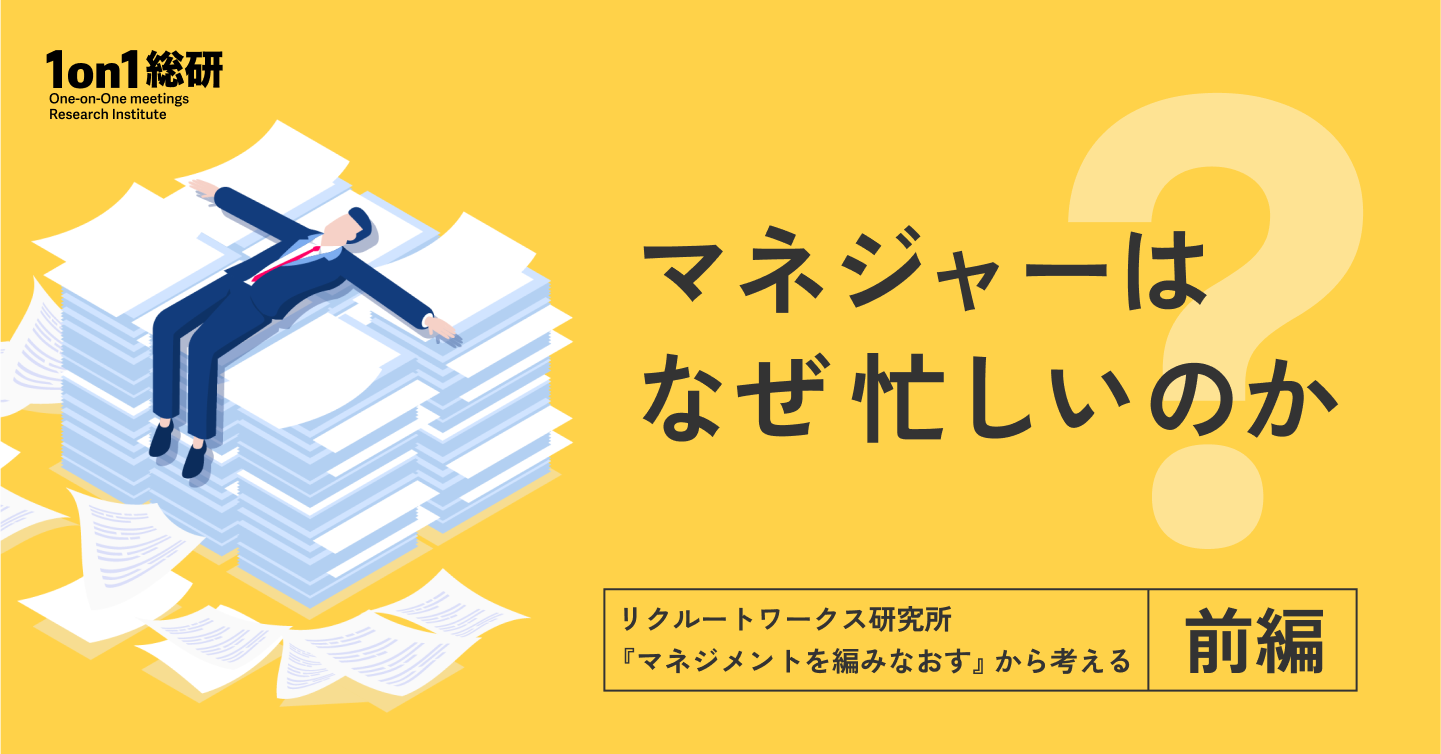
【必見】AI時代の「キャリアデザイン」完全ガイド
近年「同じ会社で定年まで勤め上げれば安泰」という終身雇用の常識が崩れただけではありません。生成AIの進化により、私たちの「存在意義」そのものが問われる時代がやってきました。
例えば、OpenAIのガバナンス研究者であるダニエル・ココタイロを筆頭にしたAI研究者チームは、2027年までのAI発展について詳細な予測を公表し、「今後10年間の超人的AIの影響は、産業革命の影響を凌駕するほど非常に大きなものになる」という見解を示しています。
特に、これまで人間が行ってきたホワイトカラーの仕事の多くがAIやロボットに置き換わっていくことが予測される中で、私たちはどのように「自分らしさ」を見つけ、それを仕事にしていくのかという視点が強く問われています。
時代の変化が加速する今、キャリアデザインは将来を見据えた計画という枠を超え、変化に対応しながら自分らしく働き続けるための大切な指針となっています。
✏️ あわせて読みたい
・【プロパー上司の新常識】中途部下のキャリア開発「虎の巻」
・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法
・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

【2025年版】チームビルディングとは?効果的な進め方と実践例を完全解説
現代の企業経営では、もはや個人の能力だけに頼っていては、激しさを増す競争社会を勝ち抜くことが難しくなっています。技術革新や市場ニーズの変化が激しい今、求められているのは「個の力」ではなく、「チームとしての総合力」です。
特に、価値観やバックグラウンドが異なる多様なメンバーが集まる職場においては、それぞれの知識やスキルを掛け合わせ、協働によって高い成果を出す力が不可欠です。
一方で、実際の現場では、人間関係の不和やスキルのミスマッチ、目標の不明確さといった要因が、生産性の低下や組織内の摩擦を引き起こすケースも少なくありません。
こうした課題を乗り越え、メンバー一人ひとりの能力や個性を最大限に活かしながら、共通の目標に向かって協力できる「理想的なチーム」を育てていく。その土台として、チームビルディングの重要性が今、改めて注目されているのです。

部下はなぜ学ばないのか? 日本企業のリスキリングがうまくいかないこれだけの理由
一人ひとりのスキルを起点に仕事や育成を考える「スキルベース組織」への転換が進む今、マネジャーに求められるのは「部下のリスキリングの伴走者」としての姿勢だ。
これまで単なる個人の自己啓発として捉えられていたリスキリングは、欧米式の企業戦略と密接に結びつく「組織的な取り組み」へと進化している。社員のスキルを見える化し、本人のキャリア志向と会社の方向性を接続する。その鍵を握るのが、マネジャーの日常的な1on1だ。
この記事では、リスキリングの第一人者であるジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表の後藤宗明氏のインタビューから、マネジャーがいかにして部下の成長と会社の未来をつなぐ存在になれるかを探る。

後藤 宗明(ごとう むねあき)
一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事 SkyHive Technologies 日本代表
2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。現在日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。

「学ばない上司」は部下に捨てられる。管理職のリスキリング戦略
部下には学びを求めるのに、自分は学んでいない——、そんな管理職は少なくない。
スキルベースで組織をつくる流れが加速し、リスキリングは企業にとって避けられないテーマになっている。しかし、部下の成長を促す立場にあるマネジャー自身が「学ぶこと」から距離を置いてはいないだろうか。
「学んでいない上司に、部下はついてこない」。そう語るのは、リスキリング支援を通じて数多くの企業変革に携わってきた後藤宗明氏だ。経営と現場をつなぐマネジャーこそが、変化の先頭に立たなければならない。
本記事では、管理職がなぜ・何を・どう学ぶべきかを掘り下げるとともに、リスキリングによって事業構造を変えた中小企業の実例や、組織に働きかける具体的なアクションまで、実践的な処方箋を紹介する。

後藤 宗明(ごとう むねあき)
一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事 SkyHive Technologies 日本代表
2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。現在日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。

「みんなが主役」の船を作る。博報堂ケトル嶋浩一郎氏に学ぶ、現代の合意形成リーダーシップ
現代社会は「合意形成」そのものが困難な時代を迎えている。政治の世界では分極化が進み、SNSでは対話を欠いた議論が平行線をたどる。家庭では親子の価値観にずれが生じ、地域社会では多様な利害の調整が課題となっている。
企業も同様だ。かつては比較的同質的な価値観を持つメンバーで構成されていたが、今や異なる世代、多様な背景、様々な人生観を持つ人々が同じ職場で働いている。
従来のトップダウン型意思決定や暗黙の了解に基づく業務進行は機能しにくくなり、多様性を前提とした新しい形の合意形成が求められている。組織の目標と個人の価値観、上司の期待と部下の希望──これらの間に横たわる溝を埋め、真の合意を生み出すことが現代ビジネスリーダーの急務となった。
新シリーズ「ディープ・コンセンサス」は、表面的な妥協ではなく、厳しい対話を通じて本質的な合意を築く技術を探求する。
第一弾として、30年以上にわたり業界の壁を越えた合意形成を実践してきたPRのプロフェッショナルで、「本屋大賞」の立ち上げ、運営への参画、さらには博報堂ケトルでの数々の地方創生プロジェクトを通じ様々なステークホルダーと関係を築いてきた嶋浩一郎氏に話を聞いた。
(構成:樫本倫子 撮影:南 阿沙美)

【社員のタイプ別】「静かな退職」への現実的マネジメント術
辞めるわけではないが、仕事への意欲を失い、必要最低限の業務しかしなくなる──。そんな「静かな退職(Quiet Quitting)」が組織課題として注目されている。黙って与えられた仕事だけをこなす姿勢は、短期的には問題が表面化しづらいが、放置すればチームの熱量を奪い、組織の推進力を損なうリスクがある。
働き方の多様化やキャリア観の変化を背景に、「静かな退職」に至る理由は一様ではなくなっている。マネジャーは、こうしたメンバーとどう向き合えばいいのか。必要なのは、価値観を否定せず、現実的な対話と実務的な工夫によって、チーム全体の熱量を維持することだ。この記事では、その考え方と具体的なアプローチを提案する。
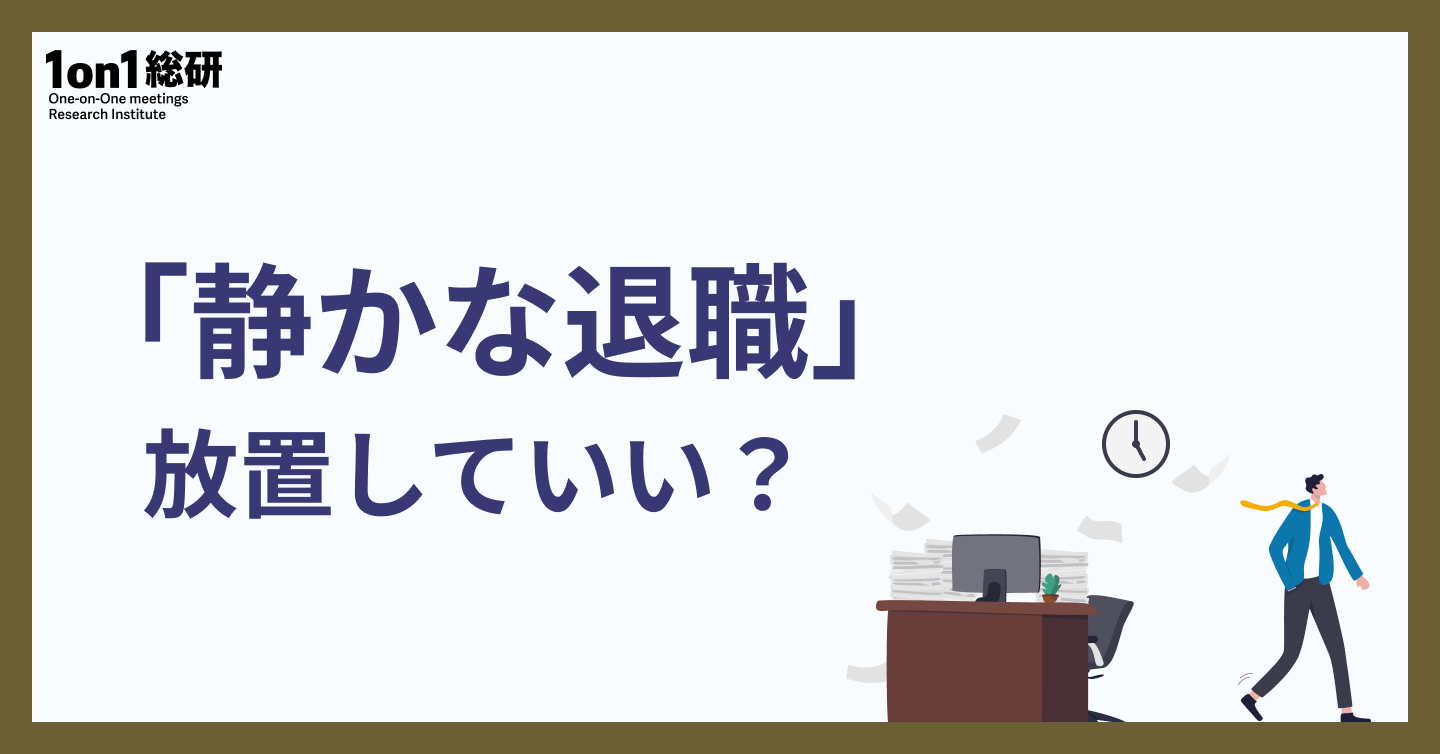
どうすれば相手から信頼されていると思えるのか? 職場の人間関係の新常識
「部下が何を考えているかわからない」「上司が自分を認めてくれない」——職場における信頼関係の構築は、多くの企業が抱える課題だ。
パーソル総合研究所と九州大学が304名の管理職とその部下1,848名を調査したところ、職場の半数以上で信頼関係に問題があることが判明した。しかし同時に、信頼関係を改善するための具体的な道筋も見えてきた。
本調査に基づき、本記事では以下の三つを解説する。
① 「相手から信頼されている」と実感する条件
② 1on1が信頼関係に与える意外な影響
③ 部下を信頼できる上司とできない上司の決定的な違い