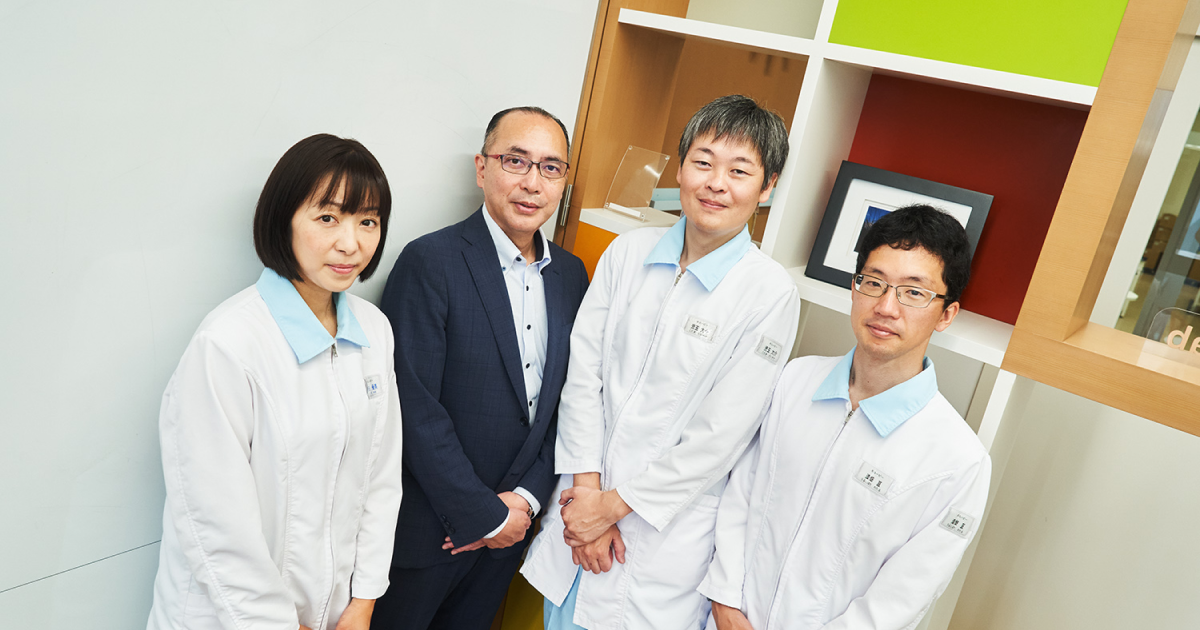「無駄な会話」から新ビジネスが生まれる。物流総合商社が重視する1on1の力

代表取締役 社長 堤 秀樹 さん/営業本部 東日本支店 一般担当 課長 鈴木 圭一 さん

- 組織再編後の上司・部下の信頼関係構築
- 若手社員からの創造的発想による「付加価値」の創出
- 1on1実施の定着後に生じた「マンネリ化」と上司主導の一方的な対話
- 社員発案によるビジネスカジュアルの導入など職場環境の改善
- Kakeaiを活用したデータ分析に基づく対話の質向上に向けた改善策の具体化
物流関連の総合商社「センコー商事」。同社は「1on1」を新たな価値創造の源泉として位置づけています。
効率重視の物流業界にありながら、あえて「無駄な話」や「悪巧み」を奨励。対話文化の醸成により「意見を出したら会社が変わる」という実感が社内に広がり、オフィス環境の改善など具体的な変化も生まれています。
1on1支援ツール「Kakeai」を活用してデータに基づいた質向上にも取り組む同社の事例から、対話を通じた組織変革のヒントを探ります。
Q:貴社が上司と部下の対話を重視する背景を教えてください。
あらゆる仕事の基礎となる「上司と部下の信頼関係」の構築に向けて。
堤社長:昨年組織を再編し、会社のビジョンと各部門のアサインメント(役割・課題)を明確にしました。アサインメントは、部門、チーム、担当者と細分化されていきます。最小単位である担当者が役割を全うするには上司のサポートが必要です。各担当者にとって上司との信頼関係は全ての土台であり、そこが崩れると仕事は成り立ちません。
私は1on1を信頼関係の構築を支える非常に重要な取り組みと捉えています。この考えの背景には、ドイツに赴任していた前職時代の経験があります。
ドイツ時代のメンバーは、私との対話を積極的に求めてきました。彼らは1対1のコミュニケーションの場で自分の考えや行動を共有し、それらに対する私からのフィードバックを強く期待していました。日本の暗黙的なコミュニケーションとは異なり、フィードバックがなければ不機嫌になることもあります。この時の経験から、上司と部下による深い対話は組織運営に欠かせないと確信しました。
Q:1on1を通じてどのような組織文化を育てたいとお考えですか?
「無駄」を恐れず、自由な発想を尊重する文化へ。
堤社長:「無駄」や「遊び」を大事にする姿勢が組織全体に広がってほしいと願っています。コロナ禍ではあらゆる業界で効率重視のウェブ会議が増え、仕事に直接関係しない会話が減ってしまいました。しかし、一見「無駄」に見える雑談こそ新しい発想の源泉となります。
そんな自由な対話を促し、様々な話題から創造的な発想が生まれる文化を育みたいと思っています。効率だけを追求すると、1on1も単なる業務報告の場になってしまいます。

Q:御社のビジネスに「無駄」や「遊び」はどう生かされているのでしょうか?
面白い「企み」がビジネスを前進させる付加価値を生み出す。
堤社長:センコーグループの基幹である物流事業では、安全・正確・迅速さが求められるため、現場ではマニュアルを遵守し、上司の指示に従うことが最も効率的といえます。余計なことを考えない方が仕事もスムーズに進みます。
一方、総合商社である当社は、付加価値の創出が不可欠です。社員が「余計なこと」を考えなければ、新しいビジネスは生まれません。
当社のビジネスを「実行」と「仕込み」の二段階に分けた場合、「実行」段階では効率を重視し、計画通りに進めます。明日の業務は明確に定義すべきです。他方、「仕込み」段階では自由な発想で様々な可能性を議論するのが望ましい。一年後のビジョンは多角的に検討し、面白いアイデアを生み出す余地が必要なのです。
だからこそ社員には、「遊び心のある“悪巧み”をしたり、面白いアイデアをどんどん仕掛けていきましょう」と声をかけています。特に若手や中堅社員には、単なる売買だけでなく、創意工夫で付加価値を生み出す「企み」をしてほしい。そういったアイデアを自由に話せる場としても1on1を活用してほしいと考えています。
Q:センコー商事は2021年から1on1を全社導入しています。現在の実施状況はいかがでしょうか。
実施率は高いものの、質の向上が次の課題。
堤社長:5年目を迎えた現在、実施率は100%に近く、「定着」という目標は達成しつつあります。その一方で、マンネリ化の声も聞こえてくるなど、「対話の質」については課題も見え始めています。
自戒を込めて言いますが、人間、上の立場になると、自分ばかりが話しがちになります。沈黙を嫌がる文化が対話をさらに難しくさせています。
そうならないよう、上司役の人間には「できるだけ聞き役に徹してください」とアドバイスをしています。1on1の時間を充実させるためには、マネジャー陣の傾聴力を高めないといけません。

Q:対話の質の向上を含め、1on1を全社展開する上で「Kakeai」がお役に立っていることはありますか?
対話の記録保存、実施率の可視化、組織課題の特定など、1on1の質向上に貢献。
鈴木さん:1on1推進者の立場でお答えすると、「Kakeai」の最大のメリットは、1on1の履歴が残ることです。上司・部下ともに、以前の対話内容を簡単に振り返ることができます。
また、実施率の集計や可視化も容易になりました。今では正確なデータをすぐに取得できます。
組織全体の傾向分析も可能になりました。堤社長からも対話の質に関する話がありましたが、データを分析すると「上司は1on1がうまくいっていると思っている一方で、部下はそう感じていない」「上司が一方的に話している」といった具体的なギャップが見えてきました。
このような課題が明確になったことで、「オフィスに限らず、歩きながら1on1をしてみる」といった、従来とは異なる視点からの発想も生まれきてそうです。

堤社長:見える化ツールとしてのKakeaiは、1on1の質を高める上で非常に役立っています。「前回はこの話をした」「次回はこのテーマを扱おう」といった計画が立てやすく、同じ話題の繰り返しを避けることができます。
対話の内容を積み上げていくことで、1on1の価値を高められると考えています。
Q:1on1の継続により社内では何かしらの変化が生まれていますか?
「提案すれば会社は変わる」という実感が社内に広がりつつある。
堤社長:1on1の導入以来、組織内の対話が少しずつ活発化し、以前と比較すると社員から多様な意見が寄せられるようになりました。
具体的な成果としては、社員の提案によるビジネスカジュアルの導入など働きやすさの向上や、気候変動への適応、健康経営の改善が実現しました。社員が自ら働きやすい環境を作っていこうとする流れが生まれたことは、1on1を継続してきた効果だと実感しています。
鈴木さん:昨年まで当社にはコミュニケーションのための専用スペースがありませんでした。しかし社員からの要望と社長の意向を受け、2024年5月の本社オフィスレイアウト変更に合わせて、フロア内にコミュニケーションスペースを新設しました。コーヒーマシンやウォーターサーバー、カウンターなどを設置し、気軽に集まれる場所となっています。

堤社長:実際にこういう空間ができてみて強く感じるのは、対話環境の重要性です。1on1をするにも日常の業務デスクでは限界がありますし、同僚が密集するオープンスペースでは本音を話しにくい。社員たちからの提案は、まさに私たちが必要としていたものでした。
鈴木さん:コミュニケーションスペース設置後、異なる部門のメンバー同士がコーヒーを片手に会話する光景が日常的になってきました。設置したコミュニケーションノートにも自発的な書き込みが増え、社内のコミュニケーション文化が変わってきたと感じています。
何より価値があるのは、「意見を出したら会社が変わる」「自分たちのやりたいことが実現する可能性がある」という実感が社員の間に広がっていくことです。社長からの「意見を出してみよう」というメッセージが、こうした前向きな変化を後押ししています。
Q:今後、1on1をどのように発展させていきたいですか?
若手の声が組織を変える文化の定着へ。
堤社長:センコーグループは実行力の高い会社ですが、その強みを活かすには新しいアイデアを生み出す文化も育てる必要があります。今後も1on1の質を高めながら、組織全体の発想力を向上させていきたいと思います。
現場の最前線に立つ社員はお客様との接点でもあります。彼らの声がしっかりと社内に上がってくることで、当社のビジネスの質は高まっていくでしょう。1on1を形骸化させず、社員一人ひとりが主体的に考え、付加価値を生み出せる組織を目指していきます。
※上記事例に記載された内容は、2025年04月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。