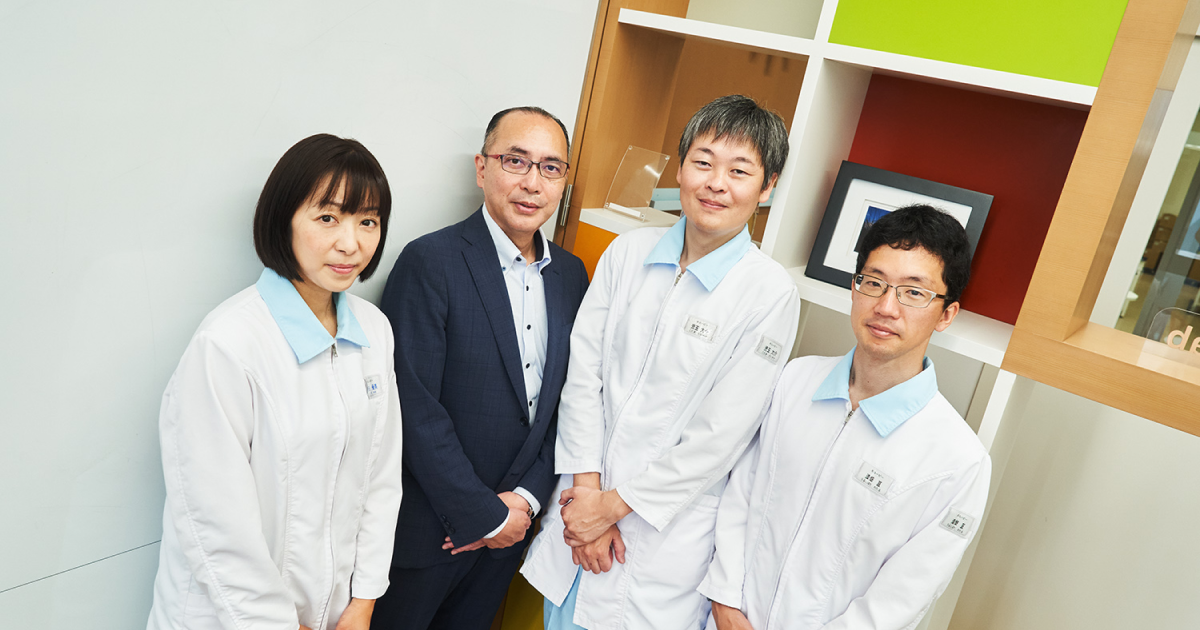3拠点を結ぶ1on1 ── 役職&職種を超えた対話が組織を強くする

人事戦略部 斎藤由雅さん/齊藤寛加さん

「決められた相手」から「選べる対話」へ──。スタッフが自由に1on1の相手を指名できる仕組みを導入した仙台消化器内視鏡内科はじめのクリニック。3拠点を構える同クリニックでは、各拠点に分散する多職種のスタッフ間で月80回以上の1on1が行われるなど、新たな対話文化が根付きつつあります。なぜ従来の1on1の形式を大きく変更したのか。職種や役職に捉われないコミュニケーションを推奨する同クリニック人事戦略部に話を聞きました。
Q:貴院では職種や役職を超えた「斜めの1on1」を実施しています。このような形態を採用している理由を教えてください。
相談相手を自由に選ぶことで、より本音の対話を促すため。
斎藤由雅さん:当院には看護師、医師、医療事務、総務課など、様々な職種のスタッフが在籍しています。
以前は360度評価で高い評価を得たスタッフが「サーヴァント」という立場に選ばれ、各スタッフは同じ職種のサーヴァントと1on1を行うことが義務付けられていました。
しかし、この制度ではスタッフは相談相手を選べず、本当に相談したいことを話せる関係性を築けているか定かではないという課題がありました。
そこで大きな方針転換を行い、職種や役職に関係なく、自分が話したい相手と1on1を実施する仕組みに移行しました。
これは、スタッフ一人ひとりがやる気に満ちあふれ、互いの得意分野を活かしながら本音で対話できる組織を目指すという院長の考えに基づいています。ただし、医師については業務に専念する方針となっているため、医師以外のスタッフ間で1on1を実施しています。

Q:実際に職種や役職を超えた1on1を実施してみて、どのような変化が見られましたか?
職種を超えた対話が可能になり、より相談しやすくなった。
斎藤由雅さん:最も大きな変化は、より本音の対話ができるようになったことです。例えば看護師の中には、あえて看護師以外のメンバーと1on1を行うケースも出てきました。普段一緒に働かない相手の方が、悩み事を相談しやすいという声もあります。
齊藤寛加さん:毎月話す相手を変えるスタッフも増えましたね。相談相手によって、プライベートな悩みを打ち明けたり、キャリアについて相談したりと、対話の内容も多様化しています。
Q:医療現場では日々の業務に追われ、1on1の時間の確保が課題となることが少なくありませんが、貴院はいかがですか?
1on1が組織文化として定着し、時間を確保することが「当たり前」となっている。
斎藤由雅さん:当院では月80回ほどの1on1が実施されていますが、この量の多さは「月1回は必ず誰かと1on1を行う」という組織文化に支えられています。
この文化は、かつての人事戦略部のメンバーや先輩方が築いたもの。そのおかげで、当院では各スタッフが1on1を「当たり前のこと」として捉え、業務中に時間を確保しています。
16時以降など現場が落ち着いたタイミングに実施するケースが多く、当日の業務状況を見ながら「今日いいですか?」と声を掛け合って調整しています。業務時間外に1on1を実施することはなく、スタッフ全員が協力し合い、30分の時間を捻出しています。
ちなみに当院では、1on1の際に1000円の補助金が支給されます。昼休みに実施する場合はランチを共にしたり、業務の合間にはお茶を飲みながら話をしたりと、リラックスした雰囲気で対話できる環境を整えています。
Q:人事戦略部は1on1運営にどのように関わっていらっしゃいますか?
実施状況を管理し、未実施者のフォローを行っている。
斎藤由雅さん:人事戦略部は、採用活動、新人教育、評価制度の仕組みづくりを担当しています。
1on1に関しては、Kakeaiの管理者として毎月の実施状況を確認し、必要に応じてフォローを行っています。例えば、医療事務スタッフが3カ月連続で1on1を実施していない場合は、その職種のマネージャーと連携して対応を検討します。
また、トークテーマの選択傾向も分析しており、「人間関係」や「業務内容」が多い一方で、「キャリア」に関する対話が少ないことなども把握しています。
Q:Kakeaiは、どのような点でお役に立っていますか?
相手に求める対応を事前に伝えられることによる、より良い対話の実現。
齊藤寛加さん:「話を聞いてほしい」など相手に期待する対応を事前に伝えられるサービスは、特に先輩に対して要望を伝えにくい若手スタッフに好評です。
「今日は一緒に相談に乗ってください」とか「今日はただ私の話を聞いてください」といった要望を、先輩などに口頭で伝えるのはためらわれます。それを1on1を設定する中で、自然な形で伝えられるのはとても便利だと感じます。

斎藤由雅さん:Kakeaiは使い方の幅が広いと感じています。「アイスブレイク」や「ホワイトボード」「画像共有」などがあり、あっさりと1on1をしたい人もいれば、じっくり話したい人もいる中で、それぞれのニーズに合わせた使い方ができる自由度の高さが良いと思います。
個人的には、自分や相手の特性を確認できる「セルフアセスメント」が特に気に入っています。同僚が評価を更新すると通知が届き、「ここが変わったんだ」と気づきを得られる機会になっています。また、プロフィール画面では、「もっと知りたい!」と相手に伝えることができます。機能を通じて、同じ相手から複数回押してもらうこともあり、継続的な対話のきっかけにもなっています。
Q:今後1on1をどのように発展させていきたいですか。
コミュニケーションの質を高め、組織の成長につなげる。
齊藤寛加さん:当院では1on1の目的を「業務を離れた部署横断的なコミュニケーション」と「360度フィードバックを通じた人格的成長支援」の二つと位置付けています。これらを軸に、1on1の質を高めていきたいと考えています。
当初は気軽な対話の場として始まった1on1ですが、組織の成長とともにより戦略的な活用へと進化させています。
今後は1on1の目的をスタッフに再周知するとともに、効果的な話し方や聞き方、フィードバックのスキルに関する勉強会も計画中です。これらを通じて、組織全体のコミュニケーションの質の向上を目指しています。
Q:1on1の質の向上を進める上で課題はありますか。
キャリア対話の不足、質の評価方法が課題。
斎藤由雅さん:主に二つの課題があると考えています。
一つ目は、キャリアに関する対話の促進です。Kakeaiで選択される話題を見ると、「人間関係」や「業務内容」が多く選ばれる一方、「キャリア」についての対話はほとんど見られません。当院は若手スタッフが多く、師長や副師長といった役職を置かない組織体制のため、キャリアという概念自体がまだ遠い存在に感じられているようです。
総合病院からクリニックへの転職は、必ずしもキャリアアップを目指して行われるわけではなく、現在の生活を大切にしたいという思いから選択されることも少なくありません。しかし、当院は3つの拠点を持ち、規模も拡大している組織です。今後さらなる成長を目指すためには、スタッフ一人ひとりがキャリア形成について考える機会を増やしていく必要があります。
二つ目は、1on1の質の評価方法の確立です。現在は実施状況の確認が中心ですが、今後は満足度や実施後の行動変容なども含めた多角的な評価方法を検討していく必要があります。1on1がクローズドな対話である中で、どのように質を測定し、向上させていくかは大きな課題です。
これらの改善に取り組みながら、職種を超えた対話を通じて個々の成長を支える組織文化を、さらに深化させていきたいと考えています。

※上記事例に記載された内容は、2025年02月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。