長期視点で社会課題解決に取り組むキユーピーの基礎研究部門「未来創造研究所」。成果が見えるまでに10年かかることも珍しくない世界で、メンバーのモチベーションをどう維持するのか。専門性がリーダーを上回るメンバーをどうマネジメントするのか。
同研究所は基礎研究組織特有の課題に対し、対話を重視した組織づくりで向き合い、高いエンゲージメントを実現。リンクアンドモチベーション主催の「Motivation Team Award 2025」で優秀賞を受賞しました。
メンバー一人ひとりが主体的に研究に取り組める組織をどのようにして作り上げたのか。その実践に迫ります。
業界:食品
従業員数:1001名~3000名
課題
- 組織変革に伴うメンバーの不安の解消
- 組織的な相互理解の不足
- 長期間の基礎研究におけるモチベーション維持
成果
- 心理的安全性の構築と相互理解の促進
- 従業員エンゲージメントの向上
- 対話を通じた研究テーマの創出
糀本さんインタビュー
Q:未来創造研究所とはどのような組織でしょうか。
「三つの特長」を強みとする基礎研究組織
糀本さん:当研究所はキユーピーグループの基礎研究組織として、10年、20年先の社会課題の解決や価値創造につながる研究に取り組んでいます。
パーパスは「その技術から生まれるKANDOをお客様に」。ここでいう「技術」とは、単に技術力の高さを指しているわけではありません。八つのコア技術、高いエンゲージメント、共感コミュニケーション力――これら全てが私たちの競争力の源泉であり、「キユーピーらしさ」を象徴しています。
Q:未来創造研究所はエンゲージメントが高い組織として外部からも表彰されています。エンゲージメント向上に取り組み始めたきっかけは?
コロナ禍での組織変革に伴うメンバーの不安の解消
糀本さん:5年前のコロナ禍が転機でした。また、未曾有の鳥インフルエンザなど想定外の事態が続き、VUCA時代における基礎研究部門の在り方を根本から問い直す必要に迫られました。
当研究所は当時、「技術ソリューション研究所」の名で比較的短期視点の研究テーマと向き合っていましたが、経営層と対話を重ね、より未来志向の「未来創造研究所」へと組織を再定義しました。

組織の役割が大きく変わることに、メンバーは不安を抱えていました。「仕事の在り方も変わってしまうのか」「私たちの立場はどうなるのか」。コロナ禍の混乱期に加えて組織変革の不安が重なり、メンバーの心は揺れていました。
このとき改めて自らのリーダー観と向き合いました。私には「この世に生まれてきた人は誰もが無限の可能性を秘めている」という信念があります。不安を抱えるメンバー一人ひとりの可能性をいかに引き出し、新しい組織でその人らしく活躍してもらうか。それがリーダーの役割と考え、エンゲージメント向上に本格的に取り組み始めました。
Q:エンゲージメント向上に「対話」が重要だと考えた理由は?
相互理解の基盤となるため
糀本さん:技術系組織には独特の構造的課題があります。多くの技術者は、技術研究に打ち込みたくて入社します。しかしキャリアを重ねると管理職を任され、不得意なチームマネジメントと向き合いながら不安を抱えます。
さらにその不安を拡大させるのが専門性の複雑さです。一つの専門領域の中には複数の専門分野が存在します。リーダーがある分野の専門家でも、別の分野ではメンバーの方が圧倒的に詳しいことが珍しくありません。
この「専門性の逆転現象」により、リーダーは「どうやってリードしていったらいいのか」と悩み、メンバーは「なぜリーダーは自分の技術を理解してくれないのか」とフラストレーションを感じてしまうわけです。

私は異業種のCTOが集まる会合に月1回参加していますが、この構造的課題は業界を超えて共通していることを実感します。
こうした環境下で、メンバー一人ひとりが主体的に未来創造に取り組むには、相互理解が欠かせません。その基盤を築くのが対話だと考え、組織全体で対話が生まれるよう、様々な取り組みを進めることにしました。
Q:相互理解を進める対話の取り組みとは具体的にどのようなものでしょうか?
経営層とメンバーをつなぐ対話の場など
糀本さん:「1on1」以外の象徴的な取り組みを紹介すると、メンバーと経営層が直接対話する機会を設けています。
具体的には二つの場があります。一つは経営層全員が集まる中でメンバーが未来創造研究所ならではの提言を行う場。もう一つは投資担当の経営層とメンバーによる対話の場。グループや業界の将来について長期的な視点で話し合います。
これらの対話を有意義な時間にするためには入念な事前準備が欠かせません。そのサポートをリーダーが担います。メンバーと事前に対話を重ね、経営の考えを分かりやすく伝えたり、メンバーの声を経営層に届く形に整えたりします。
このプロセスには相当な時間をかけていますが、丁寧に進めることでメンバーと経営層の真の相互理解が生まれ、経営層からの共感や応援を得られます。同時に、この事前準備のプロセス自体がメンバーとリーダーの深い対話の場となっています。

Q:様々な対話の仕組みがある中で、1on1はどのような位置付けなのでしょうか?
相互理解を深める定期的な対話の場として不可欠
糀本さん:1on1は組織エンゲージメント向上施策の一つですが、他とは異なる独自の価値があります。
4年間実施してきて分かったのは、業務の話だけでなく、普段なかなか話せない内容も含めて対話できる場として1on1が不可欠ということです。定期的に時間を確保し、1対1で向き合うからこそ、相互理解が格段に深まります。
また、技術系組織において1on1はメンバーのための時間であると同時に、リーダーの成長の場でもあります。メンバーとの対話を通じて、リーダー自身が自分の役割を見つめ直し、成長する。その意味で、1on1は組織全体の成長を支える重要な仕組みであると考えます。
Q:Kakeai導入の決め手は?
パーパスへの共感
糀本さん:一言でいえば「共感」です。KAKEAI社のパーパス「あなたがどこで誰と共に生きようとも、あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない」を見たとき、「私の思いと一緒ではないか」と強く感じました。
実務面では、施策の結果を定量的に把握したいという思いがありました。そこで既存のエンゲージメント測定システムも活用しながら、エンゲージメントスコアとKakeaiのデータとの相関を捉え、そこから課題を設定しアクションしていく取り組みを、チームリーダー同士が対話をしながら進めています。定性だけでなく定量でも結果を見られると、活動の質も高まっていきます。
Q:1on1の運用における工夫はありますか?
心理的安全性を最優先して「距離を取る」
糀本さん:個々のメンバーの面談内容はあえて報告を受けないようにしています。詳細が所長に伝わるとなれば、メンバーは忖度するかもしれません。チームリーダーもメンバーも信頼できる人ばかりですし、1on1では変な力学が働かないようにしたい。心理的安全性の確保が最優先です。

Q:対話の定着を通じて目指す組織像を教えてください。
「自分ブランド」を持つ個が協創する組織
糀本さん:最終的には、メンバー一人ひとりが「自分ブランド」を高めていける組織を目指しています。技術系組織でいえば「専門性×人としての魅力」の掛け算。高い専門性を持ちながら、周りが一緒に研究したくなる人材の集合体でありたい。
価値観も専門性も多様な人たちが「未来に向かって新たな価値を生み出していくぞ」と本気を出したら、計り知れない力が生まれるはずです。
そして対話の力は組織内に留まりません。食を取り巻く社会課題を解決するには、産学官との共感度を高め、エコシステムを形成することが不可欠です。対話は社会課題解決につながる力を秘めています。その意味でもKAKEAIには大いに期待しています。
児玉さん、竹田さん、漆畑さんインタビュー
Q:現場では1on1をどのように運用していますか?
週1回30分が基本
児玉さん:4年前、私が現職のチームリーダーに就いたタイミングで1on1を導入しました。前職時代に心理的安全性を構築する上で1on1の重要性を実感したことがきっかけです。
実施頻度は組織ごとに異なりますが、私のチームでは週1回30分を基本としています。年2回の考課面談での濃密な話し合いも大切ですが、週1回の日常的なコミュニケーションの積み重ねにも大切な価値があると考えます。

Q:組織的な1on1を4年続け、今年からKakeaiを導入しています。ツールの活用による変化は?
効率化と対話の質の向上
児玉さん:以前は手作業でメモを取っていましたが、Kakeaiで対話の内容や実施回数が自動で可視化されるようになり、記録の管理が楽になりました。
また「1on1をノーアジェンダで進めない」というルールを設けていますが、Kakeaiでは話すテーマを事前に設定できるので、この方針がより実践しやすくなりました。
竹田さん:メンバーからのフィードバックも助かりますよね。Kakeaiでは対話後にメンバーが満足度を入力してくれます。その結果から自分の対応の得意・不得意が明確になり、具体的な改善点が見えるようになりました。
これまでは1on1が本当に役立っているかわかりませんでしたが、その不安が解消されました。

Q:メンバーとしては1on1の価値をどう感じていますか?
心理的な不安を解消し、研究を前進させる場
漆畑さん:1on1の価値は上司にじっくり話を聞いてもらえること。
研究を進める中で壁にぶつかることもありますが、定期的な1on1で相談すると、社内外の詳しい人を紹介してもらえるため、困難に思えた技術的課題が意外とスムーズに解決することも珍しくありません。
また、基礎研究の世界では研究者が自主的にテーマを設定する姿勢が求められますが、1on1の場では、具体化する前のアイデアでも気軽に相談できます。
「こういうことをやりたい」と伝えると、上司は否定せず「どうすれば実現できるか」を一緒に考えてくれるため、アイデアを育てる機会になっています。
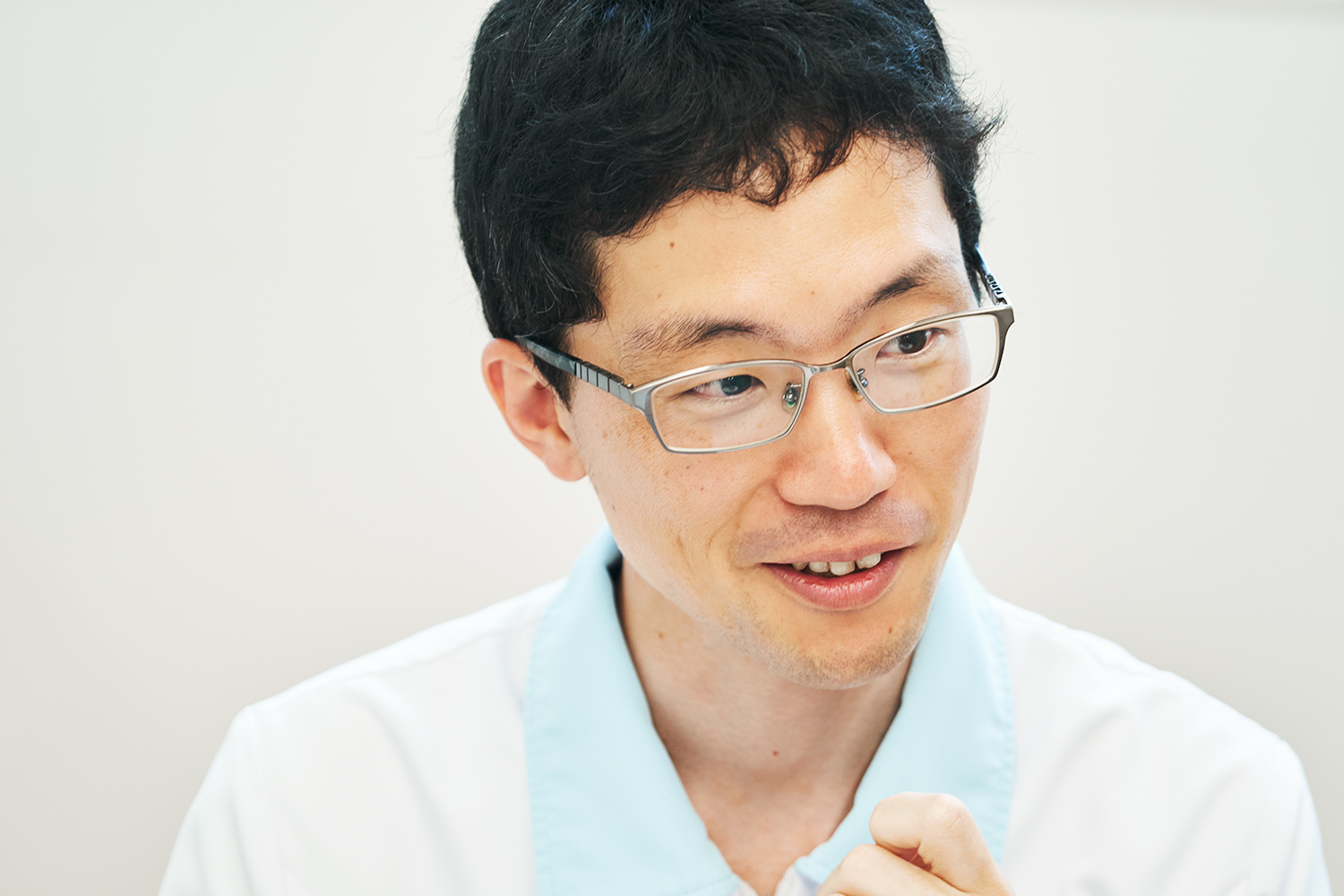
児玉さん: 実際、基礎研究の「テーマ創出」において対話は重要な役割を果たします。メンバーが1on1で語る「こんなことをやってみたい」という思いが新たな研究テーマに発展することもあれば、チーム全体の議論から生まれることもあります。
機能素材研究部では現在、40を超える研究テーマを15人で推進しています。その中にはスケールの大きなテーマも含まれます。例えば、2040年には月面で1,000人が暮らす未来が見えている中で、当社として今から何をすべきかというバックキャストでの研究など、中長期の研究テーマを多く進めています。こうしたさまざまなテーマが、日々の対話から生まれています。
竹田さん:基礎研究における対話の意義は他にもあります。研究成果がすぐに売上・利益につながらないテーマもあるため、メンバーが自らの仕事の価値を実感しにくいこともあります。そこで、チームミーティングの場で、研究成果が企業価値にどうつながるかを議論する機会を積極的に設けるようにしています。
例えば、研究発表が株価上昇につながった社内外の事例を調べてきてもらい、どういう要素が株価に影響を与えるのか、自分たちの仕事にも紐づけてみんなで話し合うのです。

児玉さん:実際当社の事例でも、2023年に「アレルギー低減卵(卵の主要アレルゲンであるオボムコイドを含まない卵)」の研究成果を発表した際、翌日に株価が上昇したことがあります。本研究の発表だけが株価上昇の要因ではなかったと思いますが、すぐには事業化の実現が難しい研究フェーズのテーマでも、その取組価値・社会的意義を発信することが企業価値向上に繋がっていくということを実感しました。
竹田さん:こうした事例はメンバーが基礎研究の価値を実感するきっかけになり、モチベーションの向上にもつながります。1on1やチームミーティングの時間では、各メンバーの研究が将来どんな価値を生み出せるか一緒に考えることも大切にしています。
Q:現場のチームリーダーとして、今後対話を通じてどんな組織を目指しますか?
個々の「心地よさ」を原動力に長期的な価値を生み出し続ける組織へ
児玉さん:理想は、一人ひとりのメンバーが「心地よさ」を感じながら、主体的に研究を進める組織へと進化することです。
糀本所長の言うところの「自分ブランド」、すなわち「専門性×人としての魅力」を持つ人材が、対話を通じて互いを高め合いながら、10年、20年先の社会課題解決に挑戦し続ける。そんな組織を実現していきたいと思っています。
※上記事例に記載された内容は、2025年06月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。

