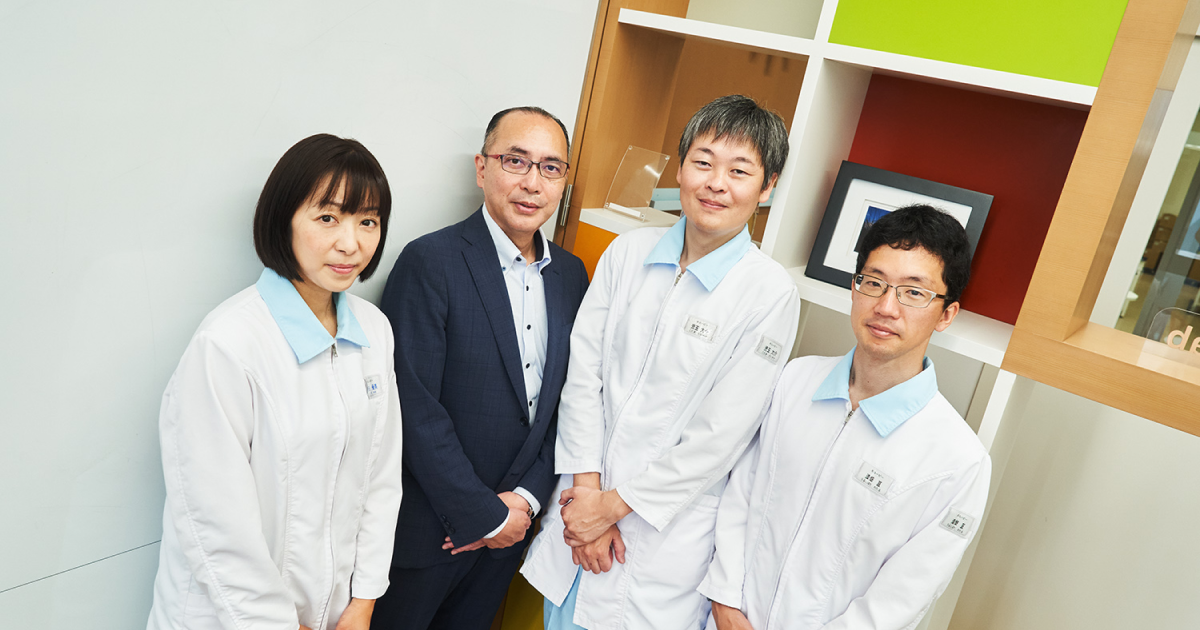1on1が変えるエンジニア組織。「技術指導」から「成長支援」への転換

デジタル技術部 第1DE推進室 熱流体系CAEグループ グループ長 安藤 隆志 さん(写真左)/デジタル技術部 第1DE推進室 熱流体系CAEグループ 森 宏樹 さん(同中央)/経営管理部 サステナビリティ推進グループ グループ長 中島 邦嘉 さん(同右)

- コロナ禍のリモートワークによるコミュニケーション希薄化
- 画一的な育成からの脱却とマネージャーのコーチングスキルの向上の必要性
- 1on1の質向上と効果測定の必要性
- 上司・部下の信頼関係構築と効果的なサポート体制の確立
- マネージャーの対話スキルの得意 / 不得意の可視化と改善機会の創出
- メンバーの自発的な相談・報告の増加とモチベーション向上
世界有数の自動車部品サプライヤーであるアイシンのグループ会社で、CAEとデータサイエンスを中心としたデジタル技術とリアルデータの融合により顧客ニーズを超える新たな価値を提供し続ける「アイシン・デジタルエンジニアリング」。社員の8割以上がエンジニアを占める同社では、コロナ禍をきっかけに2021年から1on1を全社展開しています。
初年度からアンケートを基にした改善のPDCAを回し、2024年からは1on1支援ツール「Kakeai」を導入。さらなる対話の質の向上に取り組んでいます。
4年の取り組みから見えてきた、エンジニア組織ならではの1on1のあり方とは──。
同社で1on1施策を推進・実施する中島邦嘉さん、熱流体系CAグループで実際に1on1を行う安藤隆志グループ長、安藤さんの部下であるメンバーの森宏樹さんに、それぞれの立場からの経験と気づきをうかがいました。
Q:貴社で1on1を導入した経緯を教えてください。
コロナ禍でのコミュニケーション希薄化と社員育成の課題がきっかけに。
中島さん:当社が1on1を始めたのは、コロナ初期の2021年。テレワークの普及でコミュニケーションが希薄化したことが直接のきっかけでした。
同時期に、人材育成のアプローチも転換点を迎えていました。「画一的な育成」から「社員一人ひとりの個性を活かす育成」へと方針が変わり、その実現に向けてマネジャーのコーチングスキルの向上が組織課題として浮上したのです。
そんな折に他社での1on1を知り、我々もやってみようとなりました。
当時私は新任マネージャーとして、リーダーシップの発揮の仕方に悩んでいました。トップダウンで方針を示し、力強くチームを牽引しようとしても、うまくいかないだろうと。
そこで1on1に可能性を見出しました。メンバー一人ひとりの「答え」を引き出し、対話を通じてチームをまとめられるのではないか──そんな期待が生まれたのをよく覚えています。

安藤さん:実際、エンジニア組織ではマネージャーに求められる役割が大きく変わってきています。
かつてのマネジャーは技術的な「答え」を熟知し、部下に見本を示す教育的立場でした。しかし、技術革新のスピードが加速した今、もはや上司が全ての「答え」を持つことは不可能です。むしろゴールに一番近いのは、最前線で技術と向き合う現場のメンバーたちです。
この変化により、私たちマネージャーは「答えを教える人」から「メンバーの成長をどう支援するか」「チームの仕事をどう円滑に進めるか」を考える立場へと移行しています。
私自身、以前は「答え」を全て教えてしまうタイプで、「安藤がいると後輩が育たない」と当時の社長から直接指摘されました。転機となったのは、自分の専門外のグループを任されたこと。技術を教えられない状況で、必然的にメンバーをサポートするスタイルへと変わっていきました。

中島さん:安藤さんの話に補足をすると、当社のエンジニアのメンバー時代は専門性を磨きますが、マネージャーになると専門外の領域を任されることがあります。自分が技術的に詳しくない分野のリーダーになると、「答え」を教えることはできません。必然的に「チームをまとめる」「メンバーを育成する」ことに注力することになります。
各マネージャーは試行錯誤しながら自分なりのスタイルを見つけていくわけですが、その過程で1on1は、メンバーの考えを引き出し、時に背中を押す重要な場として機能します。
Q:御社は2024年から「Kakeai」を導入していますが、その理由を教えてください。
データ分析に基づく1on1の質向上を目指して。
中島さん:1on1を開始した2021年からの3年間は、基本的に月1回・30分の対話を、マネージャーが主導して設定、実施してきました。その効果測定として、半期に一度メンバーからアンケートを収集し、マネージャー全員で振り返る場を設けていました。
しかし、この方法には限界がありました。半年間隔でのフィードバックは、記憶に新しい直近の出来事に偏りがちで、長期的かつ本質的な改善点を見出しにくかったのです。
Kakeaiの大きな魅力は、メンバーの声やマネージャーの対応データをリアルタイム性高く収集・分析できること。Kakeaiの導入により、1on1の「質」に焦点を当てた改善サイクルを回せるようになりました。
Q:「Kakeai」の導入により1on1にどのような変化がありましたか?
事前準備、履歴管理、データ分析の3点で1on1の質が向上。
中島さん:Kakeaiが私たちの1on1を変えた点は主に三つあります。
一つ目は、メンバーが事前に話したいテーマを選択できること。「1on1で何を話せばいいですか?」という声が減り、マネージャーも準備して1on1に臨めるようになりました。
二つ目は対話履歴の管理。「前回はどのような議論をしたか」「どんな課題が残ったか」を簡単に確認できるため、継続的な対話が可能になり、問題解決のフォローアップも容易になりました。
そして、私が最も価値を感じているのが三つ目のデータ分析です。
Kakeaiでは1on1を重ねるごとに蓄積されるデータから、マネージャーごとの対応の得意・不得意が見えてきます。それを基にKAKEAI担当者と振り返り会を行い、改善策を見出せるようになりました。

例えば私自身、「意見を聞きたい」というテーマへの対応が「苦手」という結果が出ていました。
私は「メンバーに聞かれたことに対してしっかり意見を言えていない」と解釈しましたが、KAKEAIのカスタマーサクセス担当者との振り返りミーティングで異なる視点が示されました。曰く、「メンバー自身に既に明確な意見があり、それとグループ長の考えの違いを知りたいというニーズかもしれない」と。
お互いの意見を並べて「ここは共通点だね」「ここは異なる視点だね」と整理しながら対話を進めることの重要性に気付かされ、ハッとしました。
Q:1on1施策にKPIは設定していますか?
「1on1の実施率100%」と「マネジャー陣の満足度スコア80ポイント以上」を達成
中島さん:1on1の実施率100%と、マネジャー陣の満足度スコア80ポイント以上を目標にしており、現時点ではどちらも達成できています。ただ、グループ長によって結果に差があるので、スコアが低いマネジャーには個別にフォローを行っています。
安藤さん:データがあると自分の立ち位置がわかって改善意欲も湧きますね。データがないと「このままでいいか」となりがちですが、結果を見ると足りていないところが見えてきて、自分自身を振り返るきっかけになります。

Q:ここまでは1on1推進者およびマネジャー目線での1on1の価値を聞いてきましたが、メンバーである森さんは、1on1をどのように捉えていますか?
業務中では言えないようなことも許容される、貴重な場。
森さん:あえて極端な言い方をしますが、私は1on1を「業務以外のことにも使える30分」とか「部下のためのアルコールのない飲み会」と捉えています(笑)。
業務中だと言えないことも許容されるのが1on1の良いところ。会社が公式に推奨している時間ですから、自分のための貴重な30分と考え、「1on1なら何を話しても大丈夫」くらいの気持ちで臨むようにしています。そういうスタンスでいると、自然と本音が話せるようになります。今では「単なる上司ではなく人生の先輩に相談するんだ」という気持ちで1on1に臨んでいます。

Q:なぜそれほど1on1を前向きに捉えられるようになったのでしょうか?
悩み相談の成功体験が転機に。
森さん:大きな成功体験があったからかもしれません。2024年に安藤さんが上司になってから、これまで10回以上1on1を重ねてきました。最初のうちは趣味や育児などの、業務とは関係ない雑談を繰り返しましたが、回を重ねるうちに信頼関係が深まり、徐々に本音の相談ができるようになりました。
転機は5回目くらいの1on1でした。「解析技術の開発を一人でやることが多くて、業務が属人化している。正直、モチベーションが下がっています」と打ち明けました。これがきっかけで業務のあるべき姿を1on1や日々の業務のなかで安藤さんと議論し、その結果、日々アドバイスをもらえる先輩社員をつけてもらえることになりました。
この経験から、「上司に悩みや課題を正直に伝えると、具体的な解決策を一緒に考えてくれる」と実感できたのです。それからは些細なことでも積極的に報告や相談をするようになりました。
Q:1on1で本音を話せるかどうかは上司との信頼関係次第とも言えます。森さんが安藤さんに信頼を感じるようになったきっかけはありますか?
否定せず共感ベースで話し合ってくれること。
森さん:安藤さんは私の考えを否定せず、まず受け止めてくれます。これが一番大きいですね。例えば悩みを相談した時に「それは違うよ」と頭ごなしに否定されるのではなく、「それは難しいよね」と共感してくれる。そこからようやく前向きな議論ができるようになりました。
印象的だったのは、顧客との難しい内容の打ち合わせの後のこと。安藤さんが「今日の内容、正直、俺にとっても難しかった」と率直に言ってくれました(笑)。上司も完璧じゃないんだと思えると、こちらも素直になれる。そういう率直なやり取りが、フラットな対話の雰囲気を作っているのだと思います。
Q:1on1の時間を有意義にするべく工夫していることはありますか?
話すことを事前に整理し、終わった後もしっかり振り返る。
森さん:シンプルですが、準備が一番大切だと思います。何も考えずにその場の思いつきで話すと、表面的な会話で終わってしまいます。自分の考えも整理できず、本当に困っていることも上手く伝えられない。だからこそ、Kakeaiでの事前テーマ設定やメモはとても役立ちます。話したいことを前もって整理できますし、事後に振り返りもできるので、次の1on1に活かせます。
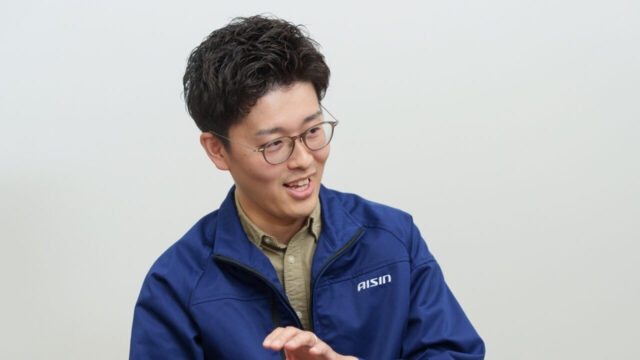
中島さん:マネジャー側の工夫としては、メンバーだけでなく自分自身のアクションも明確にすることです。悩み相談を受けた時、「あなたが次のアクションを取る時に、私にできることはないか」と必ず支援の姿勢を示します。この双方向のコミットメントが重要なんです。
1on1でよくあるのは、アドバイスを与えたメンバーが「やってみます!」と言って終わってしまうパターン。これは非常にもったいない。私も一緒に取り組む姿勢を見せることで、メンバーの目標が実行に移される確率が高まりますし、信頼関係が深まり、私からの業務依頼にも応えてくれるようになります。
現在の部署は先輩メンバーが多く、異動当初は不安でしたが、このアプローチでお互いの信頼関係を築くようにしています。
Q:ここまでのお話はエンジニア組織ならではの視点が強く反映されていると思います。改めて、「エンジニア×1on1」を進める際のポイントがあれば教えてください。
技術面だけでなく「挑戦する気持ち」も育てること
森さん:メンバー視点からすると、エンジニア組織の1on1で見落とされがちなのは「気持ち」の部分です。技術力ばかりに目が行きますが、開発の壁にぶつかった時、実はチャレンジする自信や勇気の問題だったりします。
1on1はそんな「一歩踏み出す勇気」を後押ししてくれる場なんです。一人だと「失敗しそうだからやめておこう」と思うことも、上司のサポートがあれば挑戦できる。そういう安心感が重要だと思います。
中島さん:当社で1on1が根付いているのは、「メンバーに興味を持つマネージャー」の存在が大きいと思います。形骸化防止には定期的なフォローも欠かせません。
四半期ごとに実施状況を確認し、頻度の低いグループ長には声掛けをしています。Kakeaiを活用したデータ分析と振り返りで、1on1の質向上を継続的に図ることも重要です。
エンジニアの成長は、技術力だけでなく「挑戦する気持ち」も含めて考えるべきもの。一人ひとりの個性と価値観を尊重する対話が、強いチームづくりの基盤になると思います。
※上記事例に記載された内容は、2025年04月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。