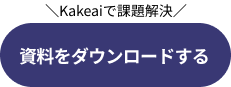整備士の離職を防止したい。150名全社員と行っていた1on1を『Kakeai』でバトンタッチ


業界:自動車整備|従業員数:100名〜499名|導入目的:離職防止
株式会社ミック
取締役副社長
池田 高之 さん
組織課題:
・中間層の離職
- 10年以上勤めてくれた「中間層」のメンバーから突然な退職の申し出が発生
解決策:
・本音で話せる環境づくりの場、マネジャーがメンバーの変化に気づくための仕組みとして「1on1」を開始
『Kakeai』を選んだ理由:
・1on1について知識がないマネジャーでも運用しやすい仕組み
- 「トピック」と「相手に期待する対応」別のヒントで、1on1の進行をサポートしてくれる
- 1on1を設定する際に「トピック」と「相手に期待する対応」をメンバー側から設定してもらえるため、相手に合わせたアプローチを事前に準備できる
株式会社ミック 取締役副社長である池田さんに、1on1支援ツール『Kakeai』の導入の背景や、目指す組織についてを伺いました。
安心して本音で話せる場所を作ることで、メンバーの変化に気づける組織にしていきたい
Q:業務内容と組織について教えてください。
千葉県を中心に「車検のコバック」を8店舗、その他、鈑金塗装や自動車販売を含め11店舗の運営を行っております。従業員数は約150名で、自動車整備士を中心に、ドライバー、洗車配送、事務、コールセンターなど職種はさまざまです。
私たちが目指しているのは「車の総合病院」。
人間でいう健康診断は車検、外科にあたるのが傷のへこみの修理や板金塗装、救急車にあたるのがレッカー対応などです。「車のことで何かお困りごとがあれば、とりあえずミックにきてください!」と地域の皆様にお伝えできる環境を作っています。

Q:組織の課題を教えてください。
「離職」を未然に防ぎたいという想いはすごく大きいです。
10年以上勤めてくれた「中間層」のメンバーから急な退職の申し出があったことで問題意識が高まりました。この業界では「段取り8分」という言葉があるくらい、いかに効率よく進められるかという「段取り力」が重要です。その段取りを任せられる中間層が辞めてしまうのは事業にとって痛手ですし、一緒に会社をつくりあげてきたメンバーの退職を防げなかったことに無力感がありました。また、退職理由は千差万別ですが、退職を決断する前に対話をして、フォローできたことも多かったのではないかと強く反省しています。
Q:離職に対してどのような取り組みをされていますか。
目が届く規模の頃は、メンバーの顔色を見ながら「飯でも行こうよ」と声がけが出来ていました。現在は150名の組織になっているので、私の独力だけではどうにもなりません。そこで、幹部には、メンバーとの飲み会などのコミュニケーションのための予算を渡しています。しかし、コロナ禍で皆で集まる場を設けることも難しい状況になっていました。
そこで、1〜2ヶ月間をかけて私が全メンバーとの1on1を実施しました。
1対1で時間を作ることで「どんな思いで仕事をしているのか」「どこに課題を感じているのか」など、普段は話せない想いや悩みを素直に話してくれたり「1on1という場を設けてくれたことが嬉しい!モチベーションに繋がりました」と言ってくれるメンバーもいました。
改めて、本音で話せる場所をつくることの重要さと、課題としていた「退職しようと決める前にフォローする仕組み」が1on1で実現できるのではないかと感じました。

『Kakeai』のヒントが、マネジャーの成長につながる
Q:1on1の実施状況について教えてください。
現在、『Kakeai』は、私と各店舗責任者との1on1で使用しています。
というのも、私がメンバー全員との1on1を継続するのは難しいので、まずは各店舗の責任者に1on1の重要性や効果を『Kakeai』を通じて実感してもらい、今後は、各店舗の責任者と各店舗のメンバーが1on1を実施する体制にしていきたいと思ってます。
Q:『Kakeai』導入の経緯について教えてください。
1on1を仕組み化するならば、何かしらのツールが必要だと考え、問い合わせたことがきっかけです。私は、コーチングが好きで、1on1に有効な質問や、コミュニケーションの在り方について勉強してきました。しかし、各店舗の責任者にはそんな時間はありません。
『Kakeai』は、1on1について知識がない各店舗の責任者でも運用しやすい仕組みと、組織長としての成長のきっかけがあることが決め手でした。
1on1の進行をサポートしてくれるヒントや、「トピック」と「相手に期待する対応」を事前に設定することで、相手に合わせたアプローチを上司側が事前に準備できる点は特に助かっています。
また、コミュニケーションがうまくいかない時は、上司側のアプローチを変えるしかないと思っているんです。そもそも相手と自分が違う考えだと認識することが重要だと思っています。ですから、メンバーとの特性の違いを見ることができる「セルフアセスメント」も活用していきたいです。

自動車整備業界は人手不足が加速。今後は、海外出身者とのコミュニケーションがより重要に
Q:今後の組織作りについて教えてください。
自動車整備業界全体で、人員確保が難しくなっています。
業界全体の有効求人倍率は、通常の約4倍。この業界を志す日本人の若者が減っていて10〜15年前の3分の1になっていると言われています。若い世代の方が車に興味がなかったり、リモートワークなどの働き方が注目されていて、現場仕事を魅力に思わない学生が多いのが現状です。
そこで、進んでいるのが、海外出身者の方の活用です。
当社でも、現在9名の海外出身者の方が在籍していて、今年の4月までにあと6名入社する予定です。
やはり苦労するのがコミュニケーションで、感覚とかニュアンスを伝えることの難しさを痛感しています。だからこそ、採用後の育成方法を今後も工夫しなければいけないと思っています。
異国の地で働いている海外出身者の方の悩みは日本出身の方とは異なると思うので、1on1でしっかりフォローしていきたいと思っています。

※上記事例に記載された内容は、2023年2月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。